【直木賞・川越宗一『熱源』が受賞!】第162回候補作を徹底解説!

2020年1月15日に発表された、第162回直木賞。文芸評論家の末國善己氏が、今回も予想! 結果は、川越宗一氏の『熱源』でしたが、当初の予想はどうだったのでしょうか? 候補作5作品のあらすじと、その評価ポイントをじっくり解説した記事を、ぜひ振り返ってみてください!
前回の直木賞(第161回)を振り返り!
今回の直木賞予想も、前回の答え合わせから始めたい。
前回は、窪美澄『トリニティ』を本命、朝倉かすみ『平場の月』を対抗、柚木麻子『マジカルグランマ』を穴と予想したが、結果は大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』だったので、またしても外れ。これで予想は2勝4敗となり、借金を増やしてしまった。
桐野夏生の選考経過によると、
最初の投票で受賞作と朝倉かすみさんの『平場の月』、窪美澄さんの『トリニティ』の三作に絞られ、長い議論の末に唯一、過半数に達した『渦』に決まった (「東京新聞」夕刊、2019年7月30日)
とあるので、かなりの接戦だったようだ。『渦』の高評価を除けば、展開の予想は悪くなかったといえる。
前回は“史上初めて候補者全員が女性”が話題を集めたが、今回は、デビュー間もない新人で、初の直木賞ノミネートが3人(ベテランだが、直木賞候補は初の誉田哲也を加えると4人)という、もともとは新人賞だった直木賞の原点に回帰したかのようなフレッシュな戦いになった。新人3人が抜けるか、ベテラン2人が意地を見せるかも楽しみだ。
選考委員は、前回まで務めた東野圭吾が抜け新たな委員が選ばれなかったので、浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、髙村薫、林真理子、宮城谷昌光、宮部みゆきの9名。この変化が、選考結果に与える影響にも注目して欲しい。
候補作品別・「ココが読みどころ!」「ココがもう少し!」
小川哲『噓と正典』

https://www.amazon.co.jp/dp/4152098864/
今回の候補者で最年少の小川哲は、2015年、視覚や聴覚を含むすべての個人情報を企業に提供する代わりに、高額な基礎保険が受け取れる近未来を舞台にした『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞してデビュー。恐怖政治と虐殺が行われたポル・ポト政権下のカンボジアで出会った少年と少女が、理不尽な世界に“ゲーム”を仕掛ける第2作『ゲームの王国』で第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞をW受賞した。初の直木賞候補となった『噓と正典』は、第3作めである。
『噓と正典』は6作を収録したSF短編集だが、いずれもジャンルの境界ギリギリを狙った一筋縄でいかない作品ばかりである。
かつて一世を風靡したが落ち目になっていたマジシャンが、娘と息子を含む観客の前でタイムマシンを使ったマジックを披露する「魔術師」は、そのタイムマシンが本物なのか、マジック的なトリックがあるのか曖昧なまま進み、ミステリー的な面白さもある。
競馬好きだった父が亡くなり、無名の競走馬「テンペスト」のオーナーになっていたことを知った作家が、父が調べた「テンペスト」の血統にまつわる原稿を読み進める「ひとすじの光」は、さらにSF的な要素がないが、最後まで読むと、緻密な構成と巧みな仕掛けに驚かされるだろう。「時の扉」は、語り手が王に物語を聞かせる『千夜一夜物語』風の展開が、現代史の“闇”とリンクするラストに圧倒された。音楽を貨幣のように使っている少数民族と、幼い頃、スパルタ指導をする父に嫌々ながらピアノの手ほどきを受け、今は音楽会を撮影する会社に勤める男の人生が結び付いていく「ムジカ・ムンダーナ」は、特殊設定を活かした一編といえる。機能性を重視し、シンプルな生活を提唱する企業の影響で「流行」が消えた社会に抗うため、無駄で過剰なヤンキーになる男を描いた「最後の不良」は、流行を追うのは正しいのか、個性とは何かを突き付けていて考えさせられる。
“珠玉”といえるほど外れがない本書の中でも、表題作「嘘と正典」は出色だ。
物語は、後にカール・マルクスと組んで共産主義の論理を構築するフリードリヒ・エンゲルスが、イギリスで工場を襲撃した容疑で裁判にかけられる場面から始まるが、すぐに舞台は東西冷戦下のソ連に移る。CIАモスクワ支局の工作担当員のホワイトは、クラインなる男から情報提供を持ちかけられていた。電子電波研究所で静電加速器の実験を担当しているクラインは、電極があれば情報を過去に伝える技術を発見したという。クラインが本当に過去との通信を可能にしたのか、それとも妄想なのかを軸に進む「嘘と正典」は、スパイ小説、エンゲルスと共産主義の歴史、過去と通信する未知の技術といった無関係に思えるエピソードを繋げながら、驚愕のラストを作った小川の手腕に圧倒された。
プロの小説家も、ジャンルの伝統やルール、長年にわたって積み重ねられてきた物語のパターンとは無縁ではいられないので、小説を読み慣れてくると、この設定が出てくればこのようなオチになると予想ができるようになる。ただ本書の収録作は、それなりにSFを読んできた経験則が通用せず、どこに連れていかれるのか、どこに着地するのかがまったく読めなかった。その意味で今回の候補作の中では一番面白かったのだが、読者を選ぶのは間違いない。選考委員が効き過ぎたエッジを理解できるのかが、それ以上に、SFは直木賞を受賞できないというジンクスを打ち破れるのかが、当落をわける鍵になるだろう。
川越宗一『熱源』

https://www.amazon.co.jp/dp/4163910417/
2018年、文禄・慶長の役(いわゆる朝鮮出兵)に至る歴史を、島津、朝鮮、琉球の視点で描いた『天地に燦たり』で第25回松本清張賞を受賞してデビューした川越宗一は、2作目の『熱源』が初の直木賞候補となった。『熱源』は、第9回「本屋が選ぶ時代小説大賞」を受賞しており、この勢いに乗って直木賞とのW受賞になるかもポイントだ。
日本の南方を舞台にした『天地に燦たり』とは一転、『熱源』は、アイヌの口承文学を言語学者の金田一京助、ポーランド人の民族学者ブロニスワフ・ピウスツキらに語り、
19世紀後半。北海道開拓使に故郷の樺太を追われ北海道に移住したヤヨマネクフは、日本人に差別されながら成長し、疫病で妻と仲間を失い失意の中で故郷に戻った。一方、ロシアに奪われた祖国ポーランドを解放するため皇帝暗殺計画に加わったとして流刑となったピウスツキは、樺太でヤヨマネクフに出会いアイヌの研究を始める。
ヤヨマネクフたちは、欧米列強が発展途上国を支配する帝国主義、人間を人種、民族などによって序列化する社会ダーウィニズムが常識だった時代を生きた。欧米諸国と対等に渡り合うため、中央集権化による富国強兵を進める日本政府に、アイヌの文化を否定され日本人になることを求められたヤヨマネクフと、ロシアの同化政策でポーランド語の使用を禁じられたピウスツキは、近代史の犠牲者といえる。そんな二人が、絶望に打ちひしがれることなく、自分たちのアイデンティティを模索していく展開には深い感動があるし、国家とは、民族とは何かを考える切っ掛けになるはずだ。
2度の世界大戦を経験した人類は、異なる国、異なる人種、異なる民族、異なる宗教であっても互いを尊重し、認め合う社会を作る方向に進んでいたが、近年は19世紀末から20世紀初頭のように、自国第一主義を掲げる国、自分が属する人種、民族を絶対と信じ、異なる価値観を持つ人たちを見下す風潮が世界的に広まっている。差別と偏見に抗い、分断を乗り越える方法を模索したヤヨマネクフたち姿は、現代の社会問題を浮き彫りにし、それを解決するヒントも示してくれているのである。
『熱源』は、2019年に刊行された歴史小説の中でもベスト3に入ると考えているので、今回の直木賞候補になった唯一の歴史小説なのも納得できる。ただ傑作だけに、細かな問題点も目に付いた。例えば、ヤヨマネクフと交流を持つ金田一京助は、アイヌ文化の理解者として描かれているが、西洋と日本の文化を最上位とし、アイヌの文化は未開人のものとする考えを完全には捨てておらず、アイヌは独自の言語を捨てて日本語を使うべきだとも主張している(このあたりは、金田一の弟子で師匠への敬愛を語りながら、アイヌへの差別や偏見を厳しく批判したアイヌの言語学者知里真志保の著者からもうかがえる)。
その意味で、近代の政治史、文学史、文化史の知識があると、美しい部分だけを強調した川越の歴史観と小説作法には違和感を覚えるし、時代考証と物語の根幹が密接に関係しているだけに、そこを否定的にとらえる選考委員がいたら、ほかの選考委員も同調して評価が下がる危険があるように思えた。
呉勝浩『スワン』

https://www.amazon.co.jp/dp/4041086396/
呉勝浩は、カリスマ的な教育家が小学校での講演中に刺殺され犯人が現行犯逮捕された事件を女性ディレクターが再調査する『道徳の時間』で、第61回江戸川乱歩賞を受賞してデビューした。『道徳の時間』は選考会での評価が分かれ、強硬に受賞に反対する選考委員もいる中での薄氷の受賞となった。呉はこの経験をバネにしたのか、ミステリーの仕掛けと社会的なテーマを融合させた高いクオリティの作品を早いペースで刊行しており、出所した犯罪者や犯罪予備軍との共生は可能なのかを問う『白い衝動』で第20回大藪春彦賞を受賞している。直木賞は、今回が初ノミネートである。
一般的なミステリーは、謎めいた事件が解決すると物語は終わる。だが呉は、デビュー作から一貫して、犯人が捕まり、謎がなくなった後も残る犯罪被害者や加害者の家族、その友人らの苦しみ、犯人や関係者の周辺を勝手に詮索して事件を娯楽として消費する高度情報化社会の実像などを徹底して暴くことで、一つの事件の終わりとはなにか、“真実”とは何かを問い続けている。『スワン』も、この系譜の作品である。
3人の男が、首都圏にある巨大ショッピングモール「湖名川シティーガーデン・スワン」の駐車場に、車を止めた。2人は仲間の1人を殺すと、自作した拳銃や日本刀を持って売り場に入り無差別殺戮を開始。スカイラウンジでは、人質に次に殺す人間を選ばせるゲームをした犯人は、死者21名、重軽傷17名を出した後に2人とも自殺した。
それから半年後。スワンの惨劇を生き延びた高校生の片岡いずみは、奇妙な会合に招待される。集められた5人の男女は、いずれも事件当日にスワンにいた。主催者の弁護士によると、スカイラウンジで殺された老婦人が、犯人たちが銃を乱射している渦中に不可解な行動を取ったので、その真相を調べるために集まってもらったという。
記憶をたどりながら、事件の日にスワンで見たこと、自分が取った行動を語っていく5人によって、次第にスカイラウンジで何が起きたのかが明らかになっていく。それと並行して、加熱した報道、ネットで巻き起こったバッシングなどでいずみたちの人生が大きく変わってしまった現実も浮かび上がるようになっている。
『スワン』は、マスコミの報道は必ずしも事件の本質を伝えているとは限らないこと、自分たちが作った安易な“物語”を信じて事件関係者を善悪に色分けし、悪を徹底的に叩く現代日本の風潮の是非など、タイムリーな社会問題を突き付けている。それだけに、まったく悪くないいずみたちが社会に蔓延する悪意に追いつめられていく展開は、読者もいつ同じ立場になるか分からないだけに、恐怖が身近に感じられるのではないだろうか。
テーマの設定は見事だし、トリックとメッセージ性を巧く融合させたところも評価できる『スワン』だが、映像作品であれば、登場人物のナレーションをバックに再現映像が流れる回想シーンが多く、そこでの人物の動きが複雑なので、ミステリーを読み慣れていないとつらいように思えた。またネットの無責任な書き込みとどのように向き合うべきか、事件報道のあり方、いずみたちの再生の物語など様々なエッセンスが詰め込まれているが、どれも踏み込みが足りず、すべてのテーマが十分に深められていないのも残念だった。
誉田哲也『背中の蜘蛛』
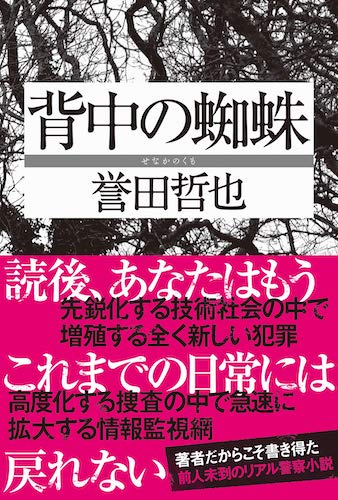
https://www.amazon.co.jp/dp/4575242144/
2002年に『ダークサイド・エンジェル紅鈴 妖の華』で第2回ムー伝奇ノベル大賞の優秀賞を受賞してデビューした誉田哲也は、2003年に『アクセス』で第4回ホラーサスペンス大賞の特別賞を受賞している。今回の直木賞候補者の中では最もキャリアが長く、女性刑事を主人公にした〈姫川玲子〉シリーズや〈ジウ〉シリーズ、剣道に打ち込む対照的な少女2人の成長を描く〈武士道〉シリーズなど、映画化、ドラマ化された人気作を幾つも抱えている誉田だが、直木賞のノミネートは今回が初となる。『背中の蜘蛛』は、誉田が得意とする警察小説である。
誉田の警察小説は、細部にまでこだわる組織の描写と、そこで働く刑事たちを掘り下げる人間ドラマに定評があるが、『背中の蜘蛛』もその持ち味が遺憾なく発揮されている。
第一部「裏切りの日」は、池袋署の刑事課長・本宮夏生が、ノンキャリアなのにFBIに派遣され、今は公安のサイバー対策の部署にいる上山章宏警部に呼び出される場面から始まる。二人の呑み会は、本宮に池袋で刺殺事件が発生したと告げる電話で打ち切られた。決定的な手掛かりがなく捜査は難航するが、ある日、本宮は捜査一課長の小菅に特命捜査を命じられる。無駄に思えた小菅の助言によって、事件は思わぬ経過をたどる。
第二部「顔のない目」は、警視庁組織犯罪対策部の植木範和警部補を主人公にしている。所轄の佐古と麻薬の売人らしい森田一樹の行動確認をしていた植木は、森田を尾行して新木場のライブハウスにたどり着く。森田がコインロッカーを利用して麻薬の売買をすると確信した植木は、現場を押さえようとするが、仕掛けられた爆弾が爆発し、森田は即死、植木も重症を負ってしまう。この事件も捜査が難航するが、植木がコンビを組んだ佐古が職務質問をした男が犯人だったと分かる。退院して捜査に復帰した植木が佐古に確かめると、タレコミがあったので職務質問をしたという。
小菅はなぜ事件解決のヒントを知っていたのか、そして佐古に情報提供したのは誰か。この謎を残したまま第三部「蜘蛛の背中」が始まる。本庁に異動し、新木場の爆殺事件を担当することになった本宮は、佐古へのタレコミと、自分かかわった小菅の特命が似ていると気付く。警視庁の怪しい動きを調べる本宮のパートと並行して、社会の底辺で生きる姉弟と知り合ったフリーターの青年が、二人を助けようと奔走する物語が描かれ、これらがどのように結び付くか判然としないまま進むだけに、そのサスペンスは圧倒的だ。
『背中の蜘蛛』には、街中に設置された監視カメラの映像を分析して、殺された現場に向かった被害者の足取り、犯人の逃走経路などを分析する最新の捜査が描かれている。ただメインになるのは、監視カメラの映像などより簡単で広範囲の個人情報を収集するシステムの是非である。誉田は、もしかしたら既に個人の監視や犯罪捜査に使われているかもしれない技術を使って物語を紡いでおり、監視社会の恐怖が身近に感じられるだろう。
『背中の蜘蛛』は、犯罪抑止や事件捜査の円滑化のためなら、ある程度まで国家による監視を認めるべきか否かという、現代的で誰もが無縁ではないテーマを描いているが、人気の刑事ドラマ〈相棒〉シリーズで先に似た問題を取り上げていたので、決して目新しくはない。監視システムを管理する側にいる、いわば“敵”を、人情(倫理)に訴えて切り崩すところも、実際に監視社会が進んでいる現状を思えばあまりに楽観的だった。
湊かなえ『落日』
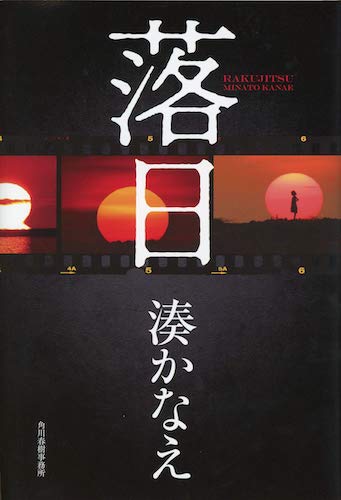
https://www.amazon.co.jp/dp/4758413428/
湊かなえは、2007年に「聖職者」で第29回小説推理新人賞を受賞、2008年に同作を含む連作集『告白』を刊行すると、各種ミステリーベスト10の上位になり確かな実力を見せつけた。その後は、「望郷、海の星」で第65回日本推理作家協会賞の短編部門を、『ユートピア』で第29回山本周五郎賞を受賞。惜しくも受賞を逃したが、2018年には『贖罪』が、アメリカ探偵作家クラブが主催するエドーガー賞の候補にもなっている。
ただ直木賞とは相性が悪く、『望郷』が第149回、『ポイズンドーター・ホーリーマザー』が第155回、『未来』が第159回と、今回の候補者の中では最多の過去3回のノミネートを果たしているが、受賞には至っていない。『落日』は、4回目の候補作である。
第159回直木賞の候補になった『未来』は、章ごとに語り手を変える手法が活かされていない、ミステリーの仕掛けが弱い、いじめ、DV、虐待、AVの強要など様々な社会問題を総花的に並べただけで深みがないと酷評したが、『落日』は近年の湊作品では突出して完成度が高い。これは偶然だろうが、犯人が捕まった事件を再調査する展開は呉勝浩『スワン』と共通しているが、作家としてのキャリアの差は歴然で『落日』が圧倒していた。
N県N市笹塚町のアパートで暮らす幼稚園児の長谷部香は、小学生用のドリルの成績が悪いと教育熱心な母にベランダに追い出されていた。ある日、香は、隣室の立石家の子供もベランダで過ごしていることを知る。成長した香は新進気鋭の映画監督になり、立石家は、引きこもりの長男・力輝斗が、妹でアイドル志望という真尋をめった刺しにして殺し、自宅に放火して両親も死に至らしめる大事件の当事者になった。
笹塚町出身の甲斐千尋は、有名脚本家の事務所で働きながら一本立ちを目指していた。そんな無名の千尋に、自殺した人たちの最後の一時間に着目した映画で高い評価を得た香が連絡してくる。笹塚町で起きた一家殺害事件の被害者が、幼い頃にベランダでささやかな交流をした真尋ではないかと考える香は、事件を題材にした映画の脚本を千尋に書いて欲しいという。被害者の真尋は、ピアニストとして世界中を飛び回っている千尋の姉・千穂、従兄の正隆と同級生だった。法事で笹塚町に帰った千尋は、正隆に高校時代の真尋と親しかった女性を紹介され、真尋の意外な一面を聞かされる。
『落日』は、パズルのピースのように断片が集まり、意外な絵を浮かび上がらせるプロット重視のミステリーで、何気ない一文が後で重要な伏線になったり、前半に描かれたシーンにまったく別の意味があったことが判明したりと、最後まで先の読めないスリリングな展開が楽しめる。暗い物語なのに、光も垣間見え読後感が悪くないのも嬉しい。
現在、何か大きな事件が発生すると、マスコミが報じ、ネットで情報が拡散され、被害者や犯人、司法とは別のところで、受け手がそれぞれに物語を作っている。そんな物語では事件の本質は見えないとするミステリーは珍しくないが、『落日』は当事者に近い香と千尋が、クリエイターとして事件と向き合い、あがきながら事件を物語化することの意義を考えており、このテーマに新たな風を送り込んだといえる。湊は、これを香たちの特殊事情とするのではなく、ミステリー作家が殺人事件を書く意味という自身の問題に重ねることで、普遍性の高いテーマに昇華させることに成功した。それだけに読者も、事件の物語化とどのように向き合うべきなのかを、真剣に考えることになるだろう。
取材で集めた素材を組み合わせて物語を作り、受け手にメッセージを伝えることの大切さ、それは関係者を傷付けるかもしれないし、間違った真相を導き出すかもしれないという困難とも表裏一体になっている事実をミステリー小説に仕立てた『落日』は、物語をめぐる物語だった前回の直木賞受賞作、大島真寿美『渦 妹背山婦女庭訓魂結び』との共通点も少なくない。選考委員が前回とほぼ変わっていないだけに、同じように評価されるかもしれないが、反対に似た傾向の作品の連続受賞は避けたいとの意見が出る危険もある。
ズバリ予想!本命は?対抗は?
以上を踏まえ、第162回直木賞を予想してみたい。
おそらく今回は、頭一つ抜けていた『熱源』と『落日』の一騎打ちになると考えている(この二作に対抗できるのは『噓と正典』だが、これは選考委員の理解の外側にあるので、受賞はないと見る)。そのため悩むのだが、辺野古新基地建設の是非をめぐる県民投票が目前に迫っていた時期に選考が行われた第160回直木賞が、沖縄の現代史を扱った真藤順丈『宝島』になったように、2019年4月、アイヌを先住民族と明記した、いわゆるアイヌ新法が成立したこと考慮するなら、センシティブなアイヌ問題に正面から挑み、ダイナミックな物語を作った川越宗一が有利なように思え、『熱源』を本命とする。昨年、大英博物館で開かれたマンガ展のキービジュアルに、野田サトルの漫画『ゴールデンカムイ』に登場するアイヌの少女アシリパが描かれるなど、少数民族の権利を守り、共生をはかることは世界的な関心事になっており、これも追い風になるように思える。
対抗は『落日』。ジャンルは違うものの、小説としての完成も、テーマの設定も『熱源』と互角だったが、これまで3回の選評が湊に辛辣だったこともあり、推し切れなかった。その一方で、最近の直木賞は功労賞的な色彩が強いので、これまでの活躍を加味すれば『落日』が有利になる可能性もある。
穴は『背中の蜘蛛』。小説のクオリティではやや劣るが、功労賞であれば、最も小説家としてのキャリアが長い誉田哲也が受賞しても不思議ではない。
選考会は、2020年1月15日、築地の料亭・新喜楽で開催される。結果を楽しみに待ちたい。
筆者・末國善己 プロフィール

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』などがある。
初出:P+D MAGAZINE(2020/01/11)





