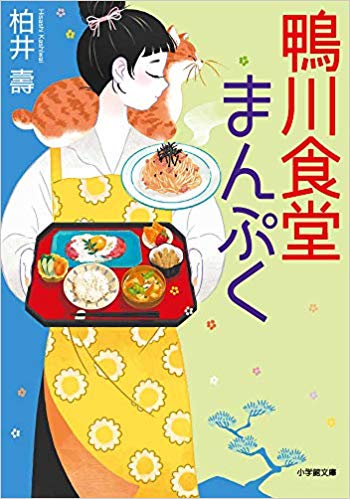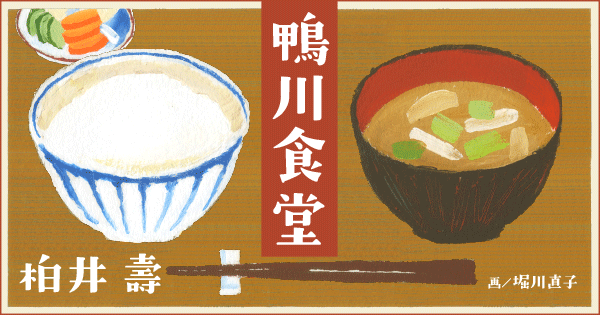「鴨川食堂」第38話 チキンライス 柏井 壽

つかれた体に、ほっと一息。どうぞ召し上がれ。
第38話 チキンライス
「いえいえ、こちらのほうがイレギュラーなことをお願いしてしまったのですから」
香織はほうじ茶で喉をうるおした。
「どうぞゆっくり召しあがってください」
流がまた厨房に戻っていった。
まだまだ料理はたくさん残っている。香織は自分でも驚くほどの日本酒を飲みながら、順に箸を付けていく。
さりげなく長皿に盛りつけてあるが、フグの白子焼なんて超が付くほどの高級料理だ。刺身や鍋はどこでも食べられるが、美味しい白子はめったに出てこない希少な食材だ。銀座のフグ料理専門店へ連れて行ってくれたときに、毅彦がそう教えてくれた。
そのいっぽうで、ただ油揚げをあぶっただけの質素なものもある。一見アンバランスなようでいて、どれもが美味しいという糸で結ばれている。食通からほど遠いところにいる香織でもそれが分かるところに、この料理のすごさがあるのだろう。
「どないです。そろそろご飯をお持ちしまひょか」
八割がた料理がなくなったころを見計らったように、流が厨房からでてきて香織の傍に立った。
「お願いします。あんまり料理が美味しいので、ちょっとお酒をいただきすぎたようです」
言葉どおり香織は顔を真っ赤に染めている。
「こいし、土鍋ごと持ってきてくれるか」
流が厨房に声を掛けると、すかさずこいしは両手で持って土鍋を運んできた。
「炊き立てですさかい、ちょっと蒸らしが足らんかもしれまへん。ゆっくり食べてもろたほうがええ思います」
流が土鍋のふたを取ると、もうもうと湯気が上がり、甘酸っぱい香りが漂ってきた。
「チキンライスが好物やてお聞きしたんで、炊き込みご飯にしてみました。具は鶏肉とタマネギとグリンピースだけ。味付けは和風と洋風の真ん中へんですわ」
流がしゃもじで土鍋から飯茶碗によそうと、香織は中腰になって土鍋を覗きこんだ。
「こんなの初めて。美味しそうですね」
「実を言うと、わしも初めて作りました。急ごしらえやさかい、あんまり自信はおへんのやが、いっぺん召しあがってみてください」
流が飯茶碗を香織の前に置くと、こいしがその横に汁椀を添えた。
「美味しい」
ひと口食べるなり、香織が大きく目を見開いた。
「よろしおした」
「おつゆはコンソメふうのおすましです。ご飯は土鍋ごと置いときますよって、好きなだけ食べてください」
こいしと流が厨房に戻っていった。
なんとも不思議な味だ。たしかにお茶碗によそった炊き込みご飯なのだが、目をつぶって味わうとチキンライスそのものなのである。どういうことなのだろう。不思議に思いながらおすましに口を付けると、またおなじ思いになる。漆のお椀に入っているけれど、味わいはコンソメスープに近い。でもやっぱりおすましだ。まるでマジックを見ているみたい。
何より驚かされるのはその早業ぶりだ。
最初に出てきた料理を食べていたのは、わずかに三、四十分のはずだ。そのわずかなあいだにこのご飯を作ったということだ。こいしから話を聞いてすぐに思い付き、調理をはじめて短時間で完成させる。おつゆはともかく、炊き込みご飯のほうはただ炊くだけでもそれぐらいの時間はかかる。
炊き込みご飯を味わいながら、香織は廊下の両側にびっしり貼られた料理写真を思い浮かべている。あの料理のなかにも、こんなふうに即興で作ったものがいくつかあるのだろう。そしてそれはきっと、限りなく食べる側に思いを、心を寄せているのだ。だからこんなに美味しいものが作れる。
では、あの〈南海飯店〉のおばちゃんはどうだったのだろう。香織に心を寄せて、あのチキンライスを作ってくれたのだろうか。香織の心のなかでくすぶっているのは、その一点だけだといってもいい。
大食漢とは縁遠い存在だと思っていたのに、炊き込みご飯も二度お代わりし、料理も完食した。そして何より驚いたのは、四合瓶のお酒が半分ほどしか残っていないことだ。つまりは二合ほども飲んだことになるのだが、酔っているという自覚はまるでない。
箸を置いて手を合わせると、さほど間を置かずに流とこいしが厨房から出てきた。
「ごちそうさまでした」
「きれいに食べてもろて」
器をさげながらこいしが笑顔を香織に向けた。
「捜してはるのはこんなんと違いましたやろ」
流が土鍋にふたをした。
「ぜんぜん違うものでしたけど、とても美味しくいただきました。チキンライスといってもいろんなバリエーションがあるんですね」
香織が名残惜しそうに土鍋に目をやった。
「だいたい二週間あったらお父ちゃんが捜してきはるので、そのころに連絡させてもらいます」
「どうぞよろしくお願いします。今日のお食事代を」
香織が財布を手にした。
「探偵料といっしょにいただきますので」
「ほんとうに今日はありがとうございました。お話も聞いてもらって、美味しいものもたくさんいただいて、なんだか心が軽くなりました」
「よろしおした。しばらくお待たせしまっけど、ちゃんと捜しておきます」
「えらいお父ちゃん自信満々やね」
「自信とかやない。全力で当たりまっせ、っちゅう決意表明や」
「愉しみにしてます」
香織がくすりと笑って、店の外に出た。
「お気をつけて」
こいしが背中に声を掛けると、香織は振り返って会釈した。
ふたりは店に戻って後片付けをはじめる。流が土鍋を両手で持った瞬間、こいしが怒気を帯びた声をあげた。
「めっちゃむかつくわ。女の人から九百万円もの大金をだまし取るやなんて」
「そない大きい声を出さんならんことやない。世の中にはようある話や。人間っちゅうのはおろかなもんや。人をだまして金を持ってもけっして楽にはならん。寝覚めも悪いやろし、悪銭身に付かずていうて、すぐに出て行ってしまいよる。きっとその男も後悔しとるはずや。そんなよけいなこと言うてんと旅行の用意しとけよ。一緒に東京へ行くさかいにな」
「うちも連れて行ってくれるん? 嬉しいなぁ、東京て何年ぶりやろ」
「遊びに行くのと違う。仕事しに行くんやていうことを忘れたらあかんで」
「はいはい。チキンライス捜しのお手伝いさせてもらいます」
こいしが肩をもむと、流はまんざらでもなさそうに目を閉じた。
2.
二週間後の京都は秋が更に深まっていた。
どんよりと重い曇り空は、秋というより冬に近い感じがした。慣れた足取りで正面通を東に向かって歩く香織は、白いコーデュロイのパンツに、黒のダウンコートを羽織っている。
「こんにちは」
「ようこそおこしやす」
香織が引き戸を引くと同時に、こいしが明るい声で出迎えた。
「お待ちしとりました」
流は暖簾のあいだから顔だけを覗かせた。
「なんだかいい匂いがしてますね」
香織がダウンコートを脱いでコート掛けに掛けた。
「うちも味見しましたけど、ほんまに美味しかったです。愉しみにしててくださいね」
こいしはランチョンマットとスプーンをセットした。
「はい。しっかりお腹を空かせてきました」
「味は覚えてないて言うてはりましたけど、食べはったら思いださはる思います」
こいしが意味ありげにほほ笑んだ。
やがて厨房から漂ってくる香りが変わった。それは二週間前にここで香織が食べた炊き込みご飯によく似た、甘酸っぱい匂いだった。
どんなチキンライスが出てきたとしても、あの日食べたものとおなじかどうかなど、香織には判別できない。それほどに記憶が抜け落ちているのだ。
香織には経験はないが、酔って記憶をなくすのとおなじなのだろうと思う。〈南海飯店〉に入っておばちゃんから聞かされたこと、その次の記憶は家に帰ってひどく落ち込んでしまったこと。そのあいだはすっぽりと記憶が消えてしまっているのだ。
訊かれたから答えたものの、鶏肉がどれぐらいの大きさで、どれほどの量が入っていたかまで正確に覚えているわけではない。色についても赤くなかったことだけはたしかだが、白っぽかったような気もするし、桃色がかっていたようにも思う。その程度の記憶しかない。
「お待たせしましたな。特製チキンライスです」
銀の丸盆に載せて流が運んできたのは、白い丸皿に盛られたチキンライスだ。とは言ってもふつうのチキンライスとは似て非なるものなのである。
誰もが思い浮かべるチキンライスといえば、きまってケチャップ色に赤く染まっているものだが、目の前にあるそれは、ほんのりと桃色がかってはいるが白っぽいのだ。ぜんたいを眺めても、スプーンで少しなかをほじっても、ピラフだとかヤキメシにしか見えない。
手を合わせてから、スプーンで掬(すく)ったそれを口に運んでみる。
熱々のチキンライスを吸いこんだ息で冷ましながら味わうと、二週間前の炊き込みご飯がよみがえってきた。甘酸っぱい香りがふわりと広がる。ふつうのチキンライスと違うのは鶏肉の食べ応えだ。三センチ角ほどの鶏肉がごろごろと混ぜ込んである。
よく見ると鶏肉はかすかに赤く染まっていて、嚙みしめるとあの店の光景が頭に浮かんできた。
おばちゃんはたえず仕事をしていた。
大きな寸胴鍋のスープをかき混ぜると湯気が上がり、なんとも言えずいい匂いが店中に広がった。ニンジンをゆっくりと輪切りにし、飾り包丁を入れる。よくあんな大きな包丁で細かな細工ができるものだ。と思えば今度はリズミカルな音を立てて、ダイナミックにキャベツの千切りをはじめた。そんなにたくさんの仕込みをする意味があるのだろうか。香織が行くときはいつも客はまばらだ。ボウルの氷水に浸けてあったモヤシのひげ根を一本一本取っている。こんな面倒な仕事をしても、気付かないお客さんがほとんどなんだけどね。そう言っておばちゃんは哀しそうに笑っていた。そうだ。思いだした。あのキッチンのなかでひときわ目立っていたのは、大きなケチャップの缶だ。
あのころはなんとも思わなかったが、今考えると不思議だ。あの店にはエビチリもメニューになかったし、ケチャップを使う料理なんてなかったように思う。なぜあんな大きなケチャップの缶があったのか。しかも有名メーカーのブランドではなかったような覚えがある。
ほんとうに食べものというのは不思議だ。食べているうちにいろんなことを思いだす。十五年という長い歳月を経ても、まったく色褪せていない。
たしかにこんなチキンライスだった。鶏肉はケチャップの味がするのに、ご飯のほうはリゾットのようなスープ味で、でも粘りはなくあと口もさっぱりしていた。
記憶があいまいなのだから、あのときのチキンライスとまったくおなじだと言い切ることもできないが、ぜんぜん別ものだとも言えない。ただ薄ぼんやりとだけど、あの日のおばちゃんの言葉や表情が、浮かんだり消えたりしているのはたしかだ。
あの日のチキンライスはこんなに美味しいものだったのか。あんなことさえおばちゃんが言いださなければ、じっくり味わうことができただろうに。なぜあんな話を。
大きな疑問とともに、悔しいような、不愉快なような気持ちがない交ぜになる。
「どないです。こんなんと違いましたか」
ふいに現れた流が低い声を出した。
「すみません。正直なところ、記憶があいまいなので、これとおなじだったような気がしますけど、違うかもしれません」
香織はあいまいな答えかたをするしかなかった。
「料理っちゅうもんは、食べたほうは忘れとっても、作ったほうはちゃんと覚えてます。それがプロっちゅうもんですわ」
「ということは、あのおばちゃんにお会いになったんですね」
香織が背筋を伸ばした。
「お話しさせてもらいますわ」
流が香織の向かいに座った。
「名前もお聞きしてなかったので、きっと無理だと思っていました。ありがとうございます」
頭を垂れ、香織が目をうるませている。
「最初に東京へ行きましたんやけど、まったく手がかりはつかめまへんでした」
「すみません。わざわざ行っていただいたのに、わたしの記憶があいまいだったせいで」
「いやいや、なんにも気にしてもらうことおへん。こいしとふたりで、おのぼりさんツアーしてきました。こういうことでもなかったら、絶対に十条てなとこへ行かなんだ思います。東京にもこんなとこがあるんや言うて、えらいこいしは気に入っとぉったみたいです。肝心の〈南海飯店〉ですけど、七、八年前に店を閉めはったようです。ご近所のお店に訊き込みしたんでっけど、どこへ行かはったかは知らはりまへんでした。ハルさんて呼ばれてはったそうですわ。誰も姓名までは覚えてはらなんだ」
「ハルさん、ですか。そう言えば出入りの業者さんが、そう呼んでられたような」
香織が記憶の糸をたぐっている。
「お店を閉めはったんは、契約更新のときにテナント料で折り合わんかったかららしいと聞きましたさかい、おそらくどこかほかの場所でお店を続けてはるはずやと思うたんです。食いもん商売にもいろいろありまっけどな、食堂をやっとる料理人は、お客さんの喜ぶ顔を見とうて店をやってますんで、そう簡単にはやめられまへんのや。長いこと店やっとると屋号にも愛着がありますさかい、たぶんおんなじ〈南海飯店〉のはずや。そう当たりを付けて捜してみました」