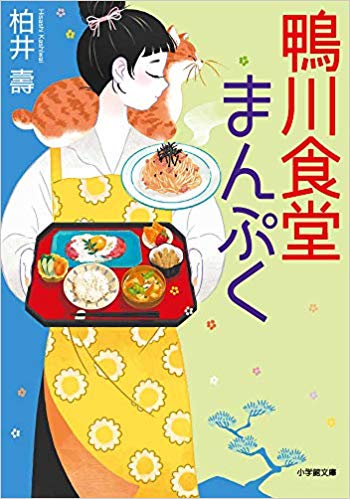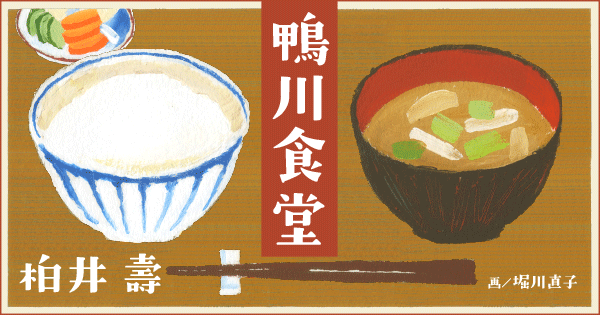「鴨川食堂」第38話 チキンライス 柏井 壽

つかれた体に、ほっと一息。どうぞ召し上がれ。
第38話 チキンライス
「半年ほどの付き合いでしたけど、彼とはお互いに結婚するつもりでいましたから、すごいショックを受けて、半分も食べずにすぐ席を立ちました。食事代を払うと言ったんですが、自分が勝手に作って出したんだから要らない、とおばちゃんが言い張ったので、結局払わずにお店を出ました。まさかそんなことを言われるなんて、思ってもいなかったので呆然としてしまって、どうやって家に帰ったか覚えていないほどでした」
「お気持ちはようよう分かりますわ。結婚しようとまで思うてはった相手やのに、いきなり早ぅ別れなさいて言われてショックを受けへん人間はいませんわ。けど、なんでそんなことを言いださはったんやろ。何かその理由を言うてはりました?」
「もちろん訊きましたよ。なぜ? って。そしたら何も言わないんです。あなたにはふさわしくない相手だ、その一点張りで」
「それではらちが明きませんわね」
「次の日は少し冷静になれたので、お店に行っておばちゃんの話を聞こうと思ったんですが、なんとなく怖くなって、結局それ以来お店に行くことはありませんでした」
「怖いっていうのは?」
「そんなことは絶対ないと思っていましたけど、彼のことで何か根拠があっておばちゃんが反対したのだとすれば……。万にひとつ、もしもそんなことがあったとしても聞きたくないと思いました」
「それぐらい好きやったし、相手の男性を信頼してはったんやね」
こいしがそう言うと香織はこっくりとうなずいた。
こいしには、ひとごととは思えなかった。
いつか誰かと結婚することになるのか。一生このままの暮らしを続けていくのか。先々のことは分からないが、いずれにせよ結論は自分で出したいと思っている。周りからとやかく言われたくない。結婚するとしても、相手も自分で決める。
「そのお店は今もあるんですか?」
こいしは話の向きを変えた。
「もうありません」
「お店の名前とかは覚えてはります?」
「〈南海(なんかい)飯店〉っていうお店で、十条駅のすぐ近く、十条銀座のなかにありました」
こいしはペンを走らせた。
「東京にも十条ていう駅があるんですね。初めて聞きましたわ。どの辺ですか」
こいしがタブレットを香織に向けた。
「ここが赤羽で、少し南にあるのが十条の駅です。駅前ののんびりした雰囲気が好きだったので、仕事場のある渋谷から赤羽に帰る途中、よく寄り道してたんです。〈南海飯店〉は十条銀座に入ってすぐ、そう、この辺にありました」
ディスプレイをなぞっていた香織の指が止まった。
「えらい遠いとこまで大変ですねぇ」
言いながら、こいしがノートにメモした。
「地図で見るとけっこう離れているみたいですけど、埼京線の快速に乗れば、渋谷から赤羽までは二十分ほどですし、十条だと十五分くらいなんです」
「それやったらいいですね。京都に住んでると、電車で移動する距離感がよう分からへんのですわ。京都の地下鉄ていっつも空いてますけど、東京の通勤電車てたいへんなんでしょ? テレビとかで見てたらたいていすし詰め状態みたいやし」
「はい。でもそんな満員電車から降りてしばらく歩くと、店の明かりが見えてくる。おばちゃんのお店はオアシスのような存在だったのです」
香織は笑っているのか、怒っているのか、どちらとも判別できないような表情を浮かべている。
「肝心のチキンライスですけど、どんなんでした? ケチャップ味のふつうのチキンライスでしたか? それともなにか変わったもんが入ってたとか? 中華ふうのチキンライスでした?」
こいしが矢継ぎ早に訊いた。
「それがよく覚えていないんです。食べはじめたときにいきなり言いだされたので、味わう余裕なんてありません。頭が真っ白になってしまっていて」
「そらそうですよねぇ。そんな話を聞かされながら冷静に味わって食べられるわけないわ」
「ただひとつだけ記憶に残っているのは、ふつうのチキンライスみたいに赤くなかったことです。ほんのり赤いというか、どっちかっていうとピンクに近かったような気がします。と言ってもおぼろげな記憶ですけど」
「ピンクのチキンライスかぁ。なんか美味しそうな気がします。味なんかは覚えてはりませんよねぇ」
「はっきりとは覚えていないんですが、わたしの好物のチキンライスとはぜんぜん違う味でした。かすかに甘酸っぱい味がしたような気もします。あとは鶏肉がごろごろとたくさん入っていたかなぁ。それぐらいしか覚えてなくて」
香織が天井をぼんやりと見つめている。
「うちもチキンライスは好きやけど、お肉はこま切れがちょこっと入ってるぐらいで、あとはタマネギとかグリンピースとかばっかりていう印象ですわ。お肉がごろごろ入ってるチキンライスなんて一回も食べたことない」
「ふつうはそうですよね。おばちゃんは中華料理しか作ったことがないから、チキンライスがどういうものか分からなかったんじゃないでしょうかね」
「街の中華料理屋さんて、おじさんが作ってはるもんやと思うてました。おばちゃんて珍しないですか?」
「おばちゃんの身の上話も聞かされてたんですが、子どものころに中国から移住してきたらしいんです。最初は和歌山に住んでたのが、両親が離婚してから東京へ働きに出てきて、中華料理屋さんのご主人と結婚したんだけど、五年ほどで別れてしまって、自分で店をやるようになった。そう言ってました」
「中国から来てはったんか。苦労してはったんやなぁ、おばちゃん」
「苦労話はあんまり好きじゃなかったみたいで、愉しかった思い出ばかり話してくれてました。和歌山の紀(き)ノ川で泳いでいて溺れかけた話とか、別れたご主人が酔っぱらって、裸で歩道橋で寝てしまい警察に連れていかれた話とか、ユーモアたっぷりに話してくれるから、お腹の皮がよじれるほど笑いこけて」
香織は当時を思いだして目を細めている。
「ええおばちゃんやないですか。もう一回話をしはったらよかったのに」
最初に香織から話を聞いたときから、少しずつこいしの印象が変わっていった。世話焼きおばさんにありがちな、余計な口出しかと思っていたが、どうやらそうではなさそうだ。
「今も独身やていうことは、当時恋人やった、そのお相手とはうまくいかへんかったんですよね。そこのところも聞かせてもろてもよろしい?」
こいしが遠慮がちに訊いた。
「そこもちゃんとお話ししないといけませんよね」
口をつぼめた香織がためいきをついた。
「差しつかえのない範囲でいいですし」
こいしはノートを繰って、綴じ目を手のひらで押さえた。
「埼玉の大学を出てすぐ、東京に住むようになりました。今とおなじところです。勤め先は今の店と違って渋谷の大きなデパートでした。最初に配属されたのが紳士服の売り場で、彼とはそこで知り合いました」
「同僚やったんですか?」
「いえ。お客さんです」
「お客さんにナンパされはった?」
「まぁ、そうなりますね。ネクタイの柄を選んでくれと頼まれて、奨めたらシャツも一緒に買ってくれて。いいお客さんだなぁと思っていたら、次の日もまたベストを買いに来てくれて。一度お茶でもと誘われたんです」
「それからお付き合いがはじまった。見初められたいうことですね。どんな人やったんやろ。写真とか残ってへんのですか?」
「いつか削除しなきゃと思いながら、なかなか消すことができなくて」
遠慮がちなようで、誇らしげにも見える様子で、香織がスマートフォンの画面を見せた。
「絵に描いたようなイケメンさんですやん。ええスーツ着てはるけど、お仕事は何を?」
「そのころIT関係の仕事をはじめたばかりでした」
香織の目が輝いた。
「完璧にツボですね。イケメンでIT関係の仕事ていうたら、女優さんらの憧れですやんか」
こいしはノートにイラストを描きつけている。
「正直わたしにはよく分かりませんでしたが、会うたびにいっぱい夢を語っていました」
「うちも実はよう分かりませんねん。そもそもITて何なん? てお父ちゃんに訊いたら、インフォメーション・テクノロジーの略や、て言われて、よけい分からんようになりましたわ」
こいしにつられて香織も笑ったが、そのあとは急に黙りこくってしまった。
「続きを聞かせてもろてもよろしい?」
しばらく沈黙が続いたあと、上目遣いに香織の顔を覗きこんで、こいしが口を開いた。
「付き合いはじめたころは夢中でした。素敵な男性と出会えたねと同僚や友人にもうらやましがられてました。でも、正直に言うと少し疑っていたんです。こんな男の人なら、それこそ女優さんだとかモデルさんなんかと付き合っててもおかしくないし、なんでわたしなんかと、とも思いました」
「そう言われたらそうかもしれませんけど、香織さんかて充分魅力的な女性ですやん。彼はきっとそこまで見抜いてはったんやと思いますよ」
「ありがとうございます。友だちもそう言ってくれてたのですが、やっぱりどこか心の片隅では疑っていました。そんなときに、完全に疑いを払しょくするできごとがあったんです」
香織はお茶を吞んでひと息入れてから続ける。
「イタリア料理のお店でデートをした帰り路でした。わたしを送るのに渋谷駅に向かって歩いているときに、道端でしゃがみこんでいるおじいさんを彼が見つけて声を掛けたんです。ご気分が悪いんですか、と。そしたらそのおじいさんが言うには、財布をすられて困っている、家に帰れないということでした。気の毒に途方に暮れてましたが、彼はためらうことなく自分の財布から十万円ほどのお札を無造作につかんで、おじいさんにわたしたんです。おじいさんは涙を流さんばかりに喜んでましたが、彼はよかったよかったと言って、すぐに立ち去ろうとしたんです。おじいさんは彼に名前を聞かせてくれと言ったのですが、名乗るほどの者でもないと言って、彼はそのままさっさと歩いていきました。ときどきニュースでもそんな話を聞きますが、まさか彼がそんなことをするとは想像もしていなかったので、驚いたのと、それから彼を疑うことをきっぱりやめたんです」
「ほんまにかっこええんや。お話を聞いただけで惚れてしまいますわ」
「それから鎌倉や京都へも一緒に旅行しましたし、週末はかならず彼と一緒に過ごすようになりました。〈南海飯店〉のおばちゃんから言われたあともまったく変わらないどころか、ますます付き合いは深くなりました。やっぱりあのおばちゃんの言うことに耳を貸さなくてよかった、そう思っていました。おばちゃんから言われた日からちょうどひと月経ったときでした。彼からお金を貸して欲しいと頼まれたんです」
「IT関係の仕事してはったらお金持ちなんと違うんですか」
「彼が言うには仕事の規模を拡大するために、買収したい会社があるのだけど、実績がないから銀行が融資してくれない。確実に利益の上がる会社の買収だから、半年後には二倍にして返すから。そう言われて」
「どんな会社かしらんけど、買収するとなったら、けっこうなお金が要るんと違います?」
「五千万円必要で、自己資金や友人たちから借りたお金でなんとか四千万集まった。あと一千万なんとかしてくれないかって」
香織が重い冬空のように顔を曇らせた。
「い、一千万」
こいしが声を裏返した。
「もちろんわたしはそんな大金を持っているわけがありませんし、断ろうと思ったのですが、哀しそうな彼の顔を見ると、なんとかしてあげたいという気持ちが勝ってしまったんです」
「いや、うちもその気持ちは分かりますけどね、けど一千万てはんぱな金額と違いますやんか」
「倍にして返してくれるからと親を説得して、なんとか工面してもらいました。母親は猛反対したようですが、最後は父が貯金を取り崩してくれて……」
最後が涙声になったのは、きっと香織が後悔しているからなのだろう。続きを訊くのは酷なような気もするのだが。
「親てほんまにありがたいですね」
こいしの言葉に香織は何度もうなずいた。
「いつもデートに連れていってくれるお店は、素敵なレストランばかりだったし、オシャレな格好してるので、お金持ちだと信じて疑いませんでした。いえ、お金持ちだから付き合っていたとか、そういう意味じゃありませんよ。でも、お金ってないよりあるほうがいいし、格好が悪いよりは良いほうがいい。その程度のことだったんです。結婚して将来お金で苦労するのは嫌だったけど、大金持ちの奥さんになりたいなんて、これっぽっちも思っていませんでした。そして困った人がいれば平気で自分の有り金をわたしてしまう。そんな彼をわたしも見習わなきゃ、そう思ったんです。人から見ればおかしいかもしれませんが」
香織は自分に言い聞かせるように言葉を並べた。
「ふつうの感覚やと思いますよ。相手を信じるていうか、信じたいですよね。彼はそれに応えてくれはったんでしょ?」
こいしの問いかけに、香織はまた口を閉じてしまった。
二度、三度とため息を繰り返したあと、おもむろに語りはじめた。
「振込をすると税務上ややこしくなるから現金にしてほしいと頼まれ、デートの場所にお金を持って行きました。そんな大金を手にしたことがないので、真冬なのに汗だくになりました。震える手で紙袋に入れたお金を渡すと、彼はそれを抱えてお手洗いに行きました。たしかめに行ったのでしょう。戻ってきた彼はわたしの手を両手で包みこんで、涙を流しながらお礼を言ってくれました。よかった、わたしはだまされていたんじゃなかった、ともらい泣きしてしまいました」
「よかったですやん」
相槌を打ちながらも、話はこのまま終わらないだろうと、こいしは表情を変えなかった。
「それからちょうど一週間後でした。彼が夕食をご馳走すると言って、六本木のお鮨屋さんへ連れて行ってくれました。紹介制らしく芸能人とかがお忍びで来る店だと彼が言ってました。トロやアワビやウニなんかの高そうなお鮨をいっぱい食べて、ワインも飲んで、お勘定はいくらぐらいになるんだろう。ひょっとしてわたしに払わせるんじゃないかと思ってたら、彼がすんなりと現金で払いました。横目で見てた感じでは十数万円だったように思います」
「東京のお鮨屋さんて高いんですね」