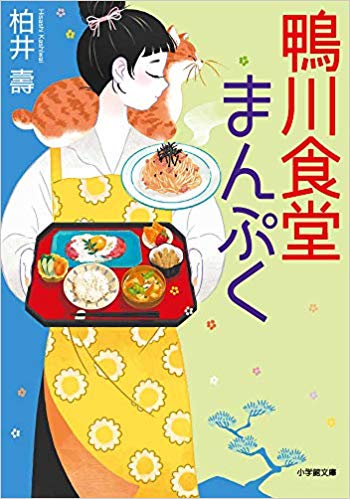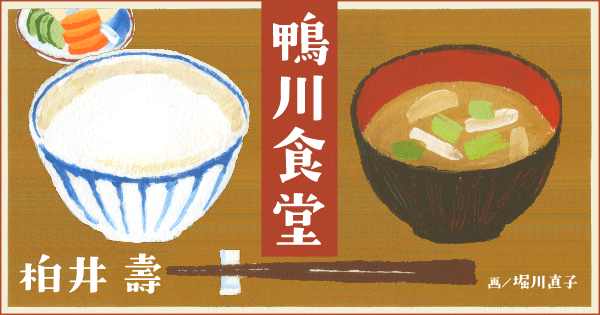「鴨川食堂」第40話 ハムカツ 柏井 壽

あなたが探したい、思い出の食べものはなんですか?
第40話 ハムカツ
1.
新幹線が京都駅に着いたというのに、米山清三(よねやませいぞう)はまだ迷っていた。それを捜しだすことにどんな意味があるというのか。
手のなかの切符は京都までだが、このまま新大阪まで行ってもいい。
いっそ博多まで行ってしまえば、フグでもアラでも、この時季ならではの旨いものがたくさん待っている。向こうの料理人仲間とバカ騒ぎしながら博多の夜を愉しむのも悪くない。
いや、やっぱり初志貫徹だ。発車のベルが鳴りはじめると同時に、清三はバッグをひったくるようにして席を立ち、小走りで新幹線から降りた。
日帰りのつもりだったから小ぶりのトートバッグひとつ持って、東京の自宅を出たのは朝八時過ぎだ。朝食を摂るひまもなかったせいで腹は減っている。
地図で見るかぎり京都駅から『鴨川(かもがわ)探偵事務所』までは歩いて十分ほどだ。烏丸(からすま)通という京都のメインストリートを通って行くのだから、目についた店に入ればいいだろうが、駅ビルのテナントのほうが無難なような気もする。いつからこんな優柔不断な性格になったのだろうか。ほとほと自分でも嫌気がさしている。
ガラスに映り込んだ自分の姿に、清三は思わず目をそむけた。
黒のダウンコートにダメージジーンズ、トートバッグにショートブーツ。どれもファストファッションだ。人一倍ファッションには気を遣うほうだったのが、いつの間にか楽なスタイルを選ぶようになった。すべてのエネルギーを料理に費やすようになったからだ。
スマートフォンで軽いブランチによさそうな店を検索すると、次々と店が出てくるがどこも気を引くにはいたらない。
そう思って歩いているとパン屋が目に入ってきた。『志津屋』と言えばたしか、古くから京都にある店だ。テレビのバラエティ番組でも紹介されていた〈カルネ〉と名付けられた惣菜パンが旨そうだ。これで小腹を満たしておいて、うまくいけば『鴨川食堂』なる店でも食べられる余地が残る。
「カルネふたつください。袋は要りません」
こんなときにダウンコートはありがたい。両側のポケットに一個ずつ〈カルネ〉を放り込み、地図を見ながら地下道を出て北に向かって歩く。
京都というのは本当に寒いところだ。マフラーで首を隠し、両手をコートのポケットに突っ込んで、〈カルネ〉を握りしめても、自然と身震いしてしまう。
地図ではもっと遠いように見えたが、どうやら目指す『鴨川探偵事務所』はすぐ近くのようだ。烏丸七条の交差点を北へわたり、公園でもないかと捜してみたが、まるで見当たらない。向かい側には大きなお寺が並んでいるのだが、寺の境内でパンをかじるというのは、いかにも行儀が悪い。かと言って歩きながら食べるわけにもいかない。
どうしたものかと案じるうちに、とうとうそれらしき場所まで来てしまった。おそらくここに違いない。モルタル造の二階家。暖簾も看板も出ていないが、辺りに食べものの匂いが漂っている。こうなったら入るしかない。ふたつの〈カルネ〉をトートバッグに入れ、玄関の前に立ってゆっくりと引き戸を開けた。
「こんにちは。どなたかいらっしゃいますか」
しんと静まり返った店のなかに低い声が響く。
カウンターがあり、テーブル席もある。間違いなくここは『鴨川食堂』だろう。奥なのか二階なのかは分からないが、この建家のどこかに『鴨川探偵事務所』もあるはずだ。今の今まで人が居た気配があるものの、返事は返ってこない。出汁の香りが漂っているだけだ。
「こんにちは」
さっきより少しだけ声を大きくしてみた。
「はーい。すぐ行きますよって、ちょっと待ってくださいね」
若い女性の声が返ってきて、清三はホッと肩の力を抜いた。
昼まではまだ時間がある。仕込みの最中なのか。それにしては静かだ。
デコラ貼りのテーブル、ビニール貼りのパイプ椅子。信州の田舎にもこんな食堂はあったが少しく趣きが違うのは、その端正な佇まいだ。コミックや雑誌が積んであるわけではなく、壁にメニューも貼っていない。テーブルにもカウンターにもメニューブックらしきものはない。カウンターやテーブルを白木に変えれば立派な和食店になる。カウンターの奥に見える厨房も清潔に保たれているのがよく分かる。ステンレス貼りの壁も、そこにぶら下がる鍋もまぶしいほどに光っている。
「お待たせしました」
白いシャツに黒いジーンズ、黒いソムリエエプロンを着けた若い女性が現れた。
「突然おじゃましてすみません。食を捜してくれる『鴨川探偵事務所』はこちらでしたでしょうか」
「探偵のほうのお客さんやったんですか。うちが所長の鴨川こいしです」
「いきなり伺って捜してもらえるものなんですか?」
清三がおそるおそる訊いた。
「大丈夫ですよ。お腹のほうはどうです? 空(す)いてはるようやったら、先に食べてもろて、それからお話を訊くていう感じですねんけど」
「いいんですか? そいつは嬉しいなぁ。申し遅れました。僕は米山清三といいまして、東京でレストランをやっているんです」
清三は名刺を差しだした。
「港区元麻布……『ア・ロー』。フレンチのお店をやってはるんですか」
両手で受けとって、こいしがじっと見つめている。
「おいでやす。食堂の主人をしとります鴨川流(ながれ)です。どうぞおかけください」
「ありがとうございます」
清三はダウンコートをコート掛けに掛け、パイプ椅子に浅く腰かけた。
「『ア・ロー』っちゅうたら、二ツ星を取ってはるフレンチやったんと違いますかな。そんな二ツ星シェフにお出しできるような料理やおへんけど、よかったら召しあがってください。おまかせしかできまへんのやが」
「ありがとうございます。でも、その二ツ星シェフ、というのはやめてください。星の数がどうとか、に疲れてしまったものですから」
清三が深いため息をついた。
「苦手なもんはおへんか」
「なんでも美味しくいただきます」
「ほな、ちょっと待っとぅくれやっしゃ。旨いもんを見つくろうてきますわ。こんな店でっさかい、大したもんはできまへんけど」
和帽子をかぶり直して、流は厨房へ駆け込んでいった。
「お飲みもんはどうしましょ。いちおうワインとかもありますし、日本酒でも焼酎でもなんでも」
「日本酒を常温でいただけますか。ブランドはおまかせします」
パイプ椅子に座ったまま、清三はあらためて店のなかを見まわしている。
「すぐにお持ちしますよって」
こいしが流に続いた。
こんな気楽な店で料理を作るのも悪くないなと清三は思った。いや、やっぱり違う。店構えはグランメゾンふうでありながら、素朴な料理を出すほうがサプライズは大きい。仕事も人間関係も、なにもかもに迷っていて、なにひとつ決断できない自分に、ずっと清三はいらだっている。
「先にお酒をお持ちしました。〈秀鳳(しゅうほう)〉ていう山形のお酒なんですけど、常温で飲まはるんやったらこれがええ、てお父ちゃんが言うてはるんで」
こいしが緑色の四合瓶をテーブルに置いた。
「はじめて見る酒です。純米酒。お米はつや姫を使っているんですね」
「うちも最近こればっかり飲んでますねん。吟醸と違うさかい香りも強すぎひんし、飲み口も甘ぅ感じるんで、ついつい飲み過ぎてしまうのが難点です」
こいしが染付の猪口にたっぷりと注いだ。
「辛口の吟醸酒ばかりがもてはやされて、日本酒の個性が失われているような気がしていたのですが」
清三がゆっくりと猪口をかたむけて続ける。
「こいつはいい。ちょっと酸味も利いていて、これなら和食だけでなく、どんな料理にでも合わせられそうですね」
大皿を両手で抱えて、流が厨房から出てきた。
「お待たせしましたな。腕利きのシェフに出せるようなもんやおへんけど、まぁ、話のタネやと思うてもろたら嬉しおす。さぶい時季でっけど、ちょっとだけ春を先取りしてみました。九品の大皿盛りですわ。左上の白磁の小鉢に入っとるのはタケノコの木の芽和え。歯ごたえのええ根っこだけを使うてます。その横はグジのフライ。柴漬けを使うたタルタルソースを掛けてます。その右の切子の杯にはハマグリのマリネを入れとります。ハーブの刻んだんを混ぜてもらえますか。その下、織部の小皿に載っとるのは才巻海老の酒蒸し。柚子胡椒がよう合います。真ん中の塗椀には穴子ちらしが入っとります。実山椒の煮たもんを添えてますさかい、それを載せてみてください。ええアクセントになる思います。その左のデミカップは牛タンの煮込み。辛子を付けてもろたらええと思います。お嫌いやなかったらパクチーも載せてください。その下は山菜の天ぷら。フキノトウ味噌を付けて食べてください。下の段の真ん中はウナギの白焼。刻みワサビを載せて、大葉で巻いたらさっぱりします。右端はトリ肝のソース煮。一味トウガラシを多めに振って食べてください。わしが好きなもんやさかい、酒のアテみたいなもんばっかりでっけど、かんにんしとぅくれやっしゃ。あとでご飯をお持ちしますんで声を掛けとぅくれやす。今日はアワビ飯を炊いとります」
一気に料理を説明して、流が清三に笑顔を向けた。
「いやはや。なんとも。どう言ったらいいのか。いったいこちらはどういうお店なんですか。僕は今日こうして突然伺ったのですから、そのために用意されたものではないわけですよね。つまり、いつでも、これだけの料理をスタンバイされているということですか? どうにも信じられないのですが」
両腕を組んで、清三が何度も首をかしげている。
「たまたま、ですがな。ご覧のとおりヒマな店でっさかい、自分の食いたいもんを仕込んどるだけです。お客さんがなかったら、これがまかないになるんですわ」
「お話はあとでよろしいやん。ゆっくり召しあがってもらわんと」
こいしが話に割って入った。
「そやな。お酒も瓶ごと置いときますんで、好きなだけ召しあがってください」
ふたりはそそくさと下がって行った。
ひとり食堂に残った清三は、大皿をにらんだまま微動だにしない。黒目だけが気ぜわしく動き、ひとつひとつの料理を凝視している。
たいして暖房が効いているわけではないのに、清三の額には汗がにじんでいる。箸を取り、料理に手を付けようとかまえてはいるが、皿にまで箸が届かない。
箸を置いた清三は猪口に手を伸ばし、四合瓶から酒を注いだ。
口を湿らせるように酒を飲んで、清三はようやく料理に箸を付けはじめた。
最初はウナギの白焼だ。流の指示どおり、刻みワサビを載せて大葉で包んで口に運ぶ。皮はパリッと芳ばしく、身はふんわりとやわらかい。川魚特有の臭みはまったくなく、串の跡から推測すると炭火を使った焼きたてだろう。まさかこんな小さな切り身だけを焼いたのではなかろう。とすれば残りのウナギはどうしたのか。
次に箸を付けたグジのフライにも驚かされた。揚げたてのグジはウロコが立っていて、皮目にはコロモを付けず揚げたようだ。甘みを抑え、酸味を利かせたタルタルソースも旨い。揚げ油はなんだろう。植物性であることは間違いないが、ふつうのサラダ油ではこれほどのコクが出ない。
九品のうち、たったふた品食べただけで、鴨川流という料理人の腕前に怖れすら感じてしまう。
清三は自分のレストランを振り返ってみた。自分を含めて六人の料理人がいるのだが、こんな短時間にこれだけの質の料理を出せるかと問われれば、瞬時にNOと答えざるを得ない。
ならばかつての店。自分ひとりで何もかも切り盛りしていた、カウンター五席だけの店。あのときならできただろうか。答えを出すのに時間は掛からない。絶対に無理だ。
余計なことは考えず、食べることだけに集中しよう。そう決めて、清三は猪口の酒を一気に飲みほした。