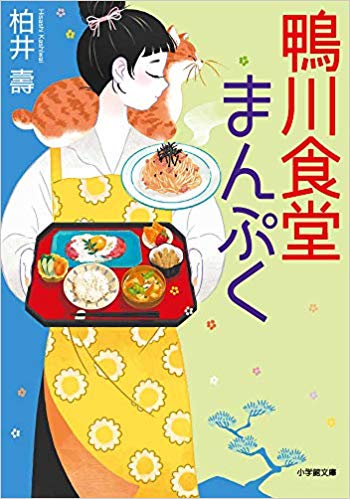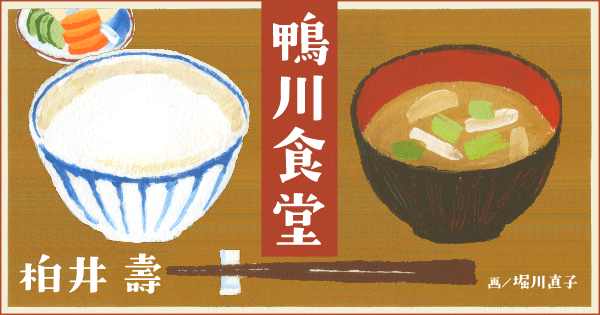「鴨川食堂」第40話 ハムカツ 柏井 壽

あなたが探したい、思い出の食べものはなんですか?
第40話 ハムカツ
「緊張してはります? リラックスしてくださいねぇ」
「こういう機会はめったにないので、どう話していいか」
清三が頭をかいた。
「米山さんてまだ四十八歳ですよね。中学を卒業しはったころていうたら、今から三十三年前ですやん。そのころやったらたいていは高校までふつうに行ってたんと違うんですか」
「ふつうはそうでしょうね。うちはとくべつ貧しかったんだろうと思います。叔父から聞いてはじめて知ったんですが、オヤジは借金の連帯保証人になっていて、破産した友人の肩代わりをさせられたらしいんです。その心労もあってか、両親とも早くに亡くなりましたし、実家は人手に渡ってしまいました。そんな育ちですから兄弟姉妹も散り散りばらばらで、一堂に会するなんて機会も今までまったくありませんでした。叔父も僕が東京に出ていくのを見届けるように、すぐ亡くなったそうです」
「そうやったんですか。お気の毒に。すんません。失礼なこと言うてしもて」
「いいんですよ。本当のことですから」
「帰る故郷もないし、身内もいいひん、て寂しいんと違います?」
こいしが訊いた。
「天涯孤独っていうのも悪くないですよ。冠婚葬祭に煩わされることもないし、帰省なんていう面倒もないしね。唯一お墓参りに行くのが帰郷ってことになるのかなぁ。実家があった場所は避けて通りますけど」
清三が浅いため息をついた。
「お茶でも淹れましょか。コーヒーかお茶かどっちがよろしい?」
「じゃあコーヒーをいただきます」
立ちあがって、こいしがコーヒーマシンをセットした。
「ふつうの高校生やったら、親元を離れて暮らすのはつらい思うんですけど」
「叔父はとてもいい人で、ときどき食事に連れて行ってくれたんです。田舎街ですから今にして思えば、飛びきり美味しいものばかりではありませんでしたが、それでも僕にはどれもごちそうでした」
「また要らんこと言いますけど、今の二ツ星シェフとはあんまりにもイメージが違いすぎて、信じられへん気がします」
こいしが清三の前にコーヒーを置いた。
「そんなもんですよ。子どものころというか、若いときに旨いものを食えなかったのでシェフになった、っていう料理人はけっこういますよ」
「そういうもんかなぁ。けど、ものすご料理を勉強せんとあかんかったんと違います?」
「一からですからね。学校の勉強はまったくしませんでしたが、料理の勉強は死に物狂いでした」
清三はコーヒーをひと口飲んで、ソファにもたれかかった。
「好きこそもののじょうずなれ、ていうのは、こういうことを言うんですやろね。で、そろそろハムカツの話をお願いしてもよろしいやろか」
「叔父には、いろんなお店に連れて行ってもらったのですが、一番衝撃を受けたのが洋食屋のハムカツなんです。世の中にこんな旨いものがあったのか。そう思ったのがきっかけで僕は料理人を目指すようになったんです」
「それもまた意外やなぁ。二ツ星シェフの原点がハムカツやったなんて。どんなんやったんやろ。めっちゃ興味あります」
こいしはノートにハムカツのイラストを描きつけている。
「ふつうのハムカツですよ。薄いし、上等じゃないし」
「そういうのが美味しいんですよね。ウスターソースをたっぷり掛けて」
「そうそう。添えてある千切りキャベツがまた美味しくてね。よくこんなきれいに切れるなと。シャキシャキしていて」
「ほんまにふつうのハムカツでした? なんか特別のんやったとか」
「ふつうのハムカツだったのですが、僕には特別なものでした。ひとにたとえるなら、初恋という感じでしょうか。そのハムカツを食べた瞬間、雷に打たれたような気がしました。親元にいるときは貧しいのがふつうでしたから、多少ひもじくてもつらいと思ったことは一度もありませんでした。その理由のひとつに、旨いものを知らなかったということもあったんだと思います。だからハムカツを食べたとき、世のなかにこんな旨いものがあるとも知らずに十五年間生きてきたんだ、って、とても哀しくなってしまったんです。食べてるうちに涙をこらえられなくなってしまいました。叔父が不思議がっていたので、辛子を付け過ぎたとごまかしました。そのとき思ったんです。誰もが子どものころから、美味しいものを食べられるような世のなかにしたい。そう言うと政治家志望みたいに思われるかもしれませんが、それは絶対無理なので、料理を作る側にまわろうと思いました」
清三はゆっくりとコーヒーを飲んだ。
「十五歳からの夢を叶えはるて、すごいことですよね。尊敬しますわ。けど、そのハムカツを食べてなかったら、シェフになってはらへんかったかもしれへんのですよね。そのハムカツもエライ」
「そうなんですよ。ずっとそのことを忘れてしまっていたのですが、最近それを思いだしてしまって」
「もうちょっとヒントが欲しいとこなんですけど。なにかあります?」
こいしがペンをかまえた。
「お店なんですけど、大分駅から歩いて行ったので、駅の近くだと思います。その店で食事をしたあと、城址公園を散歩した記憶があるので、その辺りだったんじゃないかと」
「ちょっと待ってくださいね。今、地図アプリを開きますんで。大分駅、と。ここが駅ですね。そして城址公園、と。ここですね。駅とお城の址て近いんや。ということは、この範囲内にあったんでしょうね」
こいしがタブレットの地図を指でなぞった。
「そうなんです。短い時間でしたが、一年ほど前に僕もこの辺りを歩いてみたんです。でも、それらしき洋食屋は見つかりませんでした」
「京都でも、フレンチとかイタリアンはようけできますけど、むかしからの洋食屋さんは店仕舞いしはるとこが少のうないですわ。新しい洋食屋さんもできますけど、高い店ばっかりやし」
「すみません。僕らがいけないんですよね」
「そういう意味で言うたんと違いますよ。また余計なこと言うてしもた」
こいしがぺろりと舌を出した。
「いいんですよ。僕もおなじことを感じていますから。そもそも僕がハムカツを捜そうと思ったのもそこなんですよ」
「そこって、どこです?」
「今、僕が作っている料理って、本当に美味しいものなんだろうか。っていうところです。分かってもらえますか?」
清三がこいしに顔を近づけた。
「なんとなく分かったような気ぃもしますけど」
気おされて、こいしが身体をそらせた。
「美味しいものを食べて機嫌が悪くなる人って、絶対いませんよね。美味しいものを食べるとみんな笑顔になるし、それはしあわせってことだと思うんです。そのことを気付かせてくれたのがハムカツだったのに、それをすっかり忘れ去っていた。結果どうなったかというと、料理の評判ばかり気にするようになってしまったんですよ。グルメサイトの口コミや点数も気になるし、インスタやフェイスブックなんかのSNSで、どんなふうに書かれているかが気になってしょうがない。その代表が格付けガイドブックです。あの本の日本版ができたときから、どうやって星を取るか、ばかり考えるようになってしまった。そして幸運にも星を獲得したあとは、もうひとつ上のランクを目指し、最高位まで上り詰めたい、星を減らさないように、だけを目標にするようになってしまった。はたして今の僕の料理はひとを笑顔にしているだろうか。しあわせを感じてもらえているだろうか。疑問に思うようになったんです」
コーヒーカップを手にしたまま、口を付けずに清三は語り続けた。
「なるほど。だいぶ分かってきました。お父ちゃんもときどき、そういうようなことを言うてはります。もっと原点に帰らんとあかんて」
「お父さんは大丈夫ですよ。ちゃんと技を使いながら、技巧に走りすぎることもないし。心に沁みる料理を作ってらっしゃる。弟子入りしたいと思ってるんです」
清三が真顔で言った。
「そんなあほな。うちのお父ちゃんは我流で作ってはるだけやし、二ツ星シェフに教えるようなもんと違いますやん」
「だからその二ツ星シェフっていうのは……」
「そうでしたね。ついうっかり」
こいしが背中を丸めた。
「格下げされた夢をみて、何度うなされたことか数えきれません。とある星付きのカリスマシェフは、格下げを苦に自殺したと言われていますが、まんざらその気持ちが分からないでもありません」
「縁起でもないこと言わんといてください」
こいしがわざとらしく身震いしてみせた。
「もう一度、あのハムカツを食べれば原点に戻れるような気がするんです」
「分かりました。お父ちゃんに気張って捜してもらいます」
こいしがノートを閉じた。
「よろしくお願いします」
立ちあがって、清三が頭をさげた。
こいしの先導で、清三が食堂に戻ると流が待ちかまえていた。
「えらいお時間取りましたなぁ。お忙しいやろに」
「いえいえ。このあとは何も予定を入れておりませんし、ゆっくり話をさせていただきました」
「それやったらええんですが」
「この次ですけど、お父ちゃんはだいたい二週間ぐらいで捜しだしてきはりますので、そのころに連絡させてもらいます」
「承知しました。今日の食事代をお支払いさせてください」
「探偵料と一緒にこの次に」
こいしがそう言うと、清三は黙ってうなずいた。
「気ぃつけて帰っとぅくれやっしゃ」
流とこいしが店の表まで送りに出た。
「ありがとうございます。せっかくなので今日は京都に泊まることにします」
「この時季の京都は旨いもんもようけありますさかいな」
「ホテルとかは決めてはるんですか」
「足の向くまま、気の向くまま。のんびりやりますよ」
清三は軽い足取りで正面(しょうめん)通を西に向かって歩きだした。
「何を捜してはるんや」
食堂に入ると、流がお決まりの問いかけをした。
「ハムカツ」
こいしが短く答える。
「ハムカツかぁ。そう言うたら長いこと食うてないな」
「食べたときは美味しいさかい、すぐにまた食べたいて思うんやけど、いつの間にか忘れてしもうて、一年とか二年経ってる。ハムカツてそういうもんやね」
「たしかにそうやな。で、米山はんが捜してはるのは、どっかの店のか?」
「大分の駅前にあった洋食屋さんで食べはったハムカツ」
「あった、っちゅうことは今はもうないんやな」
「一年ほど前に自分で捜しに行かはったらしいんやけど、それらしい店は見つからへんかったみたい。三十年以上前のことやさかい、お店が無くなってても不思議はないなぁ」
「大分の洋食屋……」
流が小首をかしげた。
「なに? なんか思い当たることがあるん?」
テーブルを拭きながらこいしが訊いた。
「ハムカツてなもんは食堂やとか、居酒屋で出すもんや。洋食屋でハムカツをメニューに載せるかなぁ」
流が腕組みをして考え込んでいる。
「そう言われてみたらそうやな」
こいしが片付けの手を止めた。
「とにかく大分へ行かんと。ついでに別府に行って温泉でも入ってくるか」
流が手を打った。
「うちも温泉だけ連れて行って」
「調子のええやっちゃ」
流が鼻で笑った。