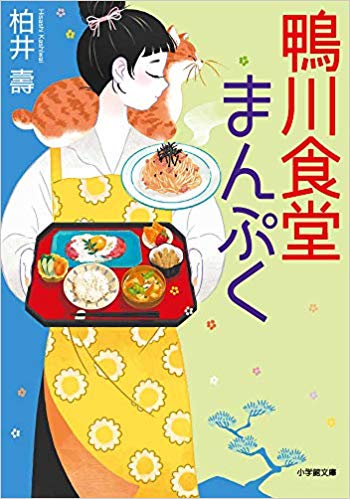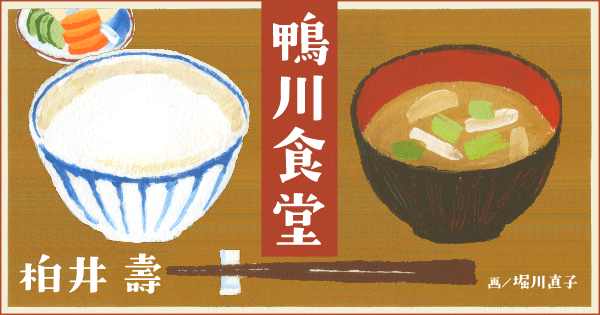「鴨川食堂」第40話 ハムカツ 柏井 壽

あなたが探したい、思い出の食べものはなんですか?
第40話 ハムカツ
2.
降り立った京都駅のホームには生ぬるい空気が漂っている。清三は季節が一歩進んだことを実感した。
春はすぐそこまで来ているのに、清三の胸の内は真冬並みの寒気に占領されている。
この二週間ほどで何かが変わったかと自問すれば、また答えに迷ってしまう。トンネルの向こうに、進むべき道が開けているような気がする反面、またすぐに次のトンネルが待っているようにも思えてしまう。
京都駅を出て京都タワーを見上げた清三は、トレンチコートの襟を立てた。都大路にはまだたっぷりと冬が残っているのだ。
今回は地図を見ることなく、迷わず目指す『鴨川食堂』の前に立てた。
「こんにちは。米山ですが」
引き戸を開けた瞬間、芳ばしい香りが鼻先をくすぐった。
「おこしやす。お待ちしとりました」
作務衣姿の流が茶色の和帽子を取って出迎えた。
「ありがとうございます。頼んでおいて言うのも何ですが、本当に二週間で捜しだされるんですね。驚きました」
トレンチコートを脱いで、清三は慣れた手つきでコート掛けに掛けた。
「こない言うたら何ですけど、今回は思うてたより早いことたどり着けました。米山はんの記憶が正しかったおかげですわ」
「ということは、やはりあの辺りにお店があったんですね」
「お話はあとにして、まずは食べてみてもらいまひょ。すぐにご用意しますわ」
和帽子をかぶり直して、流が厨房に戻って行った。
「おこしやす。今日はお酒はどないしましょ」
入れ替わりにこいしが出てきた。
「しっかり味わいたいので、今日はお茶にしておきます」
「あのハムカツやったらビールもよう合うんやけどなぁ」
「じっとがまんします」
清三が唇をまっすぐに結んだ。
「急須ごと置いときますよって、たっぷりと飲んでくださいね」
こいしがいたずらっぽい笑顔を清三に向けた。
厨房からは何かを油で揚げる音が聞こえてくる。前回通りがかったときに横目で見たが、フライヤーはなかったようだ。フライパンか鍋か、どちらで揚げているのだろう。油は何を使っているのか。厨房を覗いてみたい衝動にかられるのは料理人の性だ。
リズミカルな包丁の音が聞こえる。キャベツを千切りしているに違いない。
「ご飯があったほうがええやろ、てお父ちゃんが言うてますのでお持ちしました。要らんかったら残してください」
銀盆に載せて、飯茶碗と汁椀をこいしが運んできた。
「残すだなんて。あらかじめ頼んでおけばよかったと思っていたぐらいです。喜んでいただきますよ」
清三は飯茶碗と汁椀のなかを交互に覗きこんだ。
「お汁はタマネギとジャガイモのお味噌汁です。ご飯は少なめに盛ってますんで、足らんかったら言うてください。もうすぐ揚がる思います」
こいしが厨房を振り向いた。
「実は、おみおつけで一番好きな具がタマネギとジャガイモなんです。子どものころは毎日このおみおつけでした」
料理を載せた盆を両手で持って、流が厨房から出てきた。
「そら、よろしおした。おかずがハムカツやったら、きっとこの味噌汁が合うやろと思うたんです。これが捜してはったハムカツです。キャベツの千切りとマカロニサラダを添えときました。このソースをたっぷり掛けて召しあがってください。和辛子も置いときますさかい、お好みで付けて食べとぅくれやす」
流は清三の前に銀皿を置き、盆を小脇に抱えたまま一礼した。
「ありがとうございます。記憶がたしかではないのですが、なんとなくこんな感じだったと思います」
清三は目を輝かせて皿の上を見まわしている。
「どうぞごゆっくり」
流とこいしは厨房に戻っていった。
味はまだ分からないが、少なくとも見た目はあの日食べたものとおなじだ。楕円形の銀皿にたっぷりと千切りキャベツが敷かれ、その上に半円形のハムカツが重なり合っている。
両手を合わせた清三は箸でハムカツをつまみあげた。
薄い一枚のハムを半分に切ってからコロモを付けて揚げている。六切れあるからハムが三枚ということになる。大分で食べたときはもっと量があったようにも思うが、それもたしかな記憶ではない。
いきなりソースを掛けるのは料理人に対して無礼だとよく言われるが、清三はまったく気にならないほうだ。客が食べたいようにして食べればいい。
『ア・ロー』でも、ローストビーフにグレービーソースではなく、醬油とワサビで食べたいとリクエストする客がいるが、快くそれに応じている。
ソース瓶に入ったウスターソースをハムカツにまわし掛け、ついでにキャベツにもたっぷりと掛けた。
和辛子を米粒ほど載せ、ハムカツを口に運んだ。
実に旨い。ハムはむかしふうの、俗に言う赤ハムを使っている。コロモのパン粉は生ではなく、いくらか粗目のものだ。ウスターソースはおそらく既製品だろうが、酸味が利いていてハムカツにはぴったりだ。
あわてて白ご飯を口に入れる。清三の好みはもう少し硬めに炊いたご飯だが、こうして食べるにはやわらかめのほうが合うのだろう。
ふた切れ目は千切りキャベツを包むようにし、ご飯に載せて一緒に口に入れた。これだ。この味だ。思わず笑ってしまう。吞み込むのが惜しい。ずっと口のなかで味わっていたい気になる。
おみおつけをひと口飲んで、胸に手を当ててみた。
これからの料理人人生は、こういうものと向き合っていきたい。
今『ア・ロー』で出している料理は昼のコースが二万円からで、ディナーは三万円からだ。上客はいいワインも飲んでくれるから、夜はひとり当たり五万円ほどになる。下世話な話を承知で言えば、このハムカツなら千円も取ればひんしゅくを買うことになるだろう。へたをすると売上は今の一割にすら届かないだろうし、もちろん星など論外だ。会社も解散してスタッフも整理しないといけない。一からのスタートだ。そこまでの勇気が自分にあるのか。もっと言えばそこまでする必要があるのか。いっときの気の迷いであって、後悔するに決まっている。
だが、このまま今の料理を続けていくことにどんな意味があるというのか。
生まれ育った自分の境遇を振り返ってみればすぐに分かる。『ア・ロー』を訪れている客は特別な存在だ。一夜のディナーにふたりで十万円を平気で払う客のなかに、自分の両親などいるわけがない。大分の叔父夫婦しかり。勤めていた家具工場の社長はどうだろう。あり得ない。夜間高校の同級生たちは言うまでもない。いや、ひょっとして事業を成功させて、六本木あたりのタワマンに住んでいるヤツもいるかもしれない。仮にそうだとしても、さんざんお金に苦労してきたはずだから、そんな贅沢はせず、堅実に暮らしているに違いない。マモル、フジト、コウスケ、ヒロシ、順に顔を思い浮かべるうち、不意に涙があふれてきた。
成りあがってきたことに、ずっと誇りを感じて生きてきた。人一倍努力してきた結果のサクセスストーリーは、長く世間の注目を浴びてきたし、それは快感をともなって自信につながった。
三切れ目のハムカツを食べたあと、おみおつけに箸を付けた。
中学を卒業するまで、毎朝これを食べていた。ご飯と漬物、そしてタマネギとジャガイモのおみおつけ。それ以外の朝食を食べた記憶がない。だから、なんの疑いもなく、おみおつけは、タマネギとジャガイモの味噌汁のことだと思っていた。
タマネギはとろける寸前で、ジャガイモも箸でつまむと崩れそうにやわらかい。野菜のとろみで和風ポタージュのようになっているのも、子どものころに食べたのとまったくおなじだ。
あの洋食屋で食べたときのハムカツにライスは付いていたが、スープやおみおつけが付いていたかどうかは記憶にない。だが、もしも付いていたならこれ以外には考えられない。それほどに相性がいい。
前回は流の料理に目をみはり、どんな食材を、どう調理したのかに気を引かれてしまったが、今日は何も考えず、素直に料理を味わうことができている。
マカロニサラダを忘れていた。皿にたまったソースを和えて口に入れた。
思ったとおりの味だ。刻んだハムやキュウリとマカロニをマヨネーズで和えただけのもので、ご飯のおかずにもなってしまうほど味が濃い。
「どないでした? こんなんで合うてましたやろか」
流が厨房から出てきて、清三の傍らに立った。
「はい。たぶんこんな感じだったと思います。味までははっきり覚えているわけではありませんが」
不意を突かれて、清三はあわてて小指で目尻をぬぐった。
「ハムカツはハムカツでっさかいなぁ。味に大差はおへんやろ」
「定食屋さんや居酒屋でハムカツがメニューにあると、たいてい食べてみるのですが、こんな味ではなかったです。店のまかないとして作ってみたこともありますが、まったく別ものになってしまいました」
「そら、そうですやろ。今はみな気張って作らはりますけど、そない力入れるもんやない。元々が、ハムカツてなもんは、お肉が贅沢やったころに、肉の代用品としてハムを使うたんで、上等のハムを使うたり、ええ揚げ油を使うたりしたら別もんになってしまいますがな。今の時代は食材にしても調味料にしても、ええもんを選んだら美味しなると、みなが思いこんでまっけど、むかしは手近にあるもんをどう生かすか、を考えて料理したもんです。ハムカツはその典型ですわ」
「どう生かすか……」
清三が流の言葉をオウム返しした。
「ちょっと座らせてもろてもよろしいかいな」
「気が付かずに失礼しました。どうぞおかけください」
清三が中腰になった。
「ほな失礼して」
テーブルをはさんで、流が清三の向かいに座ると、すかさずこいしが流の湯吞に急須の茶を注いだ。
「どんなふうに捜しだされて、このように再現されたのか。教えてください」
テーブルに両手を突いて、清三が頭をさげた。
「ご想像どおりやろう思いますけど、まず大分に行きました。米山はんの記憶に従うて、駅前から城址公園辺りを隈のう歩きましたんやが、おっしゃってたように、それらしい洋食屋はありまへんでした。っちゅうか、それはわしの思うてたとおりで、もともとそんな洋食屋はなかったんや思います」
「幻の店だったということですか?」
清三がわずかに気色ばんだ。
「京都は洋食屋の多い土地なんやけど、むかしからの洋食屋にはハムカツがメニューに載ることはめったにない。裏メニューで出してるとこもあったかもしれまへんけど、ふつうの洋食屋にはハムカツはない。それはおそらく大分でもおなじやないかと思うて、古ぅからある大分の洋食屋はんで訊いてみたんやが、やっぱりそうでした。さいぜん言うてはったように、ハムカツをメニューに載せてるんは食堂やとか居酒屋ですわ。せやから米山はんが叔父さんに連れてもろうてハムカツを食べはったんは定食屋はんか大衆食堂やないかと当たりを付けたんです」
「僕の頭のなかではハムカツは洋食、というイメージだったのでお店は洋食屋さんだと思いこんでいたんですね」
「今もちょこちょこそういう店がありまっけど、むかしの食堂ていうたら、いろんな料理を本格的に作っとったんですわ。麺類やら丼もんがメインやったとしても、洋食やら中華料理まできちんと料理しとった。米山はんがハムカツ食べはった店もそういうとこやった。せやさかい洋食屋はんとおんなじ銀皿にハムカツを盛ってはったんでしょうな。おそらく叔父さんはあなたにハムカツを食べさせようと思うて、その食堂に連れて行かはったもんやさかい、メニューも見んと注文しはった。それでこの銀皿が出てきたら洋食屋やと思うても不思議やない」
「なるほど。そういうことだったのですか」
清三が大きくうなずいた。
「ただ、残念なことにそのお店は今から二十年前に店仕舞いしてしまわはりました。『ひた食堂』ていうお店でしてな、こんなハイカラな外観でしたんや」
流がタブレットの画面を清三に見せた。
「そうか、レンガ建ての店だったから洋食屋だと思ったんですね」
「それもありまっしゃろな」
「この写真はどこで入手されたんです?」
「『ひた食堂』があった場所のすぐ近くに『岳尾屋(たけおや)食堂』っちゅう店がありましてな、ここは大正時代の創業という古い店ですねん。とり天が美味しいて聞いたもんやさかい、それを食べに行きがてらご主人に話を訊いたんですわ。『ひた食堂』のご主人と先代のご主人が友だちやったらしいて、いろいろ思い出話を聞かせてもらいました」