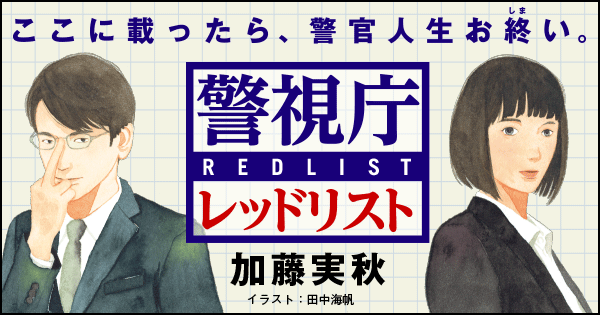〈第13回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

いよいよクライマックス!
CASE3 ゴッドハンド:神にすがる女刑事(5)
13
「続きは明日」と言って電話を切ったのに、一時間も経たずに慎から着信があった。みひろが出ると「奥多摩に出動です。今どちらですか?」と訊かれ、独身寮の近くで買い物中だと答えたところ、慎はすぐに車で迎えに来た。
カットソーにコットンパンツ、ジャケット。素材と仕立ては良さそうだし、色は全部ネイビーブルーだけど微妙に色目が違う。運転席でハンドルを握る私服姿の慎を、みひろは横目でチェックした。出動が板尾の事件絡みなのは明らかだが、詳細を訊ねてもお約束の台詞(せりふ)を返されるのは目に見えているので、つい余計なことを考えてしまう。慎の愛車は銀色のコンパクトカーで、今は中央自動車道を走行中だ。時刻は午後六時前で、外はまだ明るい。
と、スマホの着信音がして、慎はワイヤレスのイヤホンマイクをオンにした。
「阿久津です」
「柿沼だけど。阿久津さんに言われた通りにスーパーことぶきに行ったけど、河元はいなかった。奥さんの話じゃ、『具合が悪いと言って店を休みにしたのに、気がついたら家からいなくなってて、電話にも出ない』って」
隣に身を乗り出したみひろの耳に、柿沼の早口の声が漏れ聞こえてくる。前を向いたまま、慎は返した。
「恐らく、みのりの道教団の施設です。河元を発見しても、僕が到着するまで刺激せずに見張って下さい。加えて、波津広恵の動きも見逃さないように」
「波津さん? ねえ、何がどうなってんの? 教えてよ」
困惑した様子で柿沼が問う。みひろが見つめる中、慎は右手の中指でメガネのブリッジを押し上げ、答えた。
「できません。僕は予想や憶測でものを言わない主義なんです」
出た、お約束。うんざりし、みひろは息をついた。「はあ?」と声を上げた柿沼に慎は、「こちらの到着予定時刻は、午後七時四十分前後。それまで今の指示通りに行動して下さい」と告げ、柿沼は「あんた、何様? ……わかったよ」とぼやいて電話を切った。みひろは会話の内容から慎の考えを想像したが答えは出ず、そうこうしているうちにみのりの道教団の施設に着いた。時刻は午後七時四十三分。蒸し暑いが、都心よりははるかにましだ。
閉まっている門の前に停車し、慎は外に出た。みひろも続く。二人で大人の胸の高さほどの門扉を乗り越え、施設の敷地に入った。陽はとっぷりと暮れ、樹木が生い茂る敷地内は暗い。外灯が一つしかないアプローチを慎とみひろが小走りに進んでいると、前方で声と足音がした。三、四人の信者の男女がロータリーを横切って駆けて行く。明かりの点った懐中電灯を手にしている人もいた。
「どうしました?」
ロータリーに入り、慎は男女の後ろ姿に声をかけた。振り向いたのは最後尾の年配の男で、一昨日施設を見学した時に挨拶したのを覚えている。
「あなた、確か警察の──助けて下さい。あっちで刃物を持った男が、信者を人質にしているそうです」
再び駆けだしながら、年配の男は訴えた。「わかりました」と返して慎も同じ方向に駆けだし、みひろも倣う。前を行く男女に追いつき脇を抜ける時、年配の女がみひろに咎めるような視線を向けてきた。みひろの今日のコーディネートは、襟ぐりが大きく開いたハードロックバンドのTシャツに迷彩柄のロングスカート。黒革のバッグはボール形で、全体に鋲(びょう)状の飾り金具が取り付けられている。全員白い服の信者たちの中では、浮きまくりだ。
ロータリー脇の駐車場の奥には雑木林があった。駐車場の明かりを頼りに雑木林を進むと、十人ほどの信者の背中が見えた。みんな不安そうに前方を窺い、丹田集中ポーズを取っている人もいる。その間を縫い、慎とみひろはさらに進んだ。
視界が開け、樹木のない平坦な場所に出た。手前に数人の信者がいて、一人が持つ懐中電灯の明かりがその奥に立つ柿沼の黒ブラウスの背中と、向かい側の男女を照らしている。男は河元で、左手で自分の前に立つ波津の肩を摑み、右手で包丁を握って波津の首に突きつけていた。年配の男の話を聞いた時に想像した通りの状況だが、なぜこうなったのかがわからず、みひろは隣を見た。慎は深刻な顔で河元たちを見ているが、無言だ。
「なんでそいつらが来るんだよ。応援は呼ぶなって言っただろ!」
首を突き出してこちらを見て、河元がわめいた。懐中電灯の明かりで、その顔が汗だくで小さな目はつり上がっているのがわかった。一方波津の顔は、青ざめて引きつっている。 河元の言葉で慎とみひろの到着を察知したのか、柿沼は前を向いたまま返した。
「河元さん、違うって。この人たちは心配して来てくれたの。私があんたがどんなにいい人で、みんなに好かれてるか話したからね。何があったんだか知らないけど、仕方なくなんでしょ? 教えてよ」
口調や手の動かし方は、おばさんそのもの。しかしこれも、刑事のテクニックの一つなのだろう。だが河元は、
「うるせえ! 初めから俺を疑ってたクセに。だから一昨日、店に来たんだろ」
と声を荒らげ、落ち着かない様子で後ろを振り返った。雑木林の奥にはフェンスのコーナー部分が見えるので、あそこが防犯カメラの死角かもしれない。
河元が顔をこちらに戻した拍子に包丁の刃が揺れ、波津の首に軽く当たった。小さく悲鳴を上げ、波津が身を固くする。と、信者の群れの中から一人が進み出た。
「あなたが心と体に抱え込んでいるものが、私には見えます。すぐに浄化して差し上げますので、波津を返してくれませんか? 私たちの大切な友人であり、家族なんです」
そう語りかけたのは、土橋だ。気づけば、懐中電灯を構えているのは園田だった。
そんな胡散臭さ丸出しの説得、逆効果だってば。みひろは心の中で突っ込み、焦りも覚えた。案の定、「黙れ!」と怒りを露わにした河元だったが、
「なにが、『返してくれませんか?』だ。お前が広恵を捨てたんだろうが」
と続け、顎で波津を指した。
いま「広恵」って呼んだ? みひろは驚き、柿沼も動きを止めた。言葉を失った土橋に、河元はこう続けた。
「散々尽くさせた挙げ句、若い女に乗り換えやがって。だが、広恵だってとっくにお前を見限ってるぞ。その証拠に──」
「やめて!」
そう叫んだのは波津だ。河元がはっとして、波津は包丁を気にしながら後ろを見た。
「頼むから、今すぐここを出て行って。そうすれば、何もなかったことにするから……すみません。ちょっとした行き違いなんです」
最後は土橋に目を向け、媚びを含んだ口調で波津は訴えた。黙ったままの土橋に代わり、慎が口を開いた。
「そうでしょうか。『何もなかったこと』にしたいのは、波津さんでしょう」
波津と河元の目が慎に向き、みひろと柿沼も倣った。波津を見返して、慎は語りだした。
「あなたは金庫番という立場を利用し、教団のお金を抜き取っていた。そしてそのお金を生活用品の代金に紛れ込ませ、共犯者である河元に渡していた。一方河元は自宅や銀行では妻か義母に見つかると考え、スーパーことぶきの商品にお金を隠した。売り物にならないカレーやシチューのルー、菓子の箱から中身を抜き取り、同じ重さのお札を入れるという方法です」
「じゃあ、あのカレールーも?」
思わずみひろが問うと、慎は顔を前に向けたまま頷いた。
「中身はお金です。ああいった箱は底から開けて再度糊で封をすれば、開封したと気づかれません。余った箱の中身は、客に渡して処分していましたね? ……一昨日、スーパーことぶきの前で会った鈴木さんです」
最後のワンフレーズは柿沼に向けて言ったが、彼女は呆然としている。構わず、慎は続けた。
「だが、トラブルが発生した。板尾さんが、あなた方の犯行に気づいたんです。きっかけは、注文した品と代金の入った封筒の厚さのずれではないでしょうか。板尾さんはあなた方を糾弾し、計画的あるいは偶発的な事象によって後頭部を強打して死亡した。その後、河元が車で板尾さんの遺体を発見現場に運んだ。言いたいことがあればどうぞ」
向かいを見たまま、慎は冷ややかに促した。波津は顔を険しくして言った。
「よくもそんなことを。言いがかりです。証拠はあるんですか?」
「ごもっとも」と頷き、慎は続けた。
「河元の車を鑑識課員に調べさせます。遺体を運んだのなら、高確率でルミノール試験が陽性になります。加えて、この施設内のみのり岩も。根拠は遺体発見現場にあった岩との類似性で、河元は大きさや形の似ている岩のそばに遺体を置けば、転落死にカモフラージュできると考えたんでしょう」
「ふ、ふざけるな! なんで俺がそんな」
反論しようとした河元を、慎は手のひらを立てて止めた。
「あなたは今、波津に渡されたお金を所持しているのでは? ……たとえば、そのポケット」
強い口調で言い、慎は河元が穿いたベージュのカーゴパンツを指した。つられて、その場のみんなの視線が動く。カーゴパンツは両脇に蓋付きの大きなポケットが付いており、どちらも不自然に膨らんでいた。
「あっ!」
みひろも指さすと、河元がポケットを見た。その拍子に右手も動き、包丁の刃が波津の首から外れる。
チャンス! みひろは思い、柿沼を見た。しかし柿沼は、立ったまま動こうとしない。
なんで!? 戸惑うみひろの目に、視線を戻そうとする河元が映る。焦りともどかしさに突き動かされ、みひろは右腕を振り上げた。そのまま右手に持っていたバッグを放り投げる。ボール形のバッグは柿沼の頭上を抜け、河元の左顔面にぶつかった。河元が俯くのと、バッグが地面に落ちるのが同時だった。鋲状の飾り金具が直撃したらしく、河本は喉の奥から変な声を漏らし、左手で左目を押さえた。拘束を解かれた波津が、転がるようにこちらに逃げ込む。
獣のような唸り声を上げ、河元がこちらに向かって来た。左手で左目を押さえ、右手は包丁の柄を握りしめている。
標的は波津かと思いきや、河元はみひろに近づいて来た。救いを求めて隣を見たが、慎の姿はない。
「えっ!?」
驚き、みひろは周りを見ようとしたが石に躓き、地面に尻餅をついてしまう。そこに河元が接近し、包丁を振り上げた。胸がどくんと波打ち、みひろは反射的に腕を顔の前に上げた。
と、脇から伸びて来た手が河元の右手首を摑み、ぐいと捻り上げた。また変な声を漏らして河元が顔をしかめ、その脇に柿沼が姿を現した。柿沼にさらに強く手を捻り上げられ、河元は「わかった! やめてくれ」と裏返った声で訴え、包丁を手放した。柿沼は地面に落ちた包丁を遠くに蹴り、河元の手首を捻り上げたまま、こちらを覗き込んだ。
「大丈夫?」
みひろがこくこくと頷くのを確認し、柿沼は体を起こして「誰か手伝って!」と叫んだ。それを聞き、雑木林にいた男の信者たちが駆け寄って来る。男の信者と柿沼は河元を取り押さえ、どこかに歩きだした。すると空間がぽっかりと空き、その向こうに誰か立っているのにみひろは気づいた。暗がりに目をこらすと、その誰かは中腰の、いつでも逃げだせるような恰好でこちらを窺っている。
「室長?」
みひろの問いかけに慎は我に返ったように姿勢を正し、こちらに歩み寄って来た。片手にバックライトを点したスマホを持ち、身をかがめる。
「無事で何より。結果オーライとは言え、今後無茶は厳禁です。バッグは拾っておきましたから」
眉をひそめて説教してから脇に挟んだボール形のバッグを見せ、慎はもう片方の手をみひろに差し出した。
「しれっと、よくもそんな」
言い始めたとたん、みひろはどっと疲れを覚えた。やむを得ず「ご心配をおかけしました」とだけ投げやりに返し、差し出された手は無視して自力で立ち上がった。