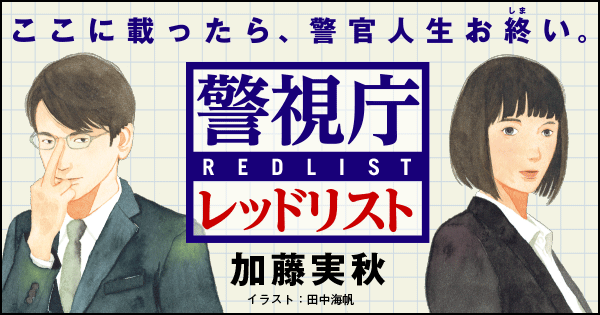〈第1回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

加藤実秋が放つ新たな警察小説、連載スタート!!
2
「ですから、どんな悩み事でも相談してもらって構いません」
そう語りかけながら、三雲(みくも)みひろは口元のマイクの位置を調節した。
「はい」
ヘッドセットのスピーカーから電話の相手の声が流れる。男性で、歳は二十二、三か。みひろの説明に納得はしたが、ためらいが残るといった様子だ。
みひろはパソコンのキーボードから両手を下ろし、口調を気持ちくだけたものに変えてさらに語りかけた。
「たとえばカラオケに行って、『お前はあの歌を唄え』みたいに強要する人がいるでしょう? あれはカラオケハラスメントと言って、立派な嫌がらせ行為なんです。他にも飲み会で人が食べるものに干渉したり、自分のこだわりを押しつけるのもグルメハラスメントと言って嫌がらせに……そうそう。最近印象的だったのが、スメルハラスメント。体臭や香水は前にもあったけど、『隣の席の人が使ってる柔軟剤の臭いがキツすぎて、頭痛がする』という相談でした」
「ああ」
実感を含んだ声で、男性が返す。すかさず、みひろは告げた。
「柔軟剤の臭いだって、職務に支障を来しているなら立派な職場問題です。すぐに対処して、解決したという報告も受けました。だからあなたも、遠慮なく話して下さい」
「わかりました」
意を決したように応え、男性は話しだした。
「署の先輩に度々『結婚しないのか』『いつまで独身でいるつもりだ』と言われて困っています。適当に受け流していたんですが、最近見合い話を持ちかけられるようになって。僕には付き合っている女性がいるんです。結婚を前提とした真面目な交際ですが、彼女はまだ学生なので」
「なるほど。先輩には、彼女のことは話していないんですね?」
相づちを打ちながらみひろは素早くキーボードを叩き、相談の内容をパソコンに入力していく。同時に視線をキーボードの奥の液晶ディスプレイに向け、入力した内容を確認する。
「ええ。話せば根掘り葉掘り聞かれて『会わせろ』と言われるし、周りに言いふらされます。プライバシーの侵害というか、ちょっとキツいかなあという感じで」
最後は「キツいかなあという感じ」と曖昧な表現でまとめたが、どんどん暗く深刻になっていく声と最後についたため息から、男性の状況が伝わってきた。キーボードを叩く手を止めず、みひろは返した。
「仰るとおり、先輩の行為はプライバシーの侵害です。加えて、マリッジハラスメント、通称・マリハラにも当たります。独身の職員に対して、相手の意志の確認をせずに縁談や合コンへの参加を強要する過干渉ハラスメントです」
「はい」
男性も返す。緊張しつつも、同意するような口調だ。
「問題の解決に向けて動きだすには個人情報を含め、いくつか伺うことになります。大丈夫ですか?」
てきぱきと話を進めていくみひろに焦りを覚えたのか、男性は早口で言った。
「ええ。でも、普段はすごくいい先輩で尊敬もしているんです。結婚だって、よかれと思って勧めてくれているんでしょうし」
手を止めて、みひろは極力穏やかな声でマイクに語りかけた。
「わかりました。そういうあなたの気持ちも含めて検討し、対処します」
「ありがとう」
男性の声に安堵のため息が混じる。その後必要事項を聞いてパソコンに入力し、みひろは通話を終えた。ほっとして机の端に置いたコーヒーのアルミボトルを取ろうとすると、
「お疲れ。淹(い)れたてだよ」
という声とともに後ろから制服の腕が伸びて来て、アルミボトルの脇に白いマグカップを置いた。マグカップから立ち上る湯気とコーヒーの芳香を確認し、みひろは振り返った。
「豆田(まめだ)係長。ありがとうございます」
「うんうん」と応えるように肉付きのいい顔を縦に振ったのは、豆田益男(ますお)。みひろの上司だ。コーヒーをすするみひろと後ろの液晶ディスプレイを交互に眺め、豆田は言った。
「丁寧かつスピーディ。さすが、相談とクレーム処理のスペシャリストだね」
「またまたあ。スペシャリストなんて、そんな大層なもんじゃないですよ」
謙遜しつつも嬉しくなり、みひろはつい声を大きくしてしまう。たちまち立てた人差し指を口に当てた豆田に「し~っ!」とたしなめられ、みひろは首を引っ込めて周囲を見回した。
ここは、警視庁本庁舎十一階の警務部人事第一課制度調査係。警視庁内の全部署から寄せられる相談や意見に対応する部署で、その窓口となっているのが「職場改善ホットライン」だ。部屋の中央にパーティションで仕切られた事務机が向かい合って三組並び、係員の男女が付いている。全員ヘッドセットを装着し、ホットラインにかかって来た電話に応対しながらその内容をパソコンに入力する。今年二十六歳になるみひろも係員の一人で、階級は巡査。豆田はみひろたちを取りまとめる係長、階級は警部だ。
「でも、『そういうあなたの気持ちも含めて検討』っていうのはやり過ぎかな。マニュアルにないし、三雲さんの私情だよね」
制服のジャケットに包まれた中年太りのお腹を撫でながら、豆田はたしなめる。マグカップを机に戻し、みひろは再度首を引っ込めて頭を下げた。
「すみません。なにしろ、中途採用なので」
「論外だな」
低く固い声にみひろはぎょっとして顔を上げ、豆田も後ろを振り返った。髪を七三分けにした男が立ってこちらを見下ろしている。歳は五十代半ば。豆田と同世代だが、引き締まった体つきで背も高い。
「鷲尾(わしお)管理官。申し訳ありません。三雲には私からよく言い聞かせます」
恐縮する豆田を無視し、鷲尾は続けた。
「新卒採用ではなくとも、研修で相談への対応マニュアルは学んだはずだ。加えて、『中途採用』ではなく『経験者採用』」
「どっちでもいいじゃない」。心の中でうんざりしたみひろだったが、口では「申し訳ありません」と頭を下げる。警視である鷲尾貴信(たかのぶ)は豆田の上司で、制度調査係のトップだ。
「それから、その相談」
続けて言い、鷲尾は顎でみひろの机の液晶ディスプレイを指した。振り向き、みひろも液晶ディスプレイを見る。いま受けた相談の内容が表示されている。
「三宿(みしゅく)署地域課の小城清正(こしろきよまさ)巡査ですね。マリハラをしている先輩は、栗原光雄(くりはらみつお)巡査部長だそうです。でも悪意はないようですし、上司に注意されればやめるんじゃないかと」
「マリハラはどうでもいい。問題は小城巡査だ。そこには『付き合っている女性がいる』とあるが、照会したところ小城巡査は交際申告書を提出していない」
「交際申告書? なんでしたっけ?」
思わず問うと、険しい鷲尾の目がさらに険しくなった。慌てて、豆田が囁いてきた。
「なに言ってんの。警察官は恋人ができたら相手の氏名や年齢、住所、職業等を記載した交際申告書を上司に提出するのが決まりでしょ」
「ああ。あれですか……うっかり出し忘れたんじゃないですか? 『真面目な交際』って話してたし、うるさいことを言わなくても」
「『組織に忠実であれ』。警察学校に入学して真っ先に叩き込まれるルールだ。そのルールには旅行、自家用車の購入、交際相手の申告も含まれている。マリハラについては今後精査するが、小城巡査の未申告は現時点で規則違反。懲戒処分だな」
表情は険しいままだが、顎を上げて蕩々(とうとう)と語る鷲尾からは、自分で自分の言葉に酔っているような気配が漂う。勢いよく、みひろは椅子から立ち上がった。
「勇気を出して相談して来た職員を処分するんですか? そもそも、いい大人がなんで勤め先に恋人の名前やら住所やらを──」
「三雲さん!」
呼びかけられるのと同時に、腕を強く引かれた。振り向いたみひろの目に、「お願いだからやめて」と言わんばかりの表情の豆田が映る。みひろは黙り、向かいで鷲尾が胸の前で腕を組む気配があった。
「どうやらきみは、警察という組織の根本を理解していないようだな……まあいい。近いうちにイヤでも理解することになる」
顔を前に戻すと鷲尾と目が合った。薄い唇を歪め、笑っている。どういう意味かみひろが訊ねようとした時、鷲尾はその場から歩き去っていった。