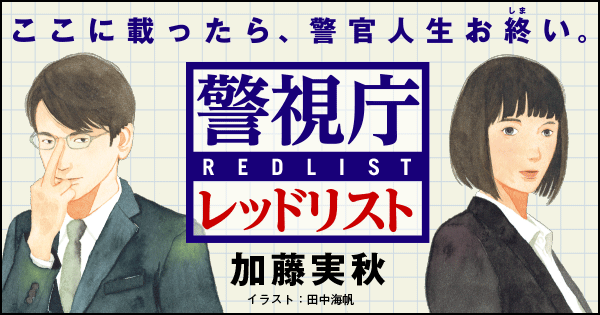〈第9回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

奥多摩に向かった。
CASE3 ゴッドハンド:神にすがる女刑事(1)
1
青梅(おうめ)街道を外れると、未舗装になった。阿久津慎(あくつしん)は車のスピードを落とし、がたごと揺れる狭い山道を登った。
「あそこですね」
助手席の三雲(みくも)みひろが、フロントガラス越しに斜め前方を指した。うっそうと茂る木々と雑草の間に脇道があり、出入口に黄色地に黒で「警視庁 立入禁止」と書かれたテープが渡されている。その左右にはパトカーが二台と、ルーフに赤色灯を載せたワンボックスカーとセダンが停められていた。
セダンの後ろに車を停め、慎とみひろは外に出た。八月に入り暑さのピークを迎えているが、都心とは違う澄んだ空気が顔に当たった。周囲の森からは、セミの鳴く声が重なり合って聞こえた。時刻は午前十一時前だ。
慎とみひろはテープをくぐり、脇道に入った。脇道は斜面を横切って延びていて、大人一人歩くのがやっとなほど狭く、石や木の根だらけだった。スーツに革靴姿の慎たちが汗だくになり、躓(つまず)いたり足を滑らせたりしながら歩き続けること約三十分。ようやく現場に到着した。脇道から十メートルほど下った場所に十人ほどの警察官がおり、大きな岩を囲むようにして立ったりかがみ込んだりしている。そこに遺体があるのだろう。
「私、事件現場って初めてなんですよね。現場検証中ですか? 鑑識課の人はいないのかな」
みひろが言った。ハンカチで額に浮いた汗を押さえ神妙な顔をしているが、目は興奮と好奇心で輝いていた。作業中の警察官たちはスーツや活動服姿で、ライトブルーのキャップとシャツ、パンツが特徴的な制服を着た鑑識課員はいない。
「いなくて当然です」
そう返し、慎も現場を見下ろした。
「事件通報を受けて現場に真っ先に駆けつけるのが、所轄署の警察官。立入禁止のテープを張る、野次馬を追い払う、ブルーシートで遺体の周辺を覆うなど現場の確保を行います。続いて現場検証となりますが、入れるのは鑑識課員だけ。もちろん、事件とは無関係の毛髪や指紋などが紛れ込むのを防ぐためです。よくテレビドラマなどで、刑事が鑑識課員に『ここを念入りに調べろ』と指示しているシーンがありますが間違いで、鑑識活動が終了するまで捜査員は現場に立ち入れません」
「へえ。じゃあ、ここはもう鑑識活動が終わった後なんですね──あ、あの『三機捜(さんきそう)』の腕章を付けた人たちはわかります。警視庁第三機動捜査隊の隊員でしょう?」
みひろが指さしたのは、岩の前に立つスーツ姿の二人組の男。慎が「ええ」と頷くと、みひろは続けた。
「初動捜査の専門部隊なんですよね。普段は覆面パトカーで担当区域をパトロールしていて、事件が発生すると現場に急行する」
「はい。今ごろ彼らの同僚が目撃者を捜したり、この近辺の防犯カメラの映像をチェックしたりしているはずです。よく知っていますね。『警察24時』で見たんですか?」
慎の質問に「違いますよ~」と不本意そうに眉を寄せて答えた後、みひろは語りだした。
「二時間ドラマの『警視庁機動捜査隊216』です。主演の沢口靖子(さわぐちやすこ)がカッコよくて、欠かさず見てます。相棒役の赤井英和(あかいひでかず)とのコンビもいい感じで」
結局テレビか。呆れながら納得し、慎もハンカチを出して顔の汗を拭った。調子よく語り続けるみひろを、「ドラマも結構ですが、警察職員なら現実の事件や事故などの情報収集を行うべきかと」と遮って教育的指導を始めた矢先、
「お疲れ様です」
と声がした。見ると、活動服を着た警察官が斜面を登って来る。歳は五十手前。小柄で細面、下向きの矢印のような形状の鼻が印象的だ。警察官は杉の高木が並び、所々岩が飛び出した急な斜面を慣れた足取りで登りきり、慎たちの前に立った。
「奥多摩(おくたま)署の署長の菊池(きくち)です。本庁の人事一課の方ですか?」
警視庁奥多摩署はJR奥多摩駅の近くにあり、鉄筋二階建てで設備は整っている。しかし署員は、十六名のみ。これは小笠原(おがさわら)諸島の父(ちち)島にある小笠原警察署の約十名に次ぐ少なさだ。署内は署長以下、警務係、警備係、捜査係と部署分けはされているが、手が空いている者がなんでもやるというのが実情だろう。
「はい。職場環境改善推進室の阿久津です。こちらは三雲。先ほど署に伺ったんですが、留守番の職員に『管内の山中で遺体が発見されて、みんなで現場に向かった』と聞いて来てしまいました。大変ですね。遺体(ホトケ)は地元住民ですか?」
菊池英樹(ひでき)、四十八歳。奥多摩署署長に着任して四年。階級は警視。挨拶と事情説明をしながら、慎は事前にインプットした情報を再確認した。
「恐らくそうでしょう。今朝八時頃、この山の持ち主が見回りをしていて発見しました……阿久津さん。すみませんが、ホトケを見ていただけませんか?」
「僕ですか?」
驚いて訊き返すと、菊池は申し訳がなさそうに眉を寄せて頷いた。
「ええ。うちの柿沼(かきぬま)がどうしてもと」
みひろも驚いてこちらを見たのがわかった。柿沼也映子(やえこ)は今回の事案の調査対象者で、奥多摩署唯一の捜査係員だ。違和感を覚えながらも瞬時に決断し、慎は返した。
「わかりました……三雲さんは、ここにいて下さい」
「いえ。私も行きます」
当然のように返し、みひろはバッグを肩にかけ直した。止める間もなく、菊池に渡された白手袋をはめている。仕方なく、慎も差し出された白手袋を受け取って両手にはめた。
菊池、慎、みひろの順で斜面を降りた。転げ落ちないように岩や木の幹に摑まり、一旦引いた汗がまた出た。晴天だが杉の枝が重なり合って伸びているので、日射しは届かない。
現場は斜面の途中にある棚状の平坦なスペースだった。菊池は警察官たちに慎とみひろを紹介した。聞き取り調査について聞いていた様子で、奥多摩署の署員たちは丁寧に挨拶をしたが、第三機動捜査隊の隊員は訝しげに慎たちを見た。
スペースを奥に進むと、脇道から見た大きな岩があった。その手前に、活動服姿の女がこちらに背中を向けて立っていた。
「柿沼さん。阿久津さんをお連れしたよ」
菊池が言い、女は振り返った。大柄でずんぐりとしており、半分白くなった髪を耳の出る長さにカットしている。
「どうも。柿沼です」
化粧気のない丸い顔を突き出すようにして、柿沼が会釈をした。無表情で声もぼそぼそとしているが、小さな目は素早く動いて慎の顔と体を眺め、後ろのみひろも見る。乱れた髪を整えて笑みを作り、慎は会釈を返した。
「職場環境改善推進室の阿久津です。後ろは三雲。よろしくお願いします」
柿沼は「お疲れ様です」と挨拶するみひろを無視し、慎に告げた。
「悪いね。せっかく本庁の人が来たんだし、意見を聞きたくてさ」
そして「よろしく」と付け足し、手の平で後ろを指して脇に避けた。視界が開け、慎の目に大きな岩とその周辺の光景が映った。
岩は高さ一・五メートル、幅二メートルほど。いびつな俵形で、遺体はその前の地面に仰向けで横たわっていた。靴は履いておらず、泥だらけの靴下に包まれた足は、大きさからして男性。生成り色で変わったデザインの、長ズボンと長袖シャツを身につけているのもわかった。だが、慎はそれ以上先に進めない。
「室長?」
後ろでみひろの声がして、背中に視線を感じた。柿沼と菊池もこちらを見ている。
ざっと強い風が吹き抜け、それに体を押される恰好で慎は歩きだした。一歩、二歩。遺体に近づくにつれ、ぶうんという羽音が聞こえた。腐ったようななんともいえない異臭も、強くはないが感じる。
三歩、四歩。遺体の脇で、慎は立ち止まった。羽音は大きく、異臭は強くなる。激しく動悸がして、指先が冷たくなっていくのを感じた。
仕事は完璧にこなす。それが俺だ。プライドが躊躇(ちゅうちょ)に勝り、慎は黒い岩肌に向けていた視線を下ろした。
遺体の短く刈り込んだ黒い髪は、生きている人と変わりがない。しかしその下の顔と首は紫に変色し、見開かれた両目には様々な種類の昆虫が大量にたかっていた。さらに左右の頰は皮膚がちぎれ、白い骨が露出している箇所もある。
胃の中が泡立つような感覚があり、動悸は胸を突き破らんばかりに激しくなった。どっと冷や汗が流れ、肌が粟立つ。目を背けたいのに、体が固まって動けない。
気配があり、慎の目は遺体の口に向いた。わずかに開いた口の中から黒く小さな塊が出て来て、唇の上で止まった。それが丸々と太ったハエだと認識するのと同時に苦い胃液がこみ上げ、猛烈な吐き気に襲われた。手のひらで口を押さえ、慎は身を翻して走りだした。
「室長!?」
驚いて呼びかけるみひろの脇を抜け、何ごとかと振り向く警察官たちの間を転がるように走った。人気のない場所まで行くとその場にかがみ込み、慎は激しく嘔吐した。