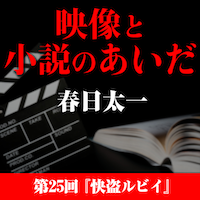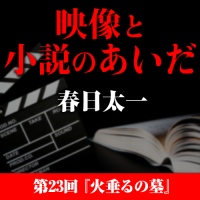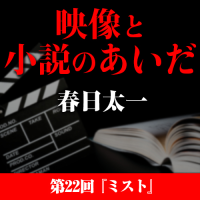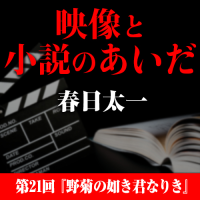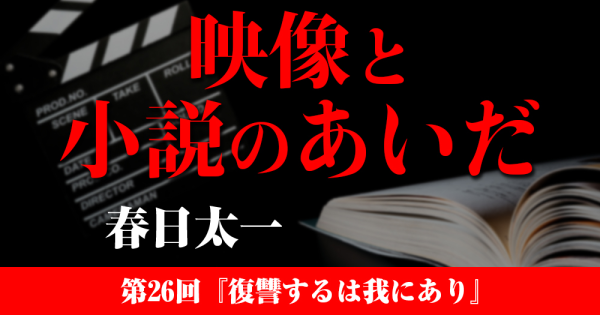連載第26回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
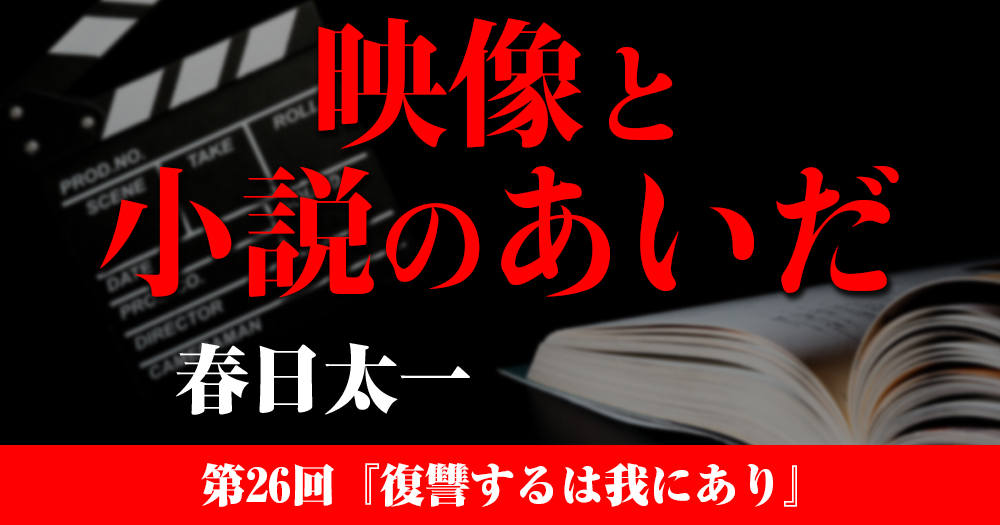
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『復讐するは我にあり』
(1979年/原作:佐木隆三/脚色・監督:今村昌平/松竹・今村プロダクション共同製作)
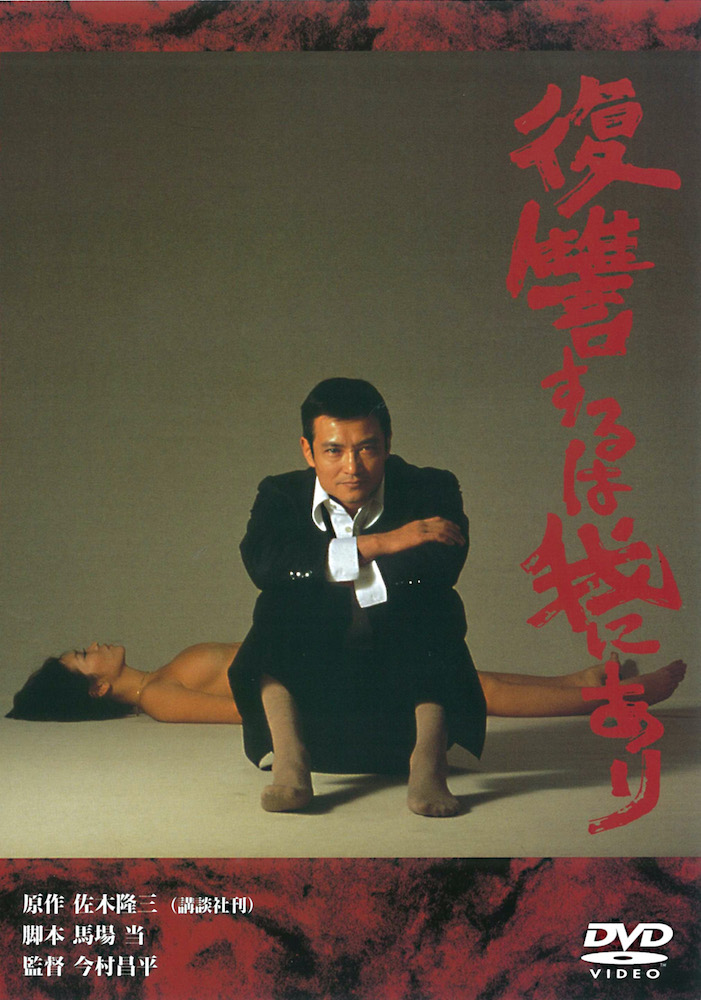
『復讐するは我にあり』
Blu-ray:3,630円(税込)
DVD:3,080円(税込)
発売・販売元:松竹
©1979 松竹株式会社/株式会社今村プロダクション
※2025年2月時点の情報です
「ちきしょう! 殺したか! あんたを――!」
1963年10月から翌1月にかけて、西口彰は全国で詐欺事件をはたらき、福岡と浜松で計5人を殺害している。そんな実際に起きた事件を佐木隆三がノンフィクション小説としてまとめたのが『復讐するは我にあり』で、タイトルそのままに映画化もされた。原作も映画も、主人公の名前を榎津巌としてある他、登場人物の名称は実際の事件から変更した。
原作は警察からの視点で展開しており、榎津の足取りを追う捜査過程とその際に得られた証言で構成されている。つまり、周辺から榎津の犯行を浮かび上がらせる、客観的な視点で貫かれているということだ。
一方の映画は、周囲の人間や捜査関係者だけでなく、榎津(緒形拳)自身の行動や心情も追った構成になっている。つまり、榎津の主観的な視点も含まれているのだ。
その結果、受け手の見えてくる景色は大きく異なるものになった。
原作は警察捜査の視点であるため、榎津の行動は後追いの形で判明していく。加えて殺人の被害者は当然、証言ができない。そのため、犯行やそこに至る当事者間の事情といった詳細は不明のままだ。
それに対して映画は、榎津の視点でも描かれているため、榎津の行動は現在進行形の時間軸として詳細に描写される。そのため、原作では描き切れなかった殺人の犯行時や前後の様子も詳細に描くことができた。
そうした表現手法の違いにより、映画でないと見えない榎津の人間性が浮かび上がる。
その第一はサイコパスな残忍さである。
最初の殺人では、ハンマーで滅多打ちにした上に千枚通しで喉元を刺す。さらに、殺害後は自らの小便で手についた血を洗い流してもいる。2度目の殺人では、命請いをする相手を息の根が止まるまで出刃包丁で刺しまくった。雑司ヶ谷のアパートでの老弁護士(加藤嘉)殺害では、殺人シーンは描かれないものの、その死体を隠すためタンスに黙々とガムテープを貼りつけていく様が詳細に描かれている。
ただ、浮かび上がるのはそうした残酷さだけではない。浜松での連続殺人事件において、榎津は思わぬ一面を見せている。
榎津は大学教授と偽って浜松の連れ込み旅館に潜り込み、そこを営むハル(小川真由美)と懇ろな関係になった。そして、やがてハルとその母・ひさ乃(清川虹子)を続けて殺害している。
この浜松の事件は、原作では榎津による数多くの一つという扱いで均等に分量が割かれている。一方、映画では他の犯罪の描写は短めにして、このパートが後半の大部分を占めていた。
原作では他と同じく、事件の顛末は宿に出入りする人たちからの証言のみをもって描写される。そのため榎津単独はもちろん、榎津とハルだけ、榎津とひさ乃だけ、ハルとひさ乃だけ、そして三人だけ――そういった証言者のいないシチュエーションは、映画でしか描かれていない。そして映画の作り手は、そうしたシチュエーションを物語としての焦点の一つと捉えていた。
ここで映画は、原作と大きく異なる設定を入れている。それは、ハルもひさ乃も、榎津の正体に気づいているというものだ。それほどハルは榎津に惚れ込んでいたし、ひさ乃は榎津を疎ましく思いながらも他に行き場所はない。そして榎津はこの空間に居心地の良さを感じていたため、逃げることはなかった。それぞれに暗い影を負った三人による、疑似家族のような関係性がいつしかできあがっていたのだ。
この追加により浮かび上がるのは、ただ残忍なだけではない榎津の人間性――弱さだ。
ひさ乃はかつて人を殺して収監されていた。だが、「殺したい奴を殺した」と今も胸を張る。そして、榎津にこう言い放つ。
「本当に殺したい奴、殺してねえんかい」
「いくじなしだね、あんた」
同じ犯罪者として、ひさ乃は榎津の弱さを見抜いていたのだ。
そして、この「本当に殺したい奴」と榎津との対峙が、物語の最大の焦点になってくる。それは誰か――。
原作では、榎津が逮捕される場面は克明かつスリリングに描かれている。また、その通報者の後日談や、榎津の裁判・死刑の過程が詳細に記される。ただ、そうした場面は映画には全くない。そのかわりに、別のクライマックスが用意されていた。
それは、父・鎮雄(三國連太郎)との対峙だった。
映画は前半から、鎮雄や妻・加津子(倍賞美津子)と榎津との葛藤のドラマを丁寧に追っている。その結果、原作の「息子・夫の罪に巻き込まれた、哀れな被害者」という家族像とは異なる見え方をすることになった。
父子の愛憎は、榎津の少年時代にさかのぼる。戦時中、網元をしていた鎮雄は軍による漁船の徴用に応じなかった。父を罵倒する軍人に怒った榎津は、棒切れで軍人に殴りかかった。この時、鎮雄は榎津を守るために徴用に応じ、榎津はだらしのない父親を軽蔑するようになった。以来、榎津が父に反抗を続けるようになる。
こうした父子の背景は映画でしか描かれていない。そしてもう一つ、原作にはない家族の肖像が盛り込まれている。それは、加津子が榎津よりも鎮雄を慕っているという背景だ。敬虔なクリスチャンとして生きてきた鎮雄を加津子は心から敬愛、その心情はやがて恋慕のように変化していく。
こうした背景を見せることで、榎津=悪人、鎮雄=善人という単純な二元論で割り切れなくなった。
加津子は何度も鎮雄を誘惑し、その度に鎮雄の心は揺らぐ。そんな父を榎津はあざ笑う。
「どげな顔して息子の嫁に手をば出すか、一度見たかち思いてな」
一方、息子の犯罪に加えて鎮雄と加津子の関係に気を病んだ母・かよ(ミヤコ蝶々)は常軌を逸してしまう。そして最後は病院を抜け出し、「私もおなごじゃけん。加津子に父さん渡したくなか」と言い放つ。つまり、鎮雄もまた息子と同じ「業」を背負う人間として描かれているということだ。
その結果、逮捕後の父子の様相も大きく異なるものになった。
原作では、鎮雄は事件後に一度も榎津に会っていない。が、映画はラストで二人を対峙させた。そして、これが最大のクライマックスに据えられる。
鎮雄は、かよの死と榎津を教会が破門したことを伝える。だが、それだけではなかった。鎮雄は加津子への邪な想いを吐露した上でこう語る。
「ワシは母さんでんお前でん、早く死ねばよかと思うとった」
そして、その「獣の心」故に自身も教会に破門してもらったと伝えるのだ。
それを受けて榎津は、これまで溜め込んだ父への憎悪をぶつける。
「あんたはオイを許さんかしれんが、オイもあんたを許さん。どうせ殺すならあんたを殺せばよかったと思うたよ」
冷たくそう言い放つ榎津。だが、鎮雄は動じなかった。
「親殺しのできる男じゃなか」「恨みもなか人しか殺せん種類たい」
ひさ乃と同じく、鎮雄も榎津の本性を見抜いていたのだ。それは、彼もまた息子と同じ「獣の心」を持っていたからに他ならない。
この言葉を受けて、ここまで劇中で他者をひたすら嘲笑ってきた榎津が、激高する。そして発したのが、冒頭に挙げたセリフだ。それはもはや、遠吠えでしかなかった。父親に完全に敗北してしまった瞬間である。
こうした父子の愛憎ドラマという面は、原作にはない。原作では、鎮雄は榎津をこのような状況に追い込んでしまったことに反省するばかりで、あくまでも「哀れな善人」でしかない。また榎津も取り調べ中に父親からの差し入れを喜んでいるなど、両者の間に愛憎は感じられないのだ。
それに対して映画は、二人の奥底に潜む毒性を徹底して炙り出し、二代にわたる「悪魔の血」の系譜のドラマとして浮かび上がらせたのだった。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。