連載第21回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
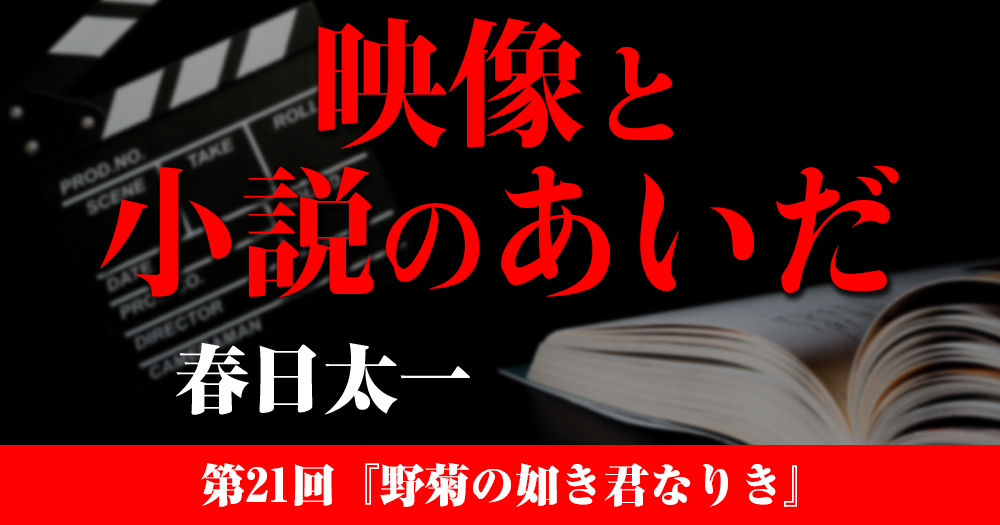
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『野菊の如き君なりき』
(1955年/原作:伊藤左千夫/脚色・監督:木下恵介/製作:松竹)

『野菊の如き君なりき』
DVD:3,080円(税込)
発売・販売元:松竹
©1955松竹株式会社
※2024年8月時点の情報です
「老い先の短い年寄りには、昔の夢しか残っておりませんもの」
舞台は明治末期の、矢切りの渡しに近い千葉のある村の旧家。満13歳になる斎藤政夫は父を亡くし、体調の優れない母親とともに暮らしていた。斎藤家には政夫の二つ年上の従妹・民子が手伝いに来ており、二人は何かと気が合った。ただ、そのために二人の仲は村での噂となる。やがて、二人の間にも恋心が芽生えるようになっていった。母親の言いつけで、二人が山に綿を摘みに行った際、政夫は民子に「野菊のような人だ」と伝える。
だが、この時代の地方では、男女関係において女性が年上というのはタブー視されていた。そのため、世間体を気にした母親は二人を引き離そうとする。政夫は寄宿制の中学に通うことになった。
休みに帰郷した際、政夫は民子が嫁に行ったと聞かされる。そしてしばらくして、民子の訃報を受ける。嫁ぎ先で懐妊したものの流産してしまい、そのまま実家に帰され、産後の肥立ちが悪いために息を引き取ったのだ。
二人を引き離したのも、縁談を勧めたのも、自身のしたことである母親は「私が殺したようなものだ」と政夫に侘びた。政夫は民子の実家に行き、その墓に参る。民子の墓の周りには、野菊が生い茂っていた──。
以上が伊藤佐千夫の小説「野菊の墓」のあらすじだ。悲恋モノの定番として知られる本作は何度も映像化されてきた。その最初の作品となったのが、木下恵介監督による映画『野菊の如き君なりき』だった。
悲恋の顛末については、その細かい描写やセリフのやり取りに至るまで、原作と映画はほとんど変わらない。登場人物の設定もほぼ同じだ。舞台が千葉から信州に変更されてはいるものの、これは物語展開そのものには影響していない。
だが、両作品の間には一つだけ大きく異なる点がある。原作は、「十余年後」の主人公からの回想として振り返る形で、物語は進んでいく。映画も、回想形式で構成されていることに変わりはない。だが、年齢設定が全く違うのだ。
映画では、民子(有田紀子)との日々を回想する政夫(笠智衆)は、73歳。原作が二十代だと計算すると、半世紀近くも歳が離れているのだ。この変更の結果、回想のもたらす印象が大きく変わってくることになった。
映画では、民子の墓参に向かう船上で、老いた政夫が船頭に語り掛ける形で物語は進行していく。
ここでの政夫は、民子の死後に家族を成し、孫もいる。つまり、民子のいない人生をそれなりに全うした上で老後を迎えているのである。民子のいない人生をこれから長く生き続けることになる原作とは、置かれている状況は異なる。
まだ生々しく民子との記憶が残る原作に対し、映画はそうではないのだ。年齢や、ここまで過ごしてきた年月を考えると、「若い日の思い出」の一つとして忘れてしまっていてもおかしくはない。だが、そうではないところがこの映画の妙味だ。
「死ぬ前に、もう一度、来たいと思っていました」と政夫は語る。長く、そしてそれなりに充実したと思える人生を過ごしてもなお、死ぬ前にもう一度、民子の墓に参っておきたい。そう思うほど、かけがえのない出来事だったことがこの序盤のセリフからは伝わってくる。「心持ちだけは、昨日のことのよう」と言うように、政夫は片時も民子のことを忘れていなかったのだ。その想いも当時のまま灯り続けているということでもある。
つまり映画における回想は、人生が終焉に近づこうとしている人間にとっての、「生涯を通して最も大切な思い出」として語られているのである。それだけに、そこで語られる回想が、よりいっそうセンチメンタルかつエモーショナルに迫ってくることになった。
主人公の年齢設定を上げた劇的な効果は、もう一つある。それは、時代設定のもたらすものだ。
原作が書かれたのは、1906年。つまり明治時代だ。そして、主人公が過去を回想する時点がその年だとすると、悲恋の物語もまた明治期の出来事ということになる。原作における民子との回想は、執筆当時の「現代劇」として綴られているということだ。
それに対し、映画は主人公を73歳としたことで、時代設定は戦後となった。つまり、「戦後に生きる人間が、明治時代の出来事を振り返る」という構図になっているのだ。その結果、原作には描かれない要素が加わることになった。
それは「時代の変化」だ。太平洋戦争を経て、日本は大きく様変わりした。そのことが、色濃く反映されているのである。それは原作からすると、想像もできない「未来」の出来事である。
戦後の農地改革により、斎藤家は立ち行かなくなっていた。その結果、一緒に暮らしていた兄(田村高廣)とは連絡がとれなくなり、政夫の育った家も今は空き家同然になっている。「自然に朽ち果てるのを、待っているんです」。政夫はそう語る。原作では実家の現状は語られていないが、それは回想の時代からそう経っていないために触れる必要がなかったのだ。
そして、政夫自身も大きく変わった。それは経年によるものだけではない。戦後ということは、政夫は太平洋戦争を通過しているということだ。「戦争で苦労しました」。そう短くしか語っていないが、短いからこそ、その「苦労」は戦禍にあった世界中の人々と同じく、途方もないものだったと想像ができる。回想の中で語られる、何も苦労をしらずに恋だけに生きる純朴な政夫少年(田中晋二)と、今ここにいる老人は何もかもが違うのである。
つまり、映画における「現代」が回想の時代と違う点は、「民子の不在」だけではない。実家も、故郷の景色も、そして政夫自身の若さも。今では全てが失われてしまっているのだ。だからこそ、回想の中の世界の全てが、輝かしくも儚く映し出されることになる。冒頭で挙げたセリフも、老いた政夫が船頭に語ったものだ。まさにこれは、過ぎ去りし夢の世界なのである。
これからの自身の生き方への誓いを立てて、原作は終っていく。それに対し映画は、老いた政夫が民子の墓を参るところで終わる。彼もまた、もうすぐ同じ場所へ行くことになるのだろう──そんな余韻を漂わせて。一つの人生、そして時代の終焉を淡く綴る、そんな脚色に仕上がっていた。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。






