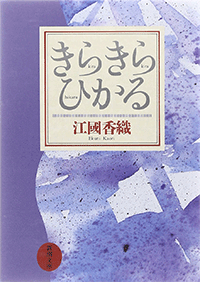吉川トリコ「じぶんごととする」 2. 酒とお菓子と女と私
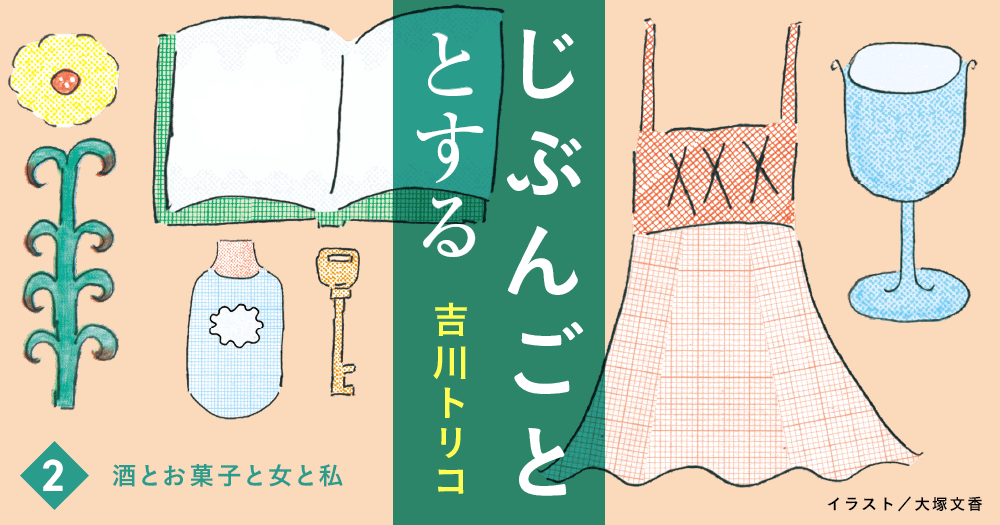
最初にビールから入ってしまったせいか、いまだにお酒はがぶがぶと量を飲むものという感覚が消えない。だから高いお酒を買ってちびちびやるよりは、大五郎的な酒をソーダか水で割ってがぶがぶいきたくなってしまう。一時期は瓶を捨てにいくのも億劫で安い箱ワインを赤白常備し、水道水のように蛇口をひねってがぶがぶ飲んでいた。大五郎、箱ワイン、ストロングゼロ。【酒やめますか? 人間やめますか?】の問いかけが頭に浮かんでくるような、大酒吞み界におけるスターたち。
ウイスキーをなめる、という感覚を知ったのは江國香織さんの小説を読んでからだと思う。最初に読んだのがいつだったかもう思い出せないけれど、うんと若く、まだウイスキーの味なんて知らなかったころだ。深い夜の静寂のなかで、舌の先でつつくウイスキーのさざ波、薄いガラスと氷のぶつかる音、はちみつみたいにとろりとした琥珀色の液体。なんて甘そうな飲み物なんだろうと憧れた。
『きらきらひかる』の主人公・笑子は「アル中」だと自称しているが、ミントジュレップやラム入りの紅茶、ジンとキュンメルのカクテル、「毒薬みたい」なウォッカとカルーアのカクテルなど、作中に出てくるお酒はどれも子どもがぺろぺろなめるキャンディのようだ(実際の味が甘いか甘くないかはそんなに関係がなく、どれも舌がしびれるぐらい甘そうに感じる、という点が重要)。酒を飲んでいないときの笑子はだいたい甘いものを食べている。薬だといって医者からドロップを処方されたりもする。朝から子ども用のシャンパンを飲んじゃうし、夕飯にドーナツなんか食べちゃう。「常識的な大人」が眉をひそめそうな、まるきり出鱈目な生活。
私はだいたいいつもなにかしらにかぶれている気がする。春樹にかぶれたあとは江國にかぶれていたし、ついでに言うと、ばななにも詠美にも龍にもかぶれたことがある。田口ランディさんの『コンセント』を読んで、ズブロッカを冷凍庫に常備していたこともある。とにかくすぐかぶれ、すぐ忘れる図抜けたミーハーである。
ひさしぶりに『きらきらひかる』を読みかえしたら、やっぱり若干かぶれてしまった。何度も読みかえしているくせにいまさらになって、シャンパンマドラーなんてすてきなものがこの世に存在するのかと感激し、思わず買いそうになっているほどである。
『ノルウェイの森』の緑になりたいとあんなにも願っていたのに、笑子になりたいと思ったことは一度もない。だって、笑子は私そのものだったから。このままなにも変わらず――だれかを変えてしまうこともだれかに変えられてしまうこともなく、甘い繭のなかにとどまっていたいとはりつめた気持ちで願っていたことが、二十代のある時期、私にもあった。ウィスキーの味も知らなければ、お酒はがぶがぶいきたいほうなのに、どうしようもないぐらい笑子だった。
作中で唯一、笑子が酒も飲まず甘いものも食べず、夕飯らしい夕飯(夫が買ってきてくれたコロッケ)を食べて、ラムもウィスキーも入っていない紅茶を飲んでいるときに口にする台詞がある。
「でも、どこかで現実と折りあいをつけなくちゃいけないでしょう?」
およそ笑子らしくもない、まっとうでちゃんとした「常識的な大人」みたいな台詞。
笑子自身や、笑子に共鳴する読者を傷つけるようなこの台詞を読んでも、もう傷つかないぐらいに私は大人になってしまった。「アル中」のように酒に耽溺するのは子どものときにだけ許されることで、大人は朝からお酒なんか飲まないし、夕飯にドーナツなんか食べない。人はだれかとかかわらずには生きていけないし、望むと望まざるとにかかわらず変わっていかざるをえない。人生が苦くなればなるほど酒の甘さが増すからキャンディなんてもういらない。うんざりするほどまっとうな考え方がいつのまにか身に沁みついてしまっている――それを、つまらないことだとすら思わない大人に。
でもね、折り合いなんてそんなにかんたんにつかないよ、だから大人も酒を飲むんだよ――とそんなことを言ったら、笑子にものを投げつけられてしまうだろうか。
お酒は週に三日。一本のワインを二日かけて飲む。シャンパンマドラーを買ったところで、もうシャンパンを買わなくなった私には必要がない。