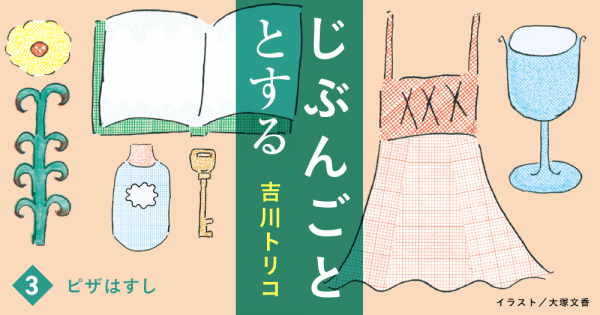吉川トリコ「じぶんごととする」 3. ピザはすし
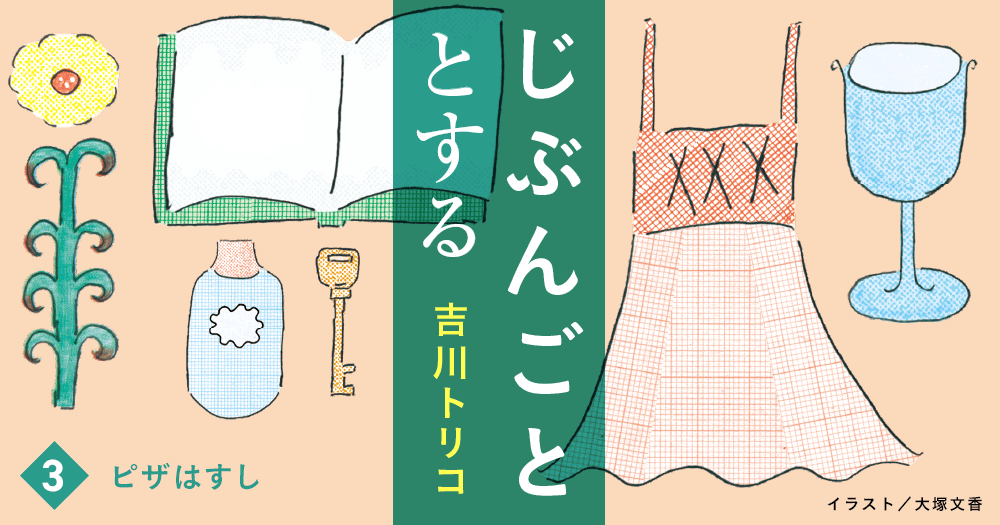
畑中三応子さんの『ファッションフード、あります。』によると、七〇年代にグルメブームをけん引したのは「an・an」「non-no」などの女性誌だったとある。チーズケーキやクレープ、オムレツ、イタリアン、サラダ等々、当時の日本にはまだなじみの薄かった洋風の料理に「なんだかとってもおしゃれ!」と真っ先に飛びついたのは若い女性たちだった。アンノン族だったうちの母は当時一世を風靡したドンクのフランスパンが世界一だとある時期まで思っていたようだし、オニオングラタンスープにも目がなかった。
「食を義務から趣味や娯楽に塗りかえて、新しい価値観を提示したファッションフードは、良妻賢母イデオロギーに対する若い女たちのレジスタンスであったのかもしれない」と畑中三応子さんは書いているが、グルメブームのはじまりがミーハーな女たちの社会運動だったととらえると、なんと痛快なことだろう。
女たちの軽薄な熱狂こそが、雁屋哲に『美味しんぼ』を書かせたのかもしれない。その権威的としかいえない発想、バカな女どもにほんとうの食というものを教えてやろうというミソジニー&マンスプ&モラハラ的な態度はそのまま山岡や雄山のキャラクターに重なる。作者のオルターエゴとして自覚的に彼らを描いていたのかどうかまではわからないが、「権威主義者」「えらそうに能書きたれてオジンぶる」「女をミーハー扱いするな!」などと栗田さんをはじめとする女性キャラにつっこみを入れさせているあたり、なかなかに複雑な入れ子構造になっていて一筋縄ではいかない。
人は往々にして海原雄山化してしまいがちだ。私だってつねに自分の中の海原雄山と戦っている。海原雄山という概念を生み出し、海原雄山状態が醜悪であるということを広く知らしめたその一点において、私は『美味しんぼ』にありがとうを言いたい(作者の意図とかはこの際どうでもいい)。
柚木麻子『ついでにジェントルメン』所収の短編小説「エルゴと不倫鮨」は鮨とワインのマリアージュをコンセプトにしたいけすかないかんじの鮨屋に、授乳期を終えた母親が赤ん坊を連れて乗り込んでくるという痛快な一編である。軽薄なグルメ気取りの男が、連れの女にあれこれマンスプをかましていると、その男よりはるかにワインに造詣の深い母親がやってきて、次々にネタを指図して職人に鮨を握らせる。カウンターだけの店内には不倫カップルしかおらず、そのうち女たちは隣の男などそっちのけで母親から目が離せなくなり、しだいに連帯感を強めていく。
山岡が軽薄なグルメ気取りを次々になぎ倒していったときの、栗田さんがその類いまれなる味覚の鋭さで男たちに恥をかかせてやったときの爽快感を思い出しながら私はこの短編を読んだ。西部劇でも見ているような気分だった。
なにより、柚木麻子の描く食べ物は鮨にかぎらず、どれもこれもが官能的なまでにおいしそうなのである。それこそ「米の飯をグイグイ飲み込む快感」のように、身体的な快楽をともなって五感を刺激する。
日々、我々が食べているものは、食そのものではなくブランドだったり情報だったり数字だったり物語なのではないかと思うときがある。もっとプリミティブに「おいしい」をたのしみたいけれど、毎食毎食、神経を研ぎ澄ませて食に向かうのもそれはそれで疲れるし、正直そんな時間もゆとりもない。一人で食べる食事は、ほとんど流動食と変わらなかったりする。
私が山岡や「エルゴと不倫鮨」の母親に憧れるのは、その知識や味覚の鋭さではなく、食に全身全霊をかける態度と熱意のほうなのかもしれない。あんなふうに全力で「おいしい」を享受できたらどんなにいいだろう。しかし、あの母親があんなふうに鮨を堪能できたのはひと晩かぎりのことで、日々子育てに追われて普段はそのような余裕もないのかもしれないと思ったら、毎回毎回、食事に全体力を割り振れる山岡にいい気なもんだねといやみのひとつも言いたくなってしまう。
ところで私はいつのころからか、「ピザはすしなので出されたらすぐに食べなければならない」と思い込んで実践しているのだが、『美味しんぼ』に描かれていたわけでもなければ、ネットで調べてみてもそんなことを書いている人はおらず、いつどこでそんなふうに思い込んだのかいまもってわからない。しかし、つい先日「ピザの賞味期限は二分」と書かれている記事を読み、やはりピザはすしなのだと認識を深めたところである。