吉川トリコ「じぶんごととする」 4. NYで夢を捨てる【ダウンタウン編】
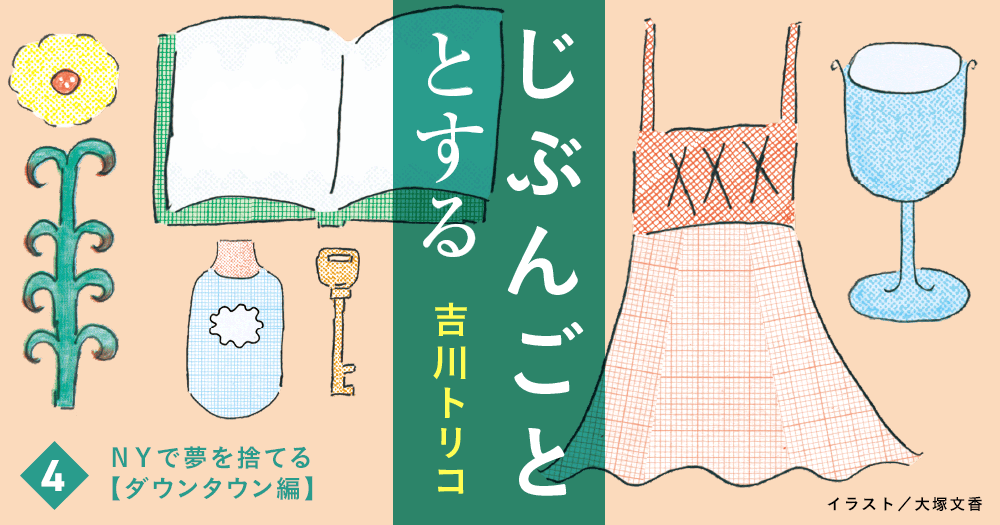
今回『BANANA FISH』を読み返して、まったくおなじ感慨を抱いた。というか『吉祥天女』と『BANANA FISH』は主人公の性別や舞台こそちがうけれど、ほとんど同じ話だといってもいい。そういうふうに生まれつき、そういうふうにしか生きられない孤独な魂を抱えた者が、自由と救済をもとめて闘う物語。
長らく私は、どれだけ傷つけられても傷つかず、何者にも支配されないタフで完璧な男の子だとアッシュのことを思っていたのだが、むしろ満身創痍、つねに全身から見えない血を流し、瀕死の魂でニューヨークに立っている少年だということにパパ・ディノの年齢になってようやく気づいた。
「どうしてそんなに冷静でいられるの? 私 立ちなおるのに半年かかったのよ」
物語の後半、レイプされた直後のアッシュに、同じ経験を持つジェシカが訊ねるシーンがある。
「立ちなおるのに半年かかっていたらおれはとっくに死んでる」
ほんとうはジェシカだってアッシュだって「立ちなおって」なんかいないのだろう。「強姦なんて女にとっては殺人と同じこと」と『吉祥天女』で小夜子が語るとおり、レイプによって受けた傷は生半可なものではない。しかし、だからといって生活や人生まで奪われてしまったらたまらない。これ以上相手の思いどおりにさせないためにも、お前なんかに支配されてたまるものかと示すためにも、立ちなおったようにふるまうしかないのだ。
「だから あたし 一生 許さないの」(『櫻の園』より)
八〇年代初頭に吉田秋生が描いた少女たちは、自分の尊厳を傷つけた相手をぜったいに許さないと静かに宣言する。日常的におこなわれるセクハラや気軽に行われるいたずら、近しい人から放たれる、悪気がないからこそたちの悪い無神経な言動。そういったいちいちに傷つき、その傷が呪いとなって窮屈な檻に閉じ込められてしまう日本の少女たちにできることといえば、(少なくとも当時は)相手を一生許さないことぐらいだった。アッシュのように拳銃をぶっ放してひとおもいに相手を撃ち殺せたらどんなにいいだろうと何度思ったことか。だけど私たちのいるところはニューヨークじゃなかったし、私たちはかなしいぐらい女の子だった。
私たちとおなじことでアッシュは傷つかないと思っていたかった。あるいは、傷ついたとしてもすぐに立ちなおる強さを持っているのだと。だからこそ私はアッシュに恋をし、アッシュになりたいと願い、身勝手な幻想をアッシュに投影していられた(やっぱり完全に月龍に同化した読み方をしていたんだなあ……)。
まったくなんにもわかっていなかった自分に啞然とすると同時に、こんなにも複雑で繊細なアッシュ・リンクスというヒーローを生み出した作者のたくらみに唸らされる思いである。視野が狭く、目の前の欲望に流されがちで、自分のことしか考えられない軽薄な少女を熱狂させるスペックを持ちながら、だれにも触れられない──英二だけが触れることを許された──孤独な魂を抱えている。うっ、うちらが大好きなやつじゃん!
この年になってようやく私はアッシュに出会えた気がしている。いまやアッシュはまばゆいばかりの崇拝の対象ではなく、大人として保護し、手を差し伸べてやらなくてはならない傷ついた十代の少年だ。大人になるということは、こうやって幻想をひとつひとつ捨てていくということなのかもしれない。それこそ、プレイヤーとなって借り物ではない自分の人生を生きるということ。パパ・ディノと同じ轍を踏まないためにも肝に銘じておきたい。
ニューヨークに降り立った最初の夜、時差ボケでふらふらする体を引きずるようにして、アパートの主人である(か)氏に案内してもらい、チャイナ・タウンまで飲茶を食べにいった(ちなみにアパートの最寄り駅はイースト・ブロードウェイ駅。そう、アッシュとオーサーが真夜中に対決したあの地下鉄の駅!)。
飲茶店のあるドイヤーズストリートは、「the Bloody Angle」の異名を持つ有名な通りらしく、
「マンハッタンは碁盤の目になってるから道がまっすぐでわかりやすいんだけど、唯一この路地だけは曲がっているからマンハッタンでいちばん殺人が多い。なぜかって、角を曲がった先で敵対勢力が待ちかまえているから」
という(か)氏の説明を聞いて、思わず「『BANANA FISH』じゃん!」と飛びあがってしまったが、とくにものものしい雰囲気は感じられなかった。「チャイナ・タウンへ目立たず入りこめるのは東洋人だけ」と『BANANA FISH』にはあったけれど、白人も黒人もヒスパニックもあたりまえのように行き来して、飲茶を食べ、ワンタンメンをすすっている。チャイナ・タウンにかぎらずニューヨーク全体がそんなかんじで、治安の悪さをあまり感じないどころか、日本のようにぎすぎすした雰囲気もなく、滞在中はあたりまえのように地下鉄に乗って移動していた。この街に、おそらくアッシュはもういない。








