『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
目に力があった。こういう目をする人は、薦める商品に一寸の迷いもない。どこから打ち込まれても完璧に対応できるだけの自信があるのだ。
これを持って帰って家で食べ、おいしかったからといって外商員の静緒にできることはほとんどない。地下の催事担当のマネージャーにちょろっと話をして推すくらいだ。本当に、ただそのためだけに月居さんは一樂さんを通して、外商の静緒に会いにきたのだろうか?
彼女は優れた商品開発のプランナーであると同時に、凄腕の営業でもある。起業したての忙しい時期に、空振り覚悟で時間を使うはずがない。
「いままでキャリアを積みあげてこられたのは和菓子なのに、今回はどうしてすぅぷ屋を?」
「よくぞ聞いてくださいました。まあ、簡単に言うと材料費がタダだったから」
「タダ……」
「起業コストをギリギリまで削減するために、うちは倉庫や工場を持ちません。レシピだけを考え、スープ工場に依頼します。出荷は工場から直接クライアントや店舗に発送できるシステムを利用しています。せやから必要なのはキッチンのみ。そのキッチンは鞍馬口の一樂のお父さんの持ち家でやらしてもらってます。昔ながらのかまどのある長屋で、みんなでDIYしてね。ちょっとインスタでも映えるんですよ」
と、インスタアカウントを見せられた。なるほど、よくパンフレットなどで見かける京長屋の一角に店舗兼開発用キッチンがある。五十年長らく店子だった人がお亡くなりになり、五十年ほとんど手を加えられずにいたため、一樂さんは次の店子を探さずにいたそうだ。
「ああいうお父さんやから、五十年前の長屋が残ってるなんてそのほうが価値があるいうてね。そのうち自分のお客さん用のゲストハウスにでもしようかと思ってはったらしい」
そこへ、月居さんが家族と大げんかして家を出、突然裸一貫で起業するという。資産家の後見人としてはボロ家を貸してあげるぐらいなんということはなかったのだろう。
「SNSやフリマサイトで展示品のキッチンをもらってきて、仲間たちで設置してね。ありがたいことにこういう地域だから、水道屋の息子も街の電気屋のあととりもみんな知り合いですねん」
みんなで掃除をし、ボロボロの土壁に漆喰を塗って補強し、ステンレスのキッチンを入れ、棚を作り、試食用のスペースは近所から古いミシン台をかき集めてもらってきて、天板だけをつけかえてカフェのようにした。長屋の冬はとにかく寒いので古い窯は壊さず、ストーブのようにして暖房兼煮込み料理ができるようにし、天井は抜いて断熱材を入れ替え、トイレとユニットバスも交換して店舗としてギリギリ営業できるようにもした。百万かからんかったけど、貯金がなくなりましたわ、とそれも月居さんは豪快に笑いながら話した。
「自分はいま二階の斜め天井の倉庫やったところで寝起きしてます。もともとおしゃれになんか興味がなかったから、営業用のスーツと、あとはパジャマ用のジャージと、仕事着のワークマンのつなぎ。バッグも大昔に母に買ってもらったケリーバッグ以外は全部うっぱらって開業資金にしましてん。でもねえ、不思議となんにも不自由してない。だって自分の会社があるからね」
ネイルも高価なアクセサリーもしていない、髪もさっぱりと耳を出すまで短くして、化粧も最低限。時計もアップルウォッチだしスーツも仕立てはよいが年代物だ。そんな月居さんだが、本人からあふれるポジティブなパワーのおかげで内側から輝いて見えるのだから人間はおもしろい。
(なるほど、よく寺なんかにある仏像の後ろに後光がついているのは、あれはポジティブパワーを具現化しているのかもしれないな)
よく考えれば、昔から聖職者や神様などというものは、ひたすら人にポジティブに生き、考え行動せよと勧めてくるものだ。
和気藹々と古民家DIYをし、商品をひとつひとつ練る様子は、インスタでこうしてスマホごしに見ていても楽しげで、まず一つ目の起業課題をクリアしていると言えよう。
(そう、いまどんな商売もSNSを使いこなすことが、コスト削減と宣伝効果どちらもメリットがあって大事なんだよね……)
ひとつ残念なことは、当のインスタのフォロワーがそこまで数が多くないことだ。
「そう。それも手探りなんです。写真が大事だって思ってるんですけど、なかなか定期的にアップできなくて。あとはレシピについては開発現場のことはオープンにできないので、なにを更新したらいいか悩んでます。もともと栗農家さんとのお付き合いがあって、丹波は牛も有名でしょ。出荷できない栗なんかを飼育に使ってる特別な牛や地鶏を育ててる牧場さんがあって、そこの社長さんがうちの牛でよかったら、てただで牛の骨をくれた。だから材料費はほとんどタダ。あとはそれを工場に持ち込んでスープにして、原価コストをできるだけ抑えて、うちの奥座敷のすぅぷ庵がスタートした。栗と京味噌のポタージュも、牛のボーンブロスも、コスト削減といままでのおつきあいのおかげなんですよ!」
ゆっくりと室温で冷凍すぅぷのパウチが柔らかくなっていく。月居さんは、慣れた手つきでテーブルが濡れないようにふきんを取り出して下に敷いた。
「あとはね、やっぱりすぅぷって人の人生そのものだなあって思うんです。生まれたら、お母さんのお乳の次に口にするのはすぅぷ。病気の人が死ぬ直前まで食べてるのもすぅぷでしょう。生まれたばかりの赤ちゃんにいい物食べさせたいって思うのは当然だけど、死ぬときまで美味しいもの食べたいって思うやないですか。せやけど、最後は病院食、流動食、点滴で亡くなる方も多い。歯もなくなってお肉を食べられなくなって、それでもお肉が食べたい人ってぜったいたくさんいらっしゃるやないですか」
高齢化する栗農家さんたちや、牧場主、お付き合いの深かった丹波のローカルエリアを回るたび、彼らが「もう食べられなくなった」と冗談交じりに零すのを聞いた。それがずっと心に残っていたのだと月居さんは言った。
「いろんなモノで心を満たすことはできると思います。でも、やっぱり一番は食やと思う。どんな人にでもおいしいものを食べてほしい。毎日じゃなくていい。目が悪くなったり、病気が進んでガスを使えなくなった人にだって、気軽にじっくり煮込んだ料理を食べてほしい。忙しいお母さんにだって栄養をとってほしい。いろんな美味しいレトルト食品はあるけれど、最後の最後までいっしょに寄り添えるすぅぷってええなあって思って。だって、世界中ですぅぷのない国はないでしょ。たぶん人生の基本なんですよ、すぅぷって。人は煮炊きができるようになっていまの人になったっていうでしょ」
それから、月居さんはひとつひとつ、すぅぷの原料や開発した意図などを丁寧に簡潔に話してくれた。銘月を辞めると決めたとき、幼なじみのシェフがいっしょに辞めてなにかやろうと言ってくれたこと。彼女は料理屋をやるつもりが、月居さんがこれからはECの時代、百貨店に常設店舗や工場を持たないすぅぷ屋をやりたいと説得し、ついてきてくれたこと。原価コストを抑えたぶん、冷凍にこだわったこと。パッケージを銀パウチにせず、透明の冷凍パウチにして、値段より見た目を重視したことなどを。
「銀パウチにして常温保存ができるようになれば、そりゃ送料も安くつくし、お中元やお歳暮の商品も作れます。だけど、中身が見えない。私はね鮫島さん。中身の見えないものを食べようとは思わないです。催事の店舗やフードマーケットなんかで、うちのブースを覗いてくれたお客さんが、写真を見て、それから現物を手に取る。それでちゃんとボーンブロスのすぅぷの色が見える。それで納得できる。栗と味噌のポタージュの色も見える。それで想像する。どんな味なのか。いくらインスタで映える写真をたくさん載せても、手に取るのが銀パウチじゃいまいちわくわくしない。いうたら悪いけどレトルトのカレーみたいやないですか。目で見て、納得してから買ってくれた人は、口にするまでにどんな味なのか想像している。わくわくしながら電子レンジに入れて、早く食べたいと思ってくれている。その口にするまでの時間もまた、食だと思ってるんです」
だから高くつくのはわかっているけれど冷凍と透明パウチにこだわるんだ、と月居さんは言った。言葉には力と確信と、それ以上の迫力があった。
あれは〝勝負〟だと静緒は思った。勝負をしている人の言葉には独特の力がある。そして勝ち筋が見えていると、そのことが言葉を通じて相手に伝わるのだ。いうなれば、月居さんは、銀パウチにして常温保存がきく商品にすれば、販売価格を抑えることができメリットも多いというのにあえて高くつく方法を選んだ。そちらにはそちらのメリットがある。そして、なによりこちらのやり方は高くつくがゆえに大部分の競合他社が回避している。そこに、彼女には勝ち筋が見えているのだ。
競合他社とまともにぶつかっては、最後は価格競争になって自滅する。あえて値下げ合戦を行わないようにするためには、あえて難しいほうをとるという手もある。
大昔、静緒は生クリームで勝負したいと生菓子にこだわった君斗と、何日も喧々囂々とやりあった日々を思い出していた。多くの洋菓子店が日持ちする焼き菓子をサイドメニューのように増やす中、ローベルジュはそうはしないと彼は言い切った。
『そんなどこにでもあるケーキ屋になってどうするんだ』
結果的に、焼き菓子などの商品を増やさず、生クリームやカスタードクリームだけにこだわった。ケーキはデコレーションにも凝らず、ただひたすら生クリームの量を少しでも多くしたい、爆弾のようなシュークリームを売りたいという彼の情熱に静緒は賛同し賭けた。あのときなぜ、そのような選択をしたのかうまく言語化できなかったが、いまならわかる。君斗に勝ち筋が見えていたから、その言葉に説得力と迫力と勝ち筋があったのが伝わったから、静緒はそうしたのだ。
二十年以上前の選択の意味を、いま、まったく違う商品を手がけている女性起業家から教えてもらっている。これが人生の未知数なところだ。
「いま、昔のことを思い出していました。私のよく知る成功者も、同じことをしていたなと」
言うと、月居さんはすぐに君斗のことだとわかったらしい。ぱっとうれしそうに顔をほころばせた。
「ケーキ屋といえばかわいく、デコレーションを凝る時代だったのに、ひたすら生クリームの量と質にばかりこだわったんです。でも結果的にそれが成功しました」
「うれしいな。そう言ってもらえて。だからどうしても、鮫島さんに会いたかったんです」
「私に?」
「お客さんがいないときに、ずっとお礼状を書いてた姿を見て、なんて熱心な売り子さんなんやろうって思ってたんです。それも同じ言葉じゃなくて、相手によって文面を変えていましたよね。名簿と照らし合わせながら切手を貼っていたでしょう。あれね、私もパクったんですよ」
恥ずかしそうに口を両手で覆って、月居さんは、
「あれや! うちらの客はもっとそういうの効くひとらやねんから、お礼状書かな!って、スタッフ総動員で名簿を作ってね。それからは、私もそうやけど、スタッフにもほかの店から盗める接客術があればどんどん共有しようって話しました。ローベルジュさんがパッケージを変えたときは、うちらも包装をどうしょうと会議したし、通販が最近売れてるらしいと聞いてうちも通販を始めました。ローベルジュさんは洋菓子やったからパクるのも罪悪感がなくてね。常設店舗を播磨の田舎の本店しかもってないのも、なるほどなあって勉強になりました。工場だけもってそこから直接出荷してる。あれは、ケーキにこだわってたらなかなかできへんかったですよね」
「まあ、ケーキは輸送に向いてないですから」
「それでも、生クリームが売りやからこそ、パンケーキと生クリームを冷凍便でセットで売って、お客さんにトッピングしてもらうって発想ができた。初めて見たときびっくりしましたもん。ああ、これは外に出られないお子さんがいる家庭や、おやつに困ってる忙しいお母さんが買うやろうなって。この前最中が出ましたよね。あれもいいですよね。中のクリームが商品やから、外側が変わっても変わらず売れる。いまさら古いと思われてたバタークリームがぎゅうぎゅうに詰まってておいしかったです。あのカロリーの爆弾みたいなやつ、ぜったいみんな好きですやん」
ローベルジュのことだけ褒めてくれているように聞こえるが、彼女はその何倍もの量をリサーチして、いいところだけをピックアップしてとりこむ力がある。そうして銘月庵でのおばけマロンの成功や、同業他社のやり方などを研究した上で、自分のもつルートとコネクションを最大限にいかして、すぅぷ屋を始めたのだ。
「だから、鮫島さんにうちの商品をどうしても食べてほしかったんです」
「そう言っていただけてありがたいです。でも、私は今は食品にはいないし、バイヤーでもないのでお力になれるかどうか」
「いいええ、大丈夫です。お会いできただけでもうれしい。本日はお時間ありがとうございました。もしよかったら、感想を聞きたいので連絡させていただけませんか」
きっかり一時間、時計を見てから月居さんは話を終えた。自然な流れで連絡先を交換し、お荷物になりますがとずっしりと重い冷凍スープの保冷バッグを二包み、手渡された。
「もしよかったら、こちらはお客様にでも。ローベルジュのオーナーシェフには、以前は関西中小産業食品協会のお正月の会合で何度かお会いしました。よろしくお伝えください。よかったらみなさんで京都にでも。うちは新快速で一本で来られるんで!」
最後まで浴びていたいポジティブさ全開で、月居さんは静緒に深々とお辞儀をしたあと手を振った。
***
「うわ、おいしいこのローストビーフ。山椒がきいてて初めて食べる味です。どうしたんですこれ」
最近はいつもなんだかんだともらってばかりだったので、その日は比較的早く上がれたのをいいことに桝家を試食会に誘った。きっかりと今月のノルマ二千万を売り終え、個人的消化試合と勉強に時間をあてていたらしい彼は、静緒が帰宅する頃にはきっちりトレーニングを終えていつもの気楽なバスローブ姿だったが、宴会がはじまると思ったらしく上下をグッチのジャージに着替えて静緒のフロアにやってきた。ルーフテラスで一杯やろうという魂胆らしい。
「あー、なんだこれ。こっちも初めて食べた。おいしいな。栗と京味噌って。これは特に熱出して倒れてるときにぜったい家の冷凍庫にあってほしいやつですよ」
「わかる。あとパンを浸して食べたい」
「この、あともうちょっと欲しかった、と思う絶妙の量しか入ってないのも頭いいですね」
名残惜しそうに桝家がスプーンでスープボウルの縁に残ったポタージュの残りをかき集めている。これはいろんな意味でパンが欲しくなる。
「で、いま商売のほうはどんなかんじなんです?」
「京都の鞍馬口で開発事業兼販売をして、だんだんと出るようになったっていってた。ECはとりあえず始めて、リピーターもちょくちょくいるって」
社員はシェフと月居さんの二人だけ、あとは宣伝やSNSまわりをお願いしている外注さんが一人というシンプルな会社だ。地元や道の駅などに出店する際は二人が店頭に出て店をやりくりしているのだという。
「当面の活動資金は月居さんがいままで貯めた貯金を切り崩してるんだろうけど、いつまでもそういうわけにはいかないよね。融資を受けて継続する道しかない」
飲食をやるには最低でも二年、赤字でも続けていけるだけの工面をしてからでないと失敗する、というのはよく言われていることである。飲食だけではなくなんでもそうなのだが、初期投資とは店の設備だけではなく、維持できる人件費という部分が大きい。月居さんの場合、すべての調理から製造出荷までを工場に外注し在庫を持たないスープブランド販売に着目したのがおもしろい点だった。しかも、丹波牛のガラを知り合いから無料で仕入れ、材料調達からかかわっているため、工場と直接交渉してコストも大分抑えられているのだろう。
いまは二人のスタッフはそれぞれ労務出資という形で給料を出していないのかもしれないし、さすがにシェフの月給は出しているかもしれない。とにかく二人ともほぼタダ働き同然で動いているのは確かだ。どのような会社の立ち上げ時期もそうなので、彼女たちが特別無理をしているわけではないが、最初は勢いがあっても何ヶ月と続けていくうちに疲労感が溜まっていく。そこをうまく乗り切れるかどうかは、融資の有無や店の売り上げにかかってくる。
「でも、なんで静緒さんにそんな話が? 外商のお客さんにすすめてくれってことですか」
「そうなんだよね。催事担当にはもう営業は進めてると思うんだ。外商の私にわざわざ会いにきたってことは」
「万策尽きたか、突破口を見いだしたかったからかですね。ビジネスの基本は人に会いまくることですから。静緒さんなら、昔の縁もあって会ってくれるんじゃないかと思ったんでしょうね」
問題は、月居さんたちがどの銀行に話をしているか、ということだろう。おそらく片っ端から融資を申し込んではいるだろうが、彼女のあの様子では、自分が銘月グループの創業者一族だとは話していまい。たとえ話していたとしても、月居さんはその子会社の実務部隊を取り仕切っていたという実績はあれど、所詮は会社員の一人である。しかも、実績を出したのはあくまでスイーツ。スープとはまったく客層も需要も異なる。
銀行の融資担当がどう判断するかだが、いまのご時世、スープ業界の経験のない若い女性が、なんの担保もなしに(恐らく)一千万ほどの当面の運転資金を貸してもらえるかどうか。
(君斗の場合は、実家が地元に根付いたベーカリーを長年経営していたことと、経営そのものにかかわっていた経験があること。ベーカリーの店舗内で試験販売をしていたシュークリームなどの売り上げがよかったことが評価されていた。あとは田舎では男性が起業するのに有利だというのもある。女性が一人で起業することに対する偏見は確かに存在する)
二十年前は、女性の起業はほとんど聞かなかった。しかし今の時代、徐々に増えてきていると聞く。銀行のほうも、女性の起業に対して積極的に融資をしようというセミナーを開催している。しかし、話は聞いてくれても最後の判断は、やはり担保と信用次第。
「銘月グループのお嬢様なこと、銀行に言うしかないと思うけどなあ」
「それしか突破口はないけれど、言ったところで、実家から支援を受けたりしている事実関係が無い限りはあんまりプラス条件にはならないと思いますけどね」
同じ京都育ちで太い実家を持つ、自称働く高等遊民の桝家に言わせると、京都にはそんな坊ちゃんお嬢さんが山ほどいるため、たいしたヒキにはならないという。
「銘月から出資を受けて、とか、個人的に父親からお金を借りて、その上で足りない分をとかいうならわかるんですよ。でも、月居さんの場合は家を出て完全に銘月とのかかわりを断ち切っているんですよね。銀行側もそのへん調査はしますから、ああ銘月グループの身内ゴタゴタで長女が家を出たんだな、くらいはわかってますよ。銘月との取引がある銀行ならなおさら、出資には躊躇するんじゃないですか」
「……深い考察」
「ってわけでもないです。まあ難しいってこと。おそらく京都周辺の公庫もひととおり回ったんだろうけれど、静緒さんにまで凸してくるってことは、いい感触は得られてないってことでしょうね」
「廃棄しちゃう牛の骨を使ってボーンブロスを作ってECで売るとか、まさに今風SDGsだと思うけどな。のっかりたい企業も多そうなのに」
「やりたいとこは多いでしょう。問題は、月居さんが独占できるようなアイデアでもないので、話だけ聞いてまるっとパクられる可能性のが大きいことですね」
ああそうかと、思わず大きなため息を吐いてしまった。NIMAさんがあれだけ強気に権利を主張できるのも、彼女がゼロから生み出し彼女にしか描けない世界観でキャラクターを生み出したからだ。レシピそのものに著作権を認めさせるのがどんなに難しいかは、以前君斗の知り合いのパティシエが独立する際に店側から起こされた訴訟の話で聞いた。元GOTENの桐生氏は権威あるコンクールでゴールドメダルを取っている実績があってなお、独自のレシピや販売法を認めさせるのは難しいのである。
ましてや、月居さんには桐生氏のような専門性も箔もない。牛のボーンブロスをスープとして売っているのは珍しいし、丹波牛の廃骨を利用するアイデアなども、ほかの企業がマネをしようとすればすぐに出来てしまう。
「ブランディングが大事ですよね」
強い宣伝を打つためには、ブランドの持つ独自力と方針を明確に言語化しておく必要がある。はたして月居さんはそこまで『すぅぷ庵』を研ぎ澄ませられているだろうか。
ボーンブロスのスープがあまりにも美味しくて、このまま食べ終わりたくないと思っていたときいいことを思いついた。たしか冷凍庫にまとめて炊いて冷凍しておいた五穀米がある。
「あーっ、天才じゃないですか」
土鍋にボーンブロスを二袋入れて、その中に刻みネギと冷凍ご飯をぶち込んで煮立てる。米の形が少し崩れてくる直前に、玉子を思い切って三個溶いてふわっと円をえがくようにまぜ、フタをして火を消す。そのままルーフバルコニーのテーブルにもっていくと、桝家が赤身のマグロを見つけた子猫のように感嘆の声をあげた。
「天才じゃないけど、天才でしょ」
「優勝めしですね。これは優勝」
「明日は、オマールエビのビスクのほうに米をぶち込んでチーズリゾットにするとか」
「なにそれ、ぜったいおいしいじゃないですか。優勝の上ですよ、総合優勝」
木製スプーンを握ったまま、チャンピオンポーズをする。
「これで明日も生きる理由ができました」
「おおげさな、って言いたくなるけど、私もそう」
「日々のモチベって大事ですよね。この歳になってくると大抵のおいしいものを食べたことあって、新鮮味にかけるというか。外商のお客さんがとにかく食器や食にお金をかけるのも、日々消費されるからっていうのもあるけど、食べるコトって生きるってことに直結してて、それが金持ちになるといまさら高い肉食っても、キャビア食ってもそんなに感動がないってことなんですよね。つまり楽しみの数が少なくなる」
「お金がない人はそもそも、キャビアなんて食べる機会自体がないんだけどな」
「まあ、そうなんですけど、楽しみの伸びしろがないっていうか。一般人が百グラム一万円の肉を来週食べられるってなったらがんばって生きようって思うけど、金持ちはフーンでたいしてモチベになんないじゃないですか。モチベのない人生ってわりと生きてて苦痛ですよ」
だから、俺くらいお金はあるけど縛りもある人生がちょうどいいかもしれないですよね、などと、親の所有する芦屋一等地のラグジュアリーマンションに住みながら親の信託財産で暮らし、自分の給料を全部なにで溶かしているか把握していないぼっちゃまはのたまった。
「そういう桝家は、いまはなにがモチベなの?」
「彼氏探し!」
「ああ……。そっか。最近出会いがないって言ってたね」
「アプリとか見てるけど、ほんとにこの業界狭いんで、己のフェチと好みで絞ると身内しかいないんですよ、おそろしいでしょ。夜に定点で激しく活動するようなシュチュエーションがない日々を送りすぎると、なんだか肌の調子悪くなる気がして、スキンケアのラインあげてサプリの数を増やしたんですよね」
どうりで最近コスメに詳しいはずである。
あっという間に空になった土鍋を水につけておこうと室内に戻ると、ワイングラスとボトルを手にした桝家が追いかけてきた。
「あれ、もうお開きなの? もうちょっと呑むかと思った」
まだグラスに一杯しか飲んでいない。いつもなら明日のスケジュールを薄目でうかがいつつ、白だ赤だと秘蔵の酒を持ち寄って夜景を楽しみながら呑むのだが。
「いやー、俺もほら、もうアラフォー近いし」
「まだアラサーでしょうが」
「っていうか、あなたの顔色あんまりよくないなと思って」
「え、そうかな」
思わずスマホの自撮りモードで確認してしまう。
「照明のせいじゃない?」
「あのね、同じ照明の下で何度いっしょに呑んだと思ってるんですか。せっかく早く戻ってきたんだから、今日はもう寝たほうがいいですよ」
お母さんのように言われてしまった。
「どうせ、これからバイヤー時代の同僚に、月居さんとこのスープをおすすめしたり催事に入れる店の候補聞いたりするつもりだったんでしょ。外商のお客でもないのに」
「うっ、すごいな。冴えてるな」
「ただでさえめんどくさい部下二人と刺客上司抱えてハンドリングもままならないのに、さらにややこしいこと増やして……、なんでかすごく肩入れしちゃってるみたいだけど」
長年同居をしているとそんなことまでわかるのかと感心してまじまじと顔を見てしまった。高級ラインをつかっているだけあって、毛穴がない。CMの女優のようだ。
「月居さんが、昔の自分みたいで気になりますか?」
「……うん、うまく言えないんだけど。応援したいなとは思う。勝手な思いなんだけどね、自分にはできなかったことをしようとしている女性の力になりたいというか」
「静緒さんも起業したらいいじゃない」
「あー、いや、私はそういうのは無理なんだ。昔からそうなの」
父親を早くになくして、早く独り立ちして家計を支えるためにそれなりにいい大学に入るべきであったのに、高校時代、学業に身が入らなかった。
「自分でやりたいことっていうのがあまりないの。だから進路もなかなか決まらずでね。本当なら、せっかく進学校に入ったんだから親のために国公立大学を出て、商社にでも入ればよかったんだと思う。でも、やりたいことが見つからないから勉強するモチベもなかったんだよね。それで、バイトに夢中になった」
勉強をしているよりも近所のパン屋で店をきりもりしているほうがずっと楽しかった。人と接して、やっと自分自身がそこに存在しているような気持ちになったのだ。
「自分に自信がないから、だれか輝く人の側にいたいんだよね。ケーキ屋さんがいいなあって思ったのも、やっぱりお祝いごとに近いところにいる仕事だったからでしょ。成り行きでパン屋でバイトして、成績が落ちてきて、そのときたまたま井崎先生の専門学校の話が高校の進路科に来て、あっさり推薦で決まっちゃったからもう考えないですんだ。楽をしたんだよね。親のために学費がかからない学校にいくべきなんだっていうもっともらしい選択肢を選んで、結果パティシエになる器用さも情熱もなくて。ただただ、だれかの成果物を売る仕事しかなかった」
「でも、天職でしょ」
「うん」
自分を卑下した生き方にコンプレックスを感じる時代はもう通り過ぎてしまった。いまの静緒にとっては、そういう自己嫌悪すらすでに若かったころの懐かしい思い出になりつつある。
「私にはあいにく、君斗や月居さんのようにこれを作るためにスタートアップするんだ、売って会社を大きくするんだ、といういい意味でのこだわりがない。かわりにだれか、すごい人のアイデアだったり、情熱を世に知らしめたいという思いはいつもある。クリームに出会っては感動し、スープに出合っては感動して、人生感動しっぱなし。だからひとつのことに集中できない」
夢中になるなにかがないと、尽くすためのだれかがいないと、自分が存在しないというタイプであることはわかっている。自分は根っからの宣伝企画セールスマンで、クリエイターやアーティストではない。
「まあ、そのナンバーツーの虚無、みたいな気持ちはよくわかるなあ。俺もそうですからね。最近は老化と闘うことで手一杯で自己表現することすらめんどくさいっていうね」
「三十代が老化とかいうな」
「男は女より早く老けるんですよ。知ってました? いまでも三十過ぎるとちょっと恰幅がいいほうが出世してる感とおちつきがあるから、中年太りしてるほうがスーツが似合う、なんて風潮ありますけど、あれ単に不健康なだけですから。何十年もかけて中年太りを肯定する文化を中年が作ってきただけですからね」
階段を下りて自分のスペースへと帰ろうとして、ふと彼は足をとめた。
「ん? 忘れ物?」
「いや……」
なにか美味しいものを口の中で味わうような顔つきで、
「最近、俺がしたかったのって結婚でも同棲でもなんでもなくて、ただただこういう会話なんだなって思っただけですよ」
やっぱり家猫のようにふいっと身を翻して広い室内のどこか見えないところへ消えてしまった。
(つづきは書籍でお楽しみください)
【12月6日発売予定!】
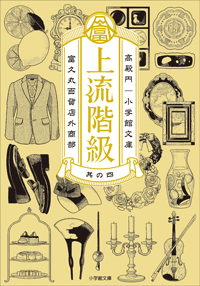
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



