『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
「一人で生きていく覚悟ができても、お金がないとどうしようもないですから」
「それな」
「どうせ静緒さんは運用とかしてないんでしょ? 老後のことを考えるとなにか手は考えておいたほうがいいですよ」
「運用……? 風呂上がりに塗る化粧水すらストック切らせてる私が運用??」
「……僕の医療用化粧水とクレ・ド・ポーのシートパックあげるから」
ミネラルウォーターをとりにいっている間に、二階から見下ろせるリビングのテーブルにあらゆるコスメグッズが並べられていた。
「春の紫外線が一年で一番きついんですから、もう冬のうちから日焼け止め塗らないとだめですよ。だから春の保湿とスキンケアが一番大事。トリートメントは三種類ぐらい使いまわさないと、髪が慣れてせっかくの栄養分吸収しなくなりますからね。シャンプーして、トリートメントつけてタオルで巻いて半身浴してから体を洗って、最後に洗い流すんですよ」
三十年ほど前に母に言われたような口調で桝家に風呂の入り方まで指導されてしまった。純粋に勉強になるので明日からすぐにそのようにしようと思う。
「ちゃんとご飯食べて寝てますか? 唇の色悪いですよ」
「え、そうかな。そういえば最近リップも塗ってないな」
「リップ塗ってどうにかなることじゃないでしょ。体中から水分が抜けて干からびてる感じしますよ。大丈夫です?」
「健康診断の結果は、そんなにたいしたことなかったよ。貧血がちょっとあるくらいで、あとはありがたいことにコレステロールも血圧も……」
ならいいんだけど、と桝家はほっと息をつき、
「お母さんのことと、家のことで去年は休みもなかったでしょ。ほんとは富久丸なんかやめて、ベンチャーの立ち上げ準備室でのんびり一年ぐらい朝ぼんやりできる休みをとるべきでしたよ。てっきりそうすると思ってたのに」
菊池屋の美魔女なんかにコキ使われちゃって、と面白くなさげに言った。ほかに渡すものがあるから待っててといわれたので、おとなしく待つ。バスルームでなにかわめきながらシャワーを浴びて、薄紫色のディオールのバスローブをかぶって出てくる彼を見るのも日常になってしまった。
「氷見塚さんの洗礼、桝家も受けてるんだ」
「だってうちの統括じゃないですか。ま、僕は下っ端なんで、その上に係長がいますけど。静緒さんみたいに期待もされてないし。採用からして違いますからね」
「桝家はキラキラのプロパーじゃないの」
「しょせんええとこのボンとかお嬢とか枠ですよ。外商にぶち込んで親戚を顧客にするだけの網みたいなものです。外商が強いとこはみんなそうでしょ。菱屋とか高砂屋も」
縁故採用とは別に、百貨店の外商で働くためだけの専門採用というのが存在したのはたしかだ。ただ、最近ではどこの百貨店も方針を変えて、そういった昔ながらの採用は減ってはいると聞く。ただ、大泉のような例がないわけではない。
(同じプロパー社員でも、香野のようにバリバリの学歴で採用されたわけじゃないから、本人も自分は実家の名前あっての採用だったと思っているんだろう。香野と比べられて息苦しい思いをしているかもしれない)
だが、それは入社前からある程度予測できたことでもある。入社して数年経つのにその言い訳を大前提にしているようでは甘いと言わざるを得ない。営業は数字がすべてだ。
「氷見塚さんなんて、関西は素通りする人。本部に帰るために手柄をさがしてるだけなんだから、静緒さんが自分の時間を他人の出世のためにささげてあげることなんてないんですよ」
「だけど、上司ってそういうものじゃない? 上にあがる人っていうか」
「だからこそやんわり抗うんです。おまえのために生きてるわけじゃないぞって常に意識しておかないと、まるっと会社って生き物に飲み込まれて気が付くとシステムの一部にされて身動きできなくなっちゃいますからね」
ぎっしりとサンプルがつまっているデパコスのショッパーを手渡された。
「これで当分しのげますよ」
持つべきものは美意識が高い同居人。無言で拝んでみせると、心底いやそうな顔をされた。
「ほんとに近くの神社とか、パワースポット行った方がいいですよ。あなたの部下は二人ともくせものだし、あの氷見塚さんに至っては妖怪なんですからね。僕なんか拝んでる場合じゃないですよ。もう一年も彼氏もいないし、この前だって目の前で素敵なフォレスティエールのジャケットをライバルに買われてしまうし」
「くやしいから、ロイヤル オークを衝動買いしたんでしょ」
オーデマ ピゲのビンテージ時計を衝動買いできる財力があれば、静緒だってここまで弱ってはいない。
「本当は、茶屋之町のあたりの桜並木を、おしゃれしてあなたとごはんにいきたかったんですよ! なんのためにこんな平日から走って歩いてトレーニングしてるかって、そんなの素敵にお洋服を着たいからじゃないですか。なのにそんなボロボロになっちゃって。菊池屋の刺客にやられてるばあいじゃないでしょ」
「上司なんだよ。どうやって避けるの」
「やる気のないとこ見せたらいいんですよ。そしたらうまく利用してこいつの手柄にのっかってやろうなんて思わないから」
およそ社会人らしからぬ高等遊民めいたセリフを口にして、桝家はコラーゲンドリンクとプロテインをおまけに追加してくれた。
モノというものは不思議だ。たとえ両手に抱えているモノがもらいもののサンプルであっても、たくさんあるというだけで人は安心感を得る。いつだったか、辛口の片付けコメンテーターが、貧乏人ほどモノを捨てられない。なぜならなにもない怖さを知っているから、どうでもいいものでも手放せないと言っていた。そういう意味では、いまの静緒も似たようなものである。
仕事がたくさんあるからどこか安心している。自分は働いている。することがあると体が自動的に動くようになっている。社会人になって二十年にもなれば、意識しなくても体が仕事をするように訓練されている。
ただ、それは若さあってのことだ。自分自身を、自然と仕事に向かうように訓練した二十年は、人生で最も体力と知力のバランスのとれている時期だった。これからは違う。体力はなくなり、知力は衰え、ホルモンバランスが崩れることによって失うものも多くなる。そして責任だけが重くなるのに、二十年訓練された体は、その責任を果たそうと自然に動くのだ。正しくは、自分を動かそうとする。
だが、いま抱えている仕事はほんとうに、静緒に必要なモノなのか? ただただ量だけがあって、本質的には必要ないものじゃないのか。いつまでも使わないのに、いつか使うかもしれない、もったいないとしまい込んでいるだけの、サンプルやもらいものなのでは?
(でも、今日みたいになにも無くなって呆然とした時にそういうものを見つけてしまうと、一種の成功体験になってしまう。それで、無くなったときのためにおいておこう、あるだけましだという考えになる。どんどんどんどん不必要なものをためこみ、抱え込んで、来るかどうかもわからない〝そのとき〟のために不必要なモノに埋もれてしまう)
とりあえず、すぐに必要なものをネットで注文した。おおかた買い物が終わったと思っていたのに、下腹部に鈍痛を感じて生理の襲来を知った。なんだか心細く不安だったのはPMSだったようだ。
(ああもう生理か。終わったばっかりだと思ったのにもう一ヶ月経ったのかあ)
昔は生理前の不安感なんて気にしたこともなかったのに、最近は大事な決断は生理前にはしないように心がけている。思えば生理前は不安でイライラし、生理中はひたすら出血を気にしてスカートの後ろが心許ない一週間を過ごす。月の半分は思い通りの自分でいられないなんて、なんて不自由なんだろう。
***
裁判、ではなく仮処分のための準備は、歴戦の猛者弁護団がついているとはいえ一般人のNIMAさんにとってはしんどいものであるらしい。モヤモヤを吹き飛ばすためにお買い物がしたいけれど、買うものがないという連絡があった。お金があるのに買いたい物がないというのは、じつは富裕層に共通する悩みではあって、そういう人たちのために〝何か〟を提案するのが外商の大切な役割である。華やかでぱーっと気分があがるお買い物をバンバンしたい、数を買いたい、というNIMAさんのリクエストに応えるためにあれこれ店頭を見て回ってみたが、そもそも店頭にあるものならば、一人で百貨店をぶらぶらするのが気晴らしのNIMAさんが買っていないはずはない。
(数を買いたい、華やかなもの)
少し前にヴァンクリーフ&アーペルのジュエリーを薦めてしまった手前、ジュエリー関係はもうネタが尽きている。もともとイラストを描くのが仕事のため、普段は上下を着心地のいいスウェットで過ごすことの多いNIMAさんにとって、服はたくさんは必要ない。当然バッグも靴も化粧品ですら必要ないので、百貨店においてあるもののほとんどは彼女の気晴らしの役に立たないということになる。
『だって、私がシャネルなんて着てどこへ行く? 裁判にでも立つ? いざ裁判にでなきゃいけないってときには、そりゃ戦闘服が必要だから上から下までシャネルのスーツを着ていくよ。でも先生たちはまだ出る必要は無いっておっしゃるし。私はいつもホテルのジャージだし。もうスニーカーは五足は買ったし。鮫島さんおすすめの、ジミー・チュウにルブタンにディオールにグッチに、あとはケリーバッグの金具がついてるエルメス』
だからこそ、彼女はデパ地下で派手に高級肉やワインを買っていたのだが、そもそもワインも質より量の人だから、そこまでお金をつかわない。現在住んでいるのがラグジュアリーホテルであり、あの巨大な豪華客船のごときホテル内には、あらゆる贅沢が詰まっている。当然、美食もエステも最高級のものが用意されていて、NIMAさんはそれにすら飽きているのだった。
クリエイターにとってストレスが一番の敵で、そのために裁判を忘れる気晴らしが欲しいというのは気持ちはよくわかる。やはりここはNIMAさんのご希望通り、このあたりか別の場所でオーシャンビューの別荘を探すべきだろうと思われた。
しかし、
『ラグジュアリー・マリーナの会員に、どんなオーシャンビューが必要だっていうのよ!』
相談した金宮寺にはややヒステリックに電話口でそうわめかれてしまった。
『ずっとそこにいればいいじゃない。全国三十カ所にある最高のホテルの居住権を持ってるのよ? 毎月季節に合わせた最高のリゾートで暮らせるのよ。あれ以上のどんなラグジュアリースイートがある? ないわよ』
彼が言うには、家族も恋人も子どももいないNIMAさんのような一匹狼クリエイターは昔から少なくなく、作家が有名温泉旅館に長居していたように、ホテル暮らしはクリエイターにはぴったりなのだそうだ。現在も帝国ホテルを住居にしている資産家や著名クリエイターは多いのだという。
『だって固定資産税はいらないし、クリーニングやベッドメイクをする必要もないしね。資産を残す必要の無いシングルにとっては、都会の一等地に住めて近場になんでもある。わざわざ家を買う必要がある人っていうと、そうねえ、インテリアにこだわりのある人かしらね』
NIMAさんが特別インテリアに興味をもちはじめたふうには見えないが、裁判が本格的に始まり、仕事も大きくなろうとしているなかで、なにか腰を落ち着けたい、もしくは自分だけのすみかを作りたいと考えているのかもしれない。
とにかく眺めがよくて広さがあってセキュリティがしっかりしている物件があったら教えてほしいと頼んだ。
『ねえ、人のことばっかりだけど、静緒の家はどうすんの?』
「あっ、そうだよね……。家、……家ね……」
金宮寺に提案してもらっている、南宮町にある中古のテラスハウスを二軒同時に買い上げる案は、とてもよさそうだが問題は資金だった。いくら駅から少し離れていて芦屋でも手頃な浜側だとはいえ五十坪以上もあればそれなりの値段はする。
『前に仮ローン審査は通っているから、四千五百万までの借り入れはできるじゃない。五千万でもそう変わらないと思うけど』
「でも月々の返済額が十五万はきついよお……」
それこそ、子どももいない静緒にとってみれば、いったいなんのために苦労して三十五年ローンを背負うのか。特段インテリアにもこだわりはないのに。
『そりゃね、五千万の現金があればアタシだって山の手にある二千五百万の借地権物件を薦めて残りの二千五百万は運用しなさいっておすすめするけど、リアルマネーがない人間の保険っていえば住宅ローンなのよ。なにせガンになったらチャラになるでしょ。ステージ1のガンでも何千万の借金が一瞬でなくなってくれるなんて住宅ローン制度だけの特権だからね。そのうち改定が入ってステージ3からとかになるわよ』
「うう、ううう……」
どんどんと情報が更新されては、古い水でいっぱいの静緒のガラスコップの上に容赦なく降り注いでくる。なにをどう受け止めていいのかすらわからず、上書きもできずに垂れ流されていくのは本当に良くない。
「最近決断力がなくなったなって思うんだ。昔はもっと思い切りがよかったのに」
『それはねえ、生命体としての本能もあるんじゃないかと思うわよ。昔は若かったから情報量も少ないし、選択肢もたくさんなかった。今は経験が増えたぶんあらゆるリスクが想像できてしまう。残された時間が少なくなって、体が動かなくなってくると自然とリスクをとるのが怖くなるのよ。この怖いっていうのは、つまり生存本能だわね』
近所に住んでいるのに、スマホ越しにしか顔を見られない彼に手を振って通信を切った。これから一樂さんに紹介された銘月リゾートのお嬢様に会って話を聞く。いったいどこに呼び出されるだろうと思っていたら、なんと阪神西宮駅のスタバだった。外商関連のお客さんにスタバに呼び出されるのは初めてかもしれない。
十分前について場所をとろうと思っていたら、電話に出た先方さんからすでに席はとってあると言われ、相手方の気合いを感じた。カフェラテを買ってフロアに行くと、すでに存在感を発している一人の女性がいる。静緒の姿を見るとすぐに立って頭を下げた。
「お忙しいところ、お時間いただきありがとうございます!」
ショートカットの三十代後半くらいの女性で、ネイビーのパンツにポロシャツというさっぱりしたいでたちだった。どこか見覚えがあるように感じるが、名前までは思いだせない。
「ああ、やっぱりローベルジュの方だ。私、実はお会いしたことあるんですよ」
月居さんはそう言ってにこにこと静緒に上座を勧めた。外商のお客さん相手に上座に座ることもそうそうないので戸惑いながらも座る。
「一樂さんからお聞きしましたけど、以前催事で?」
「そうそう、うちは実家の手伝いで銘月庵ていう店を出させていただいてましたー」
「おばけマロンの銘月庵さんですよね」
「そうそう、そうです!」
と、お嬢様は大きな朱色の目立つ紙バッグからマロン菓子を取り出した。今度ははっきりと覚えていた。ちょうどローベルジュのシュ・クレームが人気が出始めたころ、京都の和菓子屋さんが出した栗のグラッセがおいしいと君斗が並んで買っていたのを思い出したのだ。
「うちは京都でリゾートをやらしてもらってたんですけど、もともとは丹波なんですよ。で、丹波といえば栗が有名で、ホテルや旅館で出していた茶菓子を美味しいと言ってくれる人が多くて、それで持ち帰り用を作ったのが始まりなんです。おばけマロンは、丹波でとれる銀寄という品種で、4Lくらいの大きさのものになります。だいたい2L以上を丹波栗といって売るので、4Lは特級ですー。これを丁寧にグラッセにしたものがおばけマロン」
京都の人らしいイントネーションで、パンパンと話が進む。
「食べたことあります。とってもおいしかったです。やっぱり大きくて迫力ありますよね」
なにせ一粒千円。おばけという名前も伊達ではない。
「丹波のお化け栗、おばけマロンという名前は、社長さんがおつけになったんですか」
「そうですねん。はじめは茶菓子として出していたうちの家のレシピだったんですよ。名前もなにもなかったので、私が適当につけましてん」
結婚指輪のような桐のケースに一粒入っているインパクトが評判を呼んで、あっという間に催事の常連になった。
「あの売り方も、最初は親や役員に大反対されたんですけど、どうしてもやりたいって期間限定でやったんですよね。やっぱり見た目がよかったみたいで、九州のテレビの通販番組でとりあげてもらってからはすごい人気になりましたわ」
今で言うインスタ映えするお菓子だったのである。期間限定の予約者のみに送付される5Lサイズの超特大栗のマロングラッセは、毎年数が決まっていないので争奪戦になった。
その5Lサイズが催事で限定十個出るというので、地下が大騒ぎになったこともあったという。
「ローベルジュのオーナーシェフが、マロンクリームもやりたいけど、栗は扱いが難しいと試行錯誤していたのを思い出します」
「うちはもともと丹波の栗農家さんとお付き合いがあったからできたことなんですー」
昔話に花が咲いて、催事でどこへ行った、あのころの担当マネージャーのだれだれさんはもう定年で……など、会話が途切れず三十分が過ぎた。
(さすが、ただのお飾り創業者一族役員ってわけじゃない。現場に立って商品開発してきただけある)
話は自然と、月居さんの現状におよんだ。いろいろあって今は銘月グループを出て、裸一貫で創業したんだ、という。
「よくある話です。やっぱり跡取りは男だっていう風潮ですかねえ。もともと私は親に期待されてなかった。実際、勉強もあまり好きやなかった。周りはお嬢様ばかりのエスカレーター式の学校で育って。甘さもあったと思います。実家が太いからたぶんなんとかなるんやろうなっていう」
けれど、親に何度見合いを勧められても月居さんは結婚して家庭に入る気にはなれなかった。
「だって、働く楽しみを知ってしまったんで!」
快活さが、さらにガッツポーズをしているような明るさが月居さんから後光のように飛び散った。
「いままでどんなにお礼を言われても、それって親の財産だったりお金だったりしたわけですよ。だけど、銘月庵部門で働き始めて、試行錯誤してひとつ店を出し、商品を開発し、百営業して百無視されたとしても今度は二百やればええ。三百詣でればええ……そんなことをしているうちに、認めてくれるひとがぽつぽつ現れたんです。最初はたしかJR関係の父の友人、それから一樂さん。それで富久丸さんにも呼んでもらえて。すぐには結果が出なかったですけど、栗を刻んで爪楊枝を刺して、道行く人にどうですか、どうですかって丁寧にやっていたら、店舗を探して来てくださるようになる。お茶菓子にと買って行かれる富裕層の方が多くて、みんなお茶席でいつも同じようなお菓子やから、新しいものを探してたっておっしゃるんですよね。それで、ああもしかしたら高価格帯のものが求められているのかもしれない、じゃあやっぱりマロングラッセだ、って。役員たちを粘り強く説得して、銘月のホテルから引き抜いてきた幼なじみのシェフに毎日毎日、一年以上栗を煮てもらって。私も一時、食事は栗しか食べてなかったせいで大分太りましたね」
「……そういうことって、ありますよね。試食しなきゃいけないけど、まじめにやってると太っちゃうっていう」
あまりにも身に覚えがある話に、静緒は途中から自分の半生を聞いているのでは無いかと錯覚するほどだった。月居さんはスタート時点こそ大きく違うが、名も無いところから起業して新商品の開発と同時に寝る間を惜しんで営業して、お客様の反応と客筋から新商品を思いつき、それを実現化して成功を収めた。
(私といっしょだ。いや、月居さんのほうがスケールが大きい。銘月庵のおばけマロンは日持ちすることもあって、成田空港や関空などのお土産品店では必ず扱っているし、京都を代表する銘菓にだって何度も選ばれている。たしか皇室への献上品になったこともあったはず……)
数年前にオーストラリア人のユーチューバーがとりあげたことで世界的にも有名になり、近年では一番大きいサイズは予約がとれない人気商品として、どの百貨店でもとりあいになっていたのだ。
そんなマロングラッセフィーバーの仕掛け人である、京都老舗リゾート創業家の女社長が、いったいなぜ、すべてを捨てて新しい会社を作ったのだろう。同じ食品で勝負するならば、すでに成功している銘月庵でやったほうがよほど仕掛けやすいし、展開も容易だ。なにしろ実績と信頼と背景、三方良しなのだ。
「それそれ、それですねん。まあつまり、言葉はよくないけど実の弟に手柄をとられたってこと。それ自体はようある話。もうええと思ってます。実際なにもかも置いて家を出ましたから。いまは実家の家業はなにひとつやってないし、役職にもついてません。株ももってないしね。だからほんとうにすかんぴん」
アハハハハ!と大きな声で笑って、月居さんは軽く机を叩いた。彼女が笑うと、なんでもないことのように思えるのが不思議だ。
「家を出たら、なんにもないですけど、すっきりしました。いやもう、最初は住むところもなかったんですけど、気持ちだけはスッキリ。鮫島さんのように自分でなにもかも……、学校も出て就職されて、キャリアを築いていらっしゃる方には不思議に聞こえるかもしれませんけど、三十代も後半になってね、親から『おまえは銘月グループがなかったらなにもできへんのや』と言われ続けるのがね、ほんとうに辛くて。実際そうですねん。だって私、四十年近く親の金で何不自由なく生活して、学校に行って家に就職したんですもん。いくら中で商品開発してヒットさせたいうて、下駄はかせてもらってなかったわけやないですもん。みんな月居のお嬢様や、銘月リゾートの社長さんの娘はんやって私のことみてますもん。私の名前は名字が全てで、二十年社会人やって店に立って、営業やってきた実績とかそういうキャリアのなにもかもが、銘月におったらブラックホールみたいに無限に吸い込まれてしまうんですわ。そんなんもう、しんどくて」
「私のようなものが口をだすのもはばかられるんですけど、今回、一般企業に就職はお考えにはならなかったんですか?」
「もちろん考えました。せやけどなかなか難しいね。ゆっくり考えたんですよ。これからどこかの企業に入って、商品開発してそれを売り込んでってできるまで、石の上に何年かかるやろうって。若い頃やったらそういうのも大事やと思うけど、でも二十年イチからやってきただけの経験はある。それに、また同じようにヒット商品作っても、所詮外様の傭兵、いつでも手柄横取りされて追い出される。身内にやってされたんやから、きっとそうなる。苦労知らずのお嬢様やったけど、いちおう社会人やってるといろんなもん見ますやんか。なんもしてないのに、成功したらあれは俺がやった、俺もあそこにいた、チームの一人やった、ってしれっと乗っかってきてうまいこと上に上がる人とか。そういうのの踏み台にされるのももうごめんやったんです。それに、なにより親に『おばけマロンのヒットも、所詮は銘月の金でやったことやろ、銘月の名前があってやれたことやろ』て言われてなんにも言い返せない。一生私こんなふうに生きるんか、と思たらね。もういらんと。そんなことがあって、じゃあどうしたらええんやろ、そうや、今度は自分自身のブランドを作ったらええんやないやろか……」
どこまでもポジティブな月居さんは、苦労を語る時まで楽しげだった。ああ、この人になら、周りに人が集まるのではないか、一樂さんのような人も力を貸そうと思うのではないかという綺麗な空気がある。
人というものは不思議なもので、いつも上を向いてポジティブに構えている人間ほど成功する。それは、やはり自分自身の力というよりは、周りが力を貸そうと感じるからなのだろう。もっとビジネス的に言うならば、義理堅いとわかっているポジティブな人にこそ恩を売っておこうとなるし、お金を投資したいと感じる。
静緒は、今まで学歴もキャリアもたいしたことのないバツイチの自分に、なぜ過分な評価が集まるのか不思議に思っていた。しかし、外から見ているとなんとなく理解できる。自分はポジティブなつもりはないが、外からはひたすらポジティブで前向きに見えるのだろう。そういう相手に時間や手間や金を投資したいと思っている層に、自分の生き方がたまたまフィットしたのだ。
意識して前向きに生きようと思っていたわけではないので、これはもう親の教育とか、生まれ持った資質や環境が、自分という個性にあっていたとしか思えない。
「それでね。作りましてん。新しい会社」
おもむろに月居さんは、社ロゴの入った保冷バッグから凍った透明のパウチを取り出した。ゴト、ゴトと音を立ててテーブルの上に並べていく。
「合同会社A24〝京都奥座敷のすぅぷ庵。かまどのすぅぷ〟」
「A24ってのは、えにしの当て字でね。海外でも通じるように。ブランド名のほうは姑息に〝庵〟だけは実家からもらってきましてん。いうても銘月に庵つけようって言ったのは私やもん」
凍って見えなくなったパウチの表面を指で溶かしながらこすると、中がよく見えるようになった。
「これは、テールスープですか」
「そうです。健康にいいスープ屋はいっぱいあるけど、テールスープはめずらしいでしょ」
「たしかに」
最近日本でもヴィーガンブームがきていて、胃に負担をかけないスープ食が流行りつつある。ボーンブロスは牛だけではなく、鴨もあり、ほかにも丹波栗と京味噌のポタージュ、丹波地鶏の生姜チキンソテー、丹波牛のローストビーフなどどれも本当に美味しそうだ。
「いまここで食べていただけないのが歯がゆいですが、うちの店に来ていただいたらいつでもお出しします。こちらもぜひおうちでご家族と食べてください。絶対おいしいんで」
【12月6日発売予定!】
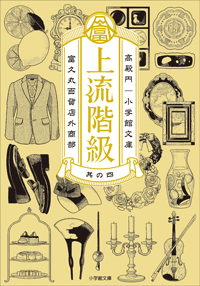
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



