『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
一樂有之さんは七十過ぎの和服の似合う老紳士で、実家は京都の清水寺近く、ボートが好きだからと芦屋浜のマリーナ近くにセカンドハウス(本当の意味ではセカンドではないだろうが)をお持ちの資産家である。
「僕の家はね。もともと上賀茂神社の上のほうでずーっと田んぼをやってたらしいのよね。昔はあのあたりはぜーんぶ田んぼでね。正確には京都じゃないんだよね」
京都には洛中と洛外という目には見えない国境線があり、京都の人の言う京都とは洛中のことを指すのだ、とはなんとなく伝え聞いていた。京都生まれの京都育ち、生粋のボンである桝家に言わせると「ああたしかに一樂さんのところは京都じゃない」らしい。よくわからない。
「明治とか大正とかのあたりなんか田んぼどころかがれきの山だったりしたのよ。それがあれよあれよという間に都会になっちゃって、うちも先代のころから田んぼつぶしてビル建てたりしてね。僕のおじいちゃんのころまではたしかに米作ってたんだけどね」
そんなボン中のボンである一樂さんは、次男ということもあってかふわっと同志社大学に入り、そのままふわっと東京に出て完全なる縁故で銀行に就職した。しかし元から労働に向いていない性格で、本人がおっしゃるには、会社を辞めたり旅に出たり絵を描いたり踊ったりしながらふわふわ生きているうちに七十年が経過していたそうだ。
「時計もね、はじめから詳しかったわけではないの。ただお友達がみんな、一樂くん時計ぐらいしなさいよ、なんておっしゃるからね。葉鳥さんに頼んで、まあ恥をかかない程度のなにか用意していただけますかってね。そしたら、ほら、葉鳥さんもまだそのころはうんとお若くて、真面目で思い込んだら一直線みたいなところがあってね。たまたま僕が、三井倶楽部で時計をしていないことをからかわれた、なんてふわっと話しちゃったもんだから、彼が血相を変えてあらゆるところから時計をかき集めてきたわけ」
当時は高度経済成長期で日本がいけいけどんどんだったころ、豊かなエンを求めて日本には世界中から良いものもそうでないものも集まっていた。大事なお客様のためにと葉鳥氏が集めてきたものはどれもすばらしく思えたが、なにせそこまで時計に執着もなかった一樂さんは、説明を聞いた後値段も聞かずに全部買い上げた。そして葉鳥氏の説明通りに、お茶席にはこの時計、クラブや同窓会など学校関連にはこの時計、ビジネスの相手との会食にはこれ、目上の人のお祝いの席にはこれとマニュアル通りに使い分けていた。ところが一樂さんは、もともと趣味人で小さい頃から当たり前のようにお茶やお花、踊りを習い、実家の資産を管理するために親に言われて古美術の資格ももっていたから、いわゆる「お呼ばれの席に合わせる」文化が自然と身になじんでいた。
「お茶席なんかでは、その日のお客さんにあわせてテーマが決まっているから、訪問着から場所、掛け軸、お道具なんかも亭主がひとひねりもふたひねりも仕込んでいてね。なぜこのようなセットになったのか謎解きをするのが楽しみの一つでもあるわけ。だから、なるほど外国の人はスーツや時計やカフスで自己表現をしたり、ホストへの敬愛を示したりするんだなあと思って、そこから興味をもったんだよ」
そうして、自前の資金力を生かしてスイスへ留学、あっという間にその世界では名の通った趣味人、日本の〝ミスタースイス〟として知られるようになった。
「ふと気づいたら、『いい時計ですね』なんて言われることが多くてね。時計からすごく話がはずむんだ。ヨットクラブなんて名前で買っただけなのに、いまじゃ手に入らないから欲しい人が多いらしい。たいして高くもなかったんだよ。でもそうなると手放せないね」
IWC社のヨットクラブは知る人ぞ知るというヨット愛好家のためのモデルなので、この時計をしているだけでさぞかしヨット好きの間で話に花が咲いただろうと思われる。静緒もIWCのパイロットウォッチが好きだ。そう言うと、じゃあ買おう、とビッグ・パイロット・ウォッチ・トップガン〝モハーヴェ・デザート〟を注文してお帰りになった。
お客様というものは不思議と連鎖するもので、その日呉宝美のフロアで一樂さんをお見送りしたあと、時任さんに声をかけられた。
「さめちゃん、いまいい?」
彼女の切羽詰まったような顔は珍しいので、次の予定を確認したあと、少しならと念押しして彼女の持ち場へ立ち寄った。
「あそこにいらっしゃる若い男性、外商に入りたいんやって」
「お客様ですか?」
「うん、さっきオーデマ ピゲのロイヤル オークご購入。クロノグラフね」
オーデマ ピゲは三大高級時計メーカーのひとつで、クロノグラフとなると約八百万だ。時任さんの仕事は今日はもう終わりである。
「それにした決め手は?」
「うーん、最初は上品で年上の人たちに受けるものがいいって悩んでたけど、最後は自分の好みにするって」
なんとなく外商を必要とする理由に察しがついたので、静緒はうなずいた。時任さんと連れだってくだんの男性に声をかけにいく。
「えーっと、あなたが外商の方ですか?」
まだ三十代半ばほどに見えるラフなカーゴパンツにTシャツ姿の男性だった。オフィスワーカーの男性に好まれるアウトドア系の高級ブランドで、靴だけがジョンロブのレザースニーカー。キャップ帽はバレンシアガ。平日の昼間にふらっと高級時計を買いにくるあたり勤め人とは思えない。
(これはNIMAさんのような、強い時計を探しに来た感じではないな)
「よろしければ、こちらでお話を承ります」
呉宝美フロア専用の別室に案内する。ガス入りの炭酸水が出されるとそれに口をつけた。ゆっくり話をしたいという客側の姿勢がよくわかる。
「お恥ずかしいことなんですけど、僕は、いままで百貨店でろくに買い物をしたことがなくて」
男性は八太諒多と名乗り、自身が投資家であることを手短に話した。服や身の回りのものを路面店で買うことはあっても、外商というシステムがあることすら最近まで知らなかったそうだ。
「こちらへは、どなたかのご紹介ですか?」
「いえ、ぶっちゃけた話ネットで調べて、高額な買い物をすれば百貨店から声がかかると聞いたので、今日一日買い物しまくっていました」
思わず時任さんと顔を見合わせた。八太さんは手ぶらだったが、すでにスーツ二着と靴、香水、バカラのワイングラスをお買い上げ済みだった。
「今日は昼から一杯やろうと思っていたので、車はもう代行に戻してもらいました。だから荷物も送りました」
「お任せいただければ、こちらで責任をもってお送りいたしますので」
「ああ、そうなんですね。そんなことまでしてくださるんですねえ。すごいなあ、外商」
正確にはこれから外商口座を開けるかどうか、つまりお得意様カードを発行できるかどうかの審査があるのだが、八太さんはさも当然というふうにうなずき、
「うちは家族もごくふつうの一般人なんですけど、僕は運良く収入だけはあるので、どうかな。とにかく外商に入りたいです」
熱のこもった視線でじいっと見られた。並々ならぬ意志を感じる。
「というか、外商に入らないといけないんです。その、僕には結婚を前提にお付き合いしている女性がいるのですが、その方が資産家の娘さんで、どこで結婚式をするのか聞かれるだろうから、ご両親に挨拶をする前に百貨店の外商に入ってくれと頼まれまして」
「なるほど」
だいたい話が読めた。横で黙って聞いていた時任さんもうなずいた。彼女にしてみれば、ここでうまく顧客になってもらえれば婚約指輪も結婚指輪も、その先にもしかしたらプッシュプレゼントも彼女の仕事になる。時任さんの目が、突然LEDに変えた家の照明のように輝きはじめた。
カードの申込書を書いてもらい、連絡先を交換してエスカレーターまで見送った。
「最近多いから、てっきりプッシュプレゼントのお客さんかと思ったら」
「日本でも増えてきたんですね、プッシュプレゼント」
リッチなセレブ夫が、出産を終えた妻やパートナーに送るお疲れ様ギフト、それがプッシュプレゼントだ。欧米ではジュエリーか車が定番で、お迎え用のレンジローバーなどが人気らしい。
「そのうちライスシャワーもイースターもするようになるよ」
「百貨店的にはイベントはあったほうがいいですしね」
「北海道物産展より安定した集客が見込めるイベントになれば、役員も夢じゃないよ、さめちゃん」
「私が? まさか」
ようやくお昼休みだという時任さんに、お礼もかねてランチをおごることにした。思ったより早く接客が済んだので三十分くらいならなんとかなりそうだ。
「ねえ、菊池屋との合併で、すぐ上がごそっと菊池屋になったってほんとうなの?」
芦屋川沿いにいくつも軒を連ねるおしゃれなカフェのテラス席があいていたので、外の空気を吸いながら一息つくことができた。
「いやいや、そんなことないでしょう。しょせんうちらは田舎の一兵卒。本部の中がどうだかは知らないです」
「でも、さめちゃんはさ、紅蔵さんの派閥じゃない」
「向こうは専務取締役ですよ?」
「オエライサンに直接連絡が取れる一兵卒なんていないよぉ」
たしかに普通の会社ならそういうこともあるかもしれない。静緒の場合、紅蔵がたまたま部長だったころにスカウトしてもらったという縁があるだけなのだったが。
「菊池屋から来た上司とはうまくいってるの?」
「氷見塚さん? いいひとそうです。いかにも出来るバリキャリって感じ」
「ウチ(富久丸)の上を押しのけて役員になりそう?」
「うーん、そうだね、それは……なりそう」
規模的にいうと富久丸と菊池屋は対等合併のはずなのだが、氷見塚のように本部のポジションもちの地方司令官の中で、同じだけの戦闘力を持ち合わせた富久丸サイドの部長級がいるかというと、
「いなそう……」
「ね。ウチは課長クラスがどうにも頼りないんだわ」
富久丸百貨店はあくまで支店のひとつであり、本体のホールディングス直属の本部社員になることこそ出世といえる。若い頃に店長を経験し、本部に戻り部長になり役員になるのが理想のコースで、外商から役員が出ることはあまりない、といわれている。所詮静緒のような外国人部隊出身の外様にはもともと縁の無い話だ。
「百貨店もさ、いろいろ変わってかなきゃ厳しいと思うんだよね」
気持ちのいいくらいにクラブサンドイッチをぺろりと平らげた時任さんが言った。
「そろそろここの建物も古くなってきたじゃない? 堂島の大阪本店も建て替えて上はオフィスに賃貸するし、ここもそうなるんだろうなあ」
全国的に百貨店が老朽化による改築工事を機に、タワー型に建て替えて上を賃貸オフィスにする事業があいついでいる。もともと一等地に敷地を持っているのだから、せっかくの土地を最大限に生かして利益を得たいのはホールディングスとして当然だし、オフィスではなく高級レジデンスとして貸し出してほしいという顧客からの要望は根強くある。とくに年配の百貨店利用層にとって、住居からエレベーターで降りただけで百貨店で買い物ができるのは魅力的だろう。百貨店としても百戸も入れば毎日定期的にやってくる顧客が確保できて言うことはない。それでも元町本店だけはまだそういう噂がないのは、本丸だけは形を変えたくないという小売りの矜持がそうさせているのだと思われた。
「とはいえ、高砂屋さんも上本町の店舗をオフィスタワーにしちゃったし、うちもいつまでもつかわからないよね」
「芦屋市は規制があって五階以上の建物を建てられないので、いいところ五階までたてて三階より上のフロアを貸し出すとかでしょうか」
「でも、いまどき感じのいい大手書店が一フロア借りてくれるようなこともなくなってるって話じゃない?」
「そもそも賃料が高すぎて、有名ファストファッションでも入ってくれないですよね」
「WからもZからも断られてるって話だよね」
最近流行っているアウトドア系の低価格で丈夫なブランドが、女性をターゲットにした新ラインを展開するにあたって、フロアに入ってほしいとラブコールをしていたが、けんもほろろに断られた、というのが内部の噂である。もっともこれは我が社だけの話ではなく、どの百貨店も同じなのだとか。
「EC、郊外型の店舗が主流になってきているよね」
この流れへの危機感は、都市部大型店舗を中心に展開する百貨店はつねに抱いていた。いまでもECつまりネット通販にはできない、我々の強みを生かした企画をあげろという檄は毎月のように飛ぶし、会議もしょっちゅう開かれている。しかしながら時任さんの言うとおり、二十年、北海道物産展以上のイベントを発明できていないのが現状なのだった。
小売りでの赤を補塡するために、不動産業がメインになっていくのもまた時代の流れなのかもしれない。カメラのフィルムを作っていた会社は化粧品を、たばこの会社は飲料を、そして酒造メーカーはサプリメントを。どの会社ものれんを守っていくのに必死だ。
「堂島がオフィスビルになっても、元町本店だけはいやだ!!」
という思いは、富久丸で働く社員だれもが抱いている共通の想いでもある。この気持ちはいったいなんなのだろうと静緒は奇妙にも思う。むりやり言語化すると、「店」は本丸ということだろうか。
「ゲーム会社が、会長の個人的な運用や、スポーツクラブ業のほうが本業になっていくんだもん。もう、なに屋でもいいから店さえやれればいいんじゃないか、と私なんかは思うけどね。時代は変わるし人も変わる。採用だってずいぶん変わったよ」
話題は、菊池屋から来た静緒の上だけではなく、下に部下がついたことに及んだ。
「私が若いころはさ、外商員はもう最初から外商員として入社してきたわけよ。いいとこのボンばっかり。さめちゃんとこの桝家くんみたいな」
「桝家はうちのでもなんでもないですが……」
「まあとにかくボンボンを雇ってたらまちがいないって感じよ。そりゃそうよ。入社前にばっちり身辺調査まであったんだから。そのほうが効率がいいっていうか、適材適所なのはわかるよ。親も外商使ってて、親のそのまた親の身代までわかってる相手を雇うほうがそりゃあいいもの。いまさめちゃんの下についてる大泉さんなんてまさにそうじゃない」
「まあ、そうですね」
「ぶち込んだキャベツを回すだけでみじん切りにするカッターみたいな新人女子なんていなかったわけよ」
そっちは香野のことを言ってるんだとわかって思わすレモネードを吹きそうになった。
「香野がなにか失礼でもしましたか?」
「私にはなんにもないけど、B社の限定バッグがどうやっても手に入らないってバックヤードで愚痴ってた。日本限定商品を買いに来たシンガポールのお客さんに申し訳ないって」
ああ、うん、とうなずくしかなかった。そればかりは外商員のコネクションがものをいう。ハイブランドに顔の利く先輩外商員と仲良くなり、融通してもらうしか方法がない。何十年も変わっていないツール。あまりにもアナログな手段なので、彼女たちZ世代にとっては理解しにくいのだろうか。
(若者を育てるのは難しいな)
しかしZ世代が顧客になるのもすぐのこと。世代が違うから理解できないで終わらせていては仕事にならない。
時任さんと別れ、バックヤードへ向かおうとしてふとフロアを見てみたい気持ちになった。外商員は百貨店の社員としても外をメインにする部隊だから、こうして気をくばっておかないと店の中の変化を見落としがちである。
百貨店の最前線といえば化粧品フロア。ディオールのシンプルだが力強いロゴとみずみずしいカラーリングのメイクアップ商品が、つやめいた黒のケースには収まりきらない魅力を放っている。そして、動線の先には女王シャネル、CとDと言われる両雄ブランドを通り過ぎるとすぐに目に入るのが、外国からの観光客の大本命資生堂だ。トム・フォードなどのメイクアップが主力のエリアから、スキンケアの覇者たちが顔をそろえるエリアに自然に足が進む。最近では、カリスマスタイリストやアーティストをプロデューサーに迎え、大手化粧品会社が開発した新規ブランドが注目を集めている。百貨店コスメながらお手頃価格で幅広い客層に支持を受けるMACやオーガニックを掲げ成功しつつあるブランド、長年のリピーターに買い支えられ揺るがない外資系ライン、どのメーカーにも特色があるからこそ、この百貨店の一階、化粧品フロアに出店できている。
そして、化粧品フロアの対面に広がるのが靴、靴、靴。百貨店の顔ともいえる婦人雑貨である。静緒のような食品あがりの元契約社員ではなく、新卒として採用された若手が最初に配属になることが多く、この場所で鍛えられて成長し、おのおのが望む部署へ出世していく。
(あれ、あの子、さっき八階で見たな)
婦人雑貨の胸バッジをつけたまだ若い女性販売員が、なぜか地下の食料品売り場にいた。手には四つの手提げ紙袋を持ち、お客様と会話を続けている。おそらく靴を購入し荷物が多くなったお客様のヘルプでここまでついてきたのだろう。
婦人雑貨の人間が、売り場を離れてお客さんにつくのは珍しい。気になって観察していると、客は牛肉店で買い物をしたあと、人気ベーカリーでパンを大量購入。パンはとにかくかさばるので、販売員の運んでいる荷物と合わせるととても一人で持てる量ではなくなった。さてどうするのだろうと思っていたら、販売員はお客様を一階へご案内。婦人雑貨のレジまで荷物を運び、お客様はというと靴ためしばき用の椅子で一息。その間に、レジ奥から宅配便の伝票をもってきた。なるほど、送れる荷物は自宅へ送ってしまうように勧めたようだ。
靴を三足分と、おそらく八階で購入したと思われる造花の壁掛け、それに高級ルームフレグランスと有名メーカーの枕を奥に運び入れ、代わりに店の紙袋に手持ちで持って帰る生鮮食品をまとめる。一足分だけ靴を手元に残してあるので、なぜ送らないのだろうと思っていると、なんとその場で履いた。早く革が伸びるように、購入した靴を履いて帰りたいというお客さんは少なくない。客が履いてきた靴を箱にしまい、メジャーを伸ばして段ボール箱の大きさを説明している。すると、新しい靴を履いて気分がよくなったのか、客はおもむろに化粧品フロアに向かった。どうやらまだ買い物を続けるようだ。
結局そのお客さんは、資生堂カウンターで基礎化粧品をいくつも購入したあと、購入したものをすべて女性販売員に預けていっしょに地下二階へ向かった。
いったいなにをするつもりなのか興味をそそられふらりとあとをつけてみる。なんと、履いてきた靴を修理専門店に預け、伝票をもらって荷物をひとつ減らすことに成功した。
(なるほどなあ!)
静緒は感心してしまった。客に負担がかからないように別フロアまで荷物を運ぶ手伝いをする。地下の食料品売り場はたいてい最後に客が立ち寄る場所だから、あのお客さんはもうすぐにも帰宅するつもりだったのだろう。しかし、思いのほか地下での買い物がかさんだせいでとても一人で持てる量ではなくなってしまった。そこへすかさず、配送サービスを勧める。客はおそらく電車利用者だろう。これをぜんぶ手持ちで帰るよりかはと提案を受け入れ一階へ戻った。そこで、販売員のほうから、靴を修理に出せば荷物をひとつ減らせると提案する。新しい靴を買いにきた客は、たいてい古い靴にトラブルを抱えているものだし、接客をする際に靴のことは聞いていたのだろう。客は靴を修理に出すことにする。すると予定をしていた段ボールの大きさに余裕が出る。同じ送料がかかるのならば、ついでの買い物はございませんかとさりげなく聞く。たとえば重たい水物がかさばりがちな化粧水などの基礎化粧品。そういえばいつも使っているものも同じだしと資生堂のカウンターへ行く。そしてまとめ買いをして荷物を販売員に預け、最後に靴も修理に出す。客は生鮮食品だけを手に店をあとにする。その足取りは気のせいか、軽やかで表情も明るく見えた。
靴だけでも四足買ったということは、よほど彼女の接客が上手だったのだろう。そして、生鮮食品フロアまで足を運んだということは、この後の流れが彼女の中で予測できていたということ。重いワインやチーズを買うようなお客様ならばきっとこうなるという、彼女独自の接客プランとデータがあるに違いない。
(靴四足を売り上げ、お客さんは八階でも高級雑貨と寝具を購入している。地下では牛肉とパン。修理に出していた靴は神戸の老舗ブランド。クレ・ド・ポーでさほどお試しをせず定番の基礎化粧品を購入。あれだけの試供品をもらっているのなら絶対常連。メイクアップのラインもクレ・ド・ポーで揃えている。ざっくり今日一日で二十万円使ってもらった計算になる)
しかし、そのうち彼女の成績に直結する靴の売り上げは半分にすぎない。彼女が売り場を離れてから、お客は店のものを予定の倍購入したが、あくまでそれは別フロアでのこと。彼女の巧みな誘導と会話、接客技術が店に貢献したことはたしかであるのに、彼女にはなんのメリットもないということになるのだ。
実際、その後の彼女の行動を目で追ってみると、大荷物を奥に持ち込まれた婦人雑貨のヘルプはあからさまに迷惑顔で、彼女自身が配送の準備をするはめになっていた。こうなると、本来の仕事であるお客様の対応がおろそかになる。フロアのチーフの目も心なしか厳しい。
彼女がフロアを離れていた時間は合計二十分。八階を加えたらもう少し長いだろう。その間、婦人靴売り場で店員を探していたお客さんの対応ができなかったことになる。
「ああ、鮫島さん。いいところに」
婦人靴売り場のサブマネージャーが困ったような顔をしてスッと静緒に近づいてきた。
「見てた見てた」
「見てましたか」
「外商のお客さん?」
「じゃ、ないみたい。でも十一課に回すから、次からお願いします」
なんだか、彼女のお客さんを自分が横取りしたようで気が引けた。あのお客さんが外商を利用するようになれば、せっかく彼女についている売り上げが、靴もまとめてぜんぶ静緒のものになってしまう。
「すごく接客がうまい子だけど、ちょっと前からうちにいるよね」
「そう。倉地さん」
さりげなく靴の並び方を整えながら、微笑みながら、ギリギリ相手に聞き取れる声量までトーンを落としながら話すのは接客業の特殊技能といえるだろう。
「倉地は、神ハブって呼ばれてるのよ。どのフロアにも客を連れて行くし、初めてのお客を連れてきてつなぐ。まさに巨大空港のように人をつなぐ神のハブ女子」
「神ハブ、女子……」
「彼女がついたお客さんはすごい買うの。いつも配送。でも、そのせいで持ち場を長時間離れるのが問題になってる」
「ああ……」
倉地凜は契約社員二年目の二十六歳。もともと派遣で来ていたという。サブマネが言うには、成績はいいから上も一目置いているし本人も本採用を望んでいるが、どうしても彼女の接客スタイルと現場の方針があわないのだとか。
「むしろ外商に向いているのでは?」
「そうだよね。まあ、契約社員じゃすぐに十一課は難しいけど。正社員になれたらぜひ鮫島さんみたいにね」
つやのある黒髪のボブスタイルにほっそりとした白い首、背はあまり高くなく、どちらかというと小柄で、容姿も華やかなタイプではない。けれど二十代半ばでだれもマネできない接客スタイルを確立している。
お客さんに買っていただける力というのは、技術であり、経験であり、なによりセンスがものを言う。努力をしなくても、魔法のように売り上げをあげる人というのはいる。こればかりはもう才能という陳腐な言葉で表現するしかない。
むしろあの小さな体から、全力でお買い物を楽しみ、素敵なものと出会っていただくんだ、というパワーを感じて、静緒は常時圧倒されていたのだった。
その日から、静緒は店に寄るたび、倉地の姿を探すようになった。たいていは一階の彼女の持ち場で接客をしていたが、やはり靴を購入後は、一階に入っているセレクトショップの店舗に同伴。大いにもりあがり、出てきたときには紙袋の数は倍になっていた。
「コール ハーンは、一九二八年にアメリカで、靴職人の兄弟弟子が組んで設立したブランドなんです〜。いまではゴルフウェアなどで有名ですが、NIKEの完全子会社になったことで、ソールが改良され、スニーカーの履きやすさと革靴の正統派の魅力がMIXした新しい時代の履き物として進化しました」
聞き耳を立てていると、静緒自身も知らなかったメーカーの歴史をさらりと会話の中に織り交ぜている。
「いきなりブランド品は手が出しにくいなあ、という方にもよくご購入いただいているラインです。デザインもスタイリッシュで、かといってスポーツブランドほどでもなく、有名すぎるブランドロゴを押し出すでもなく、価格帯もこのあたりで、手頃で素敵ですよね〜」
まず足下が新しくなると、人は上も合わせたいと思うようになる。コール ハーンのハイカットスニーカーを購入し、その場で履いてタグを切った女性客は、帽子とストールを別の店で購入。倉地のことを熟知しているのか、そのショップの店員は彼女を見てぱっと顔を明るくした。神ハブ女子が来た、と思ったことだろう。
別の日には、仕事の都合でどうしてもパンプスかローファーを履かねばならないというお客さんのために、三十秒ほどで四足選んでいた。どの棚になにがあるのか、サイズの在庫はどうなっているのかもある程度把握しているようだった。
「こちらはこれでないととおっしゃる方が多いブランドですよね〜。このゼリーのようなインソールはメーカーの特許なんです。私のような立ち仕事のリピーターさんも多いんですよ」
客が購入した靴の知識を押しつけがましくなく会話に混ぜるタイミングが秀逸で、多くの客が、この店員は信頼できそうだから、ほかの買い物の相談もしてみようか、という顔つきになるのが興味深かった。
【12月6日発売予定!】
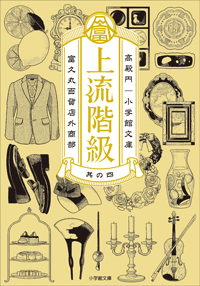
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



