『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
菊池屋との合併は、プレスで発表されてから二年かけてゆっくりと進んでいた。上の方のエライさんが何をしているのかは末端の兵隊にはあずかり知らぬこととはいえ、それなりに影響もある。長年静緒の上役だった邑智が菊池屋の名古屋支店に栄転になり、代わりに菊池屋の営業部長が本丸の統括マネージャーとしてやってきて、大号令をかけたのが先年の秋。シーズンごとにちょこちょこと人を入れ替え、そのための新しい部署が出来、統廃合されてゆく。静緒のいる外商部も営業七課になったり十一課になったり数字だけが変わり、その都度古い名刺はゴミ箱行きになった。とはいえ、静緒はただの一兵卒であるから、そんな彼女が芦屋川店の統括を兼任し直属の上司になったのはこの春だ。
「悪いわね、忙しいのに時間をとってもらって」
「いえ」
氷見塚零は五十代半ばの、いわゆるキャリア女子が理想通りに上に上がったモデルケースのような外見をした、日本橋菊池屋からはるばる関西にやってきた新しい統括マネージャーである。彼女は進戦略企画室(新ではなく進であることに意味があるらしいが、だれも社長が正月に話したことなど覚えていない)の長もかねていて、いうならば両社の合併に関して齟齬無く無理なく円満に進めるための仲人役として派遣されてきた手練れであった。
「氷見塚にはうしろめたいことでもなんでも今のうちに話しとけ」というのが、静緒を富久丸にひっぱった本店の実質トップである専務取締役、紅蔵忠士のありがたい忠告であった。これだけ大きな店の合併は双方の歴史にもない大事であり、多くの社員の人生を書き換えることになる。実際、合併を機に退職するものも増えた。
「え、森永さんおやめになるんですか」
「そうなの。だからね、ウチの古野が鮫島さんにまかせたいって」
自分のようなものが菊池屋の古野取締役と面識があったとは思えず、怪訝そうにしていると、
「二十年位前に、ローベルジュさんにいたころのあなたを催事営業として担当したことがあるそうよ。あのときにもっとひいきにしておけば良かったって言っていました」
「ああ、催事の……。そういえば、菊池屋さんには名古屋や浜松ではお世話になりました」
百貨店に常設店舗を持てない規模の店にとっては、催事は新規のお客さんにアピールし、店の価値を上げるチャンスである。もちろん呼ばれても断る人も多いが、小売りにとって食品、雑貨、服飾等にかかわらず百貨店の催事に呼ばれることがひとつのステータスであるともいえる。
「その、進戦略企画室のチーフ兼営業三課チーム長というのは、具体的にはどれくらいのリソースをチーフ業に割かねばならない業務でしょうか」
成り行きで係長試験だけは受けてはいたが、バンバン上を目指しているプロパーの友人たちとは違い、静緒は契約社員あがりの外様である。当然のことながら出世のルートも速度も違うことは百も承知だ。
急にチーフだ、チーム長だといわれても、今まで意識して仕事を見ていなかったぶんピンとこない。
「進戦略企画室は、私が統括だけれど、ようは企画をどんどん出してほしいってこと。御縁の会みたいな将来性のある企画がもっとほしいの。堂上くんから、夏前にやった高級ランジェリーのトランクショーはもともとあなたの企画だったと聞いたわ。あれは特に北海道と北陸でウケたのよ。今までだったら北海道みたいな寒い場所でレースの下着なんて売れるはずがないって思うところだけど、日本てあったかくなっちゃったのね」
もともと札幌店の店長経験のある氷見塚は、十年前はモンクレールのダウンコートばっかり売れたのに、と零した。
「私たちみたいなフツーの人間は、家にこもってる期間の長い北国で高級下着なんていつ着るの、って思うじゃない。でも発想が逆なのよね。ユニクロ着てても中はオーバドゥがいいらしいの」
「さすが堂上さんですね」
「富久丸のかにクリームコロッケ王子は、ずっと北海道に縁があるみたい」
自分がローベルジュのことを一生言われるように、堂上氏もかにクリームコロッケを北海道物産展でブームにした男として、つねに名刺代わりに呼ばれていたのだろう。彼堂上満嘉寿は先年の十月で富久丸百貨店を退職していったが、その理由の一端がわかるような気がした。
自分がローベルジュをオーナーと立ち上げ大きくしたのはもう二十年も前の話なのだ。それをいまだに言われる。それは、この二十年でそれ以上の結果を出せなかったということでもある。自分でもよくわかってはいるが、他人から二つ名がわりに呼ばれるたびに指摘されているように感じる。なかなかのいたたまれなさだ。
それを思えば、きっちり退職前に高級ランジェリーの個別即売会を立ち上げ、成功させて出て行った堂上の立つ鳥跡を濁さず感は拍手ものである。
「とにかく、チーフといっても月一の企画会議に出てもらうこと以外は営業に専念してもらえればいいから。どっちかというと、メンターのほうが忙しいかも」
「部下がつくんですか?」
「チーム長だからね。あなたが葉鳥さんにしてもらったように、そろそろ下を育てなきゃ」
タブレットを見るように言われた。起動したとたんにデータが飛んでくる。紙資料を渡されなくなったのも最近の変化だ。昔はあれだけ数が必要だったクリアファイルがたくさん家で余っている。
「とりあえず二人。一人は堂島のバイヤー五年目、もう一人は食品催事三年目、この春からあなたの下につく。それからもう一人女性の外商営業を増やしたいから、歳キャリアプロパーバイト関係なくだれかいい人いたら教えて」
教えて、というのは、探せということである。つまり大昔に静緒が引っ張り上げられたように、店舗などで店に勤務している外部の販売員で成績のいい子を引き抜きたいからよく見ておけ、ということなのだろう。
(やることが増えた……)
これでどれくらい点数があがって、給料に反映されるのかはふたを開けてみないとわからない。これが会社員の悲しいところだ。
仕事なんて生きるための方便なんですから、いくら好きでも命を削らない程度にやるといいんですよ、という桝家の口癖が聞こえた気がした。
成人式、卒業式、入学式と晴れ着関連の慌ただしい春を迎え、その背中を見送るころになるとどのフロアにも研修を終えた新人が続々と配属されてくる。店の顔が半分ほど新しくなったり、大学生のバイトがおっかなびっくり指先でレジを打つ春の風物詩が見られるフロアがあれば、宝飾やブランドフロアのように顔ぶれがほとんど変わらない場所もある。
「最近は高級品バブルで、パテックフィリップもほとんど入ってこなくなっちゃった。入ってきてもすぐ出ちゃうし、需要に供給がまったく追いついてないんだよね」
宝飾フロアのパート販売員にして実は影の主こと時任さんが、お客さんの注文を伝えに八階に立ち寄った静緒に、肩を落として言った。
「こういうモノだから、バンバン売れて欲しいかっていったら実はそうでもないんだけど、最近はちょっと売れ方が異常に感じることもあるよ。ロレックスの前は毎日長蛇の列だし」
本当に好きで大事にしてくれる人のもとへ行ってくれたらいいんだけど、と零す。
「まあね、こっちも商売だから、売れてくれればなんでもいいんだけど、でもさ毎日ガラスケース磨いて商品チェックしてたら情も移るじゃない? 何ヶ月も見向きもされなかったものを、あるお客さんがぱっと見つけて気に入ってお買い上げされたときのなんともいえない感動ってあるじゃない」
「ありますね」
売るほうも人の子だから、売る相手をよく見ている。本当に好きなのか、資産価値があるから好きなのか、見せびらかしたいのか武装したいのか、用途は客次第だが、モノに情が移るとついつい売る相手を選んでしまう。
「そういえば最近、同じような話をしたところです」
「ああ、さめちゃん出世したもんね」
「出世、っていうのかなあ、これは」
この四月から静緒には二人、直属の部下がついた。肩書きは七人の営業チームの長だが、そのうちの二人のメンターも兼ねる。さらに企画室のチーフ仕事まで上乗せされてしまった。おかげで月に三日は本部と本店での会議でつぶれるし、それ以外にも営業チームの会議を設け上に報告しなければならない。いままで一匹狼として好き勝手動いていた日々から、急にスケジュール管理しなければ首がまわらないようになってしまった。
「プロパーじゃないし、一生一兵卒だと思ってたんだけどなあ」
「いろんな意図があってのことだけど、結果だしてる人を会社が切るわけないんだから。コーヒーチケットいつもありがとうね」
地下の銀コーヒーのチケットを配り歩くついでに情報を仕入れるいつもの朝のコースも、心なしか早回しになる。
「これが出世なんだろうか?」
息苦しくなっただけのように感じるのは適性不適性だけの問題なのだろうか。
(たったこの程度のポジションアップでバタバタしてるようじゃ、転職してECベンチャーの準備室なんてまかされてたら過労でどうにかなってたかも)
パティシエ界のカリスマである恩師の井崎耀二と、幼なじみで元雇い主であるローベルジュのオーナー雨傘君斗が組んでコラボブランドを作り、本格的に海外展開に乗り出すプロジェクトは、結局静緒以外のスタッフを迎えて順調に進んでいるという。彼らからは、ゆっくりでいいからいずれ合流して欲しいと再三オファーがある。あのときは、静緒としては、富久丸の大事な顧客である清家弥栄子さんを無事お見送りできるまで、担当外商を降りられないと考えていたから、すぐに動くことはできなかった。
あれから、無事四十九日を終え、葉鳥さんはスーツを脱いでラフなポロシャツ姿でミラノへ帰国した。ああもう彼は外商としてお客さんの前に出る必要はないのだな、と思うとどこか寂しく、ついで長年にわたる重責を務め終えた姿にほっとしたような気分になった。月日が経つのは本当に速い。あの人から外商のノウハウのすべてを教えられ、そしていまもう下に教える立場にいる。
「おはようございます、おそくなってごめん」
名刺の肩書きがたった一行増えただけなのに、デスクのあるいつもの営業部のフロアで社員たちが自分を見る目が少し違う気がした。
「おはようございます」
三年目の外商部新人、大泉未玖が慌ててデスクから立ち上がり挨拶をした。もう一人がいない。十一時に営業部でと伝えておいたはずだが、連絡ミスか、それとも遅刻か。初日からこれだとしたらなかなかの大物だ。
「あの、香野さんはいまお客さんとご一緒だそうです」
「そうなの?」
「昨日の真夜中に、急にお客さんが日本に来られたそうで、朝イチで買い物がいくつもあって、いま一階でお会計通してます」
「なるほど」
海外バイヤーで経験を積んで輝かしい戦績とともに外商部に配属された香野万江は、自他共に認める若手の出世頭だ。今年のはじめに「おまえみたいなやつをよこすから、うまく育ててくれ」と紅蔵に言われてから、リサーチもしそれなりに心構えはしていたつもりだが、思っていたより香野は雰囲気も性格もいい。なにより成績がいい。
(配属されて一ヶ月で一千万売り上げるのはなかなか)
社員の売り上げは都度更新されるので、社用タブレットで彼女の動きを確認してみた。たしかに五分前に紳士服売り場で百万弱の売り上げがついている。名前から推測するに客は中国人だ。
一橋大学出身、もっと大手の商社に内定も出ていたのに、直接モノを売る現場を勉強したいと毎年二十人もとらない富久丸百貨店の最終面接で一番の高得点をたたき出し文句なしの採用になった逸材だ。バイヤー一年目から中国の富裕層相手に日本酒を売りまくり、撤退寸前だった上海の支店の建て直しに大きく貢献したことで社長賞を獲った。中国語は方言も含めて堪能で三カ国語はビジネスレベルで問題ない程度に話せるし、出身が長崎という地の利を生かして、地方特有のコネクションも太い。なにより最終面接で、富久丸百貨店が九州地方で弱い点を細かく分析し、地元の老舗M&A案から、上海長崎間のフェリー内出張店舗設営プロジェクトまで、今すぐにでも使えそうな企画をいくつも提案してみせたのは語り草となっていた。
「申し訳ありません、遅れました!」
若い子にしてははっきりとした滑舌、しかも大きな声で挨拶をしながら香野が戻ってきた。手にいくつものブランドバッグをぶら下げている。
「終わりました。お待たせしてすみません」
思いつきで日本に来る富裕層が一番欲しいのは、入国後のケアだ。彼らは手ぶらで来ることが多いので、身の回りのモノをすぐにそろえたがる。もちろん彼らの秘書がフライト前に百貨店やホテルのスタッフに連絡をいれ、現地の我々担当員がすぐに動く。中国から日本に着くまでの数時間でひととおりのものをそろえてホテルスタッフに引き取ってもらい、到着時にはすべて部屋にそろっていることがスタンダードだ。
「それは送らなくていいの?」
「えっと、こっちはディオールのソープです。DOWの秘書さんから我々に」
DOWは上海に本社を置く通信業の大手で、会長は二酸化炭素排出に反対している企業方針によりプライベートジェットを持たない主義で知られる。よって日本に来るときも定期運航便を使う。
「わ、ありがとうございます」
大泉がほんとうにうれしげに紙袋を受け取った。彼女の親は表には出してはいないが、大阪のある食品メーカーの創業者一族である。餅は餅屋とよく言うが、富豪の欲しいものは富豪出身の子女がいちばんよく知っているというわけで、昔から菱屋や大甲などの老舗呉服店系では、いわゆるいいとこのボンばかりが雇われ、外商部専属となった歴史がある。最近ではそういうあからさまな慣習もなくなってきてはいるが、超一流企業が富裕層出身の子弟を積極的に採用することはいまもあたりまえのように続いている。一種の保険だからだ。
会社が大泉に期待しているのは、もちろん親や一族を中心とした実家のコネクションであり、幼い頃からそれに囲まれて生きてきた彼女の見る目だ。野心一つを手に奨学金で上京した香野とはなにもかも正反対だが、ふしぎなことに二人ともそろって朗らかでよく気がつき、人当たりもよかった。紅蔵がアタリを送ってくれたことに感謝しかない。
もっとも、急に即戦力を見いだせ、下を育てろと上が追い立てるには理由がある。菊池屋との合併を前に、退職していった者が会社の見通し以上に多かったためだ。
(まさか板垣さんが辞めちゃうとはなあ。次の部長候補って言われていたのに)
外商部は大店ともなると百人体制で、数だけは立派だが実際売り上げを上げているのは上の二割ほど、ほかの八割はなんとなく勤務年数を重ねて、特に手柄も結果も出さずに外回りだけをしている働き蟻である。会社としてはできるだけそのようなスタッフをどこぞに追いやって、現場で実績を上げている若者を外商部に配属したいのだが、そこは会社という組織のルールと日本の法律の壁があって、なかなか切った張ったというわけにはいかない。
特に外商は、担当あってのお付き合いの面が大きいため、今回の菊池屋との合併にいい顔をしないお客さんから、けしからんことだとお叱りをうけることも少なくなかった。
「そういうときは、どんなふうに対処すればよいですか」
生真面目な大泉は疑問に思ったことはすぐに助言を求める。トラブルの種を察知する能力が高いため、あらゆる状況を想定して対処を決めておくタイプだ。対して香野は黙ってじっと聞いている。自分のやり方ではないな、と思ったことは無難に相づちをうってやりすごすが、良いと思ったことはスマホのボイスメモに録音する。手帳をもたなくなったのもこの世代の特徴だ。
「いろいろおっしゃるお客様も多いけど、口を出すってことは、うちの店に愛着があるってことだからありがたいことだと受け止めて」
「はい」
「お客さんのほうだって、菊池屋といっしょになったからって本気で取引を切りたいとは思ってない。まあ、法人でお中元お歳暮関連で数をとっている会社さんの中には最後までごねて大事になる人もいるけれど」
「そういうときはどうするんですか」
「まあ……、相手にもよるけど、店長と部長が頭を下げに行って」
「そこまでするんですか!?」
「でも、するとしてもそこまでだね。去るものは特に追わない。なぜって、どの店から買うかなんてお客さんの自由だからね」
もちろん、合併は富久丸と菊池屋だけの話ではないので、過去に他社の合併話を嫌ってこちらに切り替えたお客さんも大勢いる。しかしそういう話は狭い業界の中ではすぐに広まるし、情報は共有されていくから、結局はうちの外商をやめたからといって、他社の外商口座がすぐに開けるかといえばそうでもない。まずは〝通って〟いただきましょうかということになるだろう。
「結局はどこかで手打ちして、新しい体制でもどうぞよろしくおねがいしますで収まることが多いよ」
(お客さんだけじゃなく、外商員の転職先だってそうそうある話じゃない。たいていは辞めた後、プライベートバンクかコンサルタント、顧客のプライベートスタッフになることが多い。うちをやめて、菱屋に採用されるなんてことはほぼない)
香野が横を向いてぼそぼそとボイスメモに記録をはじめた。
静緒の年頃までは、とにかくアナログなものが商売道具とされていて、タブレットもノートも使うけれども、結局手帳がしっくりくる。しかし今のZ世代は生まれたときからスマホがあるのだから、デジタルメモでも特に違和感はないのだろう。データが飛んだらどうするんだろう、とは思うが余計なことは言わない。彼らはそのトラブルに小さい頃から慣れてきたのだ。人生に突然スマホが現れた四十代とは違うのである。
その日は、新人二人を引き連れて何人かのお客様の引き継ぎにあけくれた。静緒が葉鳥さんから引き継いだ中でも、穏やかで趣味の合う客を静緒が選んだ。小篠さんは須磨の名士で、三十歳になる娘さんが寝たきりなので、いつも季節ごとに必要なものをお届けしている。大泉の性格からしてぴったりなのではないかと思った。
芦屋の六麓荘にお住まいのエリカさんは、中国の不動産会社の社長の後妻さんで、とにかく派手なパーティが多いので、これはまさに香野にハマるのではないかと考え、二人で十分引き継ぎの打ち合わせをしてから臨んだ。
「エリカさんがネットのリアリティーショー番組にハマったらしくて、同じようにボトックスを打ち放題のパーティとかを日本でやりたいっていわれてます」
「アメリカの番組はいろいろ振り切ってるね……、とりあえず、医師の手配は個人でしてもらってください」
二人が配属になって一ヶ月も経つと、上に報告書を上げなければならない。人を評価することにあまり慣れていない静緒にとっては、これが思った以上にストレスになっていた。
堂上が去ったお得意様営業推進部改め進戦略企画室の氷見塚とは、こんなに面談する必要があるのか、と思うほどしょっちゅう顔を合わせる機会がある。彼女のほうからランチでもどう、と誘われれば、なかなか断るのは難しい。なにしろ先方にもチームにも静緒のスケジュールは筒抜けであり、その場限りのでまかせで乗り切ろうにもバリエーションがないので、三度に一度はランチやお茶にいくことになる。
(これも仕事。それに、ランチミーティングは情報交換に最適)
ただ、静緒はそのへんにふらっと入ってぼーっと食べる一人飯が好きなだけで、普段から外商員たるものだれかと話し、お茶をしながら重要な情報を手に入れるものなのだ。そうでもしなければ、上顧客さんたちが欲しがるレアな商品は手に入らない。例えばあるハイブランドの限定品は世界で二十個ほどの生産で、そのうちまずはNYに(パリは当然)、東京を含むアジア圏には二個ほど割り当てられている。日本よりも富裕層が多いといわれる中国からわざわざ買い物客がやってくるのは、円安だということもあるが、そもそも東京に割り当てられるレアな限定品目当てという目的もあるのだ。
「珍しいバーキンならいくらでも出すっていっているお客さんはたくさんいるんですよ」
中国に多くの顧客を持つ香野がストローでアイスカフェラテの氷をつつきながら言った。
「だけどなかなか手に入れられなくて。今まで何度も通ってそれなりに買い物もしたんですよ」
香野が言うには、いつ店に上顧客を連れていっても、なかなかいいものを出してくれない。それでも顧客側も三顧の礼が必要だということをわかっているので、言われるまま進められるままにそれなりにするバッグをいくつも注文して帰った。かれこれ一年はそんな調子で足繁く通っているのに、これはという限定品を薦めてもらえることはなかったという。
「鮫島さんはどうやって入手したんですか」
「うーん、それはもう地道な努力しかないかも」
「努力って、具体的には?」
「H社の店員や店長に直接働きかけても難しいなら、周囲から攻めるしかない。結局は信用の問題だから」
外商員には、ハイブランドの限定品を回してもらえるようになったら一人前、という不文律がある。だれもが知る超一流ブランドの限定品、しかもアジアで二個しかないとなればブランド側の大事な切り札だし、店のほうもだれに売るかは戦略だ。そうそう新米の外商員の顧客にまわってくるものではない。
(えらそうに構えてるけど、私だって最初は葉鳥さんに泣きついたんだったな……)
信用を得るためには愚直に年月を積み重ねていくしかないが、それでものっぴきならない事情で急に必要になるときがある。婚約指輪や不幸が迫っているときなどの特殊事情をのぞけば、それらは大抵プレスが入るパーティやショーのレセプションなど、人と知り合うために出かけるときだ。相手の素性がわからない初対面の場では、会話のきっかけはたいてい相手のセンスを褒めるところから始める。決して人の容姿には触れず、選んだ意図を褒めることによって会話を始めるためだが、相手が格上で、こちらが新参者の場合は相手の気をひくなにかが必要になる。会話をしたいと思わせるだけの珍しい時計やバッグ、靴、装飾品などは武器になるのだ。そしてそれが手に入れることが難しいと周知されていればいるほど、それを手に入れる手段を持っている相手だという情報を暗黙のうちに伝えることが可能になる。
ITや仮想通貨などの新興マーケットで富を築いたニューリッチがさらにビジネスを拡大するためには、既存の老舗や信用を得ているビッグメーカーとのつきあいが必要になる。
「大げさに言うと、イーロン・マスクの名刺をもってるだけでお金を貸してくれる銀行がいっぱいあるってことですよ」
自身も大手消費財メーカーの御曹司である桝家にとって、そのような付き合いは特にめずらしくもなんともないようで、
「女性のニューリッチが上とつなぎをつけるためになにを使ってるのかは詳しくないですが、男の場合はとにかく時計ですね。ロレックスもいいけど、やっぱりパテックフィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、普段使いならオメガ、……うーん、あとはオーデマ ピゲあたりかな」
そういう本人は一九五〇年製の手巻きのカラトラバを愛用している。理由はこれが似合うように歳をとるのが理想だからだそうで、若いのになかなかいぶし銀の趣味である。新しい客と会うときにつけている幻のグランドセイコーと呼ばれる44GSモデル(これも手巻き)は、わかる人にはわかるいい時計で話のネタになるのだそうだ。
「初恋の人が六九年生まれだったからどうしても六九年製のセイコーが欲しくて。初デートも和光だったんですよね」
「なるほど???」
ちなみに44GSは当時大卒の初任給ほどした高級腕時計で44シリーズと呼ばれ、新卒の頃この時計を目標にしていた、なんていう社長さんが大勢いるそうだ。今年グランドセイコーとして復刻されたお値段は約百十万円也。桝家はこのグランドセイコーを絶対売りまくろうと、復刻版が出る前から顧客たちに自分のアンティークを見せて44シリーズの話を念入りにふっておいたそうだ。
「だって、全世界で五百五十本しか販売されないんですよ。日本のメーカーだから百本は国内に撒いてくれますけど、それでも百本ですよ!!」
彼が思った以上に、若かりし時代を思い出してなつかしんでくれた顧客が多く、日本中に電話をしまくって苦労してかき集めていた。
「オーバーホールなんて言葉、外商に来て初めて聞いたよ」
「静緒さんは時計、しないですからね。手首が重いんでしたっけ」
「製造業やってると手袋だからね。なんとなく時計の良さがわからないまま大人になっちゃったね」
iPhone の時刻のフォントを見るのがいちばんしっくりくる静緒である
新しい部下たちとランチをして、ひととおり悩みの相談にのったあとは、自分の顧客との会食が待っている。外商員側よりお客さんのほうが詳しいことはめずらしくなく、静緒の腕時計の知識をマイナスから、それなりの基本を押さえるレベルまでたたきあげてくれたのは葉鳥から引き継いだ上顧客だった。
【12月6日発売予定!】
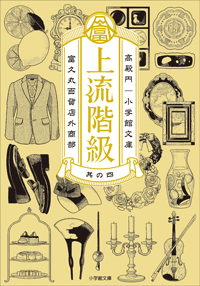
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



