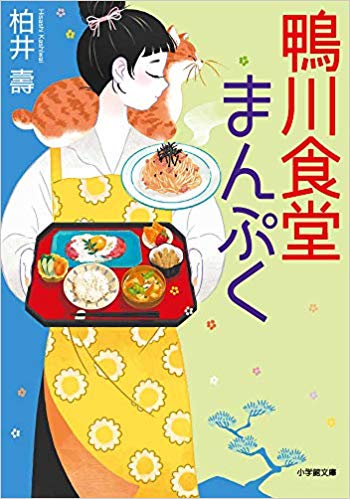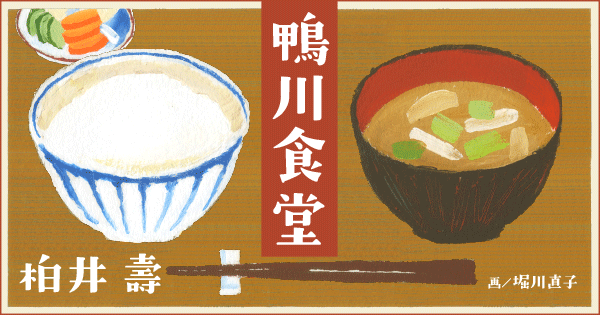「鴨川食堂」第38話 チキンライス 柏井 壽

つかれた体に、ほっと一息。どうぞ召し上がれ。
第38話 チキンライス
1.
JR京都駅の十四番ホームに降り立った市橋香織(いちはしかおり)は、小さく身震いした。
東京を出るときは蒸し暑ささえ感じていたのが、京都に着いたとたん空気が秋に変わっていた。
ベージュのパンツにオリーブ色のシャツを合わせ、紺色のジャケットを羽織った香織は、ホームからコンコースへ降りるエスカレーターに乗ろうとして、右か左のどちらに立つか迷い、二段ほどやり過ごした。
東京だと無意識に左側に立つのだが、関西は左を空けて右に立つのが一般的だ。そう香織に教えたのは、桑野毅彦(くわのたけひこ)だった。二年後には四十歳を迎える香織にとって、これまでにただひとり恋人と呼んだ男性である。
毅彦を人生最初で最後の恋人にしようと固く心に決めて、この秋でちょうど十五年になるのだが、香織の決意は夏の陽炎(かげろう)のように、ゆらゆらと揺らぎ始めている。その揺らぎを止めることができるのは、あのひと皿の料理だけだと思って京都にやってきた。
JR京都駅の中央口を出た香織は、烏丸(からすま)通をまっすぐ北に向かって歩く。京都タワーの辺りは十五年前とまったく景色が違っているようで、しかし何も変わっていないのかもしれない。
京都に限ったことではない。東京の街を歩いていても、あのころはぴったり寄り添う毅彦の顔しか見ていなかったのだから、街並みなどほとんど記憶に残っていない。
──食捜します 鴨川(かもがわ)食堂・鴨川探偵事務所──
たった一行だけの雑誌広告を見て、蜘蛛の糸を見つけたような気になった香織は、ネットの情報をつぶさに検索して、なんとかそれらしき場所をさぐりあてた。表向きは食堂のようだが、そこには暖簾はおろか、表札も看板も出ていないそうだから、どうすれば辿りつけるのか。不安は山のように積もっている。
ネットの情報なんて信用できないとも思うが、今はそれに頼るしかない。香織は七条通を越え、正面(しょうめん)通を東に折れた。
『東本願寺(ひがしほんがんじ)』が近いせいか、仏具屋や法衣を商う店、仏壇屋などが建ち並んでいるものの、それらしき建物は見当たらない。探偵事務所はおろか、食堂らしき店もまったく見当たらない。
香織は正面通の両側を一軒一軒覗きこんでは首をかしげ、少しずつ東に歩を進めていく。
両側を数えて十数軒目だろうか。一軒のしもたやの前で、香織の足がぴたりと止まった。
何ひとつ目印はないが、この家のまわりには食べ物の香りが漂っている。もちろん、ふつうの民家で、ただ食事の支度をしているだけかもしれない。もし間違いだったとしても、謝れば済むことだ。半信半疑ながら、香織は思い切って、引き戸をがらがらと引いた。
「こんにちは」
がらんとした家のなかに香織の声がこだまする。
カウンター席らしきものがあり、テーブル席も並んでいる。客の姿こそ見当たらないが間違いなくここは食堂だろう。そしてこの店の奥にはきっと〈鴨川探偵事務所〉がある。そう思うと香織の胸の鼓動は高まった。
自分の声のこだまが消えてすぐ、似たようなトーンの声が奥から返ってきた。
「おいでやす。ちょっと待ってくださいね」
背伸びして覗きこめば厨房があり、料理を仕込んでいるのか、鍋から湯気が出ていて、出汁の香りも漂ってくる。
東京の下町には、こんな居酒屋もよくある。高級割烹店の対極にあるような、場末の居酒屋だけど、知る人ぞ知る店とあって、よほどの常連客でないと門前払いを食らう。そんな店に連れて行ってくれたのも毅彦だった。
「お待たせしました。食堂の主人はちょっと留守してますんで、お食事やったらしばらく待ってもらわんとあきませんけど」
奥から出てきた、白いポロシャツに黒のソムリエエプロンを着けた女性は、香織より五歳ほど若く見える。
「食事じゃなくて、〈鴨川探偵事務所〉を捜しているのですが、こちらではありませんか?」
香織がおそるおそる訊いた。
「なんや。探偵のほうやったんですか。〈鴨川探偵事務所〉やったら、この奥にあります。うちが所長の鴨川こいしです」
口角を上げて、こいしが小さく会釈した。
「ということは、食を捜してくださるのはあなたなのですか」
香織は不安そうな表情を隠すことなく、上目遣いにこいしの顔を覗いた。
「心配しはらんでも大丈夫。ほんまに捜すのはお父ちゃんで、うちは聞き役専門ですねんよ」
「お父さま、ですか」
香織の不安はまだ消え去っていない。あのことがあってから、なんでも疑ってかかるようになってしまったのだ。
「この〈鴨川食堂〉の主人で、うちのお父ちゃん。元刑事やったさかい、どんなもんでも捜すのは得意なんです」
「そうでしたか。市橋香織と言います。食を捜していただきたくて東京から参りました」
元刑事という言葉を聞いて急に声が明るくなった。肩の力を抜いた香織は、笑顔でこいしにあいさつした。
「香織さん、お腹のほうはどうです。空(す)いてはるようやったら、ちょっと待ってもらえますか? お父ちゃんが帰って来はったら、美味しいもん作ってくれはるんで」
「ありがとうございます。お昼を食べてないのでお腹も空いてはいるんですが、探偵さんに先にお話を聞いてもらったほうがいいかなと」
「そうやねぇ。野菜を仕入れに行ってはるだけやから、そない遅ぅはならへんと思うんやけど、寄り道とかしてはったら、お待たせせんとあきませんしね」
「よろしくお願いします」
香織が頭を下げると、こいしはメモ用紙を広げてペンを手に問いかけた。
「捜してはる食はちょっと横に置いといて、苦手な食べもんとかあります? アレルギーとか」
「牡蠣(かき)がダメなんです。あとムール貝も。それ以外は大丈夫です」
「──探偵のほうのお客さん。若い女の人。奥で先に話聞いてます。お腹空かせてはる。牡蠣とムール貝はアカン──と。お父ちゃんが帰って来はって、これ読んだら分かってくれると思います」
こいしがメモ用紙に走り書きした。
「それだけで通じるってすごいですね。いつもこんな感じなんですか」
「はじめて。いっつもは、先にお父ちゃんが作った料理を食べてもろてから話を聞くんで」
「すみません。なんだかイレギュラーなことになってしまったみたいで」
「気にせんといてください。たまにはこんなんも気分が変わってええと思います。どうぞ奥のほうへ」
厨房を横目にして、こいしが長い廊下を歩きだし、香織はあわててそのあとを追った。
「このお写真は?」
廊下の両側にびっしり貼られた料理写真に目を近づけて、香織の足が止まった。
「ほとんどぜんぶお父ちゃんが作らはったんですよ。レシピを書くのが面倒くさい言うて、写真で残してはるんです」
振り向いたこいしは誇らしげに胸を張った。
「さっき、お父さまは元刑事だとおっしゃいましたよね」
「ええ」
「刑事をしておられて、こんな料理も作ってられたんですか?」
「まぁ、いろいろあるんですわ。それはええとして、まずは捜してはる食のことをお訊きせんと。ここが〈鴨川探偵事務所〉です。どうぞおはいりください」
廊下の突き当たりまで来たこいしは、ドアを開けて香織を招き入れた。
ジャケットを脱いだ香織は、ローテーブルをはさみ、こいしと向かい合ってロングソファに腰かけ、部屋のなかをぐるりと見まわしている。
「香織さん。いちおうこちらに記入してもらえますか。簡単でええので」
こいしがローテーブルにバインダーを置くと、素早く手に取った香織は、揃えた両膝の上に置いて、すらすらとペンを走らせている。
「お茶かコーヒーか、どっちがよろしい?」
「お茶をいただきます」
ペンを持ったままで香織が答えた。
万古焼の急須にポットからお湯を注ぎ、しばらく茶葉を蒸らす。急須のふたに手を置いたまま、こいしは香織の様子を横目でうかがっている。
「これでよろしいでしょうか」
書き終えて、香織がバインダーの向きを変え、ローテーブルに置いた。
「ありがとうございます」
バインダーに目を落としながら、こいしが京焼の湯吞を茶托に載せて香織の前に置いた。
「さすが京都ですね。いい香りがする」
湯吞を手にした香織が鼻先に近づけた。
「市橋香織さん。三十八歳。独身。東京都渋谷区のスポーツウェアのお店にお勤め。お住まいは都内北区赤羽台(あかばねだい)。て、どの辺のことなんです? 渋谷はなんとなく分かりますけど、東京は広いさかい、赤羽台て見当も付きませんわ」
まずはどんなところに住んでいるのか。それを知ることがひとつの手がかりになる。これまでの経験でそれを知ったこいしは、タブレットを操作して地図アプリを開いた。
「大ざっぱに言えば、東京都の北のはずれ。赤羽から荒川を越えれば、もうそこは埼玉。わたしの故郷なんです」
たしかにすぐ北に県境があるから、東京都の一番北の端。香織の生まれが埼玉だということも頭に入れた。
「早速ですけど、どんな食を捜してはるんですか」
バインダーの横にあったノートを広げたこいしは、香織とまっすぐ向き合った。
「チキンライスです」
「えらいかわいらしい料理を捜してはるんですね。子どものときの思い出か何かですか」
オムライスを食べることはあっても、チキンライスを食べることはめったにない。こいしは記憶の糸をたぐり、掬子(きくこ)がお弁当に作ってくれた、グリンピースだらけのそれを思いだした。
「いえ。今から十五年ほど前に、中華料理屋さんで食べたチキンライスです」
「東京では中華料理屋さんにチキンライスがあるんですか」
開いたノートの綴じ目を押さえながら、こいしは目を見開いた。
「メニューには載ってないのを、お店のおばちゃんがわたしのためにわざわざ作ってくれたんです。以前に好物を訊かれて、チキンライスって答えたのを、おばちゃんが覚えていてくれたのだと思います」
「リクエストしはったということですか?」
「いえ。何も言わずに今日はこれを食べなさいと言って」
「なんや不思議な話ですね。詳しいに聞かせてもろてもよろしいか」
こいしがペンをかまえた。
「東京に出てきて、ひとり暮らしをはじめてから夜はほとんど毎日外食でした。仕事を終えてアパートへ帰るまえに、駅の近くのお店で食べて帰るというパターンで、お気に入りの店を順番に回っていました。そのなかの一軒が隣の駅前にある中華屋さんで、何を食べても安くて美味しいのにいつもヒマそうな店でした。酢豚とか、天津飯とか、甘酸っぱい料理が好きで、たいていそれを頼んでました。ひとりで切り盛りしているお店のおばちゃんは、かならず話しかけてくれたので、いつしかわたしも身の上話をするようになってました」
「恋バナとか?」
「はい。上司の愚痴とか、仕事の悩みとか、おばちゃんは聞きじょうずなので、包み隠さずなんでも話してました。母親代わりっていうところでしたね」
「京都でもそういうおばちゃん、ようやはりますわ」
こいしはノートにそれらしき女性のイラストを描いている。
「おせじにもきれいとは言えない店でしたけど、思い切って恋人を連れて行ったんです。わたしはこういうお店の料理が好きだと彼に伝えたかったのと、結婚しようと思っていた相手だったので、おばちゃんに紹介しておきたかったんです」
「ほんまのお母さん以上の存在やったんかもしれませんね」
「はい。おばちゃんもすごく喜んでくれて、彼のことも気に入ってくれたようでした」
「よかったですやん。次はほんまのお母さんの番やね」
「そう思っていた矢先のことです。それから三日ほどが経ってお店に行き、いつものように注文しようとしたらおばちゃんが、今日はチキンライスを作るからそれを食べなさいと言ったんです。もちろんメニューにも載ってませんし、びっくりしたんですが、断る理由もありませんし、いただくことにしました」
こいしはチキンライスらしきイラストをノートに描いている。
「なんでその日に香織さんの好物のチキンライスを作らはったんやろ」
「それがいまだに分からないんです」
「そのおばちゃんに訊いてみはったらよろしいやん」
「それからお店に行かなくなってしまったので」
「なんでです? 料理も気に入ってはって、お母さん代わりのおばちゃんがやはって、恋人まで紹介するぐらい親しいしてはったのに。おばちゃんと喧嘩でもしはったんですか?」
「喧嘩って言うより、一方的におばちゃんから責められたんです。なぜあんな男を選んだのか、とか、早く別れたほうがいい、とか」
「いきなりですか?」
「そう。いきなりだったんで、ただただびっくりしてしまって。チキンライスが出てきて食べはじめたら、唐突に言いだされて気が動転してしまいました」
香織が顔をゆがめた。
「彼と一緒にお店へ行かはったときに何かありましたか? おばちゃんともめはったとか」
「とんでもない。帰るときは店の外までわざわざ出てきて見送ってくれたぐらいです。食事中も、しあわせにしてやりなさいね、と彼に言ってましたし」
「それで三日後にいきなり、ですか。たしかになぞやねぇ」
こいしはノートにクエスチョンマークを書き並べた。