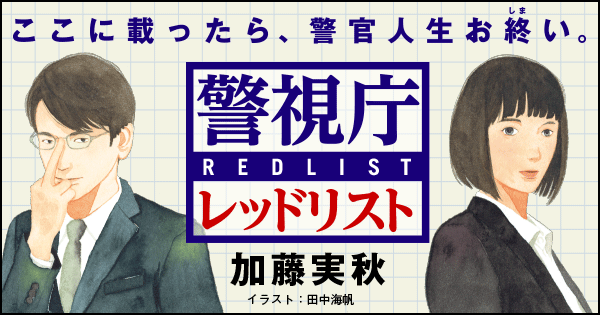〈第4回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

かと思われた事案は、
再調査で思わぬ結末に。
CASE1 赤文字リスト:退路を断たれた二人(4)
10
翌日、午前九時。みひろと慎は日本橋署の会議室にいた。長机の向かいには、星井巡査部長。
「これって昨夜(ゆうべ)? 来てたんですか? 全然気がつかなかった」
机上の写真を見るなり、星井は慎が投げかけた質問を無視して訊ねた。写真には白いドレス姿でソファに座り、客と話したり酒を飲んだりする星井が写っている。
ノートパソコンのキーボードを叩く手を止め、慎は質問を繰り返した。
「あなたは半年前から退署後、墨田(すみだ)区錦糸町のキャバクラ『CLUB G-RUSH』で働いていますね?」
「はい」
顔を上げ、星井は答えた。こちらをまっすぐに見る眼差しと低く落ち着いた声は、最初の面談や一昨日の聴取とも、昨夜の店での様子とも違う。驚きながらも、みひろは今が本来の星井なんだなと感じた。
「警視庁の職員が無許可で副業を行った場合、地方公務員法第三十八条・営利企業への従事等の制限に違反し、処分の対象となります。それを知った上で働いていたんですか?」
「ええ」
「不倫に加えて副業。事態は一変ですね。厳重な処分を覚悟して下さい」
「わかりました」
動じないのを通り越しふてぶてしさすら感じさせる星井だが、ヤケになっているのかもしれない。みひろは問いかけた。
「なぜ副業を始めたんですか?」
「欲しいバッグがあったんです。買ったら辞めるつもりだったんですけど、黒須さんに見つかっちゃって。二カ月ぐらい前に偶然、草野球チームの人と店に来たんです」
ああ、そういうこと。合点がいき、みひろは大きく頷いてからさらに問うた。
「それで、『署にバラすぞ』って関係を強要されたんですか? 『仕方なく会っていた』ってそういうこと?」
「違う違う」、みひろに合わせてタメ口になり、星井は首を横に振った。
「黒須さんは『別人みたい。すごく綺麗』って私を気に入って、店に通い詰めて指名してくれました。で、同伴とかアフターとか行ってるうちにそういう関係になって。そうしたら黒須さんは『嫁と別れるから、店を辞めて俺と結婚して』って言いだしたんです。もちろん、こっちはそんな気ないから断ったんですけど、黒須さんから毎日『会いたい』『来るまでホテルで待ってる』ってメールや電話が来るようになりました。なんかもう、怖くなっちゃって」
それで会う頻度が増えたのか。ピンと来て、不倫の強要について答えた時の黒須の目も浮かんで腑に落ち、みひろは「ああ」と頷いた。それを自分への理解または同情と受け取ったのか、星井はさらに言った。
「何度『別れたい』って言っても聞いてくれないし、普通に話し合っても絶対に無理。誰かになんとかしてもらわなきゃダメだと思って」
「ひょっとして、職場改善ホットラインに電話をしたのはあなた? 自分で自分の不倫を通報したの?」
閃くのと同時に訊ねていた。「はい」と星井は即答した。みひろは絶句し、慎も驚いた様子で顔を上げる。二人の視線を受け、星井は自慢のニュアンスの感じられる口調で返した。
「『それどころじゃない』って状況にならないと、黒須さんがストーカー化してつきまとうのは確実だったから。でも、怖くて困っていたのは本当なんです。すみませんでした」
最後に頭を下げる。気づけば、ここに来て星井が謝罪の言葉を口にしたのは初めてのことだ。しかも、さして罪の意識を感じていないのは確かだ。
「『厳重な処分』って、クビですか? 赤文字リストに名前が載るんですよね」
あっけらかんと、星井が問うた。急に赤文字リストを持ち出されてみひろはぎょっとし、慎もとっさに言葉を返せない。目を輝かせ、星井はみひろと慎を交互に見た。
「えっ。赤文字リストって本当にあるんですか? 最後に教えて下さいよ」
早口だったが星井がわずかに「最後」を強調したのに、みひろは気づいた。
私と室長に会うのは、って意味? それとも……。改めて向かいを見て、みひろは訊き返した。
「星井さん。始めから警察を辞めるつもりだったでしょう? 辞めた後、黒須さんにつきまとわれるのを避けるために、監察係に処分させようと考えて通報したのね」
そう考えれば、これまでの星井の言動も今の態度も納得がいく。規則違反がバレてヤケになったのではなく、始めから警察という職場に見切りを付け、職務への熱意も責任感も棄てていたのだ。みひろは確信を得、同時に理不尽さと怒りを覚えた。しかし星井は首を傾げ、素っ気なく答えた。
「さあ。どのみちいなくなるんだし、関係なくないですか?」
「関係なくなくない訳ないでしょ!」
早口言葉のようになってしまい、ちょっと突っかかりながらも告げてみひろは立ち上がった。驚いて星井が目を見開き、慎もこちらを振り向くのがわかった。
「辞めるのは勝手だけど、どれだけ迷惑をかけるのよ。自分でしたことの尻拭いを、人にやらせるな。しかもあれもこれも、使ったのは国民の血税だ。断じて許せない。公務員とか警察官とか以前の問題。あんたなんか、どんな仕事に就いたってダメ。一生『プロ』にはなれない!」
後半は演説口調になって捲し立て、向かいを指して断言した。星井は啞然。しかし最後の一フレーズに反応し、ダークブラウンのアイブロウで描かれた眉がわずかに上がったのをみひろは見逃さなかった。
「お説ごもっともですが、その辺で」
咳払いとともに慎に制され、みひろは「すみません」と椅子に腰を戻した。間違ったことを言ったとは思わないが、このざわめいて収まりの悪い空気をどうするのか。みひろが焦ると、慎は星井に顔を向けた。
「いつどんな辞め方をしたにせよ、職員の記録は警視庁内に残ります。今後もし、あなたが何らかの犯罪に巻き込まれ警察に助けを求めた場合、対応した警察官がその記録を照会するかもしれません。だからといって保護や捜査が疎かになる可能性は皆無ですが、彼らも人間だということは覚えておいて下さい」
よく通る声で表情をぴくりとも動かさず、一気に告げた。反対に星井はうろたえ、返した。
「なんですか、それ。脅し? ヒトイチの人がそんなこと言って――」
「『脅し』? とんでもない。僕は『覚えておいて下さい』とお願いしただけです」
きっぱりと言い、慎は右手の中指でメガネのブリッジを押し上げた。レンズの奥の目はみひろがびくりとするほど冷たく、星井の顔もみるみる強ばっていった。室内の空気のざわめきは消え、張り詰めて冷え冷えとしたものに変わった。