月刊 本の窓 スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 第3回 室屋義秀
“空のF1”と呼ばれるエアレースで世界的に活躍する日本人選手がいる。18歳からグライダーに乗り、アメリカで研鑽を積み栄光を摑み、そして被災地福島の復興に尽力する男の人生哲学とは?

レッドブル・エアレースで世界と戦う室屋。国内ではエアロバティックス(曲技飛行)を周知させるべく、全国でエアショーを実施。その他スカイスポーツ振興活動に加えて地元福島の復興支援活動や子どもプロジェクトなどにも参画する。
室屋義秀(44歳)
(レッドブル・エアレース・パイロット)
Photograph:Yoshihiro Koike
欧米の人々から“サムライ”と敬われているパイロットがいる。レッドブル・エアレースで世界一の操縦技術を証明した室屋義秀だ。両手で操縦桿を握るスタイルは、刀を持つ侍のよう。冷静沈着なレース運びで、世界中の航空ファンを唸らせ、羨望と憧れの眼差しを集める。
世界最高の飛行技術を持つ選ばれし十四人のみが出場できる究極の三次元モータースポーツ「レッドブル・エアレース」。時速三百七十キロ、最高重力十Gという、想像を超える世界でタイムを競う同スポーツは、「空のF1」と呼ばれ、欧米を中心に多くの人を惹きつけている。室屋は、そこに出場できる唯一の日本人でアジア人。誰よりも目立つ存在の室屋へ向けられる“熱狂”は、これ以上ないほどに白熱している。
同レースは、世界七か国で全八レースを戦い、総合ポイントで年間チャンピオンが決まる。室屋の活躍もあって、この六月には三年連続三度目の千葉大会が開催されたが、日本での凱旋レースで、室屋は昨年に続く優勝という“連覇”を遂げた。今季はその前のサンディエゴ大会でも優勝したので、いわば“ダブル連覇”も達成。さらに七月のブダペスト大会で三位入賞を果たし、総合ポイントで単独首位となり、年間チャンピオンの筆頭候補として最大級の注目を集めている。
千葉大会での優勝会見では、ベテランMCから「空ゆくサムライ(Samurai in the sky)」と煽られ、各国のメディアが口々に「ヨシ(室屋のニックネーム)!」「YEAH!!!」と大歓迎したほど。いかに室屋がリスペクトされているかがわかった。
その一方で、日本のメディアやファンからは、「室屋さん」と慕われてやまない。流暢な英語を操る現代の「サムライ」は、航空後進国の日本でゼロから道を切り拓いてきたパイオニアだ。どこか達観した雰囲気すら漂わせる四十四歳の超人パイロットは、何度も人生最大級の苦難を乗り越えた「不屈の人」だった。
フリーターを経て三千万円の借金スタート
挫折と失意を乗り越え「操縦技術世界一」へ
ごく普通のサラリーマンの家庭に生まれたという室屋は、子どもの頃から乗り物が大好きだったという。飛行機に乗っては窓にかじり付き、パイロットになる夢を膨らませた。その思いを抱きながら、中央大学に進学し、航空部に入部。そして、エンジンのない飛行機「グライダー」で空を飛びはじめた。
気流が滑空の“動力”であるグライダーは、気象条件などの知識や経験を積んで、操縦技術を磨くことができる。そのうちに室屋は「もっと自由に空を飛びたい」とエンジンを積んだ飛行機への熱意を抱くように。そこで在学中、アルバイトでお金を貯めて航空先進国アメリカへ渡り、現地の飛行学校に通うと、大学二年で飛行機免許を取得。だが卒業後は就職氷河期でパイロットになる道はなかった。
そんな時、兵庫県の但馬空港でエアロバティックス(曲技飛行)の世界大会(ブライトリング・ワールドカップ)が開催される。これを見た室屋は度肝を抜かれ、この道で「操縦技術世界一」を目指すことを決意した。
「空のフィギュアスケート」とも呼ばれるエアロバティックス。大空を舞うように飛行するこの競技の難易度は、三次元だけに、文字どおり、次元が異なる。室屋によると、飛行機で単なる宙返りをするだけなら、ある程度の飛行技術があるパイロットならできるといい、自動車でたとえるなら車線をはみ出さずに走るというレベル。だが、次々と高度な技を繰り出すエアロバティックスは、同じく自動車でたとえると、車の両脇が一センチずつしか空いていない壁の間を時速二百キロで走り抜けるような世界という。
かくして「操縦技術世界一」という目標を掲げ、エアロバティックスに挑戦しはじめた室屋だったが、日本では練習場も教えてくれる人も飛行機も、何もかもが身近に存在しない。そこで再び渡米して、人生初の教官ランディ・ガニエ氏に師事するように。だが、二十代前半の室屋に「世界チャンピオンになれる」と励ましたガニエ氏が飛行機事故で急逝。室屋は自暴自棄になり、東京でフリーターとしてくすぶる日々を重ねた。
その後、困窮する生活が続いたが、再び「操縦技術世界一」への思いを諦められず、アルバイトを掛け持ちして軍資金をかき集めると、今もベースにしている福島県の「ふくしまスカイパーク」の近くへ引っ越した。自家用機のオーナーの手伝いをしては飛ばせてもらったが、それではエアロバティックスの練習にはならない。そこで一念発起して、練習機を購入。三千万円の借金を背負ってスタートを切った。
返す当てもなく、あるのは情熱だけ。だが、そのひたむきな姿勢は多くの支援者を引き寄せていった。以来、室屋は身を粉にして働きながら、世界各地のエアロバティックスの大会に出場し、腕を磨き続けた。そして二〇〇六年、エアレースの運営に携わると、エアレースの発起人の一人で世界トップパイロットのピーター・ベゼネイに見出され、二〇〇九年に三十六歳でエアレースデビュー。訓練を積み、戦い続け、昨季ようやく千葉大会で悲願の初勝利をあげたのだった。

写真上:今年6月の千葉大会でエアゲートを通過する室屋の愛機Edge 540 V3。写真下:表彰台のトップで優勝を喜ぶ室屋。左は2位の昨季デビューした実力者ペトル・コプシュタイン。右は3位の空軍の戦闘機パイロットでもあったマルティン・ソンカ。(写真提供 上:Samo Vidic ©Red Bull Content Pool 下:Balazs Gardi ©Red Bull Content Pool)
多国籍のチーム構成は
「みんな好きにせい」の精神
「白人社会」と内に秘めた日本人のプライド
今、パイロットの室屋が指揮する「チーム・ファルケン」は、コーディネーターはじめ、整備を担当するテクニシャンや設計プログラムを担うエンジニアに加え、レースの戦略を担うアナリストなど、各国から選りすぐりのスペシャリストで構成される。出身国は、日本のほか、アメリカ、ブラジル、ニュージーランドなど多国籍にわたる。
当然、文化の違いなども出てくるが、そこは“尊重”する。多国籍のメンバーで、レースのために長期間のキャンプをするので、例えば、食べ物などは「みんな好きにせい」の精神で大らかに受け容れているという。「けっこう大変ですけどね」と笑いながらも、「業務上、技術や開発への最低要件で妥協するメンバーは入れない」と仕事とプライベートは別とばかりに厳しい顔をのぞかせる。
これまでさまざまな国の人々と働いてきた経験を持つ室屋だが、特に思ったことを尋ねると、ちょっと予想外の心の内を明かした。それは海外のメンバーの仕事に対する、“ドライ”すぎる姿勢だ。契約が終わったら、はい、サヨナラ。さもありなんという反応な気もするが、室屋は困ったような表情で言う。
「ほら、日本人ってやっぱり情とかね、契約がすべてじゃなくて、終わったとしてもまあちょっと頑張ろうみたいなのが結構あるじゃないですか。でも……まあ……(海外の選手は)ドライですよね。特にヨーロッパの人は、お金と契約が切れたらスパッと、サヨナラっていう。最初、慣れるまでは(ホントに終わりなんだ……へえええ……)みたいな。『そうは言っても、ちょっとぐらい手伝ってくれるんでしょ』って言っても、『ううん、サヨナラ』って……」。室屋は、肩すかしを食らったように身体を傾けると、「でももう、慣れましたけどね」と寂しそうに笑う。

相手の文化をリスペクトし、流暢な英語でチームをまとめ上げても、根っこは情に厚い日本人なのだ。そもそも、航空業界は「白人のプライド」が色濃く残る世界。そんな世界で生きてきたからこそ、室屋は日本人としてのアイデンティティやプライドを誰よりも大切に思うようになったのかもしれない。
こうした白人優位主義の風潮はそこかしこに見られるという。今やトップパイロットの室屋ですら、当初は「下に見られる」ことが少なくなかったという。でも、そんな時も室屋は、「決して、白人はエラくないし、日本人は下ではない」のスタンスでやんわりと牽制してきた。ちょっと熱を帯びて語る。
「歴史的に見ると、彼ら(白人たち)は侵略して植民地にして、全部奪っていって、酷いんだぞと。ただこんな風に思いっきり言うとケンカになるので、匂わせながら話します」。さらに、「今も世界の情勢を見たら、アメリカは経済的に当然大きくて一位だけれど、日本は三位」と国内総生産を例に挙げると、「二位は中国だけれど、(アメリカと同じく)国土も大きく人口も多いから当たりまえでしょ。それと比べると、日本は戦後も含め、これだけ復興してきた」と日本の“底力”を称える。そして、ヨーロッパ諸国もほとんどが、日本より人口は少なく、国土も小さいと指摘する。
「そもそも、彼らは戦争に勝ったことを自信にしたバックグラウンドを持っているけれども、それも自分の力じゃない。先祖の力なわけです。そうした視点からも話すと、相手も聞く耳を持ってくれるようになるんですね」
上から目線にも堂々と立ち向かい、俯瞰して対等な立場でクールに制する。そのスタイルは、室屋のエアレースでの試合運びとも似ている。今、室屋がエアレースで鎬を削るパイロットたちは、皆よきライバルで友人でもある。言いたいことを言う関係もまた、この世界でたった一人の日本人として、築き上げてきた。
挑戦とは beyond the edge
(限界を超えること)
人生は自分が主人公の
超壮大なリアル・ロールプレイングゲーム
成熟した国際人としての側面をのぞかせたかと思えば、自分の人生を子どものような視点で振り返る。この世界で研鑽と努力を重ね続ける原点は単純に「楽しいから」。だが、世界中のパイロットと鎬を削り、高みを目指すことは並大抵ではなかった。
室屋にとって挑戦とは何なのか。室屋はすべてを見越したように答える。「挑戦とは、beyond the edgeっていう、要は限界を超えていこうっていうことなんですね。限界というハードルは、人によっても、そのステージによっても全然違うと思うんですが、自分の持ってる限界を超える時には、凄まじい努力が必要になる。でも、言い訳すると、絶対超えないんですよね」
武田信玄の名言が重なった。かの武将は、「一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出る」と、真剣に取り組めば物事は成就すると説いていた。
室屋は経験則からなる自分の言葉で続ける。「そこを超えると新しい瞬間があり、自分自身の発見がある。新しいテクニックが生まれるのもそんな時なんです。破れない扉をずっとこう押して押して押して……、そこで行き詰まり続けたとしても、どこかに抜ける場所はあって、限界を突破する瞬間がある。突破した瞬間に、次の山が見えてくるんですけどね。
でも、それって結構面白いって僕は思ってるんです。言うなれば自分の人体実験、人生実験みたいなもの。超壮大な実験のロールプレイングゲームをやってる感じなんですよ。いろいろやってるとだんだん強いキャラクターが出てくるんですね。世界選手権にもなれば、ものすごい怪物みたいなのがいっぱい出てくるんですけど、ここでまた勝てば、ゲームで言うとまた次のステージに行って、またスゲえやつが出てくるみたいな。これいつまで続くんだろうって思うんですけど、限界への挑戦を繰り返すっていうのが自分としては楽しみと思ってるんです」
空から視野を広く。子どもたちや次世代に
継承しなければならないこと
子どものように瞳を輝かせてまくし立てたかと思えば、次の瞬間にはクールに地に足をつけた考えを述べる。
これからは自分の切り拓いてきた道で、次の世代が苦労なくスカイスポーツを楽しんで、新しい「気づき」の機会が得られたらと語るのだ。空を飛べば、文字どおり、視野が広がり、物事が単純に見られるのだと。
「空から見ると、関東平野や三県くらいは見渡せるんですね。すると、例えば東京ってすごく密集していて、そこだけ空気が黒かったりするんです。そこから飛行機で福島の方へ向かうとどんどん空気が澄んでいくのがわかるんですよ。そんなふうに俯瞰的に物事を見ることができるんです」
そんな室屋が世界チャンピオンを狙うなら、航空先進国アメリカを拠点にするとうんと効率がいい。だが、福島を拠点にしているのは、「やはり日本が好きだから。ここ日本で多くの人の支援を受けた幸運を、次の世代につないでいきたい」と語る。

「世界に行くと、福島には人が住んでいないとすら思われてる。でも僕が活動していることで、事実を伝える一翼を担うことができる。福島は大変なところもあるけれど、大丈夫なんだねと」と室屋は風評被害の払拭にも尽力する。(写真提供 上:Samo Vidic ©Red Bull Content Pool 下:Balazs Gardi ©Red Bull Content Pool)
だから室屋の周りにはいつも室屋を慕う人が大勢いるのだ。ふくしまスカイパークのメディアデーでは、室屋はエアロバティックスのデモンストレーションを行ったが、すると地元の人も駆けつけ、「室屋さーん」と熱心に空に向かって手を振っていた。聞けば地元の人も「室屋さんは福島の誇りです」と胸を張る。
超高齢化社会へと突入し、ますます若い世代には生きづらいと言われつつある日本。だが、きっとそれもある側面に過ぎない。
室屋の言うように、空から見れば日本は美しく、生きやすい場所はまだまだある。考え方の引き出しを増やすように、「次元」を増やした視点で見れば、見えなかったものや複雑に感じていたことがわかるようになるのかもしれない。道を切り拓いた「空ゆくサムライ」の勇姿と言葉は、大空のように広く深く、多くの日本人を勇気づけ続ける。
プロフィール

室屋義秀
むろや・よしひで
エアロバティック・パイロット、レッドブル・エアレース・パイロット。1973年生まれ。身長173センチ。福島県福島市在住。91年、中央大学航空部に入部し、グライダー飛行をはじめる。翌年、渡米して飛行機のライセンスを取得。97年からアメリカでエアロバティックス(曲技飛行)の訓練をはじめ、2003年に30歳でアンリミテッド世界曲技飛行選手権に出場。数々のエアショーを行いながら技術を磨きあげ、07年にレッドブルとスポンサー契約を締結。09年からレッドブル・エアレースに参戦し、43歳となった16年の千葉大会で悲願の初優勝。17年の同大会にも優勝し、同レース史上2人目となる母国開催での連覇を達成。
松山ようこ/取材・文
まつやま・ようこ
1974年生まれ、兵庫県出身。翻訳者・ライター。スポーツやエンターテインメントの分野でWebコンテンツや字幕制作をはじめ、関連ニュース、書籍、企業資料などを翻訳。2012年からスポーツ専門局J SPORTSでライターとして活動。その他、MLB専門誌『Slugger』、KADOKAWAの本のニュースサイト『ダ・ヴィンチニュース』、フジテレビ運営オンデマンド『ホウドウキョク』などで企画・寄稿。
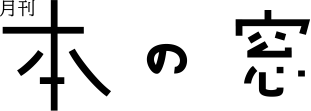
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。ページの小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激します。
スポーツエッセイ アスリートの新しいカタチ 連載記事一覧はこちらから
初出:P+D MAGAZINE(2017/07/27)






