春は「別れ」の季節。心に響くこの季節だから読みたい、「別れ」がテーマの泣ける小説5選

家族や恋人、友人など、さまざまな相手との別れを迎えることも多い春。「別れ」のシーンがあふれる今だからこそ読みたい、「別れがテーマの小説」をご紹介します。
「別れの季節」である春。新しい環境への旅立ちから友人や家族と離れ離れになったり、異動や転職で上司や先輩を送り出したりと、「別れ」のシーンが私たちの周りにあふれています。
そこでP+D MAGAZINE編集部は、別れのシーズンにこそ読みたい「別れがテーマの小説」をセレクト。家族や恋人、友人など、さまざまな相手との別れを描いた泣ける小説をご紹介します。
恋人か夢か?主人公が選んだ結論は/『檸檬のころ』豊島ミホ

出典:http://amzn.asia/3fj9ZoD
【あらすじ】
田舎の進学校に通う高校三年生で、吹奏楽部の指揮者である加代子はある日、野球部のエース・佐々木から告白される。付き合い始めたふたりが心を通わせていくなか、卒業後は東京の大学に進学すると決めている加代子と、地元の大学を選んだ佐々木には別れの日が訪れようとしているのだった。
田舎の進学校を舞台にした連作短編集、『檸檬のころ』。“地味な人なりの青春をいつ書きたいと思っていました”と作者の豊島ミホがあとがきで述べているように、この作品ではどこにでもあるような高校生活が瑞々しく描かれています。
最後に収録されている「雪の降る街、春に散る花」は、主人公の加代子が大学への進学で家族、恋人の佐々木と離れ離れになるまでの様子が綴られています。以前から「東京の大学に進学すること」を目標にしていた加代子と、地元に留まることを選んだ佐々木。働く場所も、遊ぶ場所もない地元を離れ、東京に行けばきっと何かあるはずだと上京を志した加代子にとって、佐々木と地元に残るという選択肢は最初からありませんでした。
東京に進学する加代子は、両親とも別れることになります。上京の前日、4年前に上京した兄がいなくなった時の寂しさを思い出した加代子は、初めて自分も実家からいなくなるという現実を実感するのでした。
そうして最後に、明日佐々木くんに会うことを考えた時、カチャンとドアノブが回る音がした。廊下から漏れた光の筋が一本、天井に映った。それはすぐに細くなって、ドアノブの音とともに消えてしまった。
ドアの向こうにかすかな気配がある。お母さんとお父さんに違いない。
「子どもって、いなくなるためにいるのかしら」
「やだなお前、そんなこと言うなよ……」
ひそめた二人分の声が言った。それを聞いたら勝手にぽろんと涙がこぼれた。
東京へ向かう日の朝、佐々木と駅のホームで会った加代子。お互いに何を言ったらいいかわからないまま、加代子は電車に乗り込みます。
ベルが鳴り止む。ドアが音を立てて閉まる。その間に、みるみる苦しいのが込み上げて、私は何か叫ばなくちゃいられなくなった。
「佐々木くん、私」
車掌さんが吹く笛の音が、空気を裂いた。その瞬間、私は窓から顔を出して、今までに出したことのないくらい大声で叫んでいた。
「終わんなきゃいいって、思った! 私、佐々木くんとまだ一緒にいられたらいいのにって、ほんとにほんとに思った、の」
田舎である地元にはないものが、たくさんあるはずの東京。加代子は「欲しいものは東京にしかない」という思いから地元に佐々木を残し、ひとり上京する道を選びます。それは、佐々木と過ごす日々を手放してしまうこと。「本当はまだ一緒にいられたら良かった」という気持ちに気付いた加代子は、別れの瞬間に、思わずその思いを叫びます。
上京で地元を離れるのは、その場所での思い出と別れることでもあります。加代子のように、地元を離れた経験がある人には特に響く『檸檬のころ』。上京した頃を思い出して読んでみてはいかがでしょうか。
失って初めて気づく、大切な人の存在/『劇場』又吉直樹

出典:http://amzn.asia/eAJ1JKw
【あらすじ】
無名の劇団“おろか”を主催する永田は、ある日街でナンパした女性、沙希と恋人同士になっていく。やがて金の無い永田は沙希の家に転がりこむ形で同棲を始め、良好だったふたりの関係は、永田が演劇にのめり込むにつれ、徐々に悪化。ふたりには別れのときがやってくる……。
第153回芥川賞受賞作『火花』に続く又吉直樹の二作目『劇場』は、売れない劇作家の永田とその恋人、沙希の物語です。自らが主宰する劇団が評価されないことに悩む永田が出会ったのは、女優を目指して上京した沙希でした。
永田は沙希の屈託のない性格に度々助けられていましたが、物語が進むにつれてふたりの関係は徐々にほころび始めます。演劇にのめり込むあまり、永田は沙希を振り回し、傷つけていたことに気がついていなかったのです。
「永くんおかしいよ」
「そんなん最初からやん」
「わたしもうすぐ二十七歳になるんだよ」
出会ってから、長い年月がたったのだなと思った。
「地元の友達はみんな結婚してさ。わたしだけだよ、こんなの。次は一緒に住めるかなとか思って頑張ってたけど、一人で住んじゃうしさ。適当に遊んでてもいいよ、でもここに帰って来るから許せてたんだよ。もう、なに考えてるかわかんないよ」
永田はいつでも明るくて優しい沙希に甘えるあまり、何もかもしてもらえることが当たり前になっていました。沙希も、永田を失いたくないばかりに、自分が抱いた不満や希望を口にしていません。喧嘩をしても、先に自分の非を認めて謝るばかりでした。
そんなふたりの関係は、沙希が心身ともに疲弊したことから終わりを迎えます。東京を離れ、地元に帰ることを決めた沙希とひとり東京に残る永田は、最後にふたりで暮らしていた部屋の片付けをします。
沙希は手際よく作業を進め、あっという間に荷物を整理した。ベッドのフレームや粗大ゴミは二人でアパートのゴミ捨て場まで運んだ。ゴミ捨て場の地面についた染みさえも掛けがえのないものに思えた。あとは箱詰めされた荷物を沙希の実家に送るだけだったので僕ひとりでもなんとかなりそうだった。
ただの箱と化していく部屋を見ていると、それまで呼吸していた部屋が死んでいくようにも思えた。もっとも沙希がいなくなってから既に瀕死の状態ではあったのかもしれないけれど。
作中で永田は「一番会いたい人に会いに行く。こんな当たり前のことが、なんでできへんかったんやろな」と言っているように、特別な存在だった沙希のことをないがしろにしてしまったことに後になって気がつきます。
「別れ」は、それまで会うことが当たり前だった人にもやってきます。別れた後に「もっとこうしておけばよかった」と後悔するのではなく、会えるうちに思いを伝えるべきなのかもしれません。
もう会えないはずの両親との再会/『異人たちとの夏』山田太一

出典:http://amzn.asia/bC9aBxM
【あらすじ】
妻子と別れ、ひとり孤独な日々を送るシナリオライターの原田。ある日、原田は幼い頃に住んでいた浅草で、12歳のときに交通事故死したはずの両親に出会う。幼くして死に別れた両親と再会した懐かしさから、彼らのもとに通うようになるのだった。
向田邦子、倉本聰と合わせて“シナリオライター御三家”と呼ばれ、さまざまなヒットドラマを手がけてきた山田太一。映画や演劇作品も制作された『異人たちとの夏』は、主人公と、亡くなったはずの両親とのまさかの再会が描かれた感動作です。
両親を交通事故で失った12歳の頃から、ほとんど涙を流すことがなかったという主人公の原田。離婚をきっかけに妻子と別れ、ひっそりマンションでひとり暮らしをしています。
そんな原田は誕生日の夜、幼い頃両親と暮らしていた浅草を訪れます。そこで出会ったのは、亡くなった当時の両親でした。
逢っている間、私は何度も口に出てしまいそうな質問を我慢した。時には、本当に手で口をおさえなければならなかった。
「ほんとうはぼくの両親なんでしょう?」
三十代に見える夫婦が、四十七歳の、いや今日で四十八歳になった男の両親であるはずがなかった。しかし、二人といると、自分が少年のような気持ちになった。少年がウイスキイをのんではいけないが、酔ったはずみで「お父さん」と呼んでしまい、男も「なんだ?」などと、まるで私を子供扱いなのである。
「再会した両親が、自分よりも年下だった」という奇妙な親子関係ではありましたが、12歳にして親子の思い出を作ることができなくなっていた原田にとっては、両親と食事を共にすることさえも、掛けがえのない時間でした。
次第に原田は両親のもとに通うようになる一方、はた目には、やつれ始めていることを同じマンションの住人、ケイに告げられます。このままでは自分がだめになっていくと思いつめた原田は、ついに両親と別れることを決意するのでした。
「いい?」と母が、座り直した。「気がせいて、うまくいえないけど、お前を大事に思ってるよ」
「行っちゃうの?」
そんな気がした。
「お前に逢えてよかった」と父がいった。「お前はいい息子だ」
「そうだよ」と母がいう。
「よかないよ。ぼくはお父さんたちがいってくれるような人間じゃない。いい亭主じゃなかったし、いい父親でもなかった。お父さんお母さんの方が、どれだけ立派か知れやしない。暖かくて驚いたよ。こういう親にならなくちゃって思ったよ。ぼくなんか親孝行面してるけど、お父さんたちがずっと生きてたら、大事にしたかどうか分らない。ろくな仕事もして来なかった。目先の競争心で––」
「うんと贅沢しよう」と、別れの日にすき焼きを食べに行く3人。そこで原田は、両親の姿が徐々に消え始めていることに気がつきます。残りわずかな時間の中、お互いに最後の思いを伝える場面には、きっと涙を誘われることでしょう。
不慮の事故で両親を失い、親からの愛情を十分に受けられないまま自分が親になった原田は、大人になってから再度両親の温かさを知ります。そこで初めて「自分がいい父親ではなかった」と実感しますが、それは両親との再会による気づきだったのです。
当たり前のように会えている家族も、いつかは会えなくなるかもしれないのです。「孝行のしたい時に親はなし」という言葉にもあるように、親孝行をしたいと思ったときに親が既にいないこともあるでしょう。『異人たちとの夏』は、大切な両親に会いたくなる作品です。
父との別れが生んだ、家族の絆/『星やどりの夜』朝井リョウ

出典:http://amzn.asia/6qKUR9D
【あらすじ】
海の見える町で、喫茶店“星やどり”を営む早坂家。三男・三女・母ひとり、4年前に亡くなった父の残した店を守るために奮闘を続ける一方、各々はさまざまな悩みや葛藤を抱えていた……。
作品の数々が映像化され、今最も注目されている人気若手作家、朝井リョウ。学生最後の夏に執筆したという『星やどりの声』は、一家で営む小さな喫茶店が舞台です。
形がなくなるまで野菜が煮込まれたビーフシチューとていねいに淹れられたコーヒーが看板メニューの“星やどり”は、15人も客が入れば満席になる小さな喫茶店。子どもたちが母を手伝いながら経営する店は、一見穏やかにもうつりましたが、実はそれぞれには人間関係や将来のことなど、さまざまな葛藤や悩みがありました。
そんな家族の悩みを解決に導くのは、仕事をしながら母の手伝いをするしっかりものの長女・琴美でした。
「……琴美が生まれたときのことは、忘れられないよ」
琴美は布団の中でぎゅっとパジャマを強くつかんだ。
「母さんがきょうだいみんなで食べなさいってケーキを作ってくれたとき、お前はきれいに六等分したかと思ったら、父さんにひとつ差し出してくれたよな。自分はいらないからって、仕事部屋まで持ってきてくれた。コーヒーに砂糖までつけて」
ふう、ふう、と細く息を吐きながら、琴美は喉を締めた。
「父さんな、まだまだ、お前たちに見せたいもの、伝えたいこと、教えたいこと、たくさんあるんだ。この町じゃないどこかへ飛びたっていくお前たちの姿、見たかったよ。お前たちに見せたいものも、父さんが見たいものも、まだまだたくさんあるんだ」
生前、父は、眠ろうとしていた琴美にこう呼びかけました。
亡くなった後も家族や店を支え続けた琴美は、「みんなを、よろしくな」という父の言葉も忘れられずにいました。
クライマックスで、早坂家は“星やどり”を続けるのか否かといった、大きな決断を迫られます。果たして、早坂家の決断とは……そして、父が残した、家族の絆を象徴するものとは。父との別れが生んだ、新たな出会いにきっとあなたも涙することでしょう。
大切なあの人を失った後に生まれる感動/『君の膵臓をたべたい』住野よる
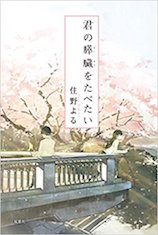
出典:http://amzn.asia/4VVs9Qj
【あらすじ】
他人に興味を持たず、いつもひとりで本を読んでいる高校生の“僕”。ある日“僕”は病院で「共病文庫」と記された文庫本を拾う。それはクラスメイトである山内桜良が綴る、秘密の日記帳だった。そこには、彼女の余命が膵臓の病気により、余命いくばくもないと書かれていて……。
第13回本屋大賞で2位、2017年には実写映画化もされた『君の膵臓をたべたい』。2018年9月1日には新たに劇場版アニメーション作品が公開されるなど、多くの人から愛される作品です。
主人公はもともと他人に興味を持たず、クラスでも孤立していた“僕”。そんな彼の毎日は、病院で1冊の文庫本を拾ったことから大きく変わります。クラスの中心人物で天真爛漫な女子、山内桜良の記した日記をうっかり読んでしまった“僕”は、桜良の病気のことを知る数少ない人物として「死ぬまでにやりたいこと」に付き合わされていくのでした。
桜良に振り回されるうち、次第に「人との交流を決意する」“僕”でしたが、突如として、桜良は亡くなります。桜良亡き後のショックを隠せない“僕”は、共病文庫“に残された最後のメッセージに涙を流します。
言ってたよね、君は名前を呼ばれた時に、周りの人間が自分のことをどう思ってるか想像するのが趣味だって。想像して、でも、正しくても間違ってても、どうでもいいって。
これは私に都合のいい勝手な解釈だけど、君は、私のことをどうでもいいとは思ってなかったんじゃないかな。
だから、君がそうするように、私が想像するのが怖かった。
君が呼ぶ私の名前に、意味がつくのか怖かった。
いずれ失うって分かってる私を「友達」や「恋人」にするのは怖かった。
桜良が日頃から「死」を臆面もなく口にしてきたように、彼らの日々にいずれ終わりが来ることは決まっていました。失うことがわかっている桜良を“僕”はいて当たり前の存在にするのを避け、名前を呼ぶことさえも最後までしなかったのではないか、と桜良は推測します。
“僕”と桜良のように、私たちはいつか来る終わりを避けられない運命にあります。いつその日が来てもおかしくないからこそ、想いは告げるべきなのだとこの作品は教えてくれます。
(合わせて読みたい
住野よるとは?デビューのきっかけやおすすめ作品
『君の膵臓をたべたい』が実写映画化。今最も話題を集める作品の魅力を探る。)
別れは悲しいことばかりではない。別れの後には出会いがある。
皆さんも、家族や恋人、友人との別れを経験したことはあるはず。ふとした瞬間に、別れた相手を思い出して寂しく思うこともあるでしょう。たしかに別れは悲しいものではありますが、一方で、新たな出会いや成長をもたらしてくれるものでもあります。
人生の悲喜こもごもが味わい深い5作品を、「別れと出会い」の季節である今、読んでみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2018/03/29)



