「平成のベストセラー」を出来事とともに振り返ろう!<前編>

2019年5月より新元号となることから、“平成”の終わりが近づいています。数多くのベストセラー作品、起こった出来事とともに平成を振り返ります。
2018年8月に天皇陛下が生前退位の意向を示し、30年間にわたる“平成”の終わりが近づいています。あらゆるところで「平成最後の◯◯」と銘打った振り返り企画も見られるようになりました。
そこで今回、P+D MAGAZINE編集部でも、平成の時代に話題となったベストセラーを中心に、その年にあった出来事を振り返ります。読んだことのある作品から、「そういえば話題になっていたな」と懐かしく思う作品までを紹介します。
“平成”の文学は、“ばなな現象”から始まった。

【1989年(平成元年)はこんな年】〈出来事〉 〈流行語〉 〈ベストセラー〉 〈芥川賞〉 〈直木賞〉 |
新年が明けて間もない1989年1月7日、昭和天皇が崩御し、“平成”の時代が始まりました。同じ年、出版業界では吉本ばななブームが巻き起こります。
1989年の単行本ベストセラーランキング(出版科学研究所調べ)で『TUGUMI』が1位に輝いたほか、2位となった『キッチン』、『うたかた/サンクチュアリ』、『悲しい予感』、『白河夜船』、『パイナツブリン』など、トップ20に6作もの吉本ばななの著書がランクインする快挙を果たしました。年間ベストセラーランキングにこれほど多くの作品がランクインした作家は今も出ていないことからも、当時吉本ばななの人気がいかに高かったのかがうかがえます。
そんな吉本ばななの作品が大ブームを巻き起こしたことを、マスコミは連日「ばなな現象」という言葉で取り上げていました。そのような状況に対する複雑な思いを、吉本ばななはベストセラーランキング2位の『キッチン』が2002年に文庫化された際のあとがきで記しています。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4041800080
この小説がたくさん売れたことを、息苦しく思うこともあった。
あの時代のものすごい波に飲まれてしまって、なんとなく自分の生き方までが翻弄されるような感じがした。『キッチン』あとがきより
吉本ばななは、作品が予想を超える形で多くの人に届いたことに戸惑っていました。しかし発売からおよそ10年後、考えの変化について述べています。
おばさんになり図太くなった今となっては、「なるようになってああなったんだから、よかったところだけを楽しい思い出にしよう」「あれだけ読んでもらったんだから、ひとつの役目は果たした。もうあとは自由に、自分の好きなようにやっていいんだ」という楽しい気持ちに変わりつつある。
『キッチン』あとがきより
『キッチン』は、唯一の肉親だった祖母を亡くした主人公の女子大生が、祖母と生前親しかった青年とその母親(女装した父親)の住む家に身を寄せる物語です。主人公が辛い境遇にありながらも、祖母の死を受け入れて成長していく姿は主に若い女性の感動を誘いました。
多くの人に読まれ、さまざまな感想をもらうなか、「『キッチン』をきっかけに、この世の女の子のマイナー性が一気に花開いて表に出てきた」という友人のひと言から「隠されていた感受性が解放されたこと」に喜びを感じたという吉本ばなな。瑞々しい感性で描かれた等身大の女性の姿に共感した女性たちによって、吉本ばななの作品は愛されていたのですね。
(合わせて読みたい:【女性らしい作風で人気】吉本ばななのオススメ作品を紹介)
“ばなな現象”に続く、“さくらももこ現象”

【1991年(平成3年)はこんな年】〈出来事〉 〈流行語〉 〈ベストセラー〉 〈芥川賞〉 〈直木賞〉 |
吉本ばななと親しく、家族ぐるみでの交流もあったという漫画家、さくらももこ。初のエッセイ『もものかんづめ』は、1991年度のベストセラーランキング1位に輝きました。
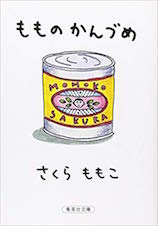
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/408747299X
前年には自身の幼少時の思い出を題材にした代表作『ちびまる子ちゃん』がアニメ化されたこと、その初代エンディングテーマ曲『おどるポンポコリン』がレコード大賞で多数の部門を独占したことで国民的な知名度を獲得していました。
そんな矢先に発表された『もものかんづめ』では、日常のささいな出来事からOLとして働いていた当時のエピソード、子供だった頃の思い出が面白おかしく語られています。誰もが経験している出来事も、独特な視点で描かれることでユーモアたっぷりの作品になる……、その魅力に多くの人が夢中になっていました。
その一方で、『もものかんづめ』に収録されている「メルヘン翁」は、祖父の死をある種のブラックユーモアを持って描いており、さくらももこの印象が大きく変わったという読者も少なくありません。
漫画『ちびまる子ちゃん』に登場する祖父「友蔵」は、ことあるごとに主人公のまる子を甘やかす、心優しいおじいさんというキャラクターです。しかし、さくらももこは実際の祖父のことを「家族の中で一番嫌っていた」とコメントするほど、良い関係ではありませんでした。
ジィさんは、死ぬ数年前からボケていたのだが、そのボケ方がどうも怪しい。知らんふりして私の貯金箱から金を盗んだり、風呂をのぞこうとしたり、好物のおかずが出たりすると一度食べたにもかかわらず、「食べてない」とトボケて食べようとしたりするのだ。
『もものかんづめ』より
家族を失った悲しみに暮れるどころか、「清々した」とまで言い切る描写に、「家族のことをそこまで小馬鹿にするのは不謹慎だ」という苦言が寄せられたとも言われています。ただ、それは最期の瞬間までも笑いに昇華させたことでもありました。時にブラックな笑いを交えながらも、思わずクスッと笑ってしまうようなさくらももこのエッセイは、これからも多くの読者に読み継がれていくのでしょう。
(合わせて読みたい:『もものかんづめ』だけじゃない。さくらももこのおすすめエッセイ8選 )
手に汗握るサスペンスに、誰もが夢中になった『真夜中は別の顔』

【1992年(平成4年)はこんな年】〈出来事〉 〈流行語〉 〈ベストセラー〉 〈芥川賞〉 〈直木賞〉 |
バブル景気が崩壊してもなお、「景気は持ち直すだろう」と楽観的に捉える人も多かった1992年。この頃は劇作家としての経験を持ち、50歳を過ぎてから小説を書き始めたアメリカのミステリー作家、シドニィ・シェルダンの作品が大ブームを迎えていました。
シドニィ・シェルダンは、『血族』を原作にした映画『華麗なる相続人』がオードリー・ヘップバーン主演で公開されたほか、日本でも『ゲームの達人』、『女医』などがドラマ化されるなど、多くが映像化されました。
シドニィ・シェルダンの代表作としても知られる『真夜中は別の顔』は、キャサリンとノエルというふたりの女性が、数奇な運命で出会う物語です。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07DJ5LQTL
誰もが羨む美貌を持って生まれるも、貧しい家に生まれたノエル。モデルになるためにパリに赴いたノエルは、休暇中だったアメリカ空軍中尉のラリーと恋に落ちますが、休暇の終わりとともにラリーは姿を消してしまいます。裏切られたうえに妊娠が発覚したノエルは、ラリーへの復讐を誓うのでした。
一方、もう一人の主人公であるキャサリンは一見真面目な雰囲気を持ちながらも「有名になりたい」という野心を抱く女性でした。
自分が誰なのかを世界中の人に知ってもらいたい、外を歩くとき、みんなから「ほら、キャサリン・アレクサンダーが歩いているよ。あの有名なーー」とうわさされる人間になりたい。ただ問題は、有名になりたいという願望だけで、どんな分野で業績を残したらいいのか、キャサリン自身もまだ分かっていないということだった。
『真夜中は別の顔』より
生まれ育った場所も価値観も異なる、ノエルとキャサリン。不思議な縁で関わりを持つようになるふたりは、やがてラリーも加わった三角関係に。その果ては手に汗握る展開につながっていきます。
『真夜中は別の顔』をはじめ、シドニィ・シェルダンの作品は主人公が波乱の運命に巻き込まれていくものが多く、怒涛の展開に惹きつけられる読者も少なくありませんでした。また、たとえ落ちぶれたとしても、意外なところから大逆転を果たす主人公の姿に爽快感を味わえるのも大きな魅力だったのでしょう。
当時はテレビ番組でも「シドニィ・シェルダン現象」として取り上げられるなど、社会現象になるほど、日本中の人が彼の作品を手に取っていました。
実写映画もヒット。流行語にも選ばれた『失楽園』

【1997年(平成9年)はこんな年】〈社会〉 〈流行語〉 〈ベストセラー〉 〈芥川賞〉 〈直木賞〉 |
消費税の引き上げによる個人消費の落ち込み、バブル崩壊の影響と平成不況の時代を迎えていた1997年(平成9年)、日本で一躍ブームを巻き起こしたのは渡辺淳一による『失楽園』でした。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062085739
『失楽園』は、1995年10月に日本経済新聞にて連載を開始。一般向け新聞連載でありながらも性描写が多く、通勤途中についつい読み入る会社員が続出したとも言われています。
物語は敏腕編集者の久木が、カルチャーセンターで書道の講師をしていた美しい人妻、凛子と知り合うところから幕を開けます。お互いに家庭を持ってはいたものの、週末毎に逢瀬を重ねていくにつれ、二人の関係は燃え上がっていくこととなるのでした。
それまでにあまりなかった“大人の不倫”を描いた『失楽園』は、1997年に実写映画化もされ、女性にも圧倒的な支持を集めました。それは久木と関係を持つ凛子の「夫からひとりの女性として見られていない」という姿に共感し、今一度誰かから深く愛されたいと願う人が多かったからなのかもしれません。
軽い弾みとともに、男が真っ先にまさぐるのは女の唇だが、すぐ思い直したように、いましがた涙が滲んだ瞼をとらえ、そこから真上へ唇を重ねる。
『失楽園』より
徐々に後戻りのできないところまでヒートアップしていくふたりの関係は、どこに行き着くのか……。当時の大人たちは、社会から孤立しながらも止めることのできない恋愛の行く末から目が離せませんでした。その人気は、1997年の流行語として「失楽園」(不倫をすることそのものを「失楽園する」とも表現)が選ばれたことでも十分証明されているのではないでしょうか。
「不倫」を描いた作品は2014年にもドラマ『昼顔』も話題となりましたが、『失楽園』はその先駆けだったのかもしれませんね。
(合わせて読みたい:小説は“濡れ場”の宝庫だ! 純文学の筆が勃ちすぎなベッドシーン【15選】)
ドラマ、映画、漫画、舞台……さまざまな形で描かれた“セカチュー”

【2003年(平成15年)はこんな年】〈社会〉 〈流行語〉 〈ベストセラー〉 〈芥川賞〉 〈直木賞〉 |
アテネ五輪での日本人のメダルラッシュ、イチローのメジャー大記録などスポーツ面で日本が活躍をした2004年、「セカチュー」(『世界の中心で、愛をさけぶ』の略称)が流行語に選ばれるほどの社会現象となりました。
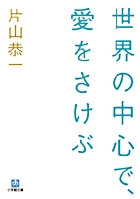
出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09408097
映画のタイトルが流行語大賞のトップテンに選ばれるのは1997年の大賞だった『失楽園』と同年の『もののけ姫』、この『セカチュー』のみ。その年を象徴するほどの快挙に選ばれたのは、多くの人に愛された作品であることに他なりません。
この『世界の中心で、愛をさけぶ』は、主人公の朔太郎が、白血病により17歳で亡くなった恋人のアキとの思い出を回想する形で進んでいきます。
冒頭で既にアキが亡くなっていることが描写されているため、読者はふたりの結末を知りながら読み進めることとなります。ふたりで学級委員になり、文化祭で「ロミオとジュリエット」を演じ、夏休みに遠出をしたという思い出が、やがて永遠の別れにつながっていくという切なさは、多くの読者の涙を誘いました。
「いま重大なことに気がついた」
「今度はなに」窓の外を見ていた彼女は、億劫そうに振り向いた。
「アキの誕生日は十二月十七日だろう」
「朔ちゃんの誕生日は十二月二十四日ね」
「ということは、ぼくがこの世に生まれてからアキがいなかったことは、これまで一秒だってないんだ」
「そうなるかな」
「ぼくが生まれてきた世界は、アキのいる世界だった」
彼女は困ったように眉を寄せた。
「ぼくにとってアキのいない世界はまったくの未知で、そんなものが存在するのかどうかさえわからないんだ」
「大丈夫よ。わたしがいなくなっても世界はありつづけるわ」
「わかるもんか」『世界の中心で、愛をさけぶ』より
アキを失ったとき、世界が「アキのいない世界」に変化することを恐れる朔太郎。それを聞いたアキは、白血病により死の可能性がある状況でも最期の瞬間まで朔太郎を愛そうとします。
セカチュー以降、「恋人が病に侵されるも、純愛を貫き通そうとする男女の物語」が次々と生み出されます。そんな「純愛ブーム」の火付け役となった「セカチュー」は、恋愛小説界において大きな指標となった作品ともいえるでしょう。
<後編>に続く
初出:P+D MAGAZINE(2019/03/25)

