連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:中野量太
『湯を沸かすほどの熱い愛』で第40回日本アカデミー賞の6部門を受賞した中野量太監督。待望の最新作は、中島京子さん原作の『長いお別れ』です。映画のこと、創作のこと、人生のこと……。監督と原作者だからこそ語れる、ちょっと深いお話のスタートです。
連載対談 中島京子の「扉をあけたら」
第三十一回
常に考えている。
家族って何だろう。
ゲスト 中野量太
(映画監督)
Photograph:Hisaaki Mihara

中野量太(左)、中島京子(右)
今までにない認知症の映画を撮る
中島 映画『長いお別れ』の完成おめでとうございます。私の小説を原作にして映画を作ってくださるというので、どんな作品ができあがるのか心待ちにしていたんです。すごく素敵な映画にしていただいて、感激しています。
中野 ありがとうございます。原作者である中島さんにそう言っていただけると、また違った嬉しさがあふれてきます。
中島 原作のある作品に取り組まれたのは、これが初めてだとお聞きしました。これまでご自身で書かれたオリジナル脚本で作品を撮ってこられた監督が、なぜこの作品を撮ろうと思ったんですか。
中野 『長いお別れ』を映画化しようと動いている方々がいて、監督をやらないかと声をかけていただいたのが直接のきっかけです。でも、中島さんの原作本を読んだときに、この小説は絶対に自分の手で映画にしたい、と思いました。正直言って、原作ものをやりたいと思ったのも初めてなんです。一方で中島さんはご自身の小説が僕たちのような別の表現者の手によって映画化されることについては、どんな思いをお持ちなんでしょうか。
中島 私の小説が映画化されるのは『小さいおうち』(二〇一四年・山田洋次監督)以来二作品目なのですが、違う表現者がひとつの作品を違う表現形態にするということは、もうその時点で、別の表現作品になるものだと思っているんです。脚本を最初に見せていただいたときに、「これは中野監督の身体を通って出てきたものだ!」という感じがしました。原作を読んで、本当に面白いと思ってくださったんだなっていうことが伝わってきて、すごく嬉しかったんです。
中野 もし原作が漫画だったらできなかったと思うんです。登場人物のイメージが出来上がりすぎているから。小説は文字だけの世界でしょう。だから、僕というフィルターを通して映像にすることができたんだと思います。でも、中島さんが書かれた人物像をそのまま……、そのままっていう言い方じゃないな……。人物像を全部生かしながら自分の中で具体化していかないといけない。一人ひとりを大好きにならないと演出できないぞ、と覚悟を決めて取り組みました。

中野 そうなんです。わからないからこそ、本人の心の動きは描いちゃだめだと思いました。最初にこの小説をどういうふうにすればいいかと考えたときに、お父さんが何を考えているかってことを、こっちが勝手に描くのは失礼だと思ったんです。
中島 そうですよね。本当は何かを考えているかもしれないんだけれど。
中野 だからお父さんの主観を描くのはやめました。原作ではお父さんが認知症になって亡くなるまで十年の時間の経過がありますが、映画ではそれを七年にぎゅっと縮めました。つまり家族にも同じように七年の月日が流れている。お父さんの主観は描かないけれど、家族を描くことでお父さんをちゃんと描くことにしようというプランを立てました。
中島 よくわかります。私も小説を書こうと思ったとき、全く同じ壁にぶつかりました。認知症を患った父の介護体験があったので、最初はお父さんを主人公にした長編を書こうと思ったんです。でも、うまくいかなかったんですね。お父さんの話だけでは、小説が息苦しくなってしまう。そう悩んでいるときに、短編を一編書きませんかという依頼が来たので、認知症のお父さんが脇役くらいのイメージで、ちょこっと書き始めたんです。そして、家族や周囲の時間をこそ、きちんと描くべきだと気づいた。それが映画のオープニングに使っていただいた、メリーゴーラウンドのエピソードです。
中野 あの原作の場面は印象的で、僕の中で大きく膨らんでいきました。娘たちはもうすでに大人になっていても、認知症のお父さんの中では幼い子どものまま。見ず知らずの子どもたちと出会い、自分の娘たちだと思いこんでいっしょにメリーゴーラウンドに乗っている。重要なシーンにしています。
中島 最初にお会いしたときに、今まで撮られたことのない認知症の映画を撮りますって言ってくださったでしょう。このシーンを観ただけで、本当にそうなっていると思いました。この言葉が適切かどうかはわからないんですが、お父さんは病気になって壊れていっちゃうんだけれど、尊厳が保たれている。壊れたが故に、奇跡的にお父さんが何か大切なものを教えてくれることもあるんだというのを映像にしてくださっていて、そこを大事にされている感じが伝わってきました。
プラスとなる家族像を描きたい
中島 定番の質問で申し訳ないのですが、子どもの頃から映画監督になりたいと思っていたのですか。
中野 それが全く(笑)。子ども時代は、スピルバーグ全盛期だったので、他の子たちと同じように『E.T.』や『グーニーズ』などの大ヒット作は観ていました。でも特別に映画が大好きだったわけではないんです。
中島 あらっ。そうなんですね。てっきり、映画少年で大学も映画学科に進まれたものだと。
中野 通ったのは普通の四年制の大学で、イタリア語を専攻していました。でも途中でイタリア語に興味がなくなってしまって、ぎりぎり卒業できるかどうかというダメな学生でした。映画監督という職業を意識し始めたのは、就職活動が始まる大学三年生ぐらいのときです。友だちの話題が就活一色に染まってきても、僕は全く就職する気が起きなかった。自分は何をしたらいいんだろうってぼんやり考えながら、アマチュアバンドの活動をしながらフラフラしていたんです。そうしているうちに、バンドもそうですが、昔から表現することで誰かを喜ばせるのが好きだったことに気づいたんです。自分の中にもなにかの形にして吐き出さなきゃいけないものが、いろいろ溜まっていたんでしょうね。表現の最高峰って何だろうって考えたときに、映画かなって、無理やり思ったんです。意を決して、映画の勉強をしようと思うんだと告白したら、友だち全員「おまえに映画なんて無理だよ」って(笑)。
中島 「無理」とまで(笑)。

中島 それは……いろんな意味ですごい話ですね。
中野 当然、映画を撮ったことなんてありません。脚本はもちろん、ちゃんとした文章も書いたこともなかった。でも、映画学校の実習で初めて自分の作品を撮ったときに、映画って、なんて楽しいんだろう、なんて面白いんだろうとこれまで味わったことのない衝撃があった。僕の運命が変わったのはそのときです。
中島 中野監督の本能が、映画という表現を求めていたんですね。監督はデビュー作からずっと家族の話を撮り続けていらっしゃる。家族をテーマにされ続けているのには、なにか理由があるんですか。
中野 父親が六歳のときに亡くなって、母が兄と僕を育ててくれたんです。また親族の死も多く経験していく中で、家族って何だろうと、小さい頃からずっと考えていました。お父さんとお母さんが揃っている家庭ではなかったけれど、僕が今あるのは、母がその環境を一回も不幸せだと思わないように育ててくれたからなんです。
中島 お母さまに、感謝されているんですね。
中野 だから、僕はその家族がどんなに苦しい状況の中にいるとしても、必ずプラスになる家族像を描く。そしてもうひとつ、残された人を描いてきました。『長いお別れ』でも、認知症の父を見送ったあと、残される家族が巡って次の世代になる。
中島 プラスの家族像って、いい言葉ですね。
中野 僕の祖母も認知症で母が介護していました。常に家族って何だろうな、どういう形が家族なんだろうとか、いろいろ考えていることが僕の表現の根本にあるんですね。だから、この映画を絶対に自分で撮りたいと思った理由のひとつが、原作の最後のほうの場面なんです。
中島 あまり詳しく話しちゃうといけないので(笑)、ごく簡単に言うと、不登校になっている孫が校長先生に呼び出されるあたりですね。
中野 認知症の父とその家族の物語だし、子どもが主役でもない。ところが、そんなところにこだわらないことに感動したんです。だから、映画でも絶対にあの形にしようと決めていた。最初、プロデューサーには反対されたんです。でも、僕は絶対これしかない。このラストで行かせてくださいと、意地を通しました。
中島 あの男の子は、いいですよね! とてもいいシーンでした。
中野 映画ではラストシーンでも、家族はずっと続いていく。親から子へ、子からまたその子へ、世代が引き継がれていく。そんな余韻を残したかったんです。
山﨑努さんが脚本を絶賛
中島 私は小説を書くときに、笑いとかユーモアの要素をすごく大切にしています。どんなにシリアスなテーマでもそれを入れたいし、自然に入っちゃうところもあるんです。ただ、笑いにはグラデーションがあって、いろんなレベルの笑いがあるでしょう。中野監督がこの映画の中にちりばめた笑いは、私が書くものに近い感じがしました。温かいんだけど、そんなにウエットじゃない。独特の間があって、気がつくとクスっと笑っていました。
中野 僕は、ずっこけて笑わせるのは本当の笑いではないと思っています。人間が一生懸命だからこそ見えてくるちょっと滑稽なところをおかしく感じるのが体温のある笑い。笑わせるんじゃなくて、つい笑ってしまうのが本当の笑いだと思っているんです。

中野 人間っておかしいじゃないですか。僕がまだ小さい頃に、おじいちゃんが亡くなった。おじいちゃんは、身長が百八十センチ以上ある大柄な人でした。普通のサイズの棺桶だと入らないだろうからと、ちょっと大きな棺桶を用意したんです。ところが昔の火葬場だったんですね。いざ火葬しようとしたら、炉の中に棺桶が入り切らなかった(笑)。陽気な性格のおじいちゃんだったのでそれを思いだしてか、みんなクスクス笑うわけですよ。子どもの頃から、そういう真剣だからこそ、おかしくてしょうがないのが、本当の笑いというか、人間っていいなっていうような、愛らしさだと思っていました。
中島 確かに人が死ぬっていうのは、厳粛で、悲しい場面なんだけど、そうであるが故に、ちょっと引いてみると生真面目な儀式がすごくおかしく見えたりします。
中野 死んだ人は、もう何もわからない。残された人がどう受け止めるかなんだろうなと思っていて。だから葬式で最後にお別れしたときに、残された人がつい笑っちゃったりしたら、最高のセレモニーかもしれない。そんなお葬式が、送られる人にとっても最高だろうなと思っているんです。
中島 そういえば、山﨑努さんが、中野監督の脚本を絶賛されたと聞いていました。
中野 山﨑さんに出演をお願いしに行ったとき、もうこの作品が遺作になってもいいというくらいの勢いで快諾してくださったんです。山﨑さん自身も中島さんの原作をずいぶん前に読んでおられて、映画化するときにはこの父親役は絶対自分のところに来るだろうって思っていたそうなんです。
中島 本当ですか。嬉しい。そういうご縁って、本当にあるんですね。
中野 山﨑さんの言葉を聞いたときに、これは最高のキャスティングになると確信しました。次女役の蒼井優さんも絶対一緒にやりたいなって思っていた方でしたし、長女役の竹内結子さんや妻役の松原智恵子さんもいろんな縁が結び付けてくれて出演が実現したんです……。
中島 実際にクランクインする前に、出演者のみなさんが家族になるための時間を作られたそうですね。
中野 映画の中で重要なシーンのひとつが、お父さんの七十歳のお誕生会です。そこでお父さんがちょっと頓珍漢な行動をして、認知症になっていることに家族がうっすら気づくんです。映画の中で七十歳の誕生会をやるのであれば、お父さんが普通に元気だった頃の誕生日を知らないといけないなって思ったわけです。だから、本番の撮影とは別に、お父さんの六十八歳の誕生日会を開こうと思い、家族役の四人を集めて誕生会をしました。
中島 それは役になりきっての誕生会なんですか。

中島 なんだか、いいですね。家族が作られていく時間。現場で拝見したかったです。その演出方法は、ご自身で編み出されたんですか。
中野 はい。ただ、他の監督さんがどんなやり方をしているかはよく知らないので、僕のオリジナルかどうか、なんとも言えませんが……。元々僕はこんな演技をしてくださいと指示を出しながら演出するタイプの監督ではないんです。だから、クランクインの日にみなさんがどれだけ演じやすい状況を作ってあげられるかが、僕の仕事かなって思っています。
中島 撮影現場にお邪魔したとき、演技中の山﨑さんを見て、失礼ながら相当お年を召されたななんて思ってしまったのですが、休憩時間にお会いしたら、いつものしゅっとした、あのかっこいい山﨑さんだった! 認知症の進み具合を演じ分けていらして、あーすごい演技力だなぁと、感動しました。
中野 今回、山﨑さんをはじめ素晴らしい俳優の方々と一緒にやらせていただいて、本当にいろんなことを教えていただいた気がします。
中島 最後に、ひとつお聞きしたいことがあるんです。今回の映画の中でも描かれていましたが、3・11の東日本大震災のことです。私にとっても大きな出来事だったのですが、監督は震災後、どう意識が変わりましたか。
中野 3・11という現実のあと、フィクションなんか作れないと、しばらくは何も撮れなくなりました。被災された方にとって、一番最初に必要なのは水や食料、住居など生きるための必需品です。でも、少し生活や気持ちが落ち着いたあとに、心を豊かにするものって何だろう。僕らの仕事もその一端を担えるんではないかと思うようになりました。震災という現実が横たわっていても、その中で映画というフィクションにも応援できることがあるんではないかと。
中島 フィクションの役割の一つは、そういうことかもしれませんね。
中野 映画を通して誰かの生活を少しでも豊かに、少しでもいい方向に持っていけたらいいなって思っています。もちろん人間には、憎たらしい人やずるい人もいるでしょう。でも、僕は土台としては今のつらい世の中いろんなことがあるけれども、その中で希望になることを表現して、生活のプラスになればいいなという思いでやっています。生きにくい世の中、家族のつながりが弱い世の中になればなるほど、僕の出番かなっていう感じはしているんです。だから、僕はこれからも、そちら側を描き続けます。
構成・片原泰志
『長いお別れ』
監督:中野量太
脚本:中野量太 大野敏哉
原作:『長いお別れ』中島京子(文春文庫)
出演:蒼井優 竹内結子 松原智恵子 山﨑努 北村有起哉 中村倫也 杉田雷麟 蒲田優惟人ほか ●配給:アスミック・エース
●5月31日(金)より全国ロードショー
©2019『長いお別れ』製作委員会
©中島京子/文藝春秋
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
中野量太(なかの・りょうた)
1973年京都府生まれ。大学卒業後、日本映画学校(現・日本映画大学)に入学し、映画の面白さにめざめる。2012年、自主長編映画『チチを撮りに』でSKIPシティ国際Dシネマ映画祭にて日本人初の監督賞を受賞し、ベルリン国際映画祭はじめ各国の映画祭に招待。国内外で14の賞に輝く。2016年、商業長編映画『湯を沸かすほどの熱い愛』で第40回日本アカデミー賞優秀監督賞・優秀脚本賞など、受賞多数。
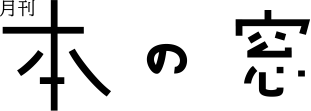
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2019/04/22)






