【著者インタビュー】中村 計『金足農業、燃ゆ』/日本中を熱狂させたチームの奇跡は、美談だけではなかった
2018年の甲子園で、エースの吉田輝星を擁して準優勝した秋田代表・金足農業高校。3年生9人だけで戦い抜き、奇蹟と呼ばれた「あの夏」は、決して美談だけではなかったといいます。大胆かつ繊細な筆致のノンフィクション!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
気性の荒い雑草集団が起こした「あの夏」の奇跡は美談だけではないからこそ
泥臭く、熱く、魅力的だった!
『金足農業、燃ゆ』
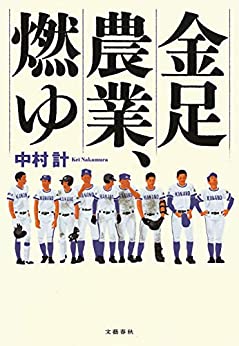
文藝春秋
1800円+税
装丁・装画/城井文平
中村 計

●なかむら・けい 1973年千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部政治学科卒。スポーツ紙を7か月で退職後、ライターとして独立。『甲子園が割れた日 松井秀喜5連続敬遠の真実』で第18回ミズノスポーツライター賞最優秀賞、『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』で第39回講談社ノンフィクション賞を受賞。他に『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』の取材・構成を担当。趣味は浅草放浪と、6時間前後で走るフルマラソン。172㌢、74㌔、AB型。
練習が厳しくても皆が野球を好きになり卒業後も野球を続けるのが一番の勝利だ
「高校野球でこれ以上心を動かされることはもうないと思っていましたが……」
北海道代表・駒大苫小牧の連覇の舞台裏を描いた前作『勝ち過ぎた監督』で、講談社ノンフィクション賞を受賞した著者の琴線に再び触れたチームが、2018年夏の甲子園に現れた。エースの吉田
「自分なりの勝てる監督像やチーム像が全部崩れて、それが気持ちよかった」
と、著者が爽快感すら覚えるほど、〈何から何まで「ありえないチーム」〉だった。しかも、県大会から甲子園決勝まで、3年生9人だけで戦い抜いたのだ。
「9人は30分程度の通学圏から集まっているだけ。練習もクラシックで、雪国というハンディもある。でもこれで勝てるんだって思いました。こんな奇跡的なチームは二度と現れないんじゃないでしょうか」
*
著者が描く甲子園ノンフィクションに一貫した力強さは、取材対象者に決して
「取材対象者が読後にどう思うのかは意識しないようにしています。もちろん気にはなりますが、そこには左右されたくない。この本を出した時も、送って2日後ぐらいに学校へ挨拶に行きました。正直、恐くて、緊張します。でもそれがないと書く意味がないと思います。相手に喜ばれるだけの作品は書きたくないです」
本格的な取材が始まったのは、甲子園が終わった直後の秋。最初は控えの選手など周辺取材にとどまり、ナインの3年生にはなかなか接触できなかった。
「中泉監督に手紙を書き、電話を掛けましたが、全然出てくれなかった。毎日1回ずつ掛けていたら、2週間後くらいに電話をくれたんです。3年生に会えたのは3回目に秋田に行った時。取材には3人1組で応じ、最初の1組目に吉田が出て来ました。普通、こちらが質問するまで黙っているじゃないですか? でも3人は勝手にべらべらと話し出した。こんなに面白い奴らだったのかって。その魅力に恋に落ちました」
3人へのインタビューは本書の冒頭に収録され、吉田は自らのチームを〈凶悪な集団〉と表現する。バットをぶん投げる、相手チームの声をつぶすほどの野次、眉毛を剃る……。次々と飛び出すエピソードは、甲子園で輝くイメージをぶち壊すような、荒っぽい集団にも感じられたが、蓋を開けてみれば、人懐っこい純な子供たちだった。
「挨拶だけはきちんとしていましたが、取材はめんどくさそうでした(笑い)。冒頭から『何時に終わるんですか?』っていう選手もいたりして。でも何だかんだ言って話すし、食堂へカレーを食べに連れて行ってくれたり。『凶悪』と言う割に恐い印象は全然なかった。逆にかわいい奴らだなと」
中でもエース吉田の素顔は、昔の野球漫画に登場する主人公を彷彿とさせた。
「勉強できるけどやんない。野球めちゃうまい。超だらしない。でも女の子にもてる。ちょっと強がりで優しい。仲間は吉田のことをディスりつつも、憧れを抱いている。僕も吉田に憧れちゃいましたね」
主役になることを躊躇しないナイン
金足農業は県内でも練習が厳しくて有名だ。とはいえ、正座をしたまま上空に向かって声を張り上げる「声出し」や、延々とヘッドスライディングをやらされる伝統的な〈ペナルティー〉など、その光景は時に、〈狂信的に映った〉。
「声出しの時は、見てはいけないものを見てしまったような感じがしました。生徒がもっとも恐れていたコーチは、その代によっては、父兄から反感も買った。金農も少しずつ変わっていくでしょうけど、時代の変化はもっと早い」
もう1つ変わるべきことが、本書で提言されている。それは投球過多の問題だ。その火種は00年代後半からくすぶり続けていたが、あの夏の吉田の球数の多さが、火に油を注ぐ形となった。
「吉田の連投を見て感動はしなかったです。いたたまれない気持ちでした」
しかし、吉田の父親は意外にも、連投に肯定的だった。著者の常識を軽々と超えていくチームに対し、甲子園を埋め尽くした観客の大半も心を奪われた。
「スタンドが自分たちに拍手を、歓声を送ってくれる。超快感だと思います。武道館を満員にしている歌手のように、俺たち今主役なんだと。でも金足のナインは、自分たちが主役になることに全く躊躇していない。吉田を筆頭に、自信を持った若者ってこんなに美しいんだって思いました」
決勝では大阪桐蔭に敗れたものの、球児たちが秋田に帰省すると、地元民の歓待ぶりに、〈世界が一変していた〉。卒業後は、プロ入りした吉田だけでなく、全員が野球を続けることにした。
「純粋にいいなって思いました。あんな厳しい練習をさせられても、皆野球好きになった。卒業後も野球を続ける野球部ほど良いと思います。それが一番の勝利っていうか。まだ野球をやりたいって思わせるのは、指導者にとっても栄誉です」
〈甲子園は、人を変える力がある〉。その言葉の意味を考えさせられる一冊だ。
今年の夏は、金属バットの快音が響くだろうか。
●構成/水谷竹秀 1975年三重県生まれ。ノンフィクションライター。11年、『日本を捨てた男たち』(集英社)で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。著書多数
●撮影/黒石あみ
(週刊ポスト 2020年6.5号より)
初出:P+D MAGAZINE(2020/09/12)

