『まんが 星の王子さま』 発刊記念対談 !! 星の王子さまは、 パイロットが砂漠で見た幻影!?

本サイトで1年半にわたり連載した『まんが 星の王子さま』。その単行本が、いよいよ10月30日に書店に並びます。それを記念して、翻訳・構成の奥本大三郎と、まんがのやましたこうへいが本作品に仕掛けた「解釈の補助線」について、ちょっとだけタネ明かしします。星の王子さま=パイロットという等式と、パイロット=原作者というふたつの等式。それがこのまんがを深く切ないものとしています。
――星の王子さまはパイロットだった?
奥本 王子さまは1000マイル四方、まったく人気のない砂漠に突然出現します。そして必死に飛行機を修理しているパイロットに語りかけるんですね。でもパイロットは本当に驚いているわけではありませんね。そして挨拶もなしに、王子さまが要求するヒツジの絵を、パイロットは描いてしまう。それはどうしてでしょうか。
王子さまは幼年時代のパイロット自身だと解釈すると腑に落ちます。さらに物語を読み進めていくと、王子さまは勝手な事を他人に突きつけて、逆に他人が尋ねても答えないですね。だから自分中心の坊や……パイロットの子ども時代の姿なのだろうと思うわけです。
山下 この物語を描きはじめたころには、パイロットと王子さまは同一人物という解釈はすでにありました。砂漠に不時着して、極限状態の中で肉体と魂が離れ、過去と現在が行き交い……死ぬ前の走馬燈のような物語かとも思ったんですよね。
奥本 人が死ぬ前に一瞬のうちに、自分の一生を思い出すっていうのがあるよね。
山下 あれが一週間、砂漠であったのかもしれません。
奥本 アンブローズ・ビアスに『アウル・クリーク橋の一事件』という作品があるんだけど、長い物語があって、それは主人公が首を吊って、がくんと落下するまでの一瞬の話なんです。
山下 しかしこの物語は運良くというか、助かった話ですね。パイロットは6年後にその体験を書くことになります。
奥本 ところで「パイロット=王子さま」の等式で大事なのは、パイロットは「箱の中のヒツジ」がもう見えなくなっていること。彼はそれを恥じています。
王子さまにねだられて、パイロットはヒツジの絵を描くのですが、描いてあげるたびに「ちがう」と言われる。最後にくしゃくしゃっと、箱の絵を描いて、「その中にヒツジがいる」と投げ渡すと、意外なことに王子さまは「これがほしかったんだ」と満足します。無垢な子どもの目には、箱の中のヒツジが見えるんですね。
子どもには見えるのに、常識を身につけ、話を相手に合わせる大人になってしまうと、もう箱の中のヒツジは見えない。この物語の底辺には、ヒツジが見えなくなったパイロットの恥ずかしさと後ろめたさが流れているんですよ。すべての大人はそれを考えるべきですね。
山下 原作の中で、パイロットの言葉を借りて「もう見えなくなっているかもしれない」と書いていますものね。

山下 まったくない人たちが、星の住人となって現れる。王子さまは地球にたどり着く前に6つの星を経巡ってやってくるのに、そこの住人、つまり王様、うぬぼれ屋さん、酔っぱらい、ビジネスマン、点灯夫、地理学者といったタイプの大人に会います。すごく深いことを言っているなと感心しますね。
サン=テグジュペリは、きっと子どもの心を持ったパイロットで、地上の人間世界を見ていたんだと思います。彼の人間観察はとても細かいですよね。
奥本 実にフランス的でもあります。
山下 あれはやっぱりある種の社会風刺であって……
奥本 まっすぐ単純に、子どもの立場に立って言っている。忖度しない。
山下 自分の中にある「子ども」を大切にしていたんでしょうね。そういうところから星巡りの大人たちのパターンを肉付けしている。
――初めて『星の王子さま』を手に取ったときに感じた懐かしさ
奥本 デジャヴュ(既視感)という言葉があるじゃないですか。大学に入ってすぐに、フランス語を習いはじめの自分にも読めるような本がないかなと思って、丸善の洋書売り場に行ったら、この本が並べてあったんです。ぱっと開いて、ボア・コンストリクターに呑まれそうになっている間抜けな熊みたいな動物や、アフリカ象の背中がへこんで帽子みたいに見える絵(インド象だったらそう見えない)を見て、「あれ、見たことあるぞ」と思ったんです。この本は私にとってデジャヴュなんです。
岩波の翻訳はそのあと読みました。実をいうと、ところどころ翻訳に違和感を覚えました。
山下 このまんがも、以前先生が翻訳した『ファーブル昆虫記』と同じような感じで読めました。やさしくかわいらしい文章です。
奥本 これ以外では書けない。
山下 喋っている感じで、場面が浮かび上がります。
奥本 絵にするの、ラクだったでしょ。
山下 それはまあ別で……(笑)。
奥本 星の住人でうぬぼれ屋さんが出てくるでしょ。あれは落語のたいこもちのセリフなんです。昔の林家正蔵の「いやあ、おいでなすったねえ、うれしいねえ」なんて。また王様のセリフはこれも落語の殿様の言い回しです。「星めらも輝いておるか」など、落語はすごい。
いわゆる直訳しただけの文では、こういうニュアンスは出てこないと思います。ぜひ他の訳文と読み比べてください。
それにしても原作の、物語の作り方はとても巧みですね。とくに王子さまの地球からの去り方っていうか、終わらせ方っていうのは、非常にうまいですね。ヘビに嚙まれて、魂だけがふうっと行ってしまう……「体は重すぎるから」とか、ああいう話は凡庸な作家には書けない。
山下 文章だけで読んでいた物語を、実際に描いてみると、複雑に時間軸が動いたりしているのがわかります。先ほども話に出た星巡りのところ、あのあと地球にやって来てから、複雑に話の時間軸が動いています。
バラとの出会いと別れ、星の住人たち、鉄道や商人、フェネックの話という長い物語を、王子さまは砂漠でひたすらパイロットに話すんですよね。一日で。これは聞いているパイロットも「話が長いぞ」と思ったでしょう。しかしこの複雑な時間軸を表現するのに、まんがという手段は、伝えやすいと思いました。
――原作の絵はサン=テグジュペリが描いている。
山下 サン=テグジュペリは最初、画家を目指して、実際、美術学校に入ったようですが、早々に挫折してパイロットになる。それでも原作「星の王子さま」の挿絵はすべて、本人が描いています。
奥本 絵には不思議な魅力があるんだけど、テクニックとしてはどうでしょうか。ムラがありますね。バオバブの絵なんかはうまいんですけど、キツネの耳はどうでしょう。それから王子さまの目なんかただの白抜きでしょう。サン=テグジュペリがアメリカにいた頃、「ジグス&マギー」というまんがが流行していますね。あれも、目が白抜きだったと思う。
山下 キツネの耳に関しては、最初から先生は言っていた(笑)。描きたいものとそうでないものと差があります。
奥本 あれで黒目を描き込んだら、しんどいことになるから、そこは避けているんだと思います。
山下 そう思います。あとは人にポーズをとらせて、必死でスケッチしたのがわかる絵があります。そのこだわり様から、本人が納得する境地まで到達するのに、だいぶエネルギーがかかったんだなと想像できます。
奥本 リアリズムから素朴派に進むに当たって、だいぶ迷いがあったんではないですか。妙に上手に描きはじめたら泥沼でしょう。
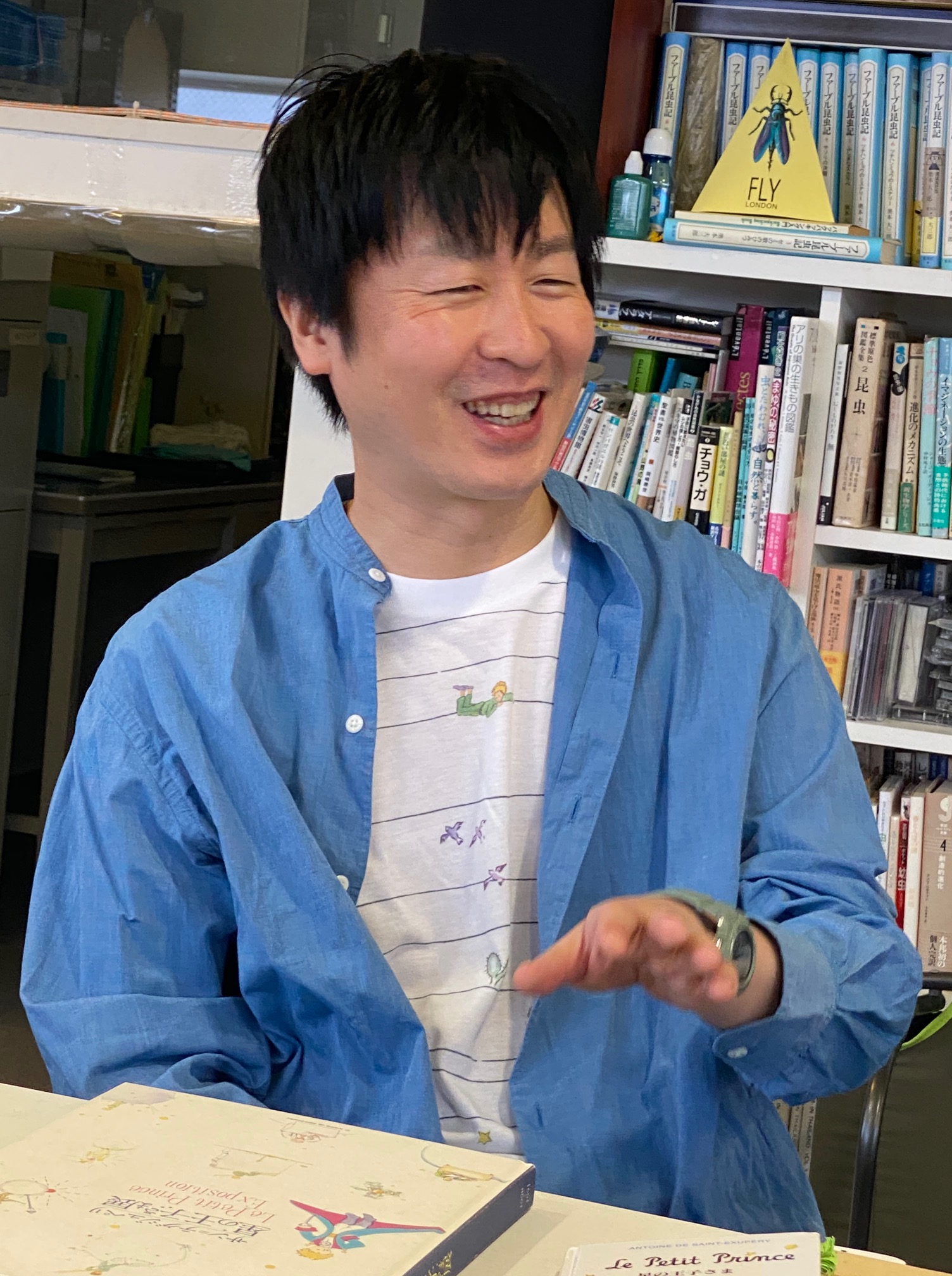
奥本 それで私は考えたんですよ。これを、絵の訓練をした上手な人が描いたら、どうなるのか。それを見てみたかったんです。
いま、多数の翻訳本があります。みんな翻訳はいじるのです。それでみんな同じ所を間違えるんだ(笑)。それがフランスと日本とのズレの部分です。でも絵をいじったのは、3作くらいしかない。
山下 絵をいじるのは、非常に危険な行為かと思います。
奥本 だからそれをあえてやろうと思ったんです。僕の中にあるフランスへの憧れというか、しゃれたもの、フランスのいいところ、それがやっぱりこの物語に出ています。これをなくさないで、日本語をいじって、絵もいじって、本質を変えることなしに、別の可能性を実現してみたかった。
フランスでフランス料理を食べるでしょ、それを日本で食べるとどうなるか、醤油をひとたらしするとか、和風にするでしょ。そうすると「洋食」になっていく。とんかつもメンチカツも日本にしかありません。たとえるとヴェルサイユ宮殿と数寄屋造りの混合みたいなものを作りたかった。気候風土のちがいが、人間の造るものを変えていく。そんな味をちょっと出したかった。
それは成功したと思います。
今まで絵をいじった作品は、なんか「星の王子さま」の美しさに復讐するかのように、ことさら刺激的に描いているではないですか。美しいものを壊そうとする……なんか恨みでもあるのかしら。僕としては思い切り理想化してきれいなものをと思ったんです。
たとえば王子さまに誘われてふたりで夕陽を見に行く章なども、夕陽を美しく描くことで、王子さまが抱えている寂しさがしみじみと伝わります。今まで文章だけだと読み飛ばされがちな、細かい部分をよく表現されたと思いますよ。
山下 先生の言う理想になったかわかりませんが、自分としては原作に「素直になる」という戦い方しかありませんでした。
奥本 それから、このまんがでは砂漠の美しさが強調されていますね。何にもない、過酷で熱いだけのように見える砂漠なんだけど、夜になると星がものすごくきれいだし、昼間でも風紋とか、よく見るといろんな生き物がいるんですよね。ゴミムシダマシとかスカラベもいるだろうし、わずかな植物もしぶとく生えているわけでしょ。
山下 原作にない部分も絵にしました。誰も気づいてもらえないと思うのですが、黄色いカタツムリを描いたんです。サン=テグジュペリの砂漠の体験を小説にした『人間の土地』に出てくるのです。フェネックは擬人化されていますが、ほかの生き物が出てくるほうが自然かと思いました。
それから始めと最後に、こっそり、スカラベを登場させたのは、「星の王子さま」というより、この作品の前に先生と6年連載でご一緒した「ファーブル昆虫記」の象徴と言いますか、共著のシンボルとして登場させたという遊び心からです。ただ、それだけでなく、再生の象徴として、パイロットはこの砂漠から生きて帰るということも暗示してみたかったからです。
奥本 砂漠も生き物がいっぱいいるところと、そうでないところとがあるんですね。フェネックなんかは食物連鎖の上のほうですから、相当の食物がないと生きていけないです。ゴミムシダマシばかり食べているわけにはいかない。あれはおもに何を食べているんですか。
山下 イヌ科ですから、トカゲやネズミなんか食べているんではないですか。
奥本 砂漠にもそういうのがたくさんいると思いますよ。
サン=テグジュペリの他の物語を読んでいると、『星の王子さま』の舞台である北アフリカのベドウィン族、彼らは水についてすごく不思議な観念を持っていますね。
ベドウィン族をサン=テグジュペリたちはフランスに連れて行くんですよね。あれは日本人も昔、台湾でやったことなんですよ。台湾の高砂族を宮城に連れて行って、「日本」というのがいかに強大な国であるかを知らしめようとするんです。それをベドウィン族相手にフランスもやっています。連れて行かれたベドウィンの人たちが一番感心したのは、フランス文明ではなくてフランスの水の豊かさなんですね。フランスでベドウィンの人が岸辺に座ったままずっと飽きずに水を見ている。「何を待っているのか」と訊くと「この水が終わるのを待っている」って言うんです。
生まれたときから水がたくさんあるところで育った人と、水のきれいさとか貴重さをつぶさに感じている人は違いますね。
山下 そんな過酷な砂漠にぽつっとパイロットが落ちて……
奥本 ところが1000マイルも歩かないと人のすんでいるところにたどり着かないって言っているんだけど、ベドウィン族にとっては、どこの道を行けばどこに出るかというのがわかっているんですよ。我々が、田舎の道を行くくらいわかるのではないですか。星を見てもわかるし植物を見てもわかる。同じように見える風景が、じつは違うってわかっているんじゃないかなあ。それだけわれわれは鈍いんでしょう。スマホが圏外だと何もできない。
――パイロット=原作者の等式
山下 サン=テグジュペリが描いた挿絵に戻りますが、物語のなかでパイロットの口を借りて、彼はこんな言い訳しています。「僕は子どものときから絵を描いていないので、出来のばらつきがあるのは当然だ」って。こういうところからも、パイロットはサン=テグジュペリだというのがわかります。
奥本 そのへんは曖昧でいいんですよ。
山下 そんな言い訳を物語の中に入れて、パイロットは自分なんだよ、って作者は言っている。つまりパイロット=王子さまという等式のほかに、パイロット=作者という等式もあります。こんな入れ子構造をしている物語は、じつに不思議な本です。
奥本 今回は最初からパイロットの名前もアントワーヌにして、作者であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリという設定にしました(原作では別)。
山下 たとえば砂漠を走る鉄道の中に子どもがいて、人形を大切にしているというエピソードがあるのですが、サン=テグジュペリも子ども時代にテディ・ベアを大事にしていました。実際、彼もサハラ砂漠に飛行機で不時着して、九死に一生を得る体験があり、極限状態の中で、自分の子ども時代が走馬燈のように出てきてもおかしくないと思います。それで人形を持った子どもを列車内に描き込んだのです。
奥本 星の王子さまは誰なのか、パイロットは誰なのかも含めて、読者の受け止め方はいろいろでしょうが、文章だけでは伝わりにくい微妙なニュアンスを今回は絵の力を借りて、届けることができました。大切に読んでいただけるといいな、と思います。


フランス文学者の奥本大三郎が、原文を読み解き、その作品世界を構築。絵本作家のやましたこうへいが「まんが」にしました。文章ではなかなか伝えにくい美しくも切ない新たな「星の王子さま」をお届けします。
10月30日(金)発売予定!
文・奥本大三郎 まんが・やましたこうへい
A5判ハードカバー 256ページ オールカラー
定価 本体2,800円+税
試し読みリンク https://www.shogakukan.co.jp/books/09388705
プロフィール

文:奥本大三郎
1944年大阪府生まれ。フランス文学者、作家、NPO日本アンリ・ファーブル協会理事長。埼玉大学名誉教授。おもな著書に『虫の宇宙誌』(読売文学賞受賞 集英社文庫)、『楽しき熱帯』(サントリー学芸賞 講談社学術文庫)、『虫の文学誌』『蝶の唆え』(ともに小学館)など多数。『完訳 ファーブル昆虫記』(集英社)で第65回菊池寛賞。一連の活動に対して2018年第53回JXTG児童文化賞。

まんが:やました こうへい
1971年神戸出身。グラフィックデザイナー、絵本作家。キャラクターを中心に幅広くデザイン活動を行う。おもな著書に『かえるくん と けらくん』(福音館書店)、『ばななせんせい』(童心社)、『ちびクワくん」『世界を救うパンの缶詰』(産経児童出版文化賞 ほるぷ出版)など多数。奥本大三郎との共著で、『ファーブル先生の昆虫教室』など。website:www.mountain-mountain.com
初出:P+D MAGAZINE(2020/10/29)



