“パスティーシュ”ってなに? 小説用語を徹底解説

“先行作品の模倣”を意味する用語、「パスティーシュ」。小説の世界には、素晴らしいパスティーシュ作品が多数存在します。それらの作品を紹介しつつ、「パスティーシュ」とはどんなものか、解説していきます。
小説を読んでいて、「この文体の雰囲気、どこかあの作家に似ているな……」と感じたり、「この一節と同じフレーズが古典作品のなかにもあった気がする」と思ったりしたことはないでしょうか。もしかするとそれは、過去作品の“パスティーシュ”かもしれません。
パスティーシュとは、「作風の模倣」を意味するフランス語です。音楽や絵画、演劇作品においてもたびたび見られる技法ですが、小説の世界でも、パスティーシュは古今東西のさまざまな作品のなかで用いられています。今回はそんなパスティーシュについて、実際の作品を例に挙げながら解説していきます。
パスティーシュ=「パロディ」「文体模写」?

パスティーシュよりも一般的な言葉に、「パロディ」があります。パロディは、先行作品を批評的な意図を込めて模倣するという意味で使われる言葉。パスティーシュも広くはこの「パロディ」に含まれると考えられますが、小説の世界では、ある作家や作品の文体を模倣する技法、「文体模写」に近い意味で用いられることが多いです。
一例を挙げましょう。イタリアの小説家・哲学者であるウンベルト・エーコによる『ノニータ』は、ウラジーミル・ナボコフによる『ロリータ』のパスティーシュ小説です。
ノニータ。わが青春の花、わが眠れぬ夜の悩み。二度ときみには会えまい。ノニータ。ノニータ。ノニータ。三音節、やさしさでつくられた否定語のよう。ノ。ニー。タ。ノニータ、きみのことなら思い出せる、きみのすがたが闇にまぎれ、きみの棲み処が墓になるまで。(中略)
愛していたのだ、友人読者よ、あの狂おしく燃える歳月、私はほんとうに愛していたのだ、きみなら迂闊にも鈍感に「ババア」と呼ぶような女たちを。青い心の襞の迷路の奥底で私は欲していたのだ、すでにして仮借ない年齢の過酷さが刻まれ、八◯年という死に至る韻律にひざまずき、待ち焦がれていた老衰という亡霊に残忍に蝕まれている、あのか弱い生き物たちを。
──ウンベルト・エーコ『ウンベルト・エーコの文体練習』「ノニータ」より
お読みいただければわかるとおり、原作では幼女に対して恋心を抱く主人公が、ここでは老女に恋する人物として書き換えられています。パスティーシュにおける先行作品の“模倣”は、(もっともわかりやすい場合は)このような形でおこなわれます。
視点を替える、現代的に読み換える──パスティーシュのさまざまな形式
パスティーシュには、単に“文体を似せる”だけではなく、非常にさまざまなやり方・形式があります。多種多様なパスティーシュ作品を知り、味わうことができる作品集として、『小さいおうち』などの代表作を持つ小説家・中島京子による『パスティス 大人のアリスと三月兎のお茶会』が挙げられます。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4480435867/
本書には、日本・海外の名作文学を下敷きにした16の短編小説が収録されています。
そのなかの1篇、『腐心中』は、森鴎外の『普請中』のパスティーシュ小説です。『普請中』は主人公の渡辺という男性が、かつての恋人であったドイツ人女性に再会するという、『舞姫』の後日譚のようなストーリー。『普請中』では男性視点で書かれていた物語を、中島はその元恋人の視点を用い、インタビュー形式の作品に書き換えました。
『腐心中』の舞台は、ふたりが別れてから数十年後のニューヨーク。渡辺の元恋人であるエリーゼ・コジンスキーに、インタビュアーが“二十五年前に訪日した、本当の理由を、お聞かせいただけませんか?”と尋ねます。エリーゼの話を聞いていくと、『普請中』では渡辺に対して断ち切れない恋心を抱いていたから彼女が訪日したかのように書かれているものの、じつは単にお金の工面に行っただけで、断ち切れない思いを抱いていたのはむしろ渡辺のほうだった──という事実が浮かび上がってくるのです。このように、本作は先行作品のほかの登場人物を語り手にすることによって、原作の主人公の一方的な主観に対する批評性を発揮した作品になっています。
また、アンデルセンの『親指姫』のパスティーシュである『親指ひめ』では、主人公の親指姫がさまざまな動物にさらわれ、無理やり結婚させられそうになってしまう展開を、現代の女性の生きづらさになぞらえています。
親指ひめは、ひきがえるのおばさんにさらわれては
「あら、かわいい。うちの息子の嫁にぴったり!」(中略)
「女の幸せは結婚相手で決まるんだから、あんた、いいのをつかんだよ。嫁になったからには、子供を産んでもらうよ。あたしの老後のためにも、国の年金のためにも、子供がいっぱい必要なんでね。戦争が始まれば、兵隊も必要さ。いくら産んだって産みすぎるってことはないよ。人もかえるも時代について行かなきゃ」
などと勝手に縁談を進められそうになったり、そこから逃げられたあとも、
「なんだこのブス。こんな醜いのは見たことがないよ」
とこがねむしの集団に罵倒されたりと、個人としての人格を否定され続けます。本作は、ストーリーの大筋は先行作品から変更せずに、現代的な文脈で読み替えをするという形式のパスティーシュになっています。
著者は作品のあとがきのなかで、パスティーシュ小説を書くという試みは、“先行作品との、そしてその作品の作者との、時空を超えた対話のようなもの”だと語っています。本書は、さまざまなタイプの作品を通してその“対話”の妙を感じることのできる、パスティーシュの好例です。
清水義範、佐川恭一──パスティーシュの名手たち
批評性はもちろん、巧みな文体模写や意外な改変によって読者を思わず笑わせてしまうようなユーモアも、忘れてはならないパスティーシュの大きな要素です。ここでは、パスティーシュの名手である現代作家たちの作品のなかから、特にユーモラスなパスティーシュ小説を2つご紹介しましょう。
1冊目は、パスティーシュの手法を用いた短編作品を数百篇以上執筆し、パスティーシュ小説の代表的作家として挙げられる清水義範の作品集です。
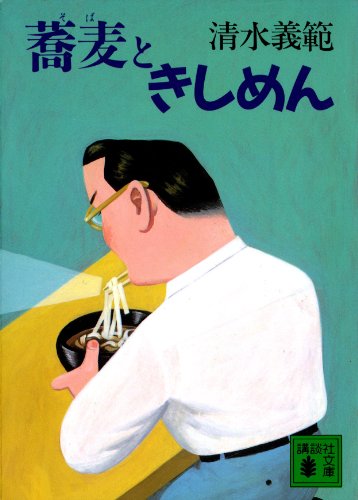
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B00GYTHTCI/
『蕎麦ときしめん』は清水が1986年に発表した、最初のパスティーシュ作品集。本書には、無名のサラリーマンの妙な論文という体で書かれた表題作の『蕎麦ときしめん』や、ある学術書の序文という設定で書かれた『序文』など、ひねりのあるパスティーシュ小説が多数収録されています。
なかでも面白いのが、ある寝装品メーカーに勤める歴史小説好きな社員が、その企業の社史の執筆を任されて筆を執った──という設定の小説『商道をゆく』。
第一章 坂の上の星
会社の歴史は時に物語に似ている。
主題、がある。
このさほど大きくない寝装品メーカーの場合、それは、
発明──、
であった。
会社の創立もある発明をきっかけとしたものであったし、度重なる不況を脱出したのもすべて発明によってであった。
その発明のことごとくを社長の田島静夫がなした、ということは立派であるのを通りこして何やら滑稽ですらある。
──『商道をゆく』より
タイトルや癖のある文章からもわかるとおり、本作は架空の社史という形で司馬遼太郎の文体模写をしているのです。特徴的な読点の打ち方や、語り手がときに大きく話題に介入し“余談”の説明を加えていくところなどは非常に巧みで、司馬遼太郎を一度でも読んだことのある読者であれば、つい笑ってしまうはず。
清水義範は本書でパスティーシュの技法を確立し、以降は、現代文の入試問題の解き方を指南するという体の短編集『国語入試問題必勝法』や、英語教科書に登場する有名なキャラクターたちのその後を描いた『永遠のジャック&ベティ』など、創意工夫に富んだパスティーシュ作品を多数発表し続けています。
そして、2冊目は2011年にデビューした現代作家・佐川恭一による作品集、『童Q正伝』。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07NCCZ3LN/
本書は、連続テレビ小説『半分、青い。』のパロディとして著者が衝動的に書き下ろしたという『半分、入ってる。』や、ゼロ年代の京都大学の様子を赤裸々に描いた『童Q正伝』など、悪ふざけとも呼べるような問題作ばかりの作品集。なかでも、『ナニワ最狂伝説ねずみちゃん』は、村上春樹の『風の歌を聴け』の大胆すぎるパスティーシュ作品となっています。
おまえら聴けぇ、聴けぇ! 静かにせい、静かにせい! 風の歌を聴けっ! 男一匹が、命をかけて諸君に訴えてるんだぞ。いいか。いいか。静聴せい、静聴せい! おまえら、風の歌を聴けぇっ!
「金持ちなんて・みんな・くそくらえやろが!」
ねずみちゃんはカウンターに両手をついたまま誰に向けてともなくそう怒鳴った。ねずみちゃんは、いつも上下ねずみ色のスウェットを着ているので、ねずみちゃんなのだ。
「ほんま、うちらなんか、スウェット買うのでギリやっちゅうねん。」
そう言いながら、ねずみちゃんはビールをガブガブ飲んだ。ねずみちゃんは一日最低1000ミリのビールを飲むのだ。
──『ナニワ最狂伝説ねずみちゃん』より
という冒頭箇所からして思わず笑ってしまいますが、著者の作品にはこのように下世話でありながらどこか爽快感もあり、読後には諸行無常を感じてしまうような、巧みなパスティーシュの技術が多用されています。
ブラックユーモア、時事ネタ、皮肉、下ネタ──。清水義範、佐川恭一の作品には、そんなパスティーシュならではの面白さが詰まっています。
おわりに
清水義範はかつて、「文学は、どんな大作もすべてパスティーシュからできている」と述べました。遡ればミルトンの『失楽園』やオスカー・ワイルドの『サロメ』が旧約聖書を下敷きにした話であるように、どんな物語も先行作品を咀嚼して著者なりに再構築・再解釈をしないことには成り立たない、という意味でしょう。
読み手にとっても、文学作品に向き合っているときに「もしかしてこれはあの作品のパスティーシュ?」と気づくことは、読書の、数ある喜びのひとつです。今回ご紹介した作品のほかにも、作家の技術と先行作品への敬意のたまものであるパスティーシュ小説を見つけたら、ぜひ楽しんで味わってみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/02/27)

