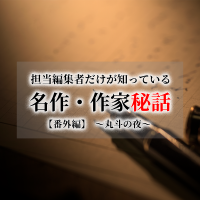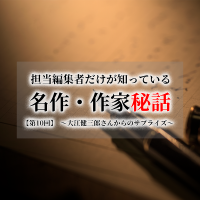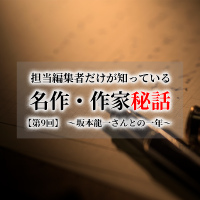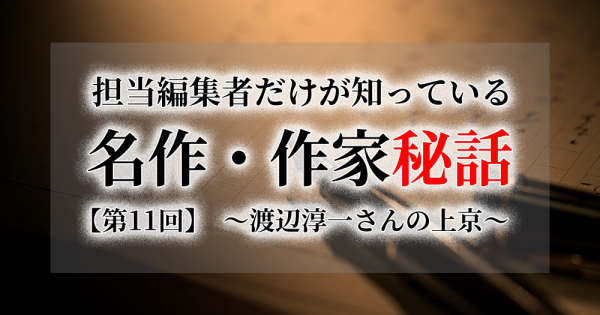連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第11話 渡辺淳一さんの上京
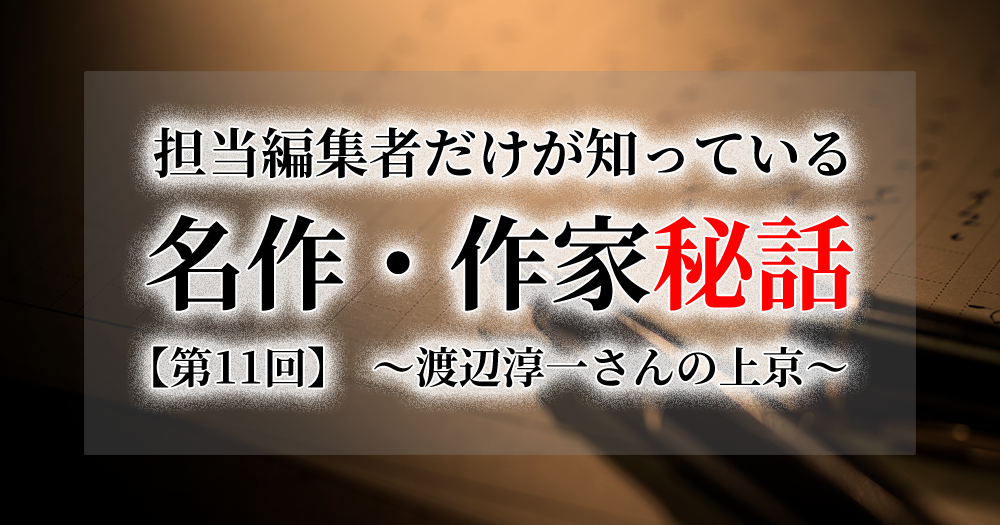
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第11回目です。「渡辺淳一」といえば、数々のベスト・セラーを生んだ人気作家の一人。「失楽園」の爆発的なヒットは、記憶に新しいと言えるでしょう。その名を冠した文学賞も第8回を数えます。北海道出身の渡辺淳一が上京する際のエピソードを、担当編集者が振り返ります。
渡辺淳一さんの上京
2023年度の「渡辺淳一文学賞」の当選作が、古谷田奈月氏の『フィールダー』に決まったようだ。この賞は、渡辺さんが亡くなってすぐ、集英社が設立したもので、もう8回目になっている。現在の選考委員は浅田次郎さん、小池真理子さん、髙樹のぶ子さん、そして宮本輝さんの四人。豊かなストーリー性と合わせて、深く文学的に達成した作品を書いてきた作家たちだ。
渡辺淳一さんは、生前、ベスト・セラーを連発して、大きな文学賞をいくつも受賞し、ついには自分の名前を冠した文学賞まで設立されたことになる。
私は、ベスト・セラーになった長篇小説『失楽園』を出版した部署の責任者だった。1997年のことだ。妻ある男と、夫ある女の、いまの言葉で言うとダブル不倫の物語で、この道ならぬ激しい恋も行き詰まった挙句、ふたりは愛の最高潮の中に心中することになる。
この「心中」のあり方が話題を呼ぶことになった。高級ワインとして有名なシャトー・マルゴーに青酸カリを入れて「心中」が決行されるからだ。この点については、当時も賛否両論があった。
実は、日本版の発売とほぼ同時に、英語版の刊行の計画も進んだ。同志社女子大学の教授で、翻訳の第一人者であるジュリエット・カーペンターさんに翻訳を頼んだ。カーペンターさんは、この男女がなぜ心中しなければならないのか分からないと疑問を呈された。アメリカ人の考えなら、ふたりとも離婚して新しい生活を始めるはずだということだった。なるほど、のちに渡辺さんとアメリカに行って、パブリッシャーズ・ウィークリーなどのブック・レビュー誌の編集者たちと会った時にも、一番話題になったのは、その点だった。
渡辺さんもぼくも、日本には古くから、人形浄瑠璃や歌舞伎、あるいは落語などの大きな伝統的なジャンルに、「心中物」があると力説した。近松門左衛門の「曽根崎心中」や「心中天網島」などの名作がある。現に、作家の有島武郎は、軽井沢の別荘で、編集者だった波多野秋子と心中していることも話したが、アメリカ人の編集者たちに、充分に、分かってもらえたとは思えなかったのは残念だった。
『失楽園』は、日経新聞の朝刊に連載された時から、日経の役員がこぞって、出勤のハイヤーの中で、いの一番にこの連載を読んでいるという噂が流れ、コンビニでサラリーマンが買うために日経新聞がいち早く売れ切れてしまうなどという話も聞こえてきた。

こんな風に、この小説は刊行前から、大きな話題になっていた。担当者の努力によって、我が社から刊行するということは、連載前から決まっていた。連載が完結して、いよいよ初版部数を決める社内の会議で、25万部と決まった。異例の多さなので、私でもこの数字に実感が持てなかった。
私は渡辺さんのもとに出向いて、初版部数が決まったことを告げた。
「いくつになるの?」
と、渡辺さんに訊かれて、私は答えた。
「25万部です」
「バカ!」
即座に渡辺さんは言った。
「売れ残ったらどうするんだ?」
「なに、社内では、今度は、重版をいつ、何部にするかと心配してますよ」
私は涼しい顔を装ってそう答えた。
渡辺さんは、なおも心配そうな顔をしながらも、表情を緩めていた。
連載が始まる前だったと覚えているが、渡辺さんに、
「社内恋愛をしている人たちは、社内ではどうやって連絡を取り合っているんだい?」
と、訊かれたことがある。
「相手のロッカーにメモを残すという手があるみたいですよ」
そんなことを答えたが、ちょうどその時分から、携帯電話が一般の人たちの間でも流行り出して、あっという間に、なんにでも連絡は携帯電話を使う風潮になった。小説でも携帯電話が使われていると思う。余談になるが、携帯電話が不倫事情を変えたことに異論はないだろう。妻が夫の携帯のメモリーを盗み見て、あるいは夫が妻の携帯を盗み見て、軋轢が生まれる話はよく聞く話になっている。
売れ残る心配はする必要はなかった。文字通り、売れに売れたのである。何度も行った書店でのサイン会で、開始を待つ大勢の人の行列ができたが、そのほとんどが、女性だったと思う。時間になって、渡辺さんが座っているテーブルに案内しようとして、待ちかねた人たちが必死の形相で押し寄せた時など、肉塊の雪崩に巻き込まれるような恐怖を覚えたのは、決して大袈裟な表現ではない。
渡辺さんは、札幌医科大学の青年医師で、将来を嘱望される整形外科医であった。しかし、同時に、同人誌に参加して話題作をコツコツと発表してきて、いわゆる二足の草鞋を履いていたと言える。
そうした日々を送るうち、1968(昭和43)年のことになるが、同じ医科大学で、日本で初めての心臓移植の手術が行われた。このことが渡辺さんの人生の方向が大きく変えることになる。
心臓血管外科の和田寿郎教授が行った心臓移植は、弁膜症である18歳の男性の心臓を取り出し、そこに溺死寸前で脳波が反応しなくなったとされる21歳の男性から摘出した心臓を植え付ける、いわゆる「同所性心臓移植」だった。心臓を受けた患者は、83日目に拒絶反応と感染症を引き起こし、死亡する結果となった。
渡辺さんは、そのことを材にして、中篇「ダブル・ハート」を発表する。実際の手術は「同所性心臓移植」だったが、小説では、受け手の心臓はそのままに置いて、提供者の心臓を植えつける心臓移植の方法に変え、担当していた患者の妻に、心臓を提供するドナーになることを説得するという役目を押し付けられる若い医師の苦悩を描いている。
いつだったか、新聞社の主催で京都で開かれた渡辺さんの講演会にお供したことがある。広い会場だったが、渡辺さんが語る、分刻みの心臓移植手術の実際に、会場全体が固唾を飲んだように聞き入ったことを覚えている。
その小説「ダブル・ハート」を発表したのが、心臓手術後あまり時間が経っていない時だったこともあって、話題になった。しかし、渡辺さんのこの小説は、手術に批判的な意味が込められたこともあり、大学に居づらくなってくる。
そのあたりのことは、渡辺淳一文学館の資料に以下のように書かれている。
1954(昭和29)年、札幌医科大学医学部に入学。処女作「イタンキ浜にて」発表。
1957(昭和32)年、同人誌「くりま」に参加。
1959(昭和34)年、医師国家試験に合格。『人工心肺』が脚本募集に入選し、放映される。
1964(昭和39)年、『華やかなる葬礼』、道内同人誌秀作。
1965(昭和40)年、『華やかなる葬礼』を改稿した『死化粧』で新潮同人誌賞受賞。
1966(昭和41)年、『死化粧』が芥川賞候補となる。
1967(昭和42)年、『霙』が直木賞候補となる。
1968(昭和43)年、『訪れ』が芥川賞候補となる。
1969(昭和44)年、1月、単行本『ダブル・ハート』が、「死化粧」「霙」「訪れ」を収録して、文藝春秋から刊行さる。札幌医科大学講師を辞職。3月、長篇小説「小説・心臓移植」が文藝春秋から刊行。直木賞候補となる。
そして、作家として独り立ちを志し、妻子を札幌に残したまま、渡辺さんは上京するのである。つまり、渡辺さんにも、作家として食べていけるのか不安におののく、新人作家の日々がはじまったのである。
渡辺さんは、その頃のことを、自伝的小説『何処へ』として書いている。まず、「週刊新潮」に連載されたが、小説の中での主人公・相木悠介は渡辺淳一さんがモデルになっているのだが、まさに渡辺淳一そのものと言っていい。
そして、この決断を「手術を批判して大学病院にいづらくなったためだが、同時にそれをきっかけに作家一本でやってみようと思ったからであり、さらには裕子と一緒に逃げることへの憧れもなかったとはいいきれない。人生のなかでなにか一つ、だいそれたことをしてみたい、そんな冒険心があったことも否めない。」と書かかれている。
主人公・悠介が、三十五歳で大学の職を捨てて上京してきたのは、悠介の生涯にとって、まさに清水の舞台から飛び降りるような大決断であった。まだ小説だけの収入では生活が安定しない上、学齢期の子供もいるなどの理由から単身で上京することを妻に納得させる。「妻の座にある者の自信か、それとも反対しても無駄だと知ったはての諦めか」と書かれているが、実際には悠介は札幌で付き合っていた裕子を伴って上京するのである。「駆け落ち」という言葉が悠介の頭の中に浮かぶのだった。
上京した悠介と裕子が住んだのは、墨田区向島である。
小説には、「震災記念堂がある公園に沿って真っ直ぐ行くと本所から浅草に向かうことになるが、公園の角の交差点を左に曲がれば隅田川を渡る蔵前橋に出る。悠介のアパートは、その交差点の手前を右に曲がって1ブロック行った角にある。」とある。
墨田区石原一丁目である。
悠介は、生活のことを考え、アパートから道路一本距てている病院にアルバイトの仕事を得る。こうして、東京での生活がはじまった。
『何処へ』の中に、小説G誌の編集長になったばかりの殿村(実際は「小説現代」の大村彦次郎さんである)に、
「このあたりに住んだのは賢明です。このあたりはまだ下町の風情が残っているところですから。若いうちにこういうところに住んで、いろいろなところを見ておくとあとで必ず役に立ちますよ」
と、言われるシーンがある。
ちなみに、このとき、殿村編集長に伴われて、悠介を担当する入社したばかりの編集者として紹介されるのが宮内となっているが、これが編集者に成り立ての私である。
おもはゆいことだが、そのくだりを紹介してみる。
「見たところ、宮内はまだ小説雑誌の編集者としては新人のようだが、小柄で眼鏡をかけた賢そうな顔には、これから自分が担当する新人作家への好奇心があふれているようである。」
どうです、賢そうな顔ですぞ!
そのあと時を経ずして、私はグラビアを撮るためにカメラマンと一緒に渡辺さんを訪ね、向島に近い隅田川の堤に行って写真を撮らせてもらった。
渡辺さんは、初夏の暖かい日だったが、オープンシャツにジャケットを着て、木の柵に軽くもたれ、隅田川の川面を背景に映っている。
この日のことだと覚えているが、アルバイトで勤めている病室を回る渡辺さんのあとに従って、私は雑居病室に入った。渡辺さんは、ベッドの上に起き上がっている老人の手を持って、気さくに声をかける青年医師という爽やかな印象だった。
後でオフィスに戻った渡辺さんは、
「さっきの人は梅毒でね。指がああして曲がっているんだ。この辺りは、向島が近いせいか、梅毒の人が多いんだ」
と軽い口調で言った。それこそ新人の編集者には驚くような病名だったが、もちろん完治すればなんということもない病気だったし、渡辺さんの気軽な雰囲気にも影響されて、深刻には考えなかったが、それでも半世紀以上経っているのに、老人の歪んだ手と渡辺さんの言葉は忘れられることはない。
裕子は、悠介が夜、執筆している間、時間を持て余したのと、自分で使える金を稼ぐためもあって、銀座のクラブのホステスになる。当然、生活が派手になり、気持ちの上で悠介とすれ違ってくる。『何処へ』の後半では、その心の隙間に忍び込むように、同じ病院の看護婦の雅子や新宿で出会った女優の貴子との交際がはじまり、その葛藤が、克明に描かれるが、それは以後の渡辺さんの恋愛小説の片鱗を思わせる作品になっている。
新人小説家の渡辺さんは、先輩作家・有馬頼義さんが主催する「石の会」に参加するようになる。石の会は、高井有一さん、色川武大さん、後藤明生さん、森内俊雄さん、早乙女貢さん、五木寛之さん、立松和平さんといった、当時はまだ新人作家だった人たちが集って、切磋琢磨する会であった。東京に出たばかりの渡辺さんにとって、この会の存在と、同郷の先輩作家・船山馨氏との交流は大いに文学的刺激をかき立ててくれる貴重なものとなった。
浅草にあるお好み焼き屋「染太郎」は、高見順の『如何なる星の下に』に登場する老舗である。小説の中では、「染太郎」は「惚太郎」に変えられている。少し長いのであるが、引用してみたい。私は、ここと次の章のお好み屋の描写が好きなのだ。
「私は火鉢の火が恋しくなった。『──そうだ。お好み焼屋へ行こう』」
本願寺の裏手の、軒並芸人の家だらけの田島町の一区画のなかに、私の行きつけのお好み焼屋がある。六区とは反対の方向であるそこへ、私は出かけて行った。
そこは「お好み横町」と言われていた。角にレヴィウ役者の家があるその路地の入口は、人ひとりがやっと通れる細さで、その路地のなかに、普通の仕舞屋がお好み焼屋をやっているのが、三軒向い合っていた。その一軒の、森家惚太郎という漫才屋の細君が、ご亭主が出征したあとで開いたお好み焼屋が、私の行きつけの家であった。惚太郎という芸名をそのまま屋号にして「風流お好み焼──惚太郎」と書いてある玄関のガラス戸を開くと、狭い三和土にさまざまのあまり上等でない下駄が足の踏み立て場のないくらいにつまっていた。
「こりゃ大変な客じゃわい」
辟易していると、なかから、「──どうぞ」と細君が言い、その声と一緒に、ヘット(※牛脂のこと)の臭いと、ソースの焦げついた臭い、そういったお好み焼屋特有の臭いをはらんだ暖かい空気が、何やら騒然とした、客の混雑というのとはちょっと違った気配をも運んで、私の鼻さきに流れて来た。──玄関脇の三畳間に、三つになる細君の子供が、昼寝のつづきか、奥の、といっても二間しかないが、奥の六畳間の騒ぎに一向平気で、いと安らかに眠っていた。」
と、ある。
「やきそば。いかてん。えびてん。あんこてん。もちてん。あんこ巻。もやし。あんず巻。よせなべ。牛てん。キャベツボール。シュウマイ。(以上いずれも、「五仙」)。テキ、二十仙。おかやき、十五仙。三原やき、十五仙。やきめし、十仙。カツ、十五仙。オムレツ、十五仙。新橋やき、十五仙。五もくやき、十仙。玉子やき、時価」が、惚太郎のお好み焼きの品目である。仙とは銭のことで、この字を使うのは、人が山ほど来るという意が込められているのだそうだ。
作家の野坂昭如さんを筆頭に、物書きや編集者たちの集まり「酔狂連」の飲み会を、この「染太郎」で開催したことがある。下町っ子の編集長・大村彦次郎さんの設営だった。私も野坂さんの担当者として参加していた。渡辺さんが少し遅れて姿を見せたのは、大村さんが声をかけたのだと思う。畳の上にあぐらをかいた渡辺さんは、見慣れない顔の中で、落ち着かない様子で、チビチビとビールを舐めていた。そのうち、帳場の方から、声がかかった。
「渡辺さんっていらしてます?」
「はい」
「お電話ですよ」
立ち上がって、電話をしに行った渡辺さんは、部屋に帰ってきて、襖に手をかけたまま、
「担当の病人がおかしいらしいので失礼します」
と言って、ちょっと後ろ髪を引かれるように出ていった。
あとに残った酔狂連の面々は、医者って大変だなあと、少し毒気に当たられたようだった。
渡辺さんが、実に印象的な『光と影』で直木賞を受賞したのは、それから間も無い、1970年、37歳のことである。
【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。