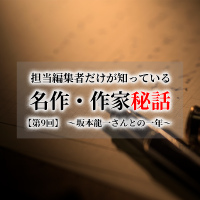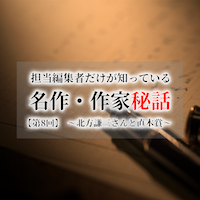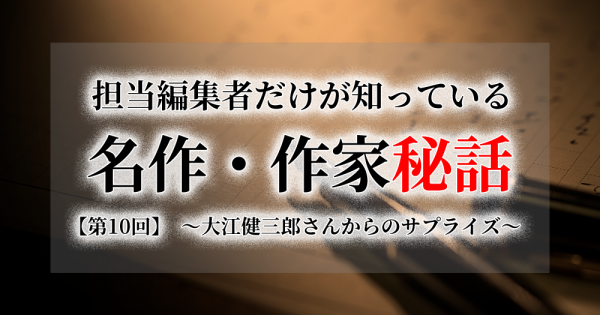連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第10話 大江健三郎さんからのサプライズ
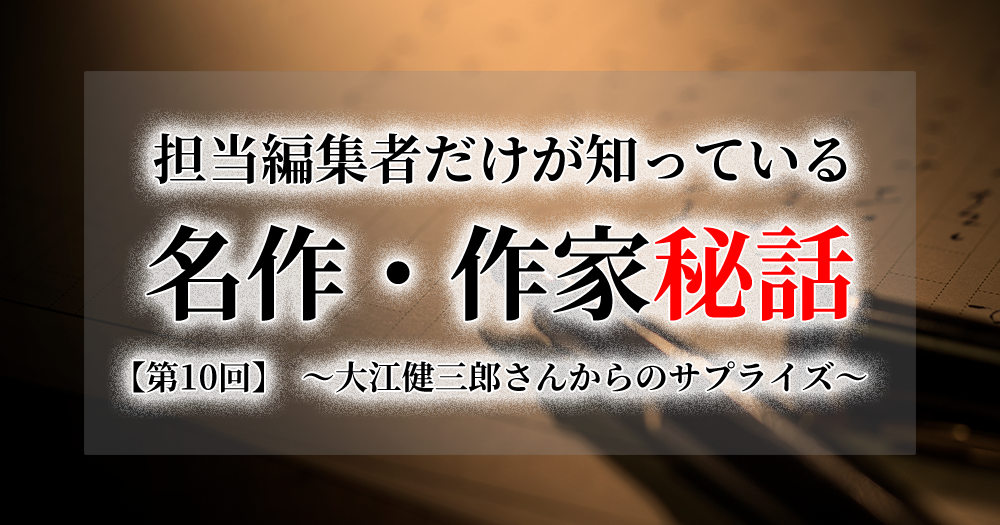
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第10回目です。「大江健三郎」といえば、1994年にノーベル文学賞を受賞した世界的文豪。その作品には難解なイメージを抱きがちですが、独特な世界観は、読み応えも抜群な名作ばかりです。2023年3月3日に老衰により88歳で逝去。それまで精力的に執筆活動をしてきた大江氏とのエピソードを、担当編集が振り返ります。
大江健三郎さんからのサプライズ
今年、2023年3月に大江健三郎さんが亡くなった。ポッカリ穴があいたようだ。しかし、私たちは、最晩年の「大江健三郎全小説(全15巻)」などを持っている。この刊行は大江さんの次代への企みだとすると、いたずらに嘆く必要ないかもしれない。しかも、文芸評論家の尾崎真理子さんが書いているこの全集の解説は、新しい読者を、よく大江さんの文学へ導いてくれるだろう。
「最後の小説」とした『燃えあがる緑の木』を連載中の1994年に、ノーべル賞を受賞することになるが、小説の創作をやめるために、1996年6月から、「大江健三郎小説(全10巻)」の刊行がはじまっている。
しかし、1996年2月、作曲家・武満徹氏への弔辞の中で、小説を再開すると告げたのである。その小説は私たちが出版することになっていた。なにかを吹っ切るためだろうか、大江さんは、同じ1996年の9月から翌1997年の5月まで、プリンストン大学の客員教授を務めた。
1997年の3月10日、私はプリンストン大学に大江さんを訪ねた。妻と一緒の旅の途中だった。宿泊していたマンハッタンのホテルからプリンストンへは、ニューヨークの出版社のCEOで、友人のロジャー・ローゼンが、自分で車で往復してくれた。
大江さんが亡くなったとき、ロジャーはメールにこう書いてきた。
「プリンストンへの旅のことはよく覚えているよ。敬愛するノーベル賞受賞作家と一緒に午後を過ごしたことは、僕にとって名誉なことだし、忘れられるものではないからね。書棚から、僕のために彼が献辞を書いてくれた『THE SILENT CRY(万延元年のフットボール)』をまた取り出してみたよ。
『To Roger With Beautiful Memory of our Conversation in Princeton, March 10, 1997』
どうだい? 素晴らしいのひと言だろう。
そうそう。あのとき、君が手書きの原稿を託されて、とてもナーバスになっていたことも覚えているよ」
あの日、大江さんは、私たちを大いに歓迎してくれ、プリンストン大学の校内の書店などを案内した上、大学のそばにあるレストランで遅いお昼をご馳走してくれた。もう細かいことは忘れてしまったが、異国での、母語ではない言葉を使っての会話は、日本では味わえないものとなった。
食事が終わると、
「ちょっと付き合ってください」
と、私たちを宿舎に連れていった。部屋から重そうな包みと本を一冊持ってきて、私に手渡した。とても持ち重りがする包みだった。本はロジャーに渡された。
「書き下ろしの原稿です」
大江さんはにこやかな顔をして言った。
私はしばらく言葉を無くしていた。まったく予期しないことだったのだ。
「あ、ありがとうございました」
それだけを言うのが精一杯だった。妻もノーベル賞作家と編集者との原稿のやり取りを見て、とても大変なことが起こっていると感じたらしく、言葉少なくなっていた。
とんでもないサプライズだった。ロジャーがあとで、「大江さんは、編集者としての君に、とても深い信頼を寄せていて、それは本当にかけがえのない関係だと僕は思ったよ」と言ってくれた。
包みを抱くようにして、停めてあった車に乗ると、私はロジャーに言った。
「ノーベル賞作家の手書きの原稿を持っているんだから、帰りの運転は慎重に頼むよ」
「手書きの原稿だって?」
「そうさ。Oe-sanはパソコンを使わず、手書きなんだ。これは世界でたったひとつしかないし、失くしたり、燃やしたりしたら、取り返しがつかないものなんだよ」
「そりゃあ大変だ。気をつけて運転しなくちゃあね」
慎重に運転してくれて、ロジャーは無事にホテルの正面に車をつけた。
ホテルの部屋に入るとすぐに包みの中身を改めた。確かに『宙返り』の書き下ろしの原稿だ。のちに単行本で上下2冊になったのだから、大そうな厚さだ。
旅の途中なので、一番安全に日本に届けるのはどうしたらいいか思案をめぐらせた。とにかく、今夜はセキュリティ・ボックスに預かってもらうしかない。そして、朝イチで、マンハッタンにある支社に行ってコピーを取ってしまおう。
包みを持って、レセプションに行き、ノーベル賞作家の手書き原稿を預かってほしいと頼んだ。手書きの原稿という意味がよく分からなかったようだが、セキュリティのかかった部屋を教えてくれた。制服の男がいてテーブルを指して言った。
「預かるから、そこに置いておきな」
包みを置くと、
「ここに俺が一晩中いるから、世界で一番安心なところなのさ」
と、鼻をうごめかした。
これで、ひと安心だ。
部屋に帰ると、妻が顔色を変えていた。
「プリンストンに行ってる間に誰か入ったみたいなの」
「気のせいじゃない?」
スーツケースの中を開けて見ると、なるほど、大した金額ではないが、現金が失くなっていた。
セキュリティに電話をすると、すぐ、制服の男がやってきて、しかつめらしい様子でスーツケースを改めている。見ると、その男はさっき、一晩中部屋にいるから安全さと自慢した男だった。それがここにいるということは、あの部屋には誰もいないんだ。そう思った途端、背筋に寒気が走った。
慌てて、その男を引き摺るようにして、セキュリティに戻ると、包みは奥の棚の上に乗せてあった。
「これは引き取るよ」
「まあいいさ、ここが世界で一番安全なんだけどな」
部屋に戻ると、もう日付が変わっていた。
私はベッドに潜り込み、包みを頭の下に置いて抱いた。これで誰かが部屋に侵入してきても、この包みだけは守れる。
オフィスが開く9時までの時間は長かった。時計の針を夜通し睨んでいたが、とても遅く感じられた。それでも時間は過ぎていった。
9時になるやいなや、オフィスに電話をした。これからしばらくコピー機を独占させてくれと頼んだ。
大江さんの原稿は、万年筆で書かれたものに、吹き出しや削除や移動などを示すために何色かの色鉛筆も使っている上、原稿用紙に継ぎ足しの紙が貼ってあったりする。この複雑さこそ大江さんが 、一度書いた文章を、撓め、歪めた上で、独特のリズムをつけたりして、あの魅力ある文体を創る手法なのである。原稿をコピー機にセットして、ポイとボタンを押せば、あとは黙っていてもコピーが取れるというわけにはいかないのだ。一枚一枚、ガラスの上に置いてコピーを取る必要がある。
初めてから4時間くらい経ったろうか、複写原稿の2通が完成した。生原稿と合わせて3通だ。万一のことを考えて、三つを違ったルートで運びたい。原本は、支社が大事なものを日本に輸送するときに使っている特別便、1通は普通の航空便、そしてもう1通は支社に保管してもらった。
旅から帰ってすぐに、包みが届いているのを確認した。経理部にある特別の金庫の中に納まっていた。火事や地震などがあっても安全な金庫の分厚い扉を厳かに開け、見覚えのある包みを見たとき、ずっと離れていた我が子に会ったような気がした。
『宙返り』は1999年6月に、講談社から書き下ろし作品として刊行された。
─教会という言葉は、私らの定義で、
魂のことをする場所のことです。
一九九九・六・七
大江健三郎
これは、我が家の書棚にある『宙返り』の上巻に書かれた、大江さんの献辞である。この意味が分かるためには、『宙返り』からの大江さんの作品を読むしか法はない。

【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。