【セカイ系とは】変化するセカイ系――「君の名は。」「シン・ゴジラ」などヒット作を考察
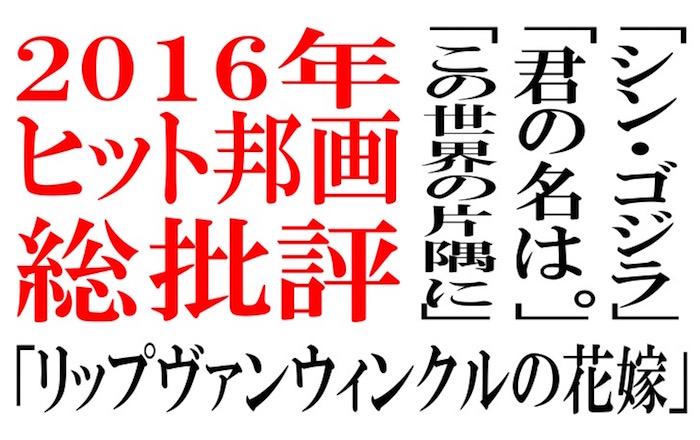
2016年に話題となった邦画から見えてくる、「日本的エンタメ」の現在地点とは? 震災の影響や、セカイ系ジャンルの変化に注目して解説します。
2016年は邦画が「当たり年」と言われた1年でした。庵野秀明監督の「シン・ゴジラ」の大ヒットに始まり、新海誠監督の「君の名は。」が公開1カ月で興行収入100億円を超える記録的なヒットに。「アニメ」、「実写」、「エンタメ」、「文芸」の枠を超えたこれらの映画は、映画批評家のみならず一般の映画ファンを巻き込んで様々な批評を呼ぶことにもなりました。
2016年のヒット作たちが生まれた背景には一体、どのような日本の状況が隠されているのでしょうか? P+D MAGAZINE編集部は今回、過去のインタビュー記事に登場いただいた作家であり批評家である坂上秋成氏に寄稿を依頼し、2016年の邦画ヒット作から見る日本的エンタメの現在地点について論考いただきました。
〔以下、坂上氏寄稿文〕
【目次】
1. 変化するセカイ系
5. 震災による変化を受けて
1. 変化するセカイ系

2016年は内容面でも興行面でも、話題となる邦画作品の多い年だった。語るべきことはいくらでもあるが、本稿では新海誠監督「君の名は。」、庵野秀明監督「シン・ゴジラ」、岩井俊二監督「リップヴァンウィンクルの花嫁」(以下、「リップ」)、そして片渕須直監督「この世界の片隅に」を中心に、わたしたちの生きる世界のイメージが大きく変化したという点について論じてみたい。
端的に言えば、それは「震災を経たことによるセカイ系作品の変化」ということになる。セカイ系とは、「主人公たちの生きる平坦な日常と、世界の命運を左右するような巨大な出来事が、直接結びついてしまうような想像力」を指す言葉として説明できる。
しかし、これはあくまでも形式や構造に対する解説に過ぎない。むしろ重要なのは、セカイ系と称される作品群のほとんどが、登場人物たちの「後ろ向きな内面」の描写に重きを置いている点である。それに合わせる形で、儚げな主題歌やBGM、夕暮れ時の空や荒れ果てた廃墟の映像、死を予感させるような登場人物の台詞と言った要素を加えていくことで、セカイ系としての雰囲気は作られていく 。(※註1)
ではそれを踏まえた上で、「セカイ系作品の変化」とはどのようなものになるのか。まずはその点について、「君の名は。」「シン・ゴジラ」「リップ」を比較することから考えよう。
2. 不能性からの脱出――「君の名は。」
初めに「君の名は。」について見ていこう。本作は東京に住む少年・立花瀧と、岐阜県にある糸守町で暮らす少女・宮水三葉の意識の入れ替わりを軸に進む物語だ。二人は初め自分たちが入れ替わっていることに戸惑うが、入れ替わっている間の出来事をスマートフォンにメモとして残すことで情報を交換し、次第に惹かれあうようになっていく。ところが、唐突に入れ替わりが起こらなくなり、連絡もとれない状況となったことで、瀧は直接三葉に会いにいくことを決意する。その過程で瀧は、糸守町が三年前の彗星の落下によって消滅しており、三葉もまた死亡しているという事実を知ることになる。そこから瀧は、三葉が生前残した、神事に使う口噛み酒を飲むことで再び入れ替わりを起こし、悲劇を回避するべく立ち回っていく。
特異な能力もない少年が、過去に起きた巨大災害を回避し、恋した少女を救うという構造は、上述したセカイ系そのものだ。しかし重要なのは、本作が徹底してポジティヴな物語として構築されているという点だ。そのことは、過去の新海誠作品と比較してみると分かりやすい。
彼の代表作である「ほしのこえ」は、地球外生命体の脅威にさらされた世界の中で、調査隊メンバーとして宇宙に向かう少女と、地上に取り残された少年の関係を中核に据えたものだ。彼らは携帯電話のメールでやり取りをするが、互いの距離が離れるに連れ、メールの往復にかかる時間も開いていく。そして物語は、彼らがそれぞれ異なった時間を生きたまま終わってしまう。また、「秒速5センチメートル」においては、主人公の男性が小学校の頃に恋した相手を忘れられないまま成長し、互いに違う場所で違う時間を生きてきたことを意識しつつ、街の踏切で初恋の相手と思われる女性とすれ違った際にも、声をかけることはできなかった。

出典:http://amzn.asia/dgkipFl
このように考えると、「男女二人の時間と距離のズレ」というモチーフが、「ほしのこえ」、「秒速5センチメートル」、「君の名は。」の3作に共通していることが分かる。けれど、前者の2作と「君の名は。」では、その先にある結末が決定的に異なっている。「ほしのこえ」と「秒速5センチメートル」はそれぞれの恋が報われないまま、儚げな雰囲気と共に話が終わるという「不能性」(=主人公が自分の望みを達成できない)を抱えた作品である。
ところが「君の名は。」では、瀧と三葉の働きによって彗星の被害は回避され、二人は現代において再会する。彼らはお互いの名前も、当時何が起きたかも覚えていないが、顔を見た瞬間に走り出し、そうして階段ですれ違った後、顔を見つめ合い、「君の名は」と言葉を発する。
ここに「不能性」というモチーフは存在せず、主人公たちの思いははっきりと結実している。言うならば「君の名は。」は、セカイ系の形式を引き受けつつも、「後ろ向きな内面」にこだわらず、「不能性」をひっくり返すような希望に満ちた結末を提示した作品なのだ。
3. 「シン・ゴジラ」における「未成熟との決別」
では、「シン・ゴジラ」の場合はどうか。端的に言えば、この作品の主人公は「日本の官僚制」であり、特定の人物ではない。内閣官房副長官を務める矢口蘭堂が最も目立つ人物ではあるが、作中における彼の内面やパーソナリティに関する描写は非常に少ない。本作のポイントはあくまで、唐突にゴジラという未曽有の大災害が訪れた時に、日本の官僚機構というシステムそのものがどう機能するのか/しないのかを描いていることにあるのだ。
同時にこれは、庵野秀明の代表作であり、セカイ系の元祖とも言われる「新世紀エヴァンゲリオン」の変形バージョンと考えられる。「エヴァ」は謎の地球外生命体である使徒に対し、14歳の少年少女が人造人間エヴァンゲリオンに乗り込んで、特務機関ネルフの命令下で戦闘を繰り返す作品だった。エヴァンゲリオンには14歳の子どもしか乗ることができないため、子どもたちはまさしく人類にとっての希望となる。しかし、「シン・ゴジラ」の世界に子どもたちはいない。超常的な力を持った人造人間に頼るのではなく、突然現れた災厄に対し、現実の政治機構が優秀さも愚鈍さも見せながら真っ直ぐに立ち向かっていく。いわばこれは、子どもたちとエヴァンゲリオンを排除して、システムとしてのネルフだけにスポットを当てたような作品なのだ。
「シン・ゴジラ」では、目の前の脅威に対し迅速な解決方法を提示する必要があるため、「後ろ向きな内面」の描写など行っている余裕はない。子どもたちを物語から切り離し、徹底してスピーディーに組織の動きを描写し続けた点に、「未成熟」との決別という監督の意志を見て取るのは自然なことだろう。
4. 不感症からの回復――「リップヴァンウィンクルの花嫁」
最後に「リップ」についてだが、これは「後ろ向きな内面」を抱えた主人公が、この世界を肯定できるようになるまでの過程を描いた作品である。主人公である皆川七海はコミュニケーション能力が低く内向的で、教師としての仕事も上手くこなせなければ、SNSで出会い結婚した男性に理不尽な離縁を告げられても言い返すことのできない人物だ。そんな彼女は、なんでも屋としてトリックスター的に動き回る安室行舛の紹介によって屋敷のメイドの仕事を紹介され、そこに住みこんでいた破天荒な女性・里中真白と心の交流を深めていくことで、徐々に生を肯定的に捉えられるようになっていく。
岩井俊二は様々なタイプの作品を撮ってきた監督だが、その中には少なからず、セカイ系的な「後ろ向きな内面」に重心を置いた作品が存在する。たとえば「PiCNiC」では精神病院を抜け出し、世界の終わりを見るために塀の上をどこまでも歩いていこうとする人々が描かれた。また、代表作のひとつである「リリイ・シュシュのすべて」は、いじめを受けている主人公がリリイ・シュシュという歌手の存在に救いを求めつつ、憧れていた少女が暴行される現場でも何もできずにいる無力感をさらけ出す作品だった。主人公はラストシーンで、リリイ・シュシュについてネット上で熱心に語り合ってきた人物が、いじめの主犯格の少年だと知り、彼を刺殺してしまう。そこに救いはない。
「PiCNiC」は世界の終わりを目指す人々を、「リリイ・シュシュのすべて」は特定の歌手を過度に神格化して自身のすべてを委ねる少年を描いた。終末戦争のようなモチーフはないものの、物語の中へ常に、人物たちの現実から遠く離れたものを置く手法は、セカイ系的な構造と強く結びついている。
ところが「リップ」は、神や世界の果てを注視せず、わたしたちの生きる日常に潜む幸福を取り出そうとする。トリックスターとして動く安室が悪人にも見えるが故に、観客は不穏な展開を想像しもするが、最終的に七海はこの現実の中で力強く生きていくことになる。世界にはあまりにも幸せが多すぎて、それをまともに見ていたらありがたさのあまりに壊れてしまうと語った真白の言葉に、この映画の核がある。「リップヴァンウィンクルの花嫁」は、あたりに溢れている幸福に気づけなかった「不感症」の人間が、真に心を許せる相手との触れ合いによって正常な感性を取り戻していく物語なのだ。
5. 震災による変化を受けて

新海誠、庵野秀明、岩井俊二はいずれも様々なタイプの作品を作ってきた監督だが、少なからず「後ろ向きな内面」に重点を置いてきた彼らが、2016年に一斉にそれを解除するような映画を発表したことの衝撃は大きい。
だが、彼らのこうした変化はなぜ生じたのか。その変化を2011年に起きた東日本大震災に求めるのは自然なことである。実際、新海と岩井はインタビューで震災を意識したことを明確に語っているし(※註2) 、庵野に関しても彼自身の言葉ではないが、「シン・ゴジラ」のプロデューサーを務めた市川南は、制作当初に3.11を経験した日本にゴジラが来た場合を考えていたと述べている(※註3)。
セカイ系とは、本来ならば手の届かない遥か彼方にあるものを、わたしたちの日常に直接引き寄せようとするような想像力だ。しかし2016年現在、わたしたちの生きる世界は、常に不穏な空気に満ちている。わたしたちは毎日のように、地震やテロに関するニュースを見聞きし、ゆるやかに世界が壊れていくような感覚にとらわれてしまう。
そうした状況においては、彼方にある超越的なものに対してナイーヴになるよりも、人間が人間として前向きに生きる姿を描く方が、作品のメッセージを率直に伝えられることは間違いない。「後ろ向きな内面」は、わざわざそれを強調せずとも、すでにわたしたちの日常に覆いかぶさっているものなのだ。
そうした日常に潜む不安の描き方において、2016年にはもうひとつ興味深い映画が存在する。クラウドファンディングで映画部門の国内史上最高額となる3622万4000円を集め、SNS上でも称賛のコメントが相次いだ「この世界の片隅に」である。
6. 日常という「戦争」――「この世界の片隅に」
片渕須直が監督した「この世界の片隅に」は第2次世界大戦中の広島を舞台に、絵を得意とする少女・すずの暮らしを描いた作品だ。広島市で暮らしていたすずは、呉市に住む北條周作の元へ嫁ぎ、彼の家族と共に新しい生活を始める。そしてこの作品の肝は、この日常の描き方にある。戦争映画であり、物資の不足や空襲といったつらい現実があるにもかかわらず、本作で描かれる日常はどこかユーモラスなものとなっている。言うなればそれは、どれだけ悲惨な出来事があろうと、その深刻さと並行してわたしたちは当たり前の暮らしをこなさなければいけないという事実を強調するものだ。そうした感性は、震災のことを意識しながらも個人的な生活空間を守らなければならないという、3.11以降の日本の状況にも通じている。
だが、時間が経つに連れ、そうした緩やかな日常を維持することはどんどん難しくなっていく。空襲後の時限爆弾によって、すずは自身の右手と、姪である幼子・晴美の命を同時に失ってしまう。そうした悲劇を経た上で、物語は終戦の日を迎える。けれど、ラジオから玉音放送が流れた後、すずが表したのは安堵ではなく強い怒りだった。すずは軍人として戦地に赴いていたわけではなく、あくまでも配給に頼りながら暮らしていただけの一般人である。それでも、悲惨な状況に置かれながら、できる限り普通に、みんなが笑えるように暮らせるよう努めることが、彼女にとっての「戦争」であり正義だったのだ。そうだからこそ、彼女にとっての敗戦とは生命の危機からの解放ではなく、自身の正義を踏みにじるものに他ならなかった。悔しさと怒りで地面に突っ伏し涙を流しながらも、物語の最後で、すずはこの世界の片隅に自分を見つけてくれた夫への感謝を述べながら、戦災孤児の少女を連れ帰り、普通の暮らしに戻っていく。
ここで注目したいのは、現実に起きた戦争を題材としていながら、本作がこれまで述べてきたセカイ系の変化とも結びついているという点である。冒頭で記したように、セカイ系の作品群の多くは、平凡な主人公が突如世界の危機と対峙するような、いわば強引な英雄譚とも呼べる構造を持つ。しかし、災厄が訪れた際、後々まで語り継がれるような英雄の物語と並行して、英雄にならず生きている人々の暮らしが常に存在する。そしてその暮らしとは、決して怠惰や無力を意味するわけではなく、目の前にある「普通」を懸命に守るための「戦争」に他ならない。言い換えれば「この世界の片隅に」は、世界の果てとは距離をとりながら、英雄譚として描かれることのない日常を守る「戦争」を描いた、セカイ系の裏面のような作品なのである。
「君の名は。」は「不能性からの脱出」を、「シン・ゴジラ」は「未成熟との決別」を、「リップヴァンウィンクルの花嫁」は「不感症からの回復」をそれぞれ描くことで、震災後の世界における前向きな生の意志を示した。それを補完するようにして「この世界の片隅に」は、ともすれば歴史の陰に埋もれてしまいそうな淡々とした日常を維持することを「戦争」化し、そこに正義を見出した。
「後ろ向きな内面」を描くセカイ系が悪いという単純な話ではない。巨大なもの、手の届かない彼方にあるものに対するわたしたちの想像力は、いつの時代も存在する。ただ、彼方のものと日常との距離が一定ではない以上、東日本大震災という巨大な災厄の経験によって、日常と巨大なものとの位置関係が変わった状況で、作家たちが想像力の変遷を見せたことは注目されるべき事実だ。
4つの作品を繋ぐ糸を探ることで、わたしたちは2016年の日本とそこにおける想像力の在り方について、新たな視点を得ることができる。前を向くことでしか人はもはや生きていけないとでも言うかのような、原始的なたくましさを備えた4作が高く評価されたことに、わたしたち自身の精神面での変化を見て取ることはそう奇妙な話ではないだろう。
〈了〉
【筆者プロフィール】坂上秋成(さかがみ しゅうせい) 1984年生。小説家、文芸批評家、ミニコミ誌『BLACK PAST』、『ビジュアルノベルの星霜圏』責任編集。 代表作に『夜を聴く者』『惜日のアリス』(河出書房新社)、「 『朝日新聞』、『産経新聞』、『共同通信』、『ユリイカ』、『 【過去のインタビュー記事】 |
【註1】
セカイ系に関して、構造や形式以外の点から定義を試みることは難しい。だからこそ多くの批評家は、「個人的な出来事が、中間領域としての社会を挟みこむことなく、世界の命運を左右する事象に直結してしまう」ことを最小限の定義としてきた。しかし筆者の考えでは、まさにこの定義が困難な部分、音楽や演出や台詞回しが生み出す独特の雰囲気があってこそ、わざわざセカイ系という言葉を使う意味がある。雰囲気について語れば、それはどうしても主観的な部分が強くなってしまうが、ここではテンプレート化できない空気の問題を論じることに意味を見出したいと思う。 (原文に戻る)
【註2】
『リップヴァンウィンクルの花嫁』岩井俊二監督インタビュー 残酷で美しい現代のフェアリーテイルはいかにして生まれたのか。
『君の名は。』新海誠インタビュー後編 震災以降の物語/『シン・ゴジラ』との共時性?
【註3】
東宝はなぜ『#シン・ゴジラ』を庵野秀明氏に託したか~東宝 取締役映画調整部長・市川南氏インタビュー~
初出:P+D MAGAZINE(2017/01/16)

