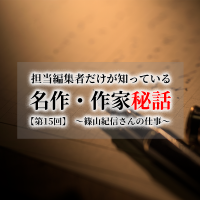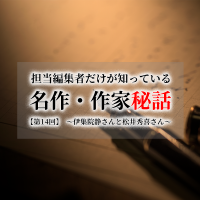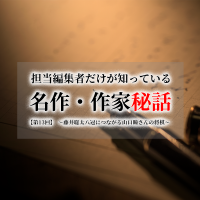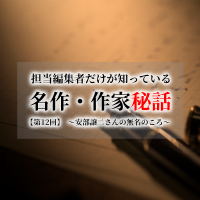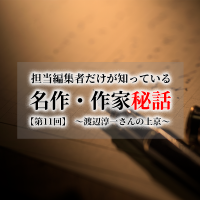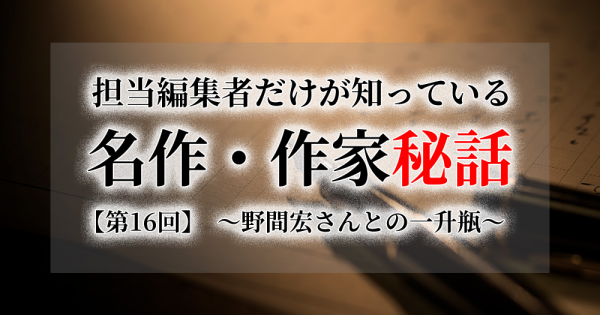連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第16話 野間宏さんとの一升瓶
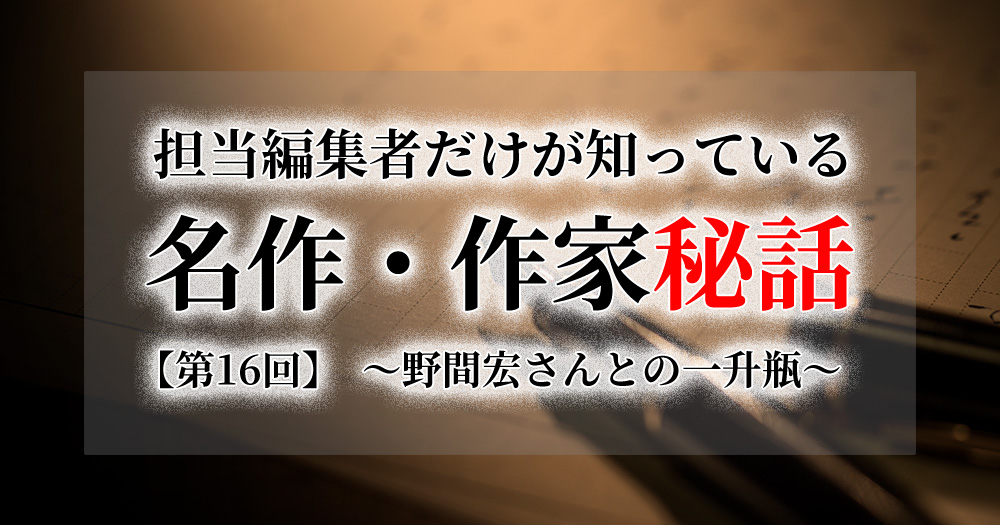
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第16回目です。戦後文学の旗手、野間宏さん。代表作『暗い絵』で鮮烈な印象を世に打ち出し、『真空地帯』で戦争・軍隊の異様さを描き、全体小説『青年の環』で人間の悪の極限を描き尽くしました。その後未完の名作『生々死々』を亡くなるまで書き続けたことでも知られていますが、その人物像はユニークだったといいます。担当編集者がリアルなエピソードを語ります。
野間宏さんとの一升瓶
袴田事件の再審が行われているが、冤罪という言葉を聞くと、私は、反射的に、作家の野間宏さんのことを思い出す。
私は、1969年だったと思うが、駆け出しの編集者として、「小説現代」のグラビア欄を担当していて、作家の野間宏さんに撮影のお願いをしたことがある。野間さんはいわゆる「戦後派」と言われる作家のひとりで、日本の純文学を代表する作家である。私は、野間さんの作品では、学生時代に、ブリューゲルの作品をテーマにした『暗い絵』と、陰湿な陸軍内務班の実態を描いた『真空地帯』だけしか読んでいなかった。
その野間さんが、文芸雑誌「新日本文学」が続けていた「日本文学学校」の校長に就任したばかりで、その仕事ぶりをグラビア写真に撮らせてもらったのだ。はじめて電話をした野間さんは、低い声で一句一句考えながら、ゆっくりとグラビアの趣旨を尋ねた。そして、「宣伝のためになることですから、引き受けましょう」と言ってくれた。
私が配属されていた「小説現代」は、小説には挿絵がついている読物雑誌だったので、その編集者が、純文学の中心的作家だった野間宏さんに電話をすることはとても緊張を強いられる時代だった。
当時、「小説現代」編集部と、純文学雑誌の極北と言われた「群像」編集部は、同じフロアにいた。編集部にそれぞれの個室があるのではなくて、隣合って配置されて、間に置かれた低い書棚がパーティションの役目をしていた。立ち上がれば、互いの編集部が見渡せた。
そんな近いところにいながら、互いに交流はなかった。私の大学の何期か上の先輩が、「群像」編集部に籍を置いていたのだが、言葉を交わすことはなかったと言えば、当時の小説雑誌と純文学雑誌の間が、どんなモノだったか、お分かりいただけると思う。そのくらい、当時の純文学の世界と読物雑誌の世界の間には広くて深い溝があったのである。
野間さんが、グラビア撮影を引き受けてくれるかどうか、心許ない気持ちでダイアルを回した。ちなみに、そのころは、もちろん、携帯電話はなかった。電話と言えば、今はほとんど見ることのない、ずんぐりとした黒い受話器だった。野間さんの家に電話をかけるためにダイアルを回した指が震えていたことを覚えている。通話が終わって、置いた受話器が汗で濡れていて湯気を立てているように見えた。
野間さんのグラビア撮影は、東中野にあった日本文学学校の校舎で、野間さんが書物を手にして講義をしているシーンを撮ったと覚えている。野間さんは授業中だったこともあり、私たちは話すことはほとんどなかった。
そのグラビア写真と一緒に掲載する、ネームと呼んでいた写真説明の原稿をいただきに本郷の自宅にうかがった。思えば、いわゆる純文学作家の自宅にうかがうのははじめてのことだった。私は、通されようとした応接室のもの凄さに文字通り腰を抜かしかけた。8畳くらいの広い応接室には、本という本が溢れかえり、それがあらゆる場所に乱雑に、と言っても野間さんにとっては整理された形なのだろう、積まれていて、応接室を埋め尽くしていたのである。
少しでも積んである本に触れたりしたら、それこそ雪崩のように本が崩れ落ち、私は本の山の下に生き埋めになるかもしれない。その部屋の、あまりの有り様に身動きできなくなった私は、応接に入ることもできずにその場で硬直していた。
丸いテーブルの向こう側の椅子に腰をおろしていた野間さんは、そんなことに意に介する風もなく悠然と、「その辺の本を動かして、座る場所を作ってください」と言った。言われるままに、恐る恐る本を何冊か動かして場所を確保した私は、驚きで抜けかかった腰をそっと下ろした。私は、撮影のお礼を言ってから、原稿を受け取り、本の山を崩さないように注意しながら立ち上がった。
そのとき、野間さんは、不意に「土のね、質が違うんですよ」と言った。それは私に向けて発した言葉でなく、ずっと考えていたことが、思わず口に出た言葉のように思えた。
「はあ?」
怪訝な顔をした私に、野間さんは、もう一度、
「土の質が違うんです」
と、繰り返して、さようならと手を上げた。たぶん、半分は心ここにあらずだったのかもしれない。
私ももう一度頭を下げて、家を出た。道を歩きながら、ああ、土の質が違うというのは、狭山事件のことだなと思いついた。
狭山事件とは、1963年5月1日、狭山市で女子高生が自転車で下校途中に行方不明になり、5月4日に遺体となって発見された事件である。
野間さんは、犯人として逮捕された石川一雄さんが被差別部落出身であることや、起訴が自白を元にしていること、別件逮捕という手法が使われたこと、また証拠として出されたモノに化学的に不審なものがあるなどを理由に、ずっと「狭山裁判」を批判していたのである。
そのとき、野間さんが気にしていたのは、事件のあと見つかった、遺体を埋めるときに使ったと言われるスコップについていた土が、遺体を埋めた地面の土と化学的に違っているということだった。
このあと、野間さんは、狭山裁判に対する批判を、雑誌「世界」に、1975年2月号から1991年の4月号まで、実に16年の長きにわたり書き継ぐのである。この労作は、1997年に全3巻、合わせて1964ページの堂々たる形で、『完本 狭山裁判』として、藤原書店から刊行されている。
私は、野間さんとは、このときの、たった一度だけしか接点がなかったことになる。ところが、私は、1974年に「小説現代」編集部から「群像」編集部に異動することになった。いくらか事情が違ってきていたとは思うが、まだ純文学の壁は残っていた。異動して間もないころ、以前から「群像」編集部にいた同僚が、「この異動を快く思っていない作家たちがまだいるから、心した方がいいですよ」と忠告してくれたものだ。
私が、「群像」に異動した時期は、野間さんは1971年に8000枚に及ぶ大長篇小説『青年の環』を完結していて、先に書いたように、狭山裁判の批判の連載をはじめる時期にあたっていた。「群像」編集部には、すでに野間さんと一緒に仕事をしてきた担当編集者がいたので、異動してきた私が担当することにはならなかった。
担当することにはならなかったが、私は、それまで入り浸っていた新宿のゴールデン街から、区役所通りを挟んだところにある文壇バーにも顔を出すようにしていた。ちなみに、そのころの、いわゆる文壇人が出入りする飲み屋やバーには、ぼんやりとではあるが、純文学系と読み物雑誌系と分かれていて、新宿の西口にある「茉莉花」とか「未来」とかは、主に純文学系のバーの代表みたいに言われていた。
そんなバーで、井上光晴さんや埴谷雄高さんのような純文学系の作家たちや編集者たちの顔をよく見た。その中に野間さんの顔もあった。「文壇三大音声」と言われたように井上光晴さんは大きな声で話していたが、埴谷雄高さんも、野間さんも静かな声で話していた。ちなみに、三大音声のあとのふたりは、丸谷才一さんと開高健さんと言われていた。
私が小さなバーに入って行くと、止まり木に大きな肩をすくめるように座っていた野間さんはなんとも言えないいい笑顔になって、横に席を作ってくれ、しばらくすると、
「『小茶』に行きましょう」
と、誘ってくれた。
そこからすぐのところにある「小茶」という飲み屋は、歌舞伎町三番街にあった店だ。「おばちゃん」と呼ばれる人が一人で切り盛りして、一階は二坪ちょっと、カウンターには五人しか座れないような小さな飲み屋だった。狭くて急な階段を上がると、二階は二畳だったか三畳だったか、畳の部屋になっていて、野間さんとはいつも、ここで胡座をかいて向かい合った。

「小茶」には田中小実昌さんや中上健次さんなどがよく顔を見せていた。野間さんと行くと、「おばちゃん」が、一升瓶と大きな丼に入った煮〆を渡してくれて、それを持って2階に上がった。
一升瓶から自分勝手にコップに注いで飲むのがここの流儀で、料金はあとで自己申告して払った覚えがある。明け方の5時までやっているので、腹が空いてくると、野間さんも私も大きな握り飯をこしらえてもらって、それを頬張った。
野間さんは、「父親が長生きしたから、我が家は長生きの家系らしい。僕も長生きする」と言い、「小説を書いている時は、飲んで精神を高揚させないといけないです」と言いながら、一升瓶から酒を注いでは飲んでいた。
コップ酒の肴は、「小茶」の名物の煮〆のほかは、これから書こうとしている作品だった。
「今度ね、『群像』ではじめようと思っている『生々死々』だけどね……」
『生々死々』は1978年の新年号からはじまっている。『生々死々』は、主に現代医学が人間の手に負えないくらい発達して病院が異常な空間になってしまうということと、自然破壊が進んで、我々が住んでいるこの地球を我が手で死滅させてしまうというふたつのテーマが絡む大きな構想の小説だった。そして、その手法は、評論、随筆、歌舞伎、落語などの古典芸能、洒落や地口、医学的用語、科学用語などが縦横に引用され、今までの野間さんが実践してきた「全体小説」の概念をも突き破るような野心作になりそうだった。
「それでね、ゴルフ場に行ってみたいんです」
野間さんはそう言った。
「ゴルフ場ですか?」
「うん。ゴルフ場は、自然を破壊しているし、なにか、悪い相談事がなされるのに、いい場所だという感じがするんだけれど、僕はゴルフをやったこともないし、ゴルフ場に入ったこともないんです」
会社が懇意にしているゴルフ場を野間さんと見学することになった。プレイもしない、言ってみれば、通りいっぺんの取材だったが、ゴルフ場でのことはもうすでに野間さんの頭の中で、しっかりと組み立てられていたのだろうと思う。ただ、その雰囲気を確かめればよかったのだろう。
ゴルフのことは、『生々死々』のはじめの方にとてもうまく書かれていて、ゴルフを一回もしたことのない野間さんの書きっぷりに、私は舌を巻いた。
千葉明星ゴルフ場が山崩れで、修復工事場は全滅、下方の農地は冠水し、五、六十ヘクタールから百ヘクタールが被害を受けたと、いう報告が、うちのオフィスから、ありましたよ
と、高級料亭で、東山長社長と木場一春社長とが密談をするシーンがある。
二人の社長は九億近い金をかけてこのゴルフ場を立て直し、別の観光会社からせしめてやろうしているのだ。
このシーンは、無計画な山野や自然を壊しての乱開発、化学肥料の見境のない濫用、土地を巡っての争いなど、それ以降、日本を今のような状況に落とし込むひとつの原因が巧みに潜ませてあると思う。
「小茶」の二階で、コップ酒を飲みながら、野間さんは「タガメ」という昆虫のことを口にするようになった。タガメは、もう絶滅種に近い水棲の昆虫である。広辞苑によると、体長約65ミリメートル。体は扁平で、前肢は捕獲肢となる。成虫・幼虫とも水生昆虫などを捕らえて体液を吸う。小魚をも捕らえ、養魚上有害。成虫は夜、水中から出て飛び、灯火にも集まるとある。
余談になるが、大江健三郎さんの長篇小説『取り替え子』にも、「田亀」という表記で、旧式のヘッドフォーンのかたちが、「森のなかの子供であった時分、谷川で獲った田亀のようだった」と出てくる。
前肢はかまきりのように体に比して大きく、鉤のようになっていて、獲物を捕獲しやすくなっている。見るからに、おそろしげな印象の昆虫なのである。
野間さんはこのタガメについて、こうした知識を繰り返し話しながら、小説の構想を練っていたのだろう、雑誌「作品」の1980年11月号に、「タガメ男」という短篇小説を書いた。短篇小説「タガメ男」は、非常に恐ろしい印象を残す作品である。
タガメ男とあだ名される大男・石見東太郎は、山間の奥地に公共事業費によって国道がつくられるという話をいち早く聞き込み、土地を手に入れ、その上、土地の人々から新事業を起こすための土地を提供させ、金の融通をさせて、そこの人々を支配してもいた。ひどく悪辣で、因業な男なのである。
その石見は、山の中を歩いているとき、雷に打たれて、仮死の状態になる。石見に支配されている男たちは、この際、こいつを殺してしまおうと図る。その時、
当の死体の辺りが、俄かにせり上がったかと思うと、歪んだ口が血を好んで吸うタガメの口のように、白く開いて、呻き声が放たれ、やがて、その土の上に投げ出されていた両手が、胸の上に舞い上がり、胸元を、はげしく掻きむしり始めたのである
と書かれているように、「タガメ男」は蘇生する。これから、どんな暗示的な結末が待つのか、読者にとっても、ひどく恐ろしい瞬間である。
一方、『生々死々』は1984年4月号で未完のまま休載になる。野間さんには、このころから、この大作を続ける体力は残されていなかったのではないだろうか。新宿にも出て来ることはなくなった。そして、1991年1月に75歳で亡くなる。野間さんの期待に反して、決して長寿とは言えない死だった。
『生々死々』は、野間さんが亡くなったあと、1991年12月に、未完のまま刊行された。未完のままでも優に八百ページを超す巨篇である。野間さんが『生々死々』で予言したように、日本では、政治も官僚システムも経済も医学も高齢化も少子化も問題は何一つ解決されないままだし、国民の先行きは酷いものになっている。そして、世界では、大きなふたつの戦争が戦われているし、地球も異常な天候が続き、破滅に向かっているようだ。
この状況を見たら、野間さんはなんと言うだろうかと思う。
「小茶」のおばちゃんも1996年に亡くなり、その偲ぶ会は新宿の映画館で行われ、400人を超す参会者があった。享年82だそうだ。
【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。