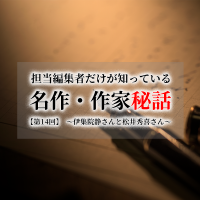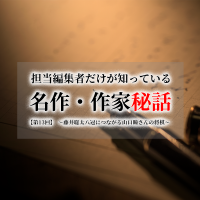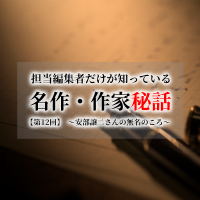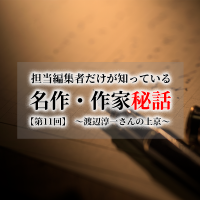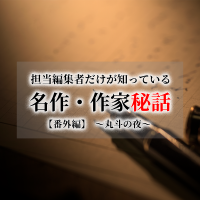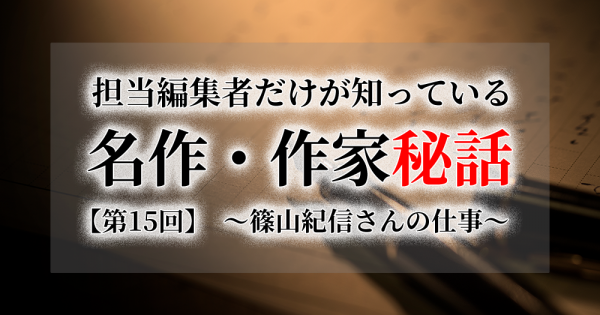連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第15話 篠山紀信さんの仕事
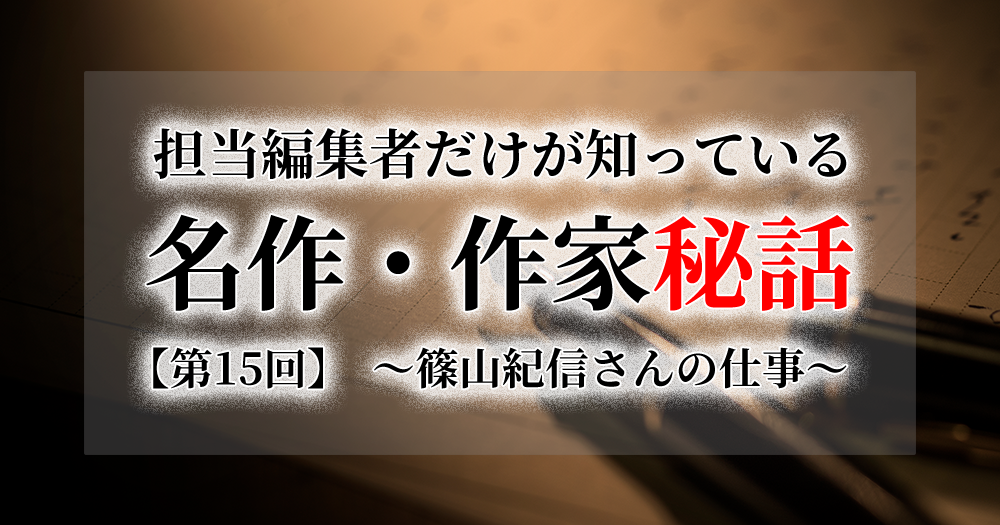
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第15回目です。年始早々に飛び込んできた、写真家・篠山紀信さんの訃報。その溢れ出る才能で唯一無二の存在だった篠山さんが切り拓いた写真の世界は、いつも斬新で芸術的なものでした。そんな篠山紀信さんとの貴重なエピソードを、担当編集者が語ります。
篠山紀信さんの仕事
篠山紀信さんが亡くなった。享年83。
1969年から1970年にかけてのことだと記憶しているが、私が属していた「小説現代」編集部の新しい編集長になった大村彦次郎さんは、新しい小説雑誌の方向を探っていたが、巻頭のカラー・グラビアのページに、もう流行カメラマンになっていた、篠山紀信さんを起用することを考えた。
まさに時代の先端を歩き、時代と取っ組み合う篠山さんのセンスを小説雑誌に取り入れようとしたのだ。

1970年の新年号から、「ヌード・ドキュメント」と題した篠山さんの、カラー・グラビアの連載を始めることになった。
「ドキュメント」と題したのは、スタジオで撮るヌード写真とは一味違って、さまざまな現場を背景にして、それも、有名な女優やタレントをモデルにするのではなく、無名でもその現場に相応しいモデルを使って撮影しようとする企画だった。
この企画に、篠山さんは大いに乗り気になって、引き受けてくれた。
そうなると次に、ドキュメントにふさわしい現場を決めなくてはならない。
そうして、最初の現場に選ばれたのが、ストリップ劇場だった。実際のストリップ劇場のステージはもちろん、楽屋などをバックにして、女性のヌード撮影を行いたい。シリーズの1回目としては、面白い構図になりそうだった。
この頃、ストリップ劇場にコントの演技で出演していて、この業界に顔の利く作家の田中小実昌さんの口利きで、相模原にある劇場で撮影を許可してもらった。
私も、田中小実昌さんの担当になってすぐ、この相模原の劇場に出演している小実昌さんのステージを観に行ったことはあった。細かいことは忘れてしまったが、シャイな小実昌さんが、照れ臭そうな雰囲気のまま、踊り子相手にじゃれるようなことをしていた。担当者としては、とても笑えたものではなく、実際、7割くらい入っていた観客も笑う人はいなかったと思う。
第1回目ということもあって、撮影の日には、私など、若手の編集者が駆り出された。篠山さんと撮影機材を運ぶために車を用意して、それに同乗して劇場まで行った記憶がある。モデルが誰だったか、記憶にないのが不思議なのだが、とにかく、その時、劇場に出演していた踊り子のナンバーワンだったのではなかったろうか。
こうして撮影された作品が「小説現代」の新年号を飾った。力作だった。
それだけに、もうひとつ懸念しなければならないことがあった。それは、過激とも言える巻頭のヌード写真が、「小説現代」に寄稿している著者や関係している社内の部署の人たちに、どんな影響を与えるかということだった。
当時は、「御前会議」などと、私がふざけた呼び方で呼んでいた「年間計画会議」というものがあった。大きな講堂で、社長以下役員が臨席し、関係の各部署から部員が出席して、編集長が今年一年の計画を述べる会議だった。それからしばらくして、「年間計画会議」は、もっと小さな会議室で、実質的なものに変わったが、それは駆け出しの私にも、大仰な会議に思えたものだ。
この会議をすんなりと通ることが、試金石になるだろう。
小説雑誌の巻頭を、さまざまな話題を呼んでいる篠山紀信さんのヌード写真で飾るのだ。
同じ号に小説を書いている作家たちが、どんな反応をするだろう? こんな激しいヌード写真が巻頭にあるような雑誌に、自分の作品を掲載したくないという作家が多く出やしないだろうか?
それがもうひとつの大きな懸念だった。「年間計画会議」では、そんな疑問が呈せられるかもしれない。
会議を前に、新編集長は、非常にクレバーな作戦を採った。つまり、自分の同世代の編集者たちに、これは実験的で、ここから大きく小説雑誌が変わり、新しい有力な作家がどんどん発掘できるという援護射撃をしてくれる人たちの発言を、根回しして、用意したのである。
こうして、ともかくも、「御前会議」は無事通過した。そうして、ここから「小説現代」は、さまざまな実験的企画を発表することができるようになるのである。篠山さんの「ヌード・ドキュメント」は「小説現代」の、新しい方向を決めるひとつのキーとなったと言える。そして、篠山さんにとっては、文芸という新しいメディアに作品を発表するきっかけともなったと思う。
のちに、小学館の青年誌「GORO」に、ヌード写真のシリーズを掲載して、「激写」なんていう言葉を流行らせたりする一方、「小説新潮」誌上で、女性の顔を撮って発表したり、作家の吉行淳之介さんとヴェニスに旅行をして、新機軸の紀行本を出版したり、更に坂東玉三郎を撮ったりして歌舞伎の世界にまで行動の範囲を広げるのである。
私は2回目と3回目の「ヌード・ドキュメント」の撮影に付き合った。
2回目の撮影場所には、渋谷駅の近く、並木橋にあった、寺山修司主宰の「天井桟敷」が選ばれた。
その時、この地下のステージで、「刺青ショウ」が行われていた。若者の背中いっぱいに、実際に刺青が彫られるのを見せるショウだった。
私も、刺青を実際に入れるのを見るのは初めてのことだった。刺青用の針の先に群青や緋色の絵の具をつけて、肌を裂くようにして色を埋め込んでいくのである。肌を裂く音が、サクッサクッと狭いステージに響いた。身体中が熱を持つので、一気に彫ることはできなくて、少しずつ進めていくのである。
これからしばらくして、新宿のバーで飲んでいたら、目の前のバーテンダーの青年が、この時のモデルだということがわかった。青年は「夏の暑い時でも、Tシャツが着られなくてねえ」とぼやいていた。
それはともかく、こうして描き上がった背中いっぱいの刺青をバックに、「天井桟敷」の劇団員である市川魔胡さんのヌードが撮影された。まだ彫り立ててで、彫物から血が滲んでいるのが刺激的だった。私が、モデルになった人の名前を覚えているのは、このあと、彼女が、女優として話題になっていったからだ。
市川さんは、のちに大島渚さんの監督作品である「愛のコリーダ」で、松田英子と芸名を変えて、阿部定を演じた。この作品の中で、相手役の藤竜也と本当にセックスをしたということでも話題になった。日本ではこうしたシーンを上映することは許されていなかったので、そのシーンは上演されることはなかったが、法的に解禁となっていたフランスでは公開され、日本からはるばる鑑賞に行った御仁もあったと聞く。
3回目の「ヌード・ドキュメント」は、渋谷桜丘にあった、東由多加の劇団「東京キッドブラザース」の劇場と屋上を背景に撮影された。70年代は、こうしたアンダーグラウンドの劇団が覇を競うように跋扈していて、こうして書いていても、とても懐かしい感じがする。
この時のモデルもどういう人だったのか、記憶にない。
劇場のあるビルの屋上の金網のフェンスに数人の劇団員に取り付いてもらい、それをバックにヌード写真を撮った。彼らは浴衣を着流していて、それが風に吹かれて、淫らであやしげな雰囲気を醸していた。その金網に取り付いている劇団員の一人が、後日、私が作家として付き合った永倉万治さんだということは、本人が明かすまでは気が付かなかった。
余談になるが、永倉さんは、幅広くいろいろな分野のことが書ける才能のある作家で、1989年に出版した『アニバーサリー・ソング』(立風書房刊)で、講談社エッセイ賞を受賞し、これから大いに書こうという矢先に、脳出血のため倒れてしまった。幸い命は取りとめて、リハビリに励み、その闘病のことを書いた作品も遺している。2000年に、脳出血を再発して他界されたのは残念でならない。
私は小説雑誌の編集者として、自分の担当を持ち、仕事をはじめたばかりなので、そのことに専念したいと思って、3回おつき合いをしたところで、「ヌード・ドキュメント」の仕事から離れることにした。3回の現場で篠山さんは、主役であり、時代の感性を汲み取りつつ、シャッターを押して行ったはずだが、私が感じたのは、そんなことではなかった。篠山さんが撮影をしていくと、やはり主役は、現場であり、モデルたちになっていき、篠山さんというカメラマンの身体から発せられるオーラみたいなものが、全体を大きく包んだような塩梅だった。
のちに篠山さんは、作家の吉行淳之介さんとヴェニスに、5泊6日の旅に行って、『ヴェニス 光と影』という、紀行文を吉行さんが書き、篠山さんが撮った写真と一体化した本を出す。その巻末の吉行さんとの対談で、篠山さんは、「写真というのは、現実を拾い上げて、それを受けとめていくものだと思う」と発言しているが、それが篠山さんの写真撮影の基本にあることだと思う。
『ヴェニス 光と影』の中で、篠山さんが撮った、街の佇まい、煉瓦のひとつひとつ、蝋燭の炎、凝った造りの家具、波の煌めき、ゴンドラ、葬儀の棺、棺の上に置かれた花束、子供たちの肌……どの写真をとっても、官能の揺らぎとかすかに漂う死の予感みたいなものが立ち上がってくるのである。
このあと、私は、篠山さんとは、銀座の文壇バー「まり花」でよく会った。このころ、篠山さんは、「シノラマ」と称して、複数のカメラを結合して、同時にシャッターをきって撮影する技法を面白がって、凝っていた。横長の写真ができるわけだが、「まり花」で撮った一枚の横長の写真がある。その写真には、篠山さんが、吉行淳之介さんや沢木耕太郎さん、居合わせた編集者たちや店のママと一緒に並んで座って写っている。
ここでも、天真爛漫な笑顔で写っている篠山さんだが、「実は、ぼくも写真嫌いなんです」と言っている。「無防備で撮られるのが照れ臭くて、いやなんです」
【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。