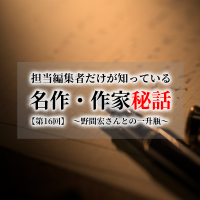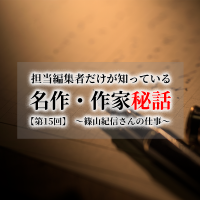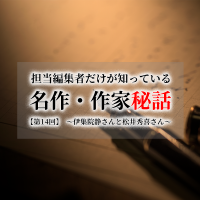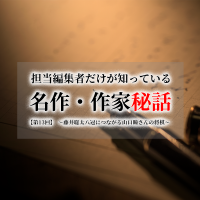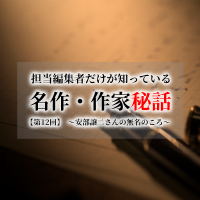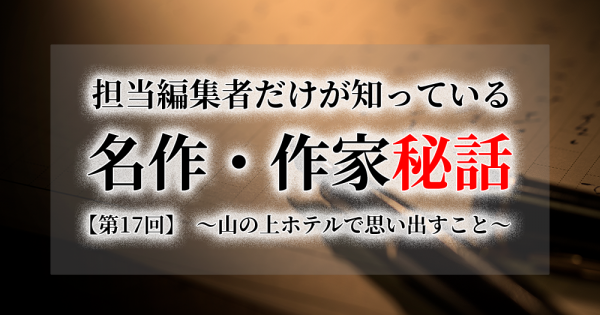連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第17話 山の上ホテルで思い出すこと
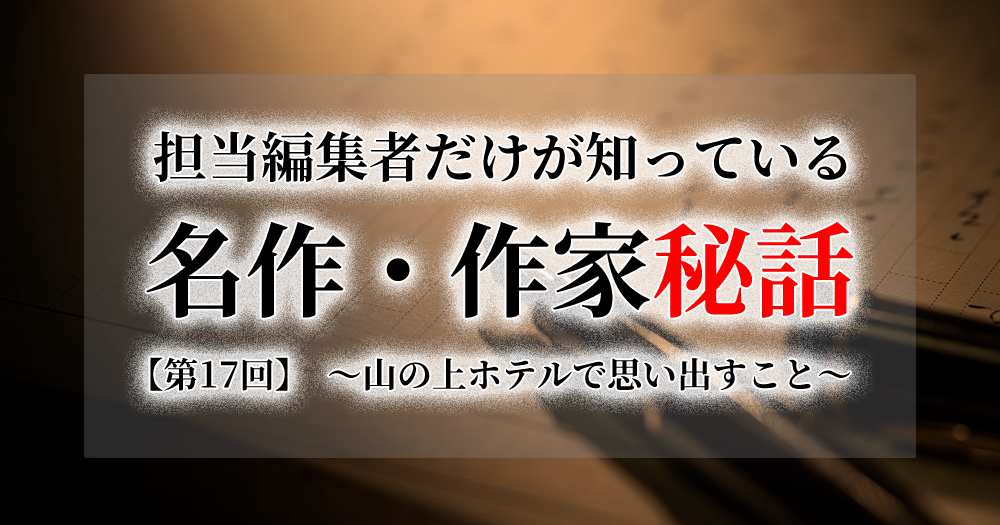
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第17回目です。先日惜しまれつつ休業となった「山の上ホテル」。多くの作家が愛した場所で、ここだけの思い出が語られるに相応しいホテルでした。山の上ホテルにまつわるエピソードは担当編集者にとっても印象的なことばかり。作家たちの個性がにじみ出る話の数々をお届けします。
山の上ホテルで思い出すこと
70年の歴史を持つ東京・山の上ホテルが、2024年2月13日をもって休業した。お茶の水や神保町の近くにあって、多くの作家たちに愛されたホテルだった。
私にとっても思い出深いホテルだったので、休業の直前、2月10日に、作家・山口瞳さんの息子の正介さんと一緒にお別れに行った。久し振りの山の上ホテルは最後の土曜日とあって、混雑していた。
ロビーのテーブルの位置などが、昔とは違っていたような気がしたが、空いていた椅子に座っていたら、ここで会った作家たちのことが思い出されてきた。
はじめに山の上ホテルを意識したのは、文芸誌の表四(裏表紙)に、「小説家に愛されれているホテル」というような広告を見たときだったと思う。
漏れ聞くところによると、畳が敷いてある和室を好む小説家のために、そうした部屋があって、その部屋のベランダには小さな庭園があるということだった。たしかに、畳の部屋だと、参考の本や資料などを身体の周囲に置いておけるので、使い勝手がいい。
私が知る限り、和室を好む作家は、開高健さんと野坂昭如さんだったが、彼らが和室を好んだわけは、眠くなったら、そのままゴロリと横になれるということだったから、ナニ、資料云々は眉唾物かも知れない。
これはエッセイに書かれている話だが、吉行淳之介さんから聞いた話でもある。吉行さんがこのホテルにこもって、原稿を書くうち難渋して筆が進まなくなった。この際、原稿から離れ、バーで一杯飲って気晴らしをした方がいいと判断した。1階のバー「ノンノン」に入ると、カウンターに座っている先客の後ろ姿が目に入った。尖った肩に見覚えがあった。高見順さんだ。高見さんも難渋しているんだと思った吉行さんは声をかけた。振り返った高見さんは、吉行さんを見て、「なんだ、君もか」と言って、なんとも言えない笑いを浮かべたそうだ。
バー「ノンノン」は右側にあるロビーの壁の奥に設けられたカウンターだけのバーだった。このバーで、私は、昆虫学者・ファーブルの「ファーブル昆虫記」(全10巻)の完訳を成し遂げたフランス文学者の奥村大三郎さんと、歓談数刻を楽しんだことがある。たしか文京区が創設した「文の京文芸賞」の手伝いをすることを仰せつかった私が、選考委員を務める奥村さんと打ち合わせする要があってのことだったと思う。

いかにもオーセンティックな雰囲気のバーで、奥村さんはマティー二だったか、ジントニックだったか、いやあるいはジンリッキーだったか、とにかくジンベースのカクテルを軽やかに何杯も空けて行って、それでいて少しも崩れたところを見せなかった。
バー「ノンノン」の佇まいは、ニューヨークのマンハッタンにあるザ・アルゴンキン・ホテル・タイムズスクエアの「Blue Bar Restaurant and Lounge」を思い出させた。
私は、実は山の上ホテルはこのアルゴンキン・ホテルのコンセプトを真似して作られたのではないかと思っている。西44丁目にある、このホテルは1902年に創業しているので、120年以上も経っているから、山の上ホテルの大先輩に当たる。そしてラウンジの席には、フィッツジェラルドやヘンリー・ミラーなどの作家たちが席を占め、彼らを打ち合わせをする編集者やジャーナリストたちで賑わっていたという。
私も、ニューヨークに行った折、「Blue Bar」に行ってみなくちゃと、そう、「ニューヨーカー」の編集者を気取ったことがある。
なるほど、「Blue Bar」はホテル・オークラの「オーキッドバー」か、山の上ホテルの「ノンノン」と雰囲気は同じだ。「Blue Bar」の中を忙しなく動き回って、注文をとりにきた人たちは皆、白髪のおじさんたちだったのが印象的だった。
伊集院静さんの著作が並んでいるライティング・デスクがあるロビーには、いまは、結婚式の打ち合わせなどに使っているらしいデスクが置いてあった。その辺りにあったソファに座っていた、詩人の谷川俊太郎さんの姿が目に浮かんだ。『ぺ』というショートショート集を再文庫化を許可してもらうために谷川さんと待ち合わせたのである。快諾してくれた谷川さんは、色彩豊かなTシャツ姿で、それがとても谷川さんにあっていて、粋に見えた。
私が座っているロビーの椅子の正面に、バー「ノンノン」があったのだが、その左に通路があって、奥がパーティの会場になっていた。私がお別れに行った日に、結婚の披露宴を予約しているカップルがあって、そこには入ることができなかったが、その会場にもいくつか思い出がある。
読売巨人軍の監督だった川上哲治さんの息子さんの貴光(よしてる)さんの、『“ムッシュ”になった男――パリの1500日』の出版記念会で祝辞を述べた。貴光さんは、作家の海老沢泰久さんの友人で、海老沢さんは貴光さんに文章のコツを、貴光さんは海老沢さんにゴルフのコツを教えるという仲で、私もそのゴルフ会を一緒した縁だった。
これはおめでたい会だったが、あとの会はおめでたいとは言い難い。
ひとつは、山口瞳さんの3回忌の会で、たしか1997年のことだったと思う。この会は、私が司会を仰せつかった。この会の時だったと記憶しているが、山の上ホテルの創業社長・吉田俊男氏ゆかりのロースト・ビーフが焼かれてサーブされた記憶がある。この時、司会をそつなくこなしたという謝礼のつもりだったと思うが、山口家から、山口瞳さんが愛した丸善の仕立て券付きのハリス・ツイードの生地を頂戴した。流石に丸善が仕立てただけあって、26年経った今でも、好んで着用に及んでいる。
2013年には常盤新平さんが亡くなって、お別れの会が、やはりこの会場であった。常盤さんとは、直木賞を受賞した『遠いアメリカ』を「小説現代」に連載してもらう以前からの付き合いだった。常盤さんには、『山の上ホテル物語』という著書もあるから、会場としてはうってつけだった。
この会を切り盛りしたのは、故人になってしまった評論家の坪内祐三さんで、私が会場に着くなり、肩を抱いて、「挨拶を頼むよ」と言った。突然のことで、なにを話せばいいのか、常盤さんの原稿が遅いこととか、山口瞳さんとのこととかなど頭に浮かぶが、気もそぞろで、中々まとまってくれない。腕時計を見るともなく目をやると、この腕時計は常盤さんが直木賞を受賞した記念に、アメリカに旅行した際、ティファニーで私のために買ってくれたもので、スーツを着なくてはならない改まった時に嵌めていることに気がついた。
白い文字盤に数字だけが書いてある実にシンプルなデザインの腕時計で、見やすい上に、どんなスーツにも合わせられる、常盤さんの趣味のよさが表れた物なのだ。突然の指名だったが、この腕時計のことを話題にして、挨拶は済ませることができた。挨拶を済ませると、腕時計を見せてくれと寄ってきた人が何人もいた。
池波正太郎さんも、よく山の上ホテルを使った。特に直木賞の候補作品をまとめて読むのに便利だったようだ。
『池波正太郎の銀座日記』(新潮文庫)の「六十七歳の誕生日なり」とある1990年の項に、「一昨日から山の上ホテルへ来ている。」と書かれ、その少しあとに、
「午後、講談社の宮田君が、ゲラを持ってホテルへ来る。コーヒー・パーラーへ行き、共にオムレツにトースト、コーヒーをのむ」とある。コーヒー・パーラーは、山の上ホテルの地下1階にあった。
この時、池波さんは、
「いつもここのはうまいんだけど、入っていかないんだよ」
と、フォークを持ったまま、苦い顔をした。そして、きのこの入ったオムレツを口に運んで、無理矢理飲み下していた。
「二度も三度も、部屋の中で転倒する。足がすべるのだ」とも書かれているが、この席では、
「腰の辺りにアザができるんだよ」
と沈んだ調子で言われた。
池波さんは、時を経ずして、この年、5月3日に亡くなった。
こうしてみると、山の上ホテルの思い出は、私にとっては楽しいことばかりなのではないのである。
【執筆者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。