連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第34話 井上ひさしさんの遅筆
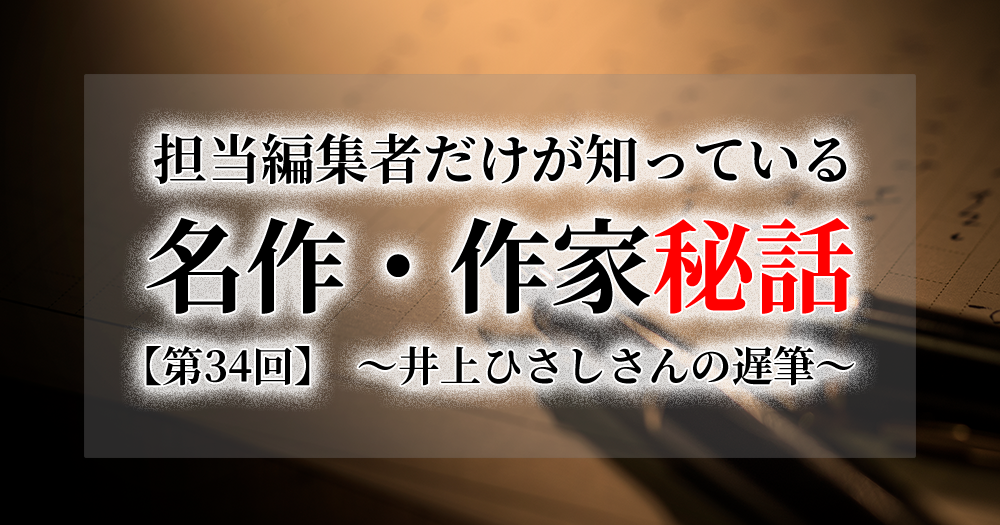
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第34回目です。今回は、数多くの作品を遺し、劇作家として、ほか多様な活動で知られる、「井上ひさし」さんとのやりとりについて。愉快で痛快な作風が多くの人々に愛された井上さん。名言、遅筆、さまざまな個性を持って作品を世に送り出してきました。担当編集者だけが知るエピソードに注目です。
文芸編集者を長く務めていると、いろいろな方からサイン本をいただくことになる。
私は、版権の売買を担当したことがあるおかげで、英語で書かれたサイン本を何冊か持っている。
珍しいのは、Puff, the Magic Dragon という絵本だろうか。
むかし、PP&Mと呼ばれて、日本でも親しまれたヴォーカル・トリオのピーター・ポール&マリーのひとり、ピーター・ヤーロウさんがサインしてくれたものだ。この絵本の著者のひとりでもあるピーターさんは、
Puff, the Magic Dragon lived by the sea
and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalee
と有名なリズムを口ずさみながらサインしてくれて、私のうしろに並んでいたアメリカ人のご婦人たちをうらやましがらせたものだ。
For Mr Miyata,
With cheers
And good
Luck!
Pete Hamill
Tokyo March 3 ’84
とサインしてあるのは、1982年9月25日に河出書房新社から刊行された、ピート・ハミルさんの『ニューヨーク・スケッチブック』(高見浩訳)だ。サインしてもらった本は初版本ではなくて、刊行の翌年の5刷である。
とてもよく売れたので、河出書房新社が、この年に、宣伝を兼ねたサイン会を催した。私は、この本をとても面白く読んだことと、さらに、井上ひさしさんや山口瞳さんたち日本の作家にも大いなる影響を与えたことを、ピート・ハミルさんに伝えたのである。
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第34話 井上ひさしさんの遅筆 写真](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/09/secret-story_34_image.png)
ピート・ハミルさんは、『ニューヨーク・スケッチブック』の長いまえがきの中で、
ここにおさめた各編はいずれも新聞のために書いたものだが、言葉の厳密な意味での報道記事ではない。あくまでも物語であり、しかも短編である。といって、ふつう〝短編小説〟という言葉から理解される、首尾結構の整った作品でもない。そうした短編小説の傑作に数えられるのは、たとえば、アントン・チェーホフ、ショーン・オフェイロン、アーウィン・ショウ、V・S・プリシェット、ジョン・オハラ、それにシャーウッド・アンダースンらの作品だろう。
と書いて、短篇小説の名手たちの名前を列挙している。
それから、1ページほどあとに、ハミルさんは、自分と同じように、新聞を仕事の場にしたことのある作家たちとして、モーパッサン、アルベルト・モラヴィア、アーネスト・ヘミングウェイたちの名を挙げている。
そうして、ハミルさんは、次のように書いている。
ここにおさめた物語は、一九六〇年代に入って書きはじめた。その頃私は、恐るべき頻度で起る戦争、暴動、暗殺、デモの取材にあたっていた。デモ隊の中にいて催涙ガスを浴びたこともあれば、密林で兵士たちと一緒にいて機関銃の斉射を受けたこともあった。
この3行は、日本の作家の開高健さんが書いた文だと言っても決しておかしくない。
生前の開高さんが、『ニューヨーク・スケッチブック』を絶賛していたことを私は覚えている。行動する作家であり、ジャーナリズム文学を確立したと言われる開高さんが、『ニューヨーク・スケッチブック』を読んで、我が意を得たりと思ったのだろう。
私が仄聞したところによると、『ニューヨーク・スケッチブック』は、ハミルさんが長い間かかって新聞に寄稿した数多くの短篇の中から厳選した作品集なのだそうで、だから、一篇一篇が研ぎ澄まされた文章の好短篇になっている訳だ。
『ニューヨーク・スケッチブック』から刺激を受けた日本の作家のひとりに、山口瞳さんがいる。
山口さんは、『ニューヨーク・スケッチブック』を読んで、短篇小説の魅力を再確認したのだろう。週刊新潮の見開きページに、「男性自身」と題して、毎週エッセイとして書き続けてきた山口さんが、突然、1983年7月7日号に、エッセイではなく、『巴里祭』という短篇小説を掲載して、それ以降、47篇の短篇小説を書くことになった。
その47篇の短篇小説は、『私本歳時記』という短篇小説集として刊行される。
それからほんのしばらくの間、「男性自身」はまたエッセイに戻るのであるが、1986年1月23日号に、短篇小説『空っ風』を掲載してから、42篇の短篇小説を書くことになる。短篇小説の魅力に取り憑かれたものと思う。この42篇の短篇小説は『梔子の花』と題し、短篇小説集として刊行されている。
さて、井上ひさしさんのことを話す前に、たいへん長く、寄り道をしてしまった。これから、私が経験した井上さんとのことについて話そうと思う。
1983(昭和58)年に、講談社から、文庫版のPR誌である「イン☆ポケット」が創刊される。そのころ、私は、文庫出版部に異動していたので、その雑誌に携わることになる。
「イン☆ポケット」を創刊するにあたって、私は、井上ひさしさんに短篇小説の連作の企画を持ち込んだ。
「ピート・ハミルというアメリカの作家が、ニューヨークに住む人たちのことを書いた『ニューヨーク・スケッチブック』という本を書いているんですが、井上さんになにか、普通に暮らす人たちのことを短篇小説に書いてもらえませんか」
「でもねえ……」
井上さんは、自分の原稿用紙に「遅筆堂」と書くくらい原稿の遅い作家だった。そのせいで、井上さんの仕事は押せ押せになっていたのである。
しかし、私は食い下がった。
「たとえば、むかし野球チームのメンバーだった子供たちが、大人になって、もう一度同じメンバーで、ゲームをやってみる。だけど、ひとりだけ来ないんですね……それはなぜなのか。そんな短篇小説を書いていただきたいんです」
読書家の井上さんは、もちろん、話題になった『ニューヨーク・スケッチブック』を読んでいて、
「短篇連作は面白そうだなあ」
と、返事が返ってきた。
そして、1983年10月号の創刊号に、「浅草橋」の商店街を舞台に、三角定規屋と桐箱屋のふたりの職人の話を書いた『隣り同士』を掲載することができた。
井上さんは、ピート・ハミルの『ニューヨーク・スケッチブック』がニューヨークを舞台にしていることに抗して、「私の東京物語」というテーマで、井上さんに縁のある16の東京の町を舞台に、16篇の短篇小説を書いたのである。
それは次のような町である。タイトルと舞台になった町を書いてみる。
『ナイン』(四谷新道)
『太郎と花子』(小岩)
『新婦側控室』(神楽坂)
『隣り同士』(浅草橋)
『祭まで』(深川たつみ運河)
『女の部屋』(新宿)
『箱』(亀戸)
『傷』(錦糸町)
『記念写真』(柳橋)
『高見の見物』(新宿)
『春休み』(市川)
『新宿まで』(築地〜新宿西口行きのバス)
『会話』(新宿)
『会食』(御徒町)
『足袋』(赤坂)
『握手』(上野)
イン☆ポケット誌上に、井上さんの短篇連作がはじまったのはいいが、実は、編集部員は私ひとりしかいなかった。
「編集会議がモメることがなくていいんだ」
と、私は言ったものだが、ナニ、強がりに過ぎなかった。
とくに、井上さんの原稿は遅くて、ほかのすべてのページは校了を済ませても、井上さんのページだけは、タイトルは出来ていたが、原稿が入っていなくて、文字を組んでもいない状態だった。
私は、井上さんのページだけを残した状態で、当時市川にあった井上さんのお宅で、「居催促」をすることにした。作家のお宅に行って、そのまま原稿ができるまで側で見張っていて、原稿を仕上げてもらうことを「居催促」と言うのである。
私は、夕方過ぎに井上邸について、一晩「居催促」をして、明け方にできあがった原稿に目を通し、おかしな表現などを書き替えてもらった。
そして、原稿を手にした私は、タクシーを呼んで、市川の駅で中央線に乗るか、中央線が動いていないときは、そのままタクシーで、小豆沢にある凸版印刷に駆けつけて、入稿するルーティンを作りあげたのである。
井上さんと、書きあがったばかりの小説を間にしてやり取りをする、この作業はとても楽しく、私にとって勉強にもなった。
16篇の作品の中で、「ナイン」が、私にとって、一番思い出が深く、好きな作品だ。
四谷駅から真っ直ぐ伸びている商店街の新道に住む少年たちが野球のチームを結成し、大会で準優勝した。その「新道少年野球団」のナインのその後の人生を描いた名品であり、この短篇集の標題ともなっている作品である。
ちなみに、準優勝した「新道少年野球団」のメンバーは以下の通りである。
1:英夫(畳屋の息子で、エースだった。のちに、正太郎に八十五万円を騙し取られたのをきっかけに、現在は、畳屋の跡取りとして畳屋を立派に継いでいる)
2:正太郎(洗濯屋の息子で、チームの主将だった。その後、寸借詐欺をしたり、英夫から八十五万円を騙し取ったり、あるいはチーム・メートの常雄の会社の事務員になって、四百万円近くの現金を持ち出し、常雄の奥さんとともに失踪する。常雄は自殺をはかるが未遂に終わり、奥さんもぼろぼろになって戻ってくる。そのことがあって、却って夫婦円満になり、事業もうまく行くようになる。)
3:昭彦(洋品屋の息子で、現在は会社員になり、店をたたんだ金で千葉の方へ引越して暮らしている。)
4:洋一(惣菜屋の息子だったが、店をつがずに、いまはホテルのコックになっている。)
5:忠(ガラス屋の息子で、いまは、コンピューター技師になっている。)
6:光二(文房具屋店の息子だったが、店に来る子供たちのために、中学教師になっている。)
7:常雄(当時は、8番打者。豆腐屋の息子だったが、自動車学校の経営者の娘と結婚して、経営を任されるようになる。主将だった正太郎にひどい目にあわされるが、高慢ちきだった奥さんは、このあと、尽くすようになり、円満の仲になるなど、すべてがいい方向に転がるようになり、常雄は正太郎を憎みながらも、感謝している。)
9:誠(魚屋のせがれだったが、いまは「文化放送」の前で小料理屋を営んでいる。)
上記の算用数字は、野球のポジションを示しているが、まことに不思議なことに、8番のセンターを守っている子のことが書かれていない。「ナイン」と標題しているのに、8人の少年のことしか書かれていないのである。
私は、明け方、井上さんから渡された原稿に目を通して、細かいところを指摘したりしたはずなのだが、センターの子が書かれていないことに気がつかなかった。不注意のそしりをまぬがれないところだ。また、この小説が短篇集として刊行されたときも、校閲部も8番の選手が書かれていないことをスルーしている。
つまり、編集者も校閲部も書かれていることの過ちは指摘するのだが、書かれていないことは指摘を逃してしまいがちなのだ、と言うのは自分勝手過ぎる言い分だろうか。
ただひとり、このことに気がついた人がいる。カバーと表紙の絵とデザインを担当した、画家の安野光雅さんである。
安野さんは、表紙と裏表紙では新道野球団の戦歴を、スコア・ボードにして描いた。そして、彼らが勝ち抜いた相手チームは、「巨仁」「半身」「早計」「カーブ」「全日本」「極悪」「忠日」「法正」「LP」「草実」「トラコン」と、音読すると、どこか聞いたことのあるような、奇妙な名前がつけている。安野さんが大いにアソビ心を発揮したところだ。
そして、カバーの挿画には、着ているユニホームはバラバラだが、クラウンが青、ツバが赤の、お揃いのキャップをかぶった子供たちが9人描かれている。それぞれのユニホーム代わりのシャツにそれぞれの名前が書いてある。小説では、ナインなのに8人しか書いてなくても成り立つが、絵となるとそうはいかない。やはり、9人の子供たちを描く必要がある。
安野さんも、苦心したのだろう、9人の子供たちの一番下の段、つまり帯を巻くと、顔だけは見えるが、それぞれの名前が書いてあるシャツはかくれてしまう場所に、8番目と9番目の選手ふたりがいるのである。
しかも、ほかの子たちは、それぞれの名前が書かれているのに、9番目(本当は書かれていない8番・センター)の少年だけは「中村」という姓が書かれている。小説に書かれていないセンターを守る選手の姓が「中村」となっているが、安野さんは、それをどこから探したのだろう。
実は、この小説の大事な登場人物のひとり、当時のエースで、正太郎から大金を騙し取られたことをきっかけで、本気で畳屋を継ぐことを決意した光二の姓が「中村」なのである。
新道少年野球団が試合をしたのは外濠公園野球場で、それはいまでも、中央線の四ツ谷駅と市ヶ谷駅の間に見ることができる。その球場は、当時、三塁側は日蔭がなくて、暑い西日の下、苦しんでいるエースのために、体を張って日陰を作ってやったのが正太郎であった。そうした細やかな気遣いの主将を中心として、心からつながっていたのが、「新道少年野球団」の少年たちなのであった。
1987年6月に単行本として刊行された「ナイン」だが、私への「為書き」がしてあって、井上ひさしさんの署名のわきに落款が押されている。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第33話 画家・村上豊さんとの付き合い](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/08/secret-story_33_banar_t-e1755494081741.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第32話 林京子さんの短篇連作](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/07/secret-story_32_banar_t-e1752224392463.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第31話 村松友視さんの作家の佇まい連載](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/06/secret-story_31_banar_t-e1749620592694.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第30話 中島らもさんの小説](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/05/secret-story_30_banar_t-e1747214926119.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第29話 桐野夏生さんとEdgar Award](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/04/secret-story_29_banar_t_-e1744880639489.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第34話 井上ひさしさんの遅筆](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/09/secret-story_34_banar-600x315.png)