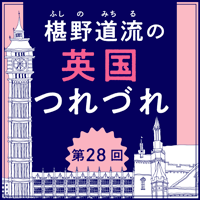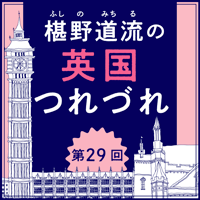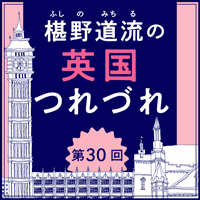椹野道流の英国つれづれ 第31回

◆前髪のある小鳥の話 #1
ほぼ毎週末に私がお邪魔していたリーブ家には、スウェーデンからの留学生、クリスが住んでおり、また、ときおり、リーブ夫妻の子供たちや孫たちが訪ねてくることがありました。
10代、20代の孫たちにとっては、クリス同様、サンデー・ディナーとその後のお茶会は、退屈極まりない、年寄り臭い行事だったようで、彼らは食事の後、すぐにどこかへ行ってしまいます。
クリスも、「週末くらい好きにさせて」と言いたげに、「チャズ、ディナーを楽しんでね!」と軽やかにハイタッチして、私と入れ違いに出かけるのがお決まりでした。
結局、大人たちの集まりに、私がひとりぽつーんと紛れることが多かったのですが、リーブ夫妻の子供たちは、両親が絶えず留学生を受け入れていることもあり、外国人に慣れていました。
私の拙い英語にも我慢強く耳を傾け、優しくフォローしてくれたものです。
いちばん陽気でお喋りだったのは、小説家の三男でした。
日本の美術に興味がある彼に、私が大好きな画家、田中一村を紹介し、イギリスまで持ってきていた大事な画集をプレゼントできたのは、とても嬉しいことでした。
「この画家は、日本のルソーだね! なんて細密で大胆な、素晴らしい絵なんだ。こんな場所が日本にあるのかい? 行ってみたいよ!」
そんな彼のコメントと輝く瞳を、今もハッキリと覚えています。
あの画集、今も持っていてくれるといいなあ。奄美大島にも行けたかな。
今でもたまに、同業の先輩である彼のことを思い出します。
あるときリーブ家を訪ねると、ジャックと、知らないおじさんが庭にいました。
誰だろうと思っていたら、ジーンいわく「うちの長男よ。この前の強風で、庭の温室が壊れてしまったから、修繕に来てくれているの。DIYが得意なのよ」とのこと。
作業があるので、その日はパブ通いはお休み。
ジーンは「たまにはこういうのもいいわね」と言い、珍しく私をキッチンに立たせてくれました。
その日のディナーのメインは、ローストビーフ。
牛もも肉の塊(本当に大きいのです)の表面をナイフでつつきまくり、そこに細長く切ったニンニクを差し込んでいくこと、塩胡椒をよく肉にすり込み、油をつけた手で全体を擦ってから、オーブンに入れること。
ポテトは切って茹でて、いわゆる粉ふきいもの状態にしてから、油をまんべんなくまとわせ、適当なタイミングでオーブンに入れること。ガーリックのみじん切りを散らすことも忘れずに。
そしてジーンは、「これはとっておきよ」と、ヨークシャープディング作りも手伝わせてくれました。
まあるくてこんがり焼けていて、フカシュカッとした不思議な食感のヨークシャープディング。
まるで中身を入れ忘れたシュークリームのようなその不思議な食べ物の作り方は、えっと思うほど簡単で、でも煮えたぎった油に生地を注ぐときだけは怖くて。
「あら、あなたは思いのほかいい助手ね。手際がいいし、余計なことをしないのがいいわ。キッチンは狭いのに、私の通り道を塞がないし。カンがいいのね」
そんなありがたい評価を下したジーンは、それからは気が向いたとき、ジャックをひとりでパブに行かせ、私をキッチンに入れてくれるようになりました。
兵庫県出身。1996年「人買奇談」で講談社の第3回ホワイトハート大賞エンタテインメント小説部門の佳作を受賞。1997年に発売された同作に始まる「奇談」シリーズ(講談社X文庫ホワイトハート)が人気となりロングシリーズに。一方で、法医学教室の監察医としての経験も生かし、「鬼籍通覧」シリーズ(講談社文庫)など監察医もののミステリも発表。ほかに「最後の晩ごはん」「ローウェル骨董店の事件簿」(角川文庫)、「時をかける眼鏡」(集英社オレンジ文庫)各シリーズなど著作多数。