【第162回芥川賞受賞作】古川真人『背高泡立草』はここがスゴイ!

古川真人『背高泡立草』の受賞が決定した第162回(2019年度下半期)芥川賞。その受賞候補となった5作品を、あらすじとともに徹底レビューします!
2020年1月15日に発表された第162回芥川賞。古川真人さんの『背高泡立草』が見事、受賞を果たしました!
今回の受賞候補作は、木村
受賞発表以前、P+D MAGAZINE編集部では、受賞作を予想する恒例企画「勝手に座談会」を今回も開催。1月某日、シナリオライターの
参加メンバー

(写真左から)
トヨキ:P+D MAGAZINE編集部。
詩歌と随筆が好き。特に好きな小説家は絲山秋子、今村夏子。
五百蔵 容:シナリオライター、サッカー分析家。
3度の飯より物語の構造分析が好き。近著に『サムライブルーの勝利と敗北 サッカーロシアW杯日本代表・全試合戦術完全解析』(星海社新書)。
菊池 良:ライター。近著に、歴代の芥川賞全受賞作を読みレビューした『芥川賞ぜんぶ読む』(宝島社)。
目次
木村友祐『幼な子の聖戦』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07Y97FMCX/
【あらすじ】
青森県の小さな村で村議をしている「おれ」は県議に弱みを握られたことで、選挙戦に立候補した同級生への選挙妨害を強いられてしまう。
トヨキ:ますは木村友祐さんの『幼な子の聖戦』からいきましょうか。お二方はどう読まれましたか?
菊池:タイミングから言っても、この作品を読んで映画「ジョーカー」を思い出す人は多いんじゃないでしょうか。“持たざるものの暴発”とも言うべきテーマがいま世界的なコンテンツの兆候として見られるので、時代と非常に共振している作品だと感じました。
五百蔵:そうですね。僕も「ジョーカー」を思い出しましたし、東北弁の使い方や時代性というもののとらえ方、ユーモアのある語り口からは井上ひさしの作品も連想しました。
菊池:フェイクニュースを主人公が作り出してしまっていたりと、現代日本の問題も取り入れられていて。
五百蔵:そういった物語の枠組みそのものがよくできていて非常に面白いとは感じるのですが、そこまで長くない作品ということもあり、文章からプロットが透けて見えてしまうような部分があるのは弱みかなと思います。
菊池:そうですね……。ただ、プロットの完成度の高さはやっぱり感じますよね。いちばん最初にクライマックス的なシーンがくるという映画的な構成も巧みで、読み手を飽きさせないですし。
トヨキ:個人的には、今回の候補作の中で一気読みしたくなる求心力がもっともある作品だと感じました。
五百蔵:やっぱりストーリーが面白いですし、重いテーマに反してディテールがコミカルなのもいいですよね。主人公が選挙妨害のためのデマのゴシップ記事を一気に書き上げて自分の文章に酔っているシーンなんて、もはや趣旨が変わってるじゃないかと笑ってしまいました。
トヨキ:そのデマのためのゴシップ記事を自分で作品と呼んで、”この作品は、ぜひ全文を読んでもらいたかった”と主人公が自画自賛しているところが面白かったですね。
菊池:でも本当に、これだけの社会課題を扱いつつも暗い文章になっていない、というのはすごいですよね。近年、こういったエンタメ的に完成度が高い小説は受賞作には選ばれにくい傾向があるとは思うのですが、やっぱり強い時代性も感じさせる作品なので……。
五百蔵:最近は映画の世界においても、いわゆるアートフィルムとエンターテインメントフィルムの境目がどんどん曖昧になってきていますし、芥川賞と直木賞に関しても同じことが言えるのかなと。ですから、こういったエンタメ性の高い作品も芥川賞の舞台で評価される可能性は大いにあると思います。
古川真人『背高泡立草』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1M63CG/
【あらすじ】
大村奈美は、母の実家・吉川家の納屋の草刈りをするために、母、伯母、従姉妹とともに福岡から長崎の島に向かう。吉村家には「古か家」と「新しい方の家」といういまは空き家になってしまったふたつの家があり、奈美は家族たちからそれらの家にまつわる話を聞くのだった。
トヨキ:続いて古川真人さんの『背高泡立草』です。古川さんはここ数回、芥川賞候補の常連になりつつありますね。今作も、これまでの候補作である『縫わんばならん』、『四時過ぎの船』、『ラッコの家』に続く同じ一族のお話として読めると思います。一貫して“記憶”や“残されたもの”についての物語を、非常に高い筆力で書き続けられていますよね。
菊池:そうですね。今作も、これまで古川さんが書かれてきたテーマを踏襲しつつ、それをさらに一歩進めたような印象を持ちました。
五百蔵:同じテーマを描きつつも、その奥行きをどんどん深めていっていますよね。物語のはじめのほうは一見これまでの作品と同じような構成にも思えますが、読み進めていくと、最初に登場した家族と直接的にはつながりのない人々の話が唐突に始まる。最初は現代日本を舞台にしているのに、満州や江戸時代の話まで出てきますからね。けれど、それぞれのエピソードがぶつ切りになっているようには感じられず、きちんと効果的な意味を持つよう構成されているというのはさすがの筆力だなと思います。
菊池:古い家の奥にぽつんと置かれているひとり用のカヌーとか、ふつうなら見逃してしまうような非常に些細なものにも歴史の厚みがある、ということを説得力を持って書ききっていると思いますし、そういった壮大な物語が“草を刈る”というあまりにも日常的な行為に収斂していくのもすごいですよね。日常の見方が変わるような作品だと思います。
トヨキ:直接は関係のない断片的なエピソード同士をゆるくつなげることによってその土地の記憶を描く、という手法からは、2018年のノーベル文学賞を受賞したオルガ・トカルチュクの『昼の家、夜の家』を連想しました。その作品も、語り手自身のエピソードや近所の噂話、料理のレシピといったさりげない挿話が重なってゆくことでひとつの土地の物語が浮かび上がってくるようになっていて……。『背高泡立草』には『幼な子の聖戦』のような現代性はないけれど、それがかえってこの作品に強度というか、普遍性を与えているんじゃないかと感じます。
五百蔵:それから、最後のシーンでは彼らが刈った草の名前が列挙されますが、その中には日本の地場の雑草もあれば外来種もあるんですよね。家族の物語の間に挟まれた挿話の中に登場する人たちも皆、島の外からやってきたり、外からやってきた人を迎える人たちで。草を刈った張本人たちは最後に島から帰ってゆくわけですが、歴史というものは実際には個人で背負って生きていくことのできない、どこかで刈り取らざるをえないものだということ、でも草(人々の歴史)はそこにあり続ける、ということも示唆していると感じました。
見事な小説だと思うのですが、古川さんの過去の候補作では『四時過ぎの船』が素晴らしかったので、個人的にはどうしてもあの作品と比べてしまうというのもありますね。
トヨキ:『四時過ぎの船』も傑作でしたね。ただ、前回(第161回)の芥川賞を受賞された今村夏子さんも、この座談会では『星の子』で受賞間違いない! と話していたところ『むらさきのスカートの女』でやっと、ということもあったので……(笑)。
五百蔵:たしかに、古川さんもこれまでの候補作がどれもハイレベルなので、今作で受賞してもまったくおかしくないですね。
乗代雄介『最高の任務』
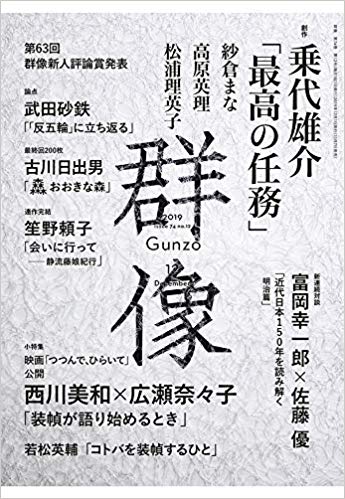
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZLHXWQT/
【あらすじ】
大学の卒業式直後、「私」は行き先も目的も告げられず、母、父、弟に家族旅行に連れ出される。「私」には生前慕っていたゆき江ちゃんという叔母がおり、彼女の薦めで小学生のときから日記をつけ続けていた。「私」は日記の中でも旅行の道中でも、折に触れてゆき江ちゃんのことを思い出す。
菊池:続いて乗代雄介さんの『最高の任務』。これは、個人的には非常に評価を容易にできない作品だなと感じました。2020年を生きている主人公が約半年前に書いた日記を読んでいるんですが、その日記は2年前のできごとを書いており、さらに時折それよりも昔の回想が交じり……と、構造的にはかなり複雑なことをしているんですよね。
五百蔵:そうですね。それを「意識の流れ」のような形で、これはいつのことだろう? そうか2年前か、と読み手に考えさせるような自然な手つきでつなぎ合わせてくれればとてもよかったと思うのですが、“2年前”、“大学入学後”と明記してしまっていることで、方法論的な意識がかえって頭にこびりついてしまって素直に読めなかった印象がありますね。
トヨキ:近い部分で言うと、“あんた、誰?”という日記のお決まりの書き出しに関しても、ある時期からは自然と書くのをやめてしまったと明記されていますが、日記の地の文をこれだけ挿入している以上それは読み手から見ても明白なので、わざわざ注釈のように書かなくてもいいなと……。親切ではあるのですが、そういった部分がダイレクトに書かれていなかったほうがより深みを感じられたのではないかな、と思います。
五百蔵:それから、わざわざ「私」にだけ目的も行き先も知らせずに家族は旅行をするわけですが、基本的に「私」と家族との関係も「私」と叔母さんとの関係もうまくいっているように書かれているので、なぜ旅行をサプライズにしなければいけなかったのかという理由がちょっと弱く感じます。仲のいい家族なのでそういう企みをしてもおかしくなさそう、という感じはもちろんするんですが、それならば最初から「私」に言っても変わらないのではと。
トヨキ:たしかに「私」は途中まで自分と叔母さんのことばかり考えていますし、家族もそんな「私」を心配してはいるけれど、だからといって実はこの家族は分裂していた、というわけではなさそうですもんね。旅行のシーンもごくふつうに、仲良しの家族の微笑ましい旅行だな、と思いながら読めてしまうので……。
菊池:そうですね。この家族ずっとすごく楽しそうですよね(笑)。
五百蔵:楽しそうですし、物語としての題材もすごくいいんですよね。日記を書く、旅行をするという行為を通じて亡くなった最愛の叔母のことを思い出す、という。
トヨキ:旅行の目的は言ってしまえばねじ木を置きにいくというだけのことなんですが、それも絶妙ですよね。互いに慕い合っていた叔母と姪という関係から物語を作ろうとするともっと劇的なラストになってしまいそうなのですが、本当にささやかな家族の旅行に終結していくというのが堂々としているなと。個人的にはとても好きな作品ではあって、なによりもキャラクターのチャーミングさと、家族のなにげないエピソードのリアリティや愛らしさが抜群だと思うんです。
五百蔵:旅行中にずっとねじ木をこっそり持たされている弟のキャラクターとか、とても可愛らしいですよね(笑)。
トヨキ:蟹炒飯の蟹がほしいと言われたら「私」に譲ってあげるっていう、すごく素直な子なんですよね(笑)。乗代さんは芥川賞候補作入りが初めての方なので、他の作品ももっと読んでみたいと感じさせられました。
千葉雅也『デッドライン』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07VDMP7T4/
【あらすじ】
「僕」は大学院で哲学を学びながら、院生の同級生たちやゲイ仲間たちと日々を過ごしていた。しかし「僕」には修士論文のデッドラインが迫っており……。
トヨキ:続いて千葉雅也さんの『デッドライン』。哲学者で批評家としての人気も高い千葉さんが初めて書かれた小説ということで、読書家の間でもすでに大きな話題作となっている作品ですが、個人的には非常に面白く読みました。主人公の「僕」が、葛藤し悩み抜いて過ごした大学院生活を追体験しているようで……。私は千葉さんご自身の哲学の専門に関しては詳しくないのですが、やっぱり「僕」が作中で取り組んでいる分野と重なっているんでしょうか?
五百蔵:まさに千葉さんが哲学で取り組まれてきたことをフィクション化した作品だと思いますね。非常に端的に言うと、90年代のポストモダンというのは相対主義──なにをしても「人それぞれだよね」に回収されてしまい、阻害されてしまう人たちのことも「人それぞれだから仕方ないよね」というロジックで容認されかねないという問題点があったのですが、それを乗り越えるために実在・非実在の枠を取り払い、すべてを「実在する」と考えることで資本主義や相対主義に対抗しようとする、つまり資本主義が「いない」ことにしてしまった人たちもたしかに「実在する」ことにする、というひとつの思想の流れが存在しています。
けれど千葉さんは、その考えはあまりに思弁的(※経験によらず、思考や論理にのみ基づいているさま)であって、実際には阻害されてしまう人たちのことを救えないのではないか、阻害は思弁から離れたところで肉体的に存在しているのではないか、ということを問うているわけです。さらに、自他や世界/非世界をはっきりと分けるような思弁性ではなく、「私」と「あなた」はたしかに別物ではあるのだけれど、別物のままで単なる「私」でも「あなた」でもないものになれるのではないか、それを探求しようという。
トヨキ:お聞きしていると、『デッドライン』に書かれていた、ヒトのままでも潜在的なレベルにおいて動物になることができるとか、他者と“ある近さにおいて秘密を共有する”ということは、まさにその千葉さんの考えと重なるように思えますね。
五百蔵:そうですね。作中で「僕」も研究対象にしているフランスの哲学者・ドゥルーズには、「リゾーム」という概念があって、これは私と他者の関係などを「体系」的に捉えるのではなく、もっと錯綜的で相互関連的なものと捉えようというものです。同じスープの中に浮かんでいるけれど、いつでも互いに溶け出すように関連し合えるAとB、みたいな感じで。その考え方でいうと生と死、始まりと終わりも互いに閉じたものではなく、連続しているものになります。だから作中におけるデッドラインという言葉も非常に象徴的で、デッドラインが来たからと言ってそれは単なる終わりではない。
トヨキ:なるほど、たしかに「僕」は修論のデッドラインを守ることができずに一度は院生としての生活も終わりそうになるけれど、彼は彼なりの新しいやり方で人生を立て直してまた始めていきますもんね。新しい連続性を最後に生み出している。
五百蔵:そうですね。そういう意味では非常に千葉さんが書いたということに意味のある内容だと感じます。ただ、一方で今回は『背高泡立草』や最後にお話しする『音に聞く』といった文章技法的なレベルが非常に高い作品が目立つので、文章技巧や文体に対する意識の行き届いていなさがネックにはなるのかなと……。
トヨキ:個人的に『デッドライン』でとてもよいなと感じたのは、最後のほう、「僕」視点の描写に突如ほかの人の視点が混ざり合うような箇所が現れるところです。“僕は歌いたくなる。その歌が、別の歌に交換されている。”、“どうでもよくなるのは僕ではなく、君だ。”……と、詩のように文体がねじれて自他の境界がなくなってゆく。この部分は読んでいて気持ちよかったですし、一人称の小説としてもとても効果的に機能していると感じました。
五百蔵:その箇所はまさにドゥルーズのリゾームという概念を物語化しているところだと思いますね。
菊池:作者自身のアイデンティティを緻密に描くというのはいわば芥川賞作品の王道です。それが哲学的な思想と結びついていくのも面白い。僕も『デッドライン』は受賞候補としてはかなり強いと思います。が、やはり今回は他の作品のレベルも高いので、この作品がどう捉えられるか難しいですね……。
高尾長良『音に聞く』
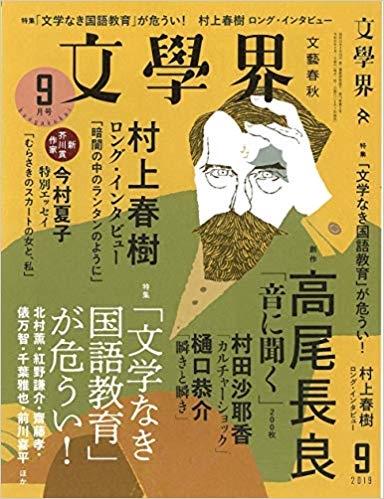
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07VHY7DFG/
【あらすじ】
作曲に天賦の才を見せる妹・真名と言語表現を模索する姉・有智子。ふたりは15年ぶりに音楽理論の大家でもある父に会うため、音楽の都・ウィーンを訪れる。
トヨキ:最後は高尾長良さんの『音に聞く』です。
五百蔵:ひとつひとつの言葉の磨かれ方や視覚的な認知を読み手に自然に呼び起こす力、ディティールの説得力など、純粋に文芸的なクオリティで言えばこの作品は圧倒的な出来だと思います。
菊池:そうですね。僕もそう感じました。ただ個人的に驚いたのが、物語の最初だけに登場する「わたし」なる人物が、有智子の三人称の手記という形をとって以降、最後まで出てこなかったことですね。おそらくですが、三人称という形をとっていながらも、有智子が書いたものだと強調しておく必要があり、ただの三人称小説として読まれる可能性を排除しておきたかった。それが作品の主題や文体のために必要だったのだとは思うのですが。しかし、一読して「わたし」は誰だったのか、驚きました。
トヨキ:私は最初に「わたし」が出てくる必然性をあまり感じられなかったので、誰だったの……? という気持ちで最後まで読んでしまいました。それから、もちろんこの作品の流麗な文章は素晴らしいと思う一方で、言葉にばかりこだわる有智子の視点で過剰なほど装飾的な文体で描かれるウィーンの様子などは、とても空虚なものに感じてしまって。
五百蔵:なるほど。僕は逆に、意味のない言葉のほぼない小説だと思いながら読みました。有智子は最初から“言葉”に拘泥しているようでいて、よくよく読んでみると彼女が執着しているのはむしろ“声”なんですよね。
トヨキ:あっ、それはたしかにそうですね。
五百蔵:最後に有智子が言葉を交わすアルヴァという人物は、彼女がウィーンという土地で一瞬でも信頼することができた、唯一足場にすることができた存在として描かれているんですが、たぶんそのきっかけもアルヴァの“声”にあって。有智子は声を通して、真名は自分の音楽を通して “言葉か音か”という問いかけに自分たちなりの均衡点を見出したというような着地をしていて、この結末も美しいなと感じました。
ただ、この作品は美学的な問題をいかに描ききるかということ一点に集中している小説なので、社会性や歴史性が希薄であることは弱みかもしれませんね。これだけ書き込むのであれば、ウィーンという土地の歴史性に対してもっと複合的な視点を織り込むこともできると思うので。
トヨキ:そうですね、土地の歴史にほぼ触れていないのはすこし気になります。私はこの衒学的な雰囲気を受け入れるまでに少し時間がかかってしまったのと、最後の“言葉か音か”という問いへの折り合いのつけ方がちょっと月並みなのかな、と感じたのは正直なところです。
五百蔵:ただ、シンプルな結論をそれだけのことではないように見せ、読み手をいかに説得するかというのは文学の重要な力だと思うのですが、僕は有智子がウィーンで見聞きしてきたものの描写には強い説得力を感じましたね。本当にクラシックな文学性で勝負している作品だと思います。
菊池:非常に限られた世界の話で、現代性や社会性もあまり感じられないですよね。直球ですよね。
五百蔵:しかも描いている対象が天才なので、共感のできない世界ですし。個人的には、『音に聞く』からはイギリスの作家、ロレンス・ダレルの『アレクサンドリア四重奏』という作品を連想しました。ロレンス・ダレルという作家も衒学的な美しい文体で非常に個人的に思えることを書く人なんですが、『アレクサンドリア四重奏』は4部作から成る長編小説で、同じ土地を舞台にしたできごとを4つの別個の見方から描いた作品です。
ひとつひとつはなにげない話なんですが、全4巻がつながるとアレクサンドリアという都市、中東と西欧の関係などの歴史性やプロットの妙が劇的に浮かび上がってくるという。高尾さんはきっとロレンス・ダレルが好きなんじゃないかなと思いながら『音に聞く』を読みましたし、そういったしかけの小説を彼女にもいつか書いてほしいなと思いましたね。
総評

トヨキ:今回もありがとうございました。ずばりお二方は、第162回の芥川賞はどの作品が受賞すると思いますか?
菊池:僕は今回の候補作の中でもっとも好きなのは『音に聞く』なのですが、いま議論になったような衒学性や美学的な雰囲気がそこまで歓迎されない可能性もあるなと思います。受賞は古川さんの『背高泡立草』じゃないかな、と思いますね。
五百蔵:僕も同じく、文芸としての純粋なクオリティでは『音に聞く』が抜きん出ていて、このすごい才能を採ってほしいなとは感じるのですが、実際に受賞するのは『背高泡立草』かなと。
トヨキ:なるほど……! 個人的には『背高泡立草』も好きなのですが『デッドライン』がとにかく面白かったので推したいですし、やはり作者の千葉さんがこういった物語を書くことに強い説得力を感じるので、受賞するんじゃないかと予想します。
今回も編集部での意見が分かれる形になりました。1月15日の芥川賞の受賞作発表が、いまから待ちきれません!
初出:P+D MAGAZINE(2020/01/12)

