【著者インタビュー】姫野カオルコ『青春とは、』/恥の光景を呼びこむ昭和50年代の青春記!
南武線沿線のシェアハウスに住み、ジムのインストラクターをしている女性が、あることをきっかけに昔のことを鮮やかに思い出す――胸キュンな恋愛話も部活の熱い話も出てこない、ごくフツウな大人のための青春小説。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
昭和50年代、共学で、公立で――。鮮やかに甦る高校時代の思い出〝あの頃〟を生きた大人たちに贈る共感度MAXのフツウな青春小説
『青春とは、』
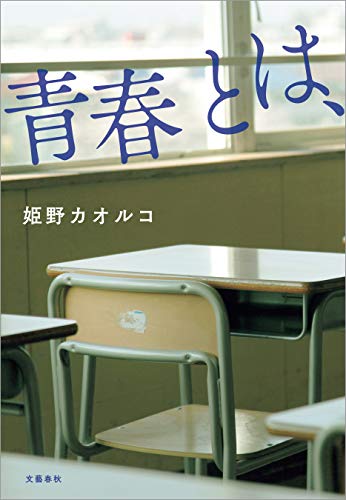
文藝春秋
1500円+税
装丁/大久保明子
姫野カオルコ

●ひめの・かおるこ 1958年滋賀県生まれ。2014年『昭和の犬』で直木賞、19年には東大生強制猥褻事件に着想した『彼女は頭が悪いから』で柴田錬三郎賞を受賞し、話題に。「前作が読者をいやな気持ちにさせる小説だったので、今回はいやな気持ちにさせない小説にしようと」。『受難』『ツ、イ、ラ、ク』『ハルカ・エイティ』『リアル・シンデレラ』『謎の毒親』の他、故郷に因んだエッセイ『忍びの滋賀〜いつも京都の日陰で』等。趣味のジャズダンスのためにストレッチは欠かさない。164.8㌢、AB型。
青春時代だけが恥ずかしいわけでなく人間は死ぬまで恥ずかしく生きていく
起点は令和2年3月現在、南武線沿線のシェアハウスに住み、ジムのインストラクターを昨年からしている、〈マドンナと同年生まれ〉の私こと〈
袋の中には〈本が一冊、名簿が一冊〉。特に本の方は〈犬井くん〉に借りたままになっているのが格好悪く、その恥ずかしさがさらなる恥の光景を呼びこむような、昭和50年代の青春記である。
*
「きっかけは確か『週刊ポスト』です。河合奈保子は作詞作曲もでき、学生時代から楽器に親しんでいたみたいな記事があって、私は『ん? 学生時代は大学からで、中高は
〈自分、クラコにせえ〉〈今日から暗子て呼んだる〉と一方的な呼称変更を告げる犬井くんは、明子の一学年上の柔道部員。その親友で女子にモテモテのサッカー部員〈中条秀樹〉のことも明子は君付けで呼び、上下左右全てに緩い校風を漢字四文字にすれば〈暢緩儘遊〉だ。
そんな虎高で巻き起こる様々な珍騒動が、本書では令和の明子の視点で綴られ、第1章「秋吉久美子の車、愛と革命の本」から終章まで、昭和50年前後の風俗が盛り込まれるのも楽しい。
〈クミコ、きみを乗せるのだから〉のCMで話題の日産車を、シベリア帰りの父は役所との往復だけに使い、定時に帰るなり高級料理本を広げ、〈
そんな彼女を「暗子」と無邪気に呼べる犬井くんは、京都
「もちろん、今だから言語化できるんですけどね。
私は10歳前後の主人公が自分の気持ちを理路整然と話す小説や映画を観る度に、『あり得ない』って思うんですよ。語彙がないばかりに闇の中にいて、ひたすら『違う』と思ったり、でも何が違うか説明できなくて、もどかしかったりするのが、子供の時代だと思うので。
特に私は今話題の超記憶症候群を疑うほど昔の記憶が鮮明で、時折押し潰されそうになるんです。それが苦しくて書くと、気持ち悪さが多少和らぐ。残像が消えてくれる。言葉をあてがい、理論的になることで、スッと楽になれるんです」
誰も欠けていない時間はとても尊い
家族という〈
「私自身、家より学校の方が圧倒的に居心地がよかったんですね。特に〈堀越学園芸能コース〉と綽名された3年7組は、同調圧力が皆無なクラスだったので。
滋賀県民の溜り場、平和堂のフードコートにもよく制服のまま行きましたし、わが家では〈「学校」という名分〉が最も有効で万能な
でも、大谷先生が
〈青春とはすべて、かっこ悪いの上塗り〉とあるが、その共有者には既に亡くなった人も少なくなく、〈同窓会にも来なくていい〉〈でも、いてくれ。いなくならないでくれ〉と明子は思う。
「この中に青春のどっちがセイでシュンか、よく混乱する同級生が出てきますが、私は彼女の訃報を聞いた時、永遠だと思っていた足元がスポンと抜けた感じがしたんですよ。誰も欠けてない時間の尊さを思い知った。しかも最近はセコかったり図々しかったり、以前とは別種の恥ずかしい人によく会うんですね、60、70代の。つまり青春時代だけが恥ずかしいんじゃない、人間は死ぬまで迷惑をかけ、恥ずかしく生きていくんだなあと、これも今の歳になって思えたことの一つです」
〈悲しかったり腹がたったりしたことが、今は、「そういうものだわネ」とオカシくなる〉。確かに45年の歳月が、桜を見てただ〈満開だ〉とだけ思ったあの頃の愚かさも愛しさもありのままに享受させるのだとしたら、それは本当に素敵なことだ。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2020年12.18号より)
初出:P+D MAGAZINE(2020/12/22)

