【直木賞・島本理生『ファーストラヴ』が受賞!】第159回候補作を徹底解説

2018年7月18日に発表された、第159回直木賞。文芸評論家の末國善己氏が、今回も予想! 結果は、島本理生氏の『ファーストラヴ』でしたが、当初の予想はどうだったのでしょうか? 候補作6作品のあらすじと、その評価ポイントをじっくり解説した記事を、ぜひ振り返ってみてください!
前回の直木賞(第158回)を振り返り!
今回の直木賞予想も、まずは前回の答え合わせから始めたい。
第158回の直木賞は、澤田瞳子『火定』を本命、藤崎彩織『ふたご』を対抗、彩瀬まる『くちなし』を穴と予想した。結果は門井慶喜『銀河鉄道の父』だったので、まったくノーマークだった作品が選ばれたことになる。これで予想は、2勝1敗となった。
選考委員の林真理子によると「ほぼ満場一致の受賞」で、選評を読んでも「私が門井さんに感心したのは、勿論、父に対する息子の気遣いもありますが、うららかな口調と、敢えて臨終の人間に感情、情緒の表現を入れたことです」(伊集院静)、「信じつつも失望させられ、裏切られても愛することをやめられない。どうしようもない父親の姿が、ほどよい距離感をもって淡々と描かれている。その筆致は心地よく強い」(桐野夏生)、「小説として、世界の拡がりを持った。それは普遍を獲得している、ということであろう。私は、この作品に丸をつけた」(北方謙三)と高く評価されているのが見て取れる。
近年の直木賞は功労賞色が強くなっている。フレッシュな顔ぶれが揃った前回も、門井が最もノミネート回数が多かったので、ルールを当てはめれば予想は容易だったかもしれない(受賞決定直後、門井さんに受賞記念インタビューをすることになり、その時に予想で挙げなかったお詫びをしてきました。私は気まずかったのですが、門井さんは予想のことをご存知なかったのか、気にされていなかったのか、なごやかに興味深いお話をうかがいました)。
『火定』に関しては、時代考証の甘さが指摘されていたが、研究者でもある澤田瞳子より古代史に詳しい選考委員がいるのかと思わずツッこみを入れたくなったが、結果は結果。『ふたご』は“政治的な理由”で対抗にしたが、選評でも完成度の低さが指摘されていて、版元が直木賞と縁が深い文藝春秋だったことも効果はなかったようだ。『くちなし』は第5回高校生直木賞に選ばれたので、一矢報いた気分である。
第159回直木賞も、前回と同じく、『破滅の王』の上田早夕里、『じっと手を見る』の窪美澄、『傍流の記者』の本城雅人が初、『ファーストラヴ』の島本理生が2回目(芥川賞は4回候補になっている)、『未来』の湊かなえと『宇喜多の楽土』の木下昌輝が3回目のノミネートであり、作家としてのキャリアも2001年にデビューした島本理生が最も長いくらいなので、新鋭の戦いといえるだろう。
ただ前回との違いは、候補作すべてが小粒なこと。前回でいえば、伊吹有喜『彼方の友へ』、門井慶喜『銀河鉄道の父』、澤田瞳子『火定』あたりは、賞をとってもとらなくてもその作家の代表作になるクオリティを備えていた。ところが今回は、各候補作家の中でも決してベストとはいえない作品が並んでいるのだ。正直な話をすると、全候補作を読み終えて真っ先に思い浮かんだのは“受賞作なし”だった。というわけで、今回の予想も難しいのだが、まずは候補作を作家名の50音順で紹介していきたい。
選考委員は前回と変わらず、浅田次郎、伊集院静、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部みゆきの9名である。
候補作品別・「ココが読みどころ!」「ココがもう少し!」
上田早夕里『破滅の王』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4575240664
SFには、細菌やウィルスのパンデミックによって崩壊する世界を描く作品の系譜がある。本書もその一編だが、パニックに陥る人たちや治療にあたる医師を描くのではなく、細菌兵器を作る科学者に焦点をあてることで新機軸を打ち立てている。上田は『火星ダーク・バラード』で第4回小松左京賞を受賞してデビューしており、本書は、小松左京のパンデミックものの傑作『復活の日』を意識したのかもしれない。
物語は1936年の上海から始まり、舞台になるのは日中の研究者が共同で基礎研究を行った実在の上海自然科学研究所である。微生物学を研究する宮本は、日中戦争が始まり、すぐに成果の出ない基礎研究への風当たりが強くなるのを感じていた。それは禁断の人体実験をしているとの噂もある関東軍防疫給水部本部(いわゆる731部隊)が、国からの潤沢な予算を得て実戦に役立つ細菌戦の研究をしているのとは対照的だった。
日米開戦の1年後、日本総領事館から呼び出された宮本は、欠落した科学論文の精査を頼まれる。それは実験ではマウスの98パーセントが死に、現在の抗菌薬と抗生物質は効かない恐るべき細菌R2v(暗号名キング)の記録だった。R2vを開発した真須木は、なぜか論文を5分割して、日本、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツの大使館に送った。宮本はR2vの開発と使用を止めるため、論文を狙う大国との争奪戦に打って出る。
原子力を持ち出すまでもなく、科学は人類を豊かにすることも、破滅させることもある二面性を持っている。本書もこの問題を扱っているが、基礎研究の予算を減らし、防衛技術に応用できる研究に助成金を出すようになった現代日本の現状を踏まえるなら、本書のテーマはより生々しくなっている。
メッセージ性が高い本書だが、当時の上海の状況や上海自然科学研究所の内実が詳しく説明される前半はやや冗長。中盤以降は、SF的なアイディアも、国際謀略小説のようなスリルもあるスピーディで盛りだくさんの展開になるが、途中で主人公の宮本が活躍しなくなることもあり、それぞれの要素が中途半端に終わった感も否めない。
本書はSFではあるが、宮内悠介『ヨハネスブルグの天使たち』と比べれば、歴史時代小説、スパイ小説色が強く、SFが苦手でも違和感なく物語世界に入っていける。そのため“SFは直木賞がとれない”とのジンクスを打ち破るかもしれない。そこも注目である。
木下昌輝『宇喜多の楽土』
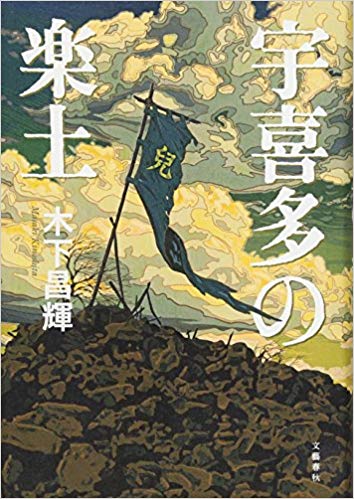
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163906525
木下昌輝は、2015年に刊行した初の単行本『宇喜多の捨て嫁』が第152回直木賞の候補になり、舟橋聖一文学賞、高校生直木賞などを受賞する鮮烈なデビューを飾った。3回目のノミネートとなった本書は、暗殺と謀略を平然と行って成り上がった宇喜多直家の生涯を連作形式で追った『宇喜多の捨て嫁』の続編で、梟雄だった父の事業を引き継ぎながらも、まったく別の道を歩んだ秀家を主人公にしている。
幼い秀家は、父に連れられ国境地帯にある干拓地へ行く。そこは直家が、流民のために作っていた「楽土」だった。汚名を着てまで貧しい人たちを救おうとした父の真意を知った秀家は、反対派の家臣を押し切ってでも干拓地を守る決意を固める。その直後に直家が没し、秀家は11歳で家督を継いだ。毛利との国境紛争を抱える秀家は、天下人への階段を登り始めた羽柴秀吉に従属し、所領を安堵してもらおうとする。秀吉に認められ、前田利家の娘で秀吉の養女になった豪と結婚した秀家だが、家中には反秀吉の勢力も根強く難しい舵取りを迫られる。特に勇猛ながら残虐な従兄・宇喜多左京亮との確執は、物語を牽引する鍵になる。
秀家は貧しい人々が安心して暮らせる「楽土」を守るため、秀吉の命で危険な最前線で戦うが、その前に、時流に乗ってのし上がってきたと豪語する徳川家康が立ちはだかる。
多くの武将が家康的なしたたかさで世を渡っていた乱世に、秀家はやさしさで時流に抗う。著者は対照的な二人が激突する関ヶ原の合戦を、新説を使って活写している。迫真のクライマックスは、「楽土」建設の難しさを突き付けていることもあり強く印象に残る。
なりふり構わなかった直家を描いた『宇喜多の捨て嫁』を創業者の物語とするなら、本書は二代目の苦悩を描いたといえる。日本が戦後復興、高度経済成長を成し遂げた時代の苦労を知らない世代が、あらゆる組織で中堅以上のクラスになった現在では、国を豊かにしようとした父の想いを受け継ぎ、より発展させようと悪戦苦闘する秀家に共感を覚える読者も多いように思える。しかし、苦労知らずの若者が上の世代が築いた遺産を守る展開は、どうしてもドラマ性が弱く、痛快さに欠ける。選考会では、否応なく『宇喜多の捨て嫁』と比較されるだろうが、主人公のキャラクターも、物語のインパクトも前作を上回っていないので、それがマイナスに働くように思えた。
窪美澄『じっと手を見る』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4344032756
2009年に、『ミクマリ』で第8回「女による女のためのR-18文学賞」を受賞してデビューした窪は、同作を含む連作集『ふがいない僕は空を見た』で第24回山本周五郎を受賞、二冊目の単行本『晴天の迷いクジラ』で第3回山田風太郎を受賞するも、その後は賞レースとは無縁となっていた。“なぜ、直木賞の候補にならないんだ”との声も高かった窪が、ようやくスタートラインに立ったのが本書である。
戦国時代の富士五湖の一つ本栖湖周辺を舞台に、複雑な過去を背負った男女が離合集散を繰り返しながら、複雑怪奇な物語を織り上げていく国枝史郎の伝奇小説『神州纐纈城』は、武田信玄の寵臣・土屋庄三郎が、妻のお妙と弟・主水の不義を疑う三角関係がすべの事件の切っ掛けとなり、出奔した妻と愛人を探すうち快楽殺人鬼となった男が登場するなど、恋愛が重要な要素になっている。富士山が見える町にある介護施設で働く男女を軸にした本書を読んで真っ先に思い浮かべたのが、この『神州纐纈城』だった。
幼い頃に両親を亡くし祖父に育てられた日奈は、恩返しのため介護士を目指すが、肝心の祖父を亡くし無気力になっていた。そんな日奈を救ってくれたのが、介護の専門学校で仲の良かった男友達・海斗だった。海斗が語る未来に共感できないまま恋人のようになった日奈は、専門学校のパンフレットを作るため東京から来たデザイナーの宮澤と肉体関係を持ち、性の悦びも覚えてしまう。物語は、宮澤との関係を知りながら日奈を愛そうとする海斗、子供の親権を別れた夫に渡し、奔放に男たちと関係を持ちながら各地の介護施設を転々としている畑中、妻と日奈の間で揺れる宮澤らが時に深く結び付き、時に別れたりしながら複雑に入り組んでいく。
特別に宮澤に魅かれているわけではないのに、セックスでは快楽を感じている日奈を描く冒頭部は、人間に必要なのは精神的な愛なのか、肉体の相性なのかを問うラジカルな視線があった。死を身近に感じる介護と性=生を対比させた手法も、多分に図式的ではあるが効果的だったし、介護士という過酷で低賃金の現場で働き、生まれ育った小さな町から出ることに積極的になれない主人公たちの微妙な心理を掘り下げることで、現代の日本を覆っている閉塞感の根本に迫ったところも見事だった。
ただ物語が結末に向けて収斂を始めると、主人公たちの葛藤が常識的な結論に落ち着き、冒頭部にあった過激さが損なわれていたように思えた。中盤の波乱に満ちた展開を読ませる伝奇小説は、完結すると平凡な作品も多い。『神州纐纈城』は、未完に終わったことで三島由紀夫も絶賛する伝説の名作になったが、結末に衝撃を受けなかったことも、本書を読んで伝奇小説をイメージした一因かもしれない。
島本理生『ファーストラヴ』
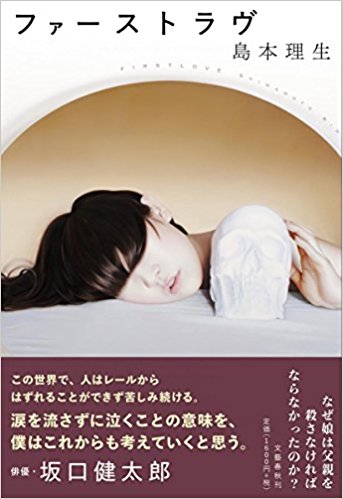
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163908412
島本理生は、15歳で「鳩よ!」の掌編小説コンクールに当選、高校時代の2001年、「シルエット」が第44回群像新人文学賞の優秀作に選ばれるなど、10代から創作活動を始めており、今回の候補者の中では最も作家生活が長い。2003年には『リトル・バイ・リトル』が第128回芥川賞の候補になり、同作で第25回野間文芸新人賞を受賞。20歳での受賞は史上最年少だった。その後も、『生まれる森』が第130回、『大きな熊が来る前に、おやすみ。』が第135回、『夏の裁断』が第153回芥川賞の候補になるなど純文学の世界で活躍していた島本だが、2011年には『アンダスタンド・メイビー』で第145回直木賞の候補にもなっており、純文学界とエンターテイメント小説界が綱引きをしている作家となっている。
美貌の女子大生・聖山環菜は、アナウンサー志望でキー局の面接を受けていたが、途中で辞退し、その足で画家の父親・那雄人が講師を務める美術学校を訪ね、女子トイレで刺殺した。血まみれで歩いているところを逮捕された環菜は、犯行は認めるが動機は本人すら分かっていないようだった。環菜を取材してノンフィクションを書くことになった臨床心理士の真壁由紀は、弁護を担当する義弟の迦葉と、環菜の動機を明らかにしようとする。
ミステリータッチの作品だが、純粋にミステリーとして読むと、由紀と迦葉が調査をすると次々と証言者が現れる展開が安易で、証言が積み重なって真相が明らかになるだけなので、“前半のあの描写が、伏線になってなっていたのか!“といった驚きもなかった。
環菜が抱えていた“心の闇”も、想像の範囲を超えていなかったし、同じようなタイプの作品をかなり読んできたので、既視感が強い(環菜の父親が画家ということもあり、すぐに大ヒットしたテレビドラマ『高校教師』を思い浮かべてしまった)。夫の我聞と迦葉には血の繋がりがなく、由紀と迦葉には過去に因縁があったことが暗示され、それを環菜の“心の闇”と共鳴させ、環菜の事例が特殊ではないと強調したところは多少読ませるが、環菜を見守る側の事情も、よくあるパターンを超えていないのは残念なところである。
おそらく環菜は、自分が価値ある人間と思えない、あるいは自分が何者かさえ分かっていない若い世代の象徴である。そんな環菜が、由紀や迦葉らの協力もあって、過去と向き合い、トラウマを乗り越えようとあがくようになる展開は、環菜に近い若者は共感できるのかもしれないが、すれっからしの大人が読むと、青臭い議論にしか思えなかった。
本城雅人『傍流の記者』
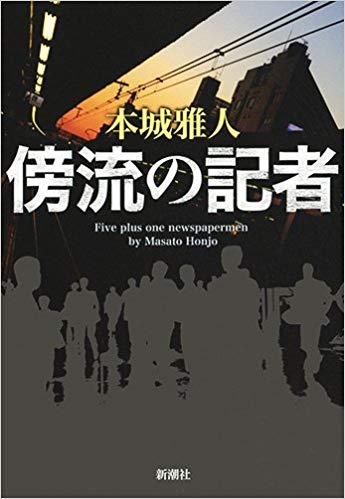
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4103360534
産経新聞社に入社し、サンケイスポーツの記者となった本城は、2009年に野球ミステリー『ノーバディノウズ』でデビュー。スポーツを題材にしたミステリーを中心に発表していたが、2016年には新聞記者を主人公にした『ミッドナイト・ジャーナル』で第38回吉川英治新人賞を受賞、翌年にも新聞社の買収を題材にした『紙の城』を発表するなど、近年は新聞を題材にした作品でも注目を集めている。本書も、その一編である。
新聞記者ものといえば、他社とのスクープ合戦や、警察に匹敵する地道な調査で難事件の真相を暴く展開をイメージしがちだ。本書にもこうした要素はあるが、それ以上に、ライバルとの出世競争、政治部と社会部の軋轢、人事の行方など、新聞社内の政治力学を丹念に描いているのが面白い。横山秀夫『陰の季節』は、犯人を追う捜査部門ではなく、警察の管理部門を取り上げることで警察小説に新風を送り込んだが、本書もそれに近い。
得意分野の異名で呼ばれる「警視庁の植島」「検察の図師」「調査報道の名雲」「遊軍の城所」「人事の土肥」、そして総務に異動した北川は全員が40歳前後で、東都新聞の社会部史上最高の同期と呼ばれていた。とにかくスクープを取って出世したい植島と図師、地道な調査報道が好きだが、植島と図師が上に行くと調査報道の人員を削られる危険があるので、仕方なく出世競争に参入する名雲など動機は様々だが、能力には自信を持つ6人が、それぞれの長所を活かしてライバルと戦う展開は読みごたえがある。主人公たちは、無理難題を押し付けてくる上司、思う通りに動かず、怒るとすぐ辞める部下に頭を悩ませているが、これは同世代の中間管理職は共感が大きいのではないだろうか。
新聞とテレビが報道を支えていた時代は既に過去となり、少しでも間違ったことを書けばネットで叩かれるなど、新聞を取り巻く環境の変化を的確にとらえつつ、新聞の役割とは何か、新聞記者の使命とは何かを再検討していく終盤も、かなり考えさせられた。
ただ本書の最大の問題点は、スクープのためなら寝る間を惜しんで働く図師の“モーレツ社員”ぶりを始め、何よりも仕事を優先する主人公たちの行動原理から、親の介護、離婚など家庭のトラブルも描かれるが主人公たちの妻はだいたいが主婦で、何より社会部史上最高の同期には一人も女性記者がいないことまで、全編に漂っている昭和臭。平成が舞台とは思えないマッチョな世界観は、選考委員の賛否がわかれる可能性が高い。
湊かなえ『未来』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4575240974
湊かなえは、2007年に「聖職者」で第29回小説推理新人賞を受賞、2008年に同作を含む連作集『告白』を刊行すると、2009年、第6回本屋大賞を受賞、『2009年版このミステリーがすごい!』で4位、週刊文春ミステリーベスト10で1位を獲得し、いきなり人気作家の仲間入りをした。その後、「望郷、海の星」で第65回日本推理作家協会賞の短編部門を、『ユートピア』で第29回山本周五郎賞を受賞している。2018年、『贖罪』が、アメリカ探偵作家クラブが主催するエドーガー賞の候補になったことが大きく報じられた。これは2004年の桐野夏生『OUT』、2012年の東野圭吾『容疑者Xの献身』に続く日本人3人目の快挙である(ただ桐野と東野は長編部門、湊はオリジナルペーパーバック部門なので、部門は異なる)。受賞していれば直木賞受賞よりも話題になったかもしれないが、残念ながら受賞は逃した。今回の直木賞はそのリベンジといえ、エドーガー賞ノミネートの先輩にあたる桐野と東野が選考委員を務めているのも、偶然だが因縁を感じてしまった。
湊がデビュー10周年の節目に書き下ろしとして刊行した本書は、大好きなパパを病気で亡くし、ずっと精神が不安定だったママと暮らす10歳の章子のもとへ、20年後の自分から手紙が届くところから始まる。30歳の章子は、自分が未来から手紙を出したと証明するために、10周年を迎えたばかりのテーマパークの30周年記念グッズを同封していた。
物語は、10歳の章子が、身辺で起きた出来事を20年後の自分に手紙で知らせるという形式で進んでいく。何も悪いことをしていないのに、章子とママが不幸になっていく展開は読み続けるのがつらくなるほどせつなく、“イヤミスの女王”の面目躍如といえる。
章子が書簡体で語る章が終わると、章子の友人や担任の先生などが語り手のパートが始まる。同じような構成の『告白』は、語り手が変わるたびに前の章の解釈が否定され、新たな仮説が提示される二転三転するスリリングな展開になっていたが、本書にはそこまでの緊密さはない。新たな語り手は章子が書簡で書いた内容を補完するだけなので、完成していく絵を眺めてだけという感じで、探偵役が手掛かりを解釈し真相を推理していくというミステリーのダイナミズムがほとんど存在していないのだ。特に、未来から届いた手紙という魅惑的な謎を、謎解きではなく単なる告白で処理したところは愕然とした。
作中には、いじめ、DV、虐待、AVの強要など現代社会で実際に起きている様々な社会問題が描かれているが、総花的に並べただけで、まったく深められていない。一部、モチーフが重なる『ファーストラヴ』の方が、まだ被害者の心理と葛藤に深く踏み込んでいた。
ズバリ予想!本命は?対抗は?
前回までの原稿と違い、“褒め”より“貶し”が多くなってしまったが、各作品の所感を踏まえて、今回の直木賞を予想してみたい。
本命は、窪美澄『じっと手を見る』。小粒な作品が並んだ場合、功労賞的な色彩が強くなるので、キャリアが長い島本理生『ファーストラヴ』もあり得るが、作品の完成度では圧倒的に『じっと手を見る』が上なこと、窪美澄はこれまで直木賞の呼び声が高かったのに候補にもなっていないので、その埋め合わせを兼ねて票を集める可能性がある。
対抗は、上田早夕里『破滅の王』。小説のクオリティも、アクチュアルなテーマも、候補作6編の中では頭一つ抜けていたので、質の争いになれば『破滅の王』に分がある。
穴は、受賞作なし。近年の直木賞は、小説の売り上げ低迷を食い止める役割も担っているので、よほどのことがない限り受賞作を出してきたが、今回の候補作だと十分になしもあり得るだろう。
あとは個人的な興味をいくつか書いておきたい。選考委員の高村薫は『冷血』で、幼少時のトラウマ、映画やゲームの影響、精神疾患といった分かりやすい動機を探して、残酷な殺人を実行した犯人を理解しようとする現代の風潮を批判した。その高村が、『ファーストラヴ』をどのように評価するのか? また日本に根強く残る男性原理的な風潮を、女性の視点で相対化してきた桐野夏生が、いさぎよく女性キャラクターを切り捨てた『傍流の記者』をどのように読むのか? 「オール讀物」に掲載される選評にも要チェックだ。
筆者・末國善己 プロフィール

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』などがある。
初出:P+D MAGAZINE(2018/07/11)





