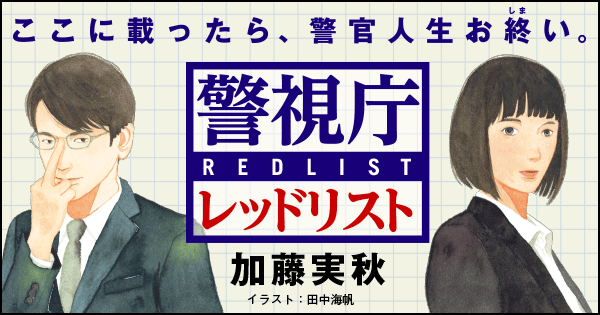〈第10回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

動揺するみひろ。
6
慎は本庁舎十一階の警務部人事一課制度調査係で、当番勤務の職員からUSBメモリを受け取った。廊下を進み、奥のトイレに入る。誰もいないのを確認し、洗面台の天板にバッグを置いてノートパソコンを出した。電源を入れ、ポートにUSBメモリを差し込んで起動させる。中身は職場改善ホットラインの通話記録の一部だ。「職場環境の調査で必要になった」と言い、当番の職員にダウンロードしてもらった。
メディアプレーヤーのソフトを立ち上げ、USBメモリ内のデータを再生した。
「はい。職場改善ホットラインです」
ノートパソコンのスピーカーから、女性警察官の声が流れる。続いて流れたのは、
「奥多摩署の柿沼也映子警部補は、新興宗教のみのりの道教団の信者だ」
という男の声。はっきりした口調でボリュームも適度、声質を変えてカモフラージュする様子もない。慎にとっては聞き慣れた、かつての部下、中森翼(なかもりつばさ)警部補の声だ。
やっぱりか。病院の駐車場で抱いた予感が確信に変わり、胸が大きくざわついた。女性警察官は「わかりました。内容を確認させて下さい」と返したが、中森は電話を切った。
柿沼のスマホに電話をかけたのも、中森だろう。当番の職員によると、今の通話の発信は番号非通知の携帯電話からで、無線基地局は神奈川県相模原(さがみはら)市の相模大野(さがみおおの)駅近くの市街地だったという。
なぜ中森が内通を? データ抜き取り事件を起こす前、柿沼と接点はなかったはずだ。どこで柿沼の信仰の情報を得た? 何より、警視庁内でも一部の関係者しか知らない職場環境改善推進室の職務の実態を把握しているのはどうしてだ?
続けて疑問が湧き、胸のざわつきがさらに大きくなる。と、トイレのドアが開き、慎は振り向きながらノートパソコンを閉じた。ダークスーツ姿の佐原皓介(さはらこうすけ)が、後ろを気にしながらトイレに入って来る。
「動きは?」
ノートパソコンを素早くバッグにしまい、慎は問うた。
「持ち出されたデータのネット流出は認められず、マスコミ、市民活動家、左翼団体などに渡った形跡もない。中森の家族や友人にシキテンを切り(張り込み)続けているが、動きはなし。じきに事件発生から四カ月だ。中森の意図が読めないのが、一番不気味だな」
ドアの脇の壁際に立ち、佐原が返した。髪は整えているが、無精ヒゲのせいか少し疲れて見える。同意なので慎が黙っていると、さらに言った。
「持井さんはデータの流出元にこだわって、警備第一課全員に監察を実施しようとしてる。
無論メンツがあるから第一課長が黙っていないし、現場は大混乱だ」
「だろうな」
状況が目に浮かび、慎は歪んだ喜びを感じた。しかし持井たちが中森が担当した事案を洗い直し、新海弘務(しんかいひろむ)に辿り着くのは時間の問題だ。何としても持井たちより先に、中森とデータの所在地を突き止めなくてはならない。
向かいの鏡越しに佐原を見て、慎は再び問うた。
「相模原市に中森の関係者はいないか?」
「いないはずだ。なぜだ?」
怪訝そうに、佐原も鏡越しにこちらを見る。調べた限りでは、相模原市に盾(たて)の家の施設などはなかった。「いや、いい」と返し、慎は話を変えた。
「沢渡暁生は、持井さんと何をやってる?」
「何って、沢渡さんは持井事案の審議委員の一人だろ」
「だが、中森の事件で事案の計画はストップしているはずだ」
「ストップはしても、中止になった訳じゃない。計画の要のシステムを配備できるかは、沢渡さんの経産省人脈にかかってるからな……なぜ俺に訊く? お前の親父だろ」
怪訝そうに訊ねた佐原だったが慎が無言なのを確認し、口を歪めて笑った。
「それができりゃ、ってところか。俺の妹の息子についてあれこれ言ってたが、お前も大変だな。エリートの泣き所か? そう言えば、警察学校時代から――」
「ぺらぺらとよく喋るな。その妹の息子だが、暴力がますますひどくなって近所の噂になってるぞ。パトカーを呼ばれる前に、なんとかした方がいいんじゃないか?」
冷ややかに問い返して黙らせ、慎が振り向くと佐原は舌打ちし、顔を背けた。その横顔を見て、慎はさらに告げた。
「沢渡の動向含め、持井事案の進捗状況も調べて報告しろ」
「……ああ」
低く応え、佐原はトイレを出て行った。バッグを摑み、慎もトイレを出て廊下を佐原とは反対方向に歩きだした。
7
翌朝。慎に「柿沼の捜査に同行します」と告げられ、みひろは大歓迎で「はい」と応えた。職場としては不満の多い警察だが、テレビの警察密着番組や刑事ドラマは大好きなので、ずっと事件捜査に関わってみたいと思っていたのだ。
午前十一時前に奥多摩署に着いた。待っていた柿沼と署の車に乗り換え、みのりの道教団の本部に向けて出発した。
「板尾は群馬県の桐生(きりゅう)市出身。子どもの頃から手の付けられない不良で、中学卒業と同時に家出して音信不通だったらしい。昨日家族に連絡したけど、遺体の引き取りを拒否されたよ」
運転席でハンドルを握りながら、柿沼が言った。みひろと慎は後部座席に座り、車は山間の曲がりくねった道を走っている。道の下には多摩川の渓流が見えた。
「では、遺体はみのりの道教団が引き取るんですか?」
ルームミラー越しに柿沼を見て、慎が問うた。頷き、柿沼が返す。
「そうなるね。板尾は入信してから半年ぐらいだけど、ずっと本部の施設で暮らしてたし、教祖の土橋日輪(どはしにちりん)先生が引き取るとおっしゃったそうだから。ちなみに日輪は宗教上の名前で、本名は土橋昇(のぼる)。年齢は七十五」
刑事と信者、どちらの立場なのか迷う話し方だ。みひろは慎重に口を開いた。
「教団の施設で暮らす出家信者は、食料を自給自足しているんですよね。人工化合物は禁止で、野菜は無農薬。樹脂や化学繊維の生活用品を使うのもダメ」
「さすが。よく調べてるじゃない」
柿沼が答えた。嫌みか感心か、これまた迷う口調だったので、みひろは小さめの声で「どうも」と返した。
ファイルの資料によると、土橋日輪は北海道の農家出身だ。有機農業にのめり込むうちに「豊穣の神から『実りの手』を授かった」そうで、「自分が手にした種や苗は浄化され、収穫された農産物を食べれば心身に神力を取り込める。実りの手は自然の一部である人間にも有効で、触れた者を浄化して災いを取り除き、『みのりの道』へと導く」と説き、二○○○年代初頭にみのりの道教団を開いた。信者は千二百人ほどで、そのうち約百名が出家し、本部施設と長野県にある農場で暮らしている。
「板尾さんが着ていた服は、出家信者のものなんですよね。土橋さんの教えにそって、オーガニックかつ無漂白の綿素材でボタンやファスナー、ゴムは使われていないとか」
言いながら、みひろはつい後ろから柿沼が身につけた服を確認してしまう。今日は私服で、たっぷりしたつくりのブラウスとスラックスという組み合わせだが、生地は化学繊維っぽいし前面にはプラスチック製と思しきボタンが並んでいる。
「私も下着とバッグは、教団のものだよ。『社会との関わりを保ち、可能な限り暮らしに教えを取り込み、道を究めるのが在家信者の務め』っていうのが先生のお考えなんだ」
そして最後に、片手でシートの脇に置いたバッグを持ち上げて見せた。飾り気のない生成り色のトートバッグで、昨日は「刑事っぽくないな」と感じたのだが、よく見れば板尾の服と同じ生地で作られている。みひろが思わず、
「なるほど」
と頷くと、柿沼も満足したように頷き、バッグを下ろした。慎は話を元に戻した。
「板尾の死因が事故ではなく、殺人だと考える根拠を教えて下さい」
「署や教団の人たちは、板尾は何らかの理由があって施設を脱走したと考えてる。でも板尾は熱心な信者で、一週間ぐらい前に会った時も『自分は、人の汚い面やずるい面にばかり触れてきた。ここで暮らしている人は汚(けが)れがなく、一緒にいると自分が浄化されていくのがわかる』って嬉しそうに話していたんだ。『外の世界に居場所はない』とも言っていたしね」
柿沼が答え、慎は考えを巡らすような顔をした。