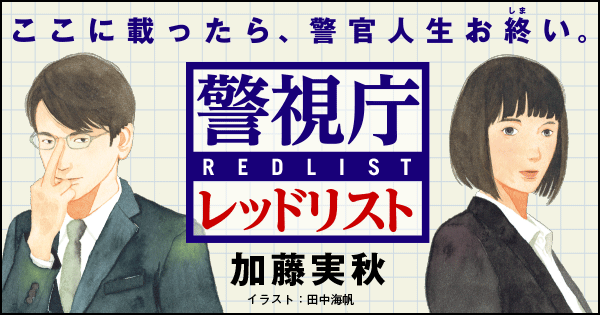〈第11回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

一行は、新興宗教施設へ向かった。
10
みひろたちは教団の施設を出て、奥多摩署のある町に向かった。
「河元初男(はつお)、四十六歳。奥多摩湖に近い町の出身で、勤務先のスーパーの娘婿になった。子どもは高校生の娘と中学生の息子……私も彼は気になってたよ。板尾に親しい在家信者はいなかったはずだから、河元が外部との唯一のつながりだ。どっちも否定してたけど、喫煙騒動の時に板尾に煙草(タバコ)を渡したのは河元だって噂もあったしね」
ハンドルを握りながら、柿沼が言った。慎が訊ねる。
「河元の素行は?」
「前科(まえ)どころか、交通違反歴もないよ。田舎町だから浮気だの借金だのもすぐ噂になるけど、聞いたことないね。奥さんとその母親の尻に敷かれてる、ちょっと情けないけど気のいい男って感じかな。義理の父親はかなり前に亡くなって、今は河元が店主だよ」
「なるほど」
頷き、慎は視線を傍らの窓に向けた。時刻は午後二時。外の気温は三十五度近くあるはずで、山から伸びる木々の枝がアスファルトにコントラストの強い影を落とし、眼下の多摩川は日射しを受けてまばゆく輝いている。そんな風景を目に映しながらも、みひろはお腹がぺこぺこで、慎と柿沼が昼食をどのタイミングで摂るつもりなのか、ということばかり考えていた。
奥多摩の町に戻り、署と同じ通り沿いにある河元の店の手前で車を停めた。小さな店で、軒先の色褪せた青いテント屋根には白い文字で、「スーパーことぶき」と書かれていた。
「こんにちは」
ガラスの引き戸を開けて柿沼が店に入り、慎とみひろも続く。傍らのレジに入っていた河元が振り向いた。
「いらっしゃい。さっきはどうも」
「念のために板尾くんの話を聞いてるんだけど、河元さんもいい?」
柿沼が確認すると、河元は「もちろん」と神妙な顔で頷いた。慎とみひろもレジの前に立ち、柿沼は質問を始めた。
「最後に板尾くんに会ったのはいつ?」
「ちょうどひと月前だね。先月の配達の時だ」
「何を話した? 変わった様子はなかったかな」
「挨拶だけだよ。変わった様子って言われても、無口な人だからね。商品と納品書を渡して代金を受け取るだけだった。あとは正直、気味が悪くて。お客さんを悪く言いたくはないけど、みんな同じ服を着て同じ顔で笑って、っていうのがどうも」
後半は声を潜め、河元が言う。みひろは思わず「ああ」と頷き、慎に咎めるような目を向けられたので、「ちょっと見て来ます」と囁いて身を翻した。
売り場には棚がいくつかあり、壁際には生鮮食品や飲み物用の冷蔵と冷凍のショーケースが置かれていた。夏休み真っ最中とあって奥多摩の駅前には大勢の観光客がいて、多摩川の河原でキャンプやバーベキューをする家族連れと若者も見かけた。しかしそういう人たちはコンビニに行ってしまうのか、スーパーことぶきに客の姿はなく、店が古いせいもあって淀んだ空気が立ちこめている。棚に並ぶ商品も薄く埃をかぶっていたり、パッケージの印刷が褪せていたりする。みひろは棚に並んだカレールーの箱を手に取った。空腹なので、カレーが皿に盛り付けられたパッケージ写真に引き寄せられたのだ。と、何気なく箱の底の賞味期限を見て、
「えっ!?」
と声を上げてしまう。「2010.6.16」、そう記されていた。
に、二〇一〇年って。驚き、うろたえながらレジを振り向くと、声が聞こえたのか慎が怪訝そうにこちらを見ていた。箱を持ち上げ、ジェスチャーで状況を伝えてみたが、慎はますます怪訝な顔をしただけだ。
河元さんに知らせるべき? この分だと、他にもとんでもない賞味期限の日付入りの商品があるはず。みひろが逡巡していると柿沼は、「ありがとう。邪魔したね」と話を切り上げて引き戸に向かった。河元に礼を言って慎も続き、みひろは迷いながらもカレールーを棚に戻し、河元に会釈して店を出た。
慎たちに続いて車に乗り込もうとしていると、通りの先から「あら。おまわりさん」と声がした。ショッピングカートを引いた年配の女性が歩いて来る。柿沼は「鈴木(すずき)さんじゃない。元気? お買い物?」と親しげに返し、開けかけた車のドアを閉めて歩道に戻った。
「違うの。食べ物をもらいに来たのよ」
そう答え、女性はスーパーことぶきを指した。
「もらうって?」
「お菓子とかカレールーとか、少しでも外箱が潰れたりキズが付いたりすると売り物にならないんだって。そういうのの中身だけを貯めておいてくれるのよ。うちが年金暮らしで旦那の具合も悪くて大変なのを知ってて、『棄てるのはもったいないし、こっちも助かるんだ。でも?られるから、嫁と義母(はは)には内緒ね』なんて気を遣ってくれてね」
説明して涙ぐみ、女性はスカートのポケットから出したタオルハンカチを目頭に当てた。
「そうだったの。優しい人だからね。でも、最近河元さんに変わった様子はなかった?」
柿沼は探りを入れたが、女性はシワだらけの首を横に振った。
「全然。すごく親切でいい人よ。それに引き換え、あそこの娘と母親は。旦那を締め付けるばっかりで、何にもやらないんだから」
「そう。ありがとう。暑いから気をつけてね」
これ以上の話は聞けないと判断したのか、柿沼は女性を送り出して車に戻った。