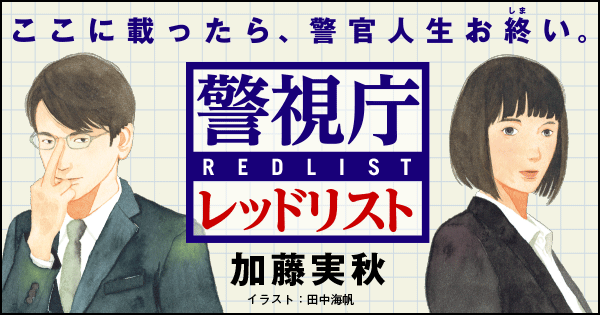〈第11回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

一行は、新興宗教施設へ向かった。
9
二十分ほどすると、ロビーにさっきの美女が現れた。「お待たせしました。土橋がお目にかかります」と告げ、「土橋の秘書で教団の広報担当の園田美苗(そのだみなえ)です」と自己紹介した。
案内されたのは、二階の奥にある土橋の仕事場という部屋だった。六畳ほどの和室で、慎とみひろが小さな三和土(たたき)で靴を脱いでいると、中央に置かれた座卓についていた土橋が立ち上がって一礼した。
「こんにちは。土橋日輪と申します」
さっきと同じ服を着て口の端を上げて笑い、お約束の丹田集中ポーズを取る。
土橋が座卓の前にあぐらを搔き、慎とみひろは向かいに座った。その隣に柿沼が座り、園田と波津は土橋の斜め後ろに並んで正座をした。質素な部屋で、座卓の他には突き当たりの窓の前に数冊の本が載った文机が置かれているだけだ。
「板尾くんの件で確認させていただきたいことがあって参りました。昨日も署で散々伺った上に、さらにお手間を取らせて申し訳ありません」
柿沼が言い、丹田集中ポーズで頭を下げた。しかし表情と眼差しは、昨日板尾の遺体発見現場で会った時と同じだ。
「とんでもない。お騒がせしましたし、柿沼さんも大事な信者さんですから……ああ。今日は警察官としていらしたのか。とにかく、何でも訊いて下さい」
土橋は言い、最後に慎とみひろに目を向けた。
朴訥(ぼくとつ)とした外見も含めて人を惹きつける魅力は感じるけど、なんか胡散臭(うさんくさ)いのよね。とくにこの笑顔。信者もみんな同じ笑い方をするけど目が全然笑ってなくて、ちょっと怖い。でもこの笑顔、どこかで見た気が──。みひろの思考を、柿沼の質問が遮る。
「ありがとうございます。板尾くんは、三日前の夜にいなくなったんですよね?」
「ええ」と土橋が頷き、斜め後ろに首を回す。細く白い首を突き出し、園田が答えた。
「はい。午後七時過ぎに作業を終えて自室に戻り、消灯時間の午後九時に就寝したのを同室の者が確認しています。でも、翌朝五時に起きたら姿がなかったそうです。土橋に報告してみんなで施設中を捜しましたが、見つかりませんでした」
「昨日もお話しした通り、警察に捜索願は出していません。出家信者が許可なく外出することは禁止されていますが、みのりの道教団は去る者は追いません。それにこの施設のフェンスには防犯カメラが設置されていますが、コーナー部分の一カ所に死角があるそうです。板尾はみんなが寝静まるのを待って、そこから出て行ったんでしょう」
波津も補足し、みひろの目は彼女と園田に向いた。二人とも涼しげな目元でモデル体型、髪はストレートのロング。歳は十近く違うが、並んで座っているのを見るとよく似ている。
「ここを出て行った理由は?」
とまた柿沼が訊ねた。園田と波津は同時に首を傾げ、土橋が答えた。
「信者たちからも話を聞きましたが、思い当たる理由がないんです。私や先輩信者の教えを守って、作業にも熱心に取り組んでいました。ただ、心身に溜め込んだ悪意は手強いものでした。原因は、ここに来る前の生活でしょう」
土橋は真顔になり、厳しい眼差しで空を見た。
「板尾は元ホストです。外の暮らしを断ち切れず、ここに来て間もない頃、隠れて喫煙したのがわかって罰を受けています。最近は落ち着いていましたが、短気なところがあって他の信者と小さなケンカなどはしていたようです。もちろん、別の信者の仲裁ですぐに仲直りしましたが」
再度波津が補足する。
あれ? さっき聞いた話と違うな。違和感を覚え、みひろは横目で隣を見た。すると、慎も質問を始めた。
「板尾さんは、どんな作業をしていたんですか?」
「厨房の洗い物やトイレやお風呂の掃除。備品の補充交換に農作業の手伝い……雑用係ですね。外の業者さんへの品物の注文と支払いもやっていました」
園田が答え、慎はさらに問うた。
「外の業者さんとは、先ほどの河元さんですか?」
「うん。ここで必要なものは在家信者が運んでくれるんだけど、生活用品だけは先生が『地元のみなさんのお役に立ちたい』って町の店に注文して下さってるんだ」
土橋を称(たた)えるような口調で説明したのは、柿沼だ。「いやいや」と笑顔に戻って首を横に振り、土橋は言った。
「二年前、ここを教団の施設にした時にはいろいろありましたから……近くのキャンプ場の経営者と別荘地のオーナー方から猛反対されました。何度も説明会を開いたんですが話し合いにならず、警察まで呼ばれてしまって。まあ、最終的にはご理解いただけたし、そのお陰で柿沼さんとご縁ができた訳ですが。最近、体調はいかがですか?」
「先日の施術のお陰で、快調そのものです。お気遣いありがとうございます」
柿沼も信者の顔に戻って笑みを浮かべる。慎は話を元に戻した。
「つまり信者以外の人間で定期的にここに出入りしているのは、河元さんだけということですね?」
「ええ。とてもいい方ですよ」
波津が答え、土橋と園田も頷く。「わかりました」と返し、慎はちらりと柿沼を見た。柿沼が小さく頷くのを確認し、慎は顔を前に戻して中指でメガネのブリッジを押し上げた。