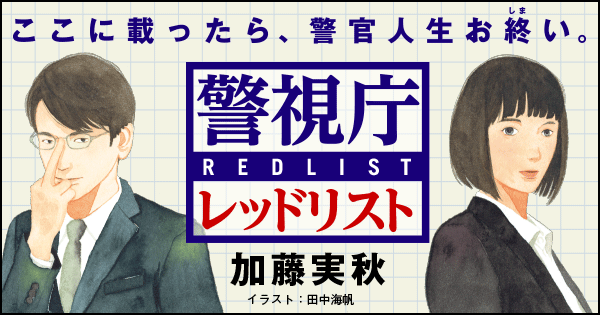〈第3回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

民間企業出身のみひろは、調査に躊躇する。
9
お腹が鳴りそうになり、みひろはバッグの中からミネラルウォーターのペットボトルを出して飲んだ。二日酔いで朝から食欲がなく、吐き気と頭痛もあったのだが、夕方になって快復してきたようだ。ほっとしながらも情けなくなり、みひろはペットボトルをバッグに戻した。ついでに横目で運転席を見たが、慎は無言無表情で白く整った横顔を車の窓の外に向けている。
昨日は慎とやり合って職場環境改善推進室を出たら、追いかけて来た豆田に「上司に対してあるまじき態度」「警察とか規則とか以前の常識の問題」と説教され、最後には「頼むよ。定年まで五年、波風立てずにやり過ごさせて」とすがりつくような目で見られた。言われたことはもっともなので部屋に戻って謝罪し、大人しく報告書を書いていたら、慎は「ちょっと庶務係に」と告げて出て行った。十五分ほどで戻って来たのはいいが、慌ただしくパソコンを操作したり、どこかに電話をかけたりし始めた。訳がわからなかったが五時になったので、みひろは「お疲れ様です」と言って退庁した。それからスナック流詩哀に行き、摩耶ママを相手にグチを言いながら飲んだくれたのだ。今日は「外回り」と連絡があった慎は夕方近くになって現れ、みひろに「出動です」と告げた。そして午後五時を回った今、みひろは日本橋署近くに停まった警察車両の白いセダンの助手席にいる。
先週張り込みをした時同様、今日も大勢の人が歩道を行き来していた。しかし少し前に小雨が降りだしたので、みんな傘をさしたりパーカーのフードをかぶったりしている。数日前に梅雨入りし、空には灰色の雲がたちこめて気温は低いが湿度が高い。
「ひょっとして、黒須たちの不倫を職場改善ホットラインに報せてきた人を捜すんですか? そこまでが調査の対象とか?」
閃いて、みひろは問いかけた。黒須の行動確認は終了したはずなのにここに来た理由がわからない。
「いえ。違います」
メガネのレンズ越しに日本橋署の通用門を見たまま、慎は短く返した。昨日みひろが謝罪した時は「わかりました」とだけ応えていたが、実は怒っているのかもしれない。
警察って組織に不満や疑問はあっても、人の役に立ってる、市民を助ける警察官を裏で助けて支えてるという自負があるから一年近くやってこられた。でも、今度の仕事は正反対。一生懸命やればやるほど、警察の仲間を追い込んで苦しめる。このまま続けていいの? それ以前に、続けていける自信が皆無なんだけど。ぐるぐる考えていると、
「来ました」
と慎の声がして我に返った。「はい」と返し、みひろは身を乗り出す。日本橋署の通用門から、女性が出て来る。赤と緑のチェックの傘をさしているので顔は見えないが、体型と黒いバッグで誰かわかった。
「星井さん?」
「行きましょう」
そう告げて、慎は運転席のドアを開けた。訳がわからないまま、みひろも続く。
慎は黒、みひろは紺地に白の水玉模様の折りたたみ傘をさし、歩道を進んだ。前方には星井。今日は一人だ。
「尾行してどうするんですか? 不倫は認めたし、彼女はむしろ被害者でしょう」
「後で説明します」
前を見たまま、少し強めの口調で慎が答えた。みひろは黙り、二人で歩道を進んだ。
水天宮前駅への出入口に差し掛かると星井は傘を閉じ、階段を降りて行った。
あれ? 独身寮に帰らないんだ。処分を待っている身なのに、よく出かける気になるな。いや、病院とか仕方のない事情があるのかも。口に出すと叱られそうなので、みひろは心の中で呟いた。みひろたちも階段を降り、駅に向かう。
星井は下りのホームに行き、到着した電車に乗り込んだ。距離を空けてちらちらと見たが、星井はホームでも車内でも人目を避けるように俯いて隅に立っていた。
落ち込んでるんだな。どのみち黒須とは長続きしなかっただろうし、私たちが表沙汰にしなければ、誰もキズつかずに済んだのかも。そう浮かび、みひろがまた仕事への疑問を感じている間に電車は錦糸町(きんしちょう)駅に到着し、星井は降車した。
駅を出ると人と車で混雑したロータリーを抜け、小さなビルに入った。遅れること二十秒、みひろたちもビルに入った。エントランスの奥に小さなエレベーターホールがあり、エレベーターは上昇中だ。壁の階数表示パネルを見守っていると、五階で停まった。壁の反対側に取り付けられたテナントの案内板を確認したところ、美容院だった。
「気分転換でしょう。気持ちはわかります」
ついかばうような口調になり、みひろはコメントした。慎は無言。腕時計を覗いてから「外で待ちましょう」とみひろを促し、ビルを出た。
ビルの斜め向かいのカフェで待っていると、星井は一時間ほどでビルから出て来た。
「えっ!?」
ぎょっとして声を上げ、みひろは口に運びかけていたコーヒーカップをソーサーに戻した。
カフェの窓越しに確認した星井は、さっきまで無造作に後ろで束ねていた長い髪を下ろしていた。それはいいのだが毛先五センチほどをきつくカールさせ、後頭部の髪を大きく膨らませている。いわゆる盛り髪というやつで、気分転換にしてはかなり過激。しかもナチュラルメイクで服装も地味なブラウスとスカートなので、ヘアスタイルとのギャップがすごい。
慎に促され、みひろはカフェを出た。星井は駅前の繁華街を進み、また一軒のビルに入った。後からみひろたちも入ったが、今度はエレベーターに乗った形跡はない。では一階の店かと傍らを見ると、ドアが一つ。黒いガラス製で、目の高さに金色の塗料で「CLUB G-RUSH」と書かれている。傍らの壁には、派手なメイクに盛り髪の女の顔写真が「有紗(ありさ)」「くるみ」「星里奈(せりな)」といった源氏名入りで並んだ看板が取り付けられていた。
うろたえ、みひろは看板と慎を交互に見た。
「ここっていわゆる」
「キャバクラですね。ちょうど開店時間です。入りましょう」
「はい!?」
みひろは再び声を上げたが、慎は構わず金属製のバーを摑んで店のドアを開けた。
「いらっしゃいませ」
ワイシャツに蝶ネクタイ、黒いベスト姿のウエイターの若い男が笑顔で進み出て来た。
「二人です。できるだけ奥の席に。ここは女性客も大丈夫ですよね?」
「はい。どうぞこちらへ」
慎の問いかけにウエイターは頷き、みひろにも会釈して店の奥に進んだ。
光量を落としたシャンデリアが照らす店内は複数のコーナーに区切られ、それぞれに黒い人工皮革のソファとテーブル、その向かいに丸椅子が置かれている。他に客はおらずがらんとして、ボリュームが大きめのJ-POPが流れていた。
流詩哀のゴージャス版って感じ? 出入口近くにカウンターバーもあるのを確認しながらみひろは思い、ウエイターと慎の後ろを進んだ。
奥まった席に案内され、慎とみひろはソファに座った。ダークスーツ姿の別の男が寄って来てメニューのようなものを差し出そうとしたが、それより早く慎は告げた。
「取りあえず一セット、ビールで。指名はないので、女性はお任せします」
「かしこまりました」
貼り付けたような笑みで会釈し、スーツの男とウエイターは席を離れた。
「星井さんは、この店に入ったんですよね? 飲みに来たんじゃないとしたら」
腰を浮かせて店内を見回し、みひろは問うた。スラックスの長い脚を組み、慎が返す。
「働いているんでしょう。星井は夜勤の日以外は、ほぼ毎日定時の午後五時に日本橋署を退署しています。しかし独身寮の玄関の防犯カメラを確認したところ、半年ほど前から帰寮は門限の午前零時ぎりぎり。しかも明らかに酔っていたり、派手な髪型や化粧をしていることが多かった」
「バイト、ていうか副業でキャバクラ嬢をしているんですか? あんなに真面目で清純そうなのに」
「いらっしゃいませ。雅(みやび)で~す!」
「こんばんは~。ティアラです」
明るく媚びを含んだ声とともに、ソファに若い女が二人近づいて来た。どちらも派手なメイクに盛り髪、露出度の高いドレス姿だ。
みひろが返事をする間もなく、雅とティアラは「やだ。イケメン!」「彼女さんですか? 羨ましい~」とハイテンションで語りかけ、みひろと慎の隣に座った。ウエイターも来て、テーブルにビールの瓶とグラス、おしぼりなどを並べる。
慎は雅たちに「自分たちは職場の上司と部下。彼女の社会勉強のためにここに来た」と説明し、みひろもそれに調子を合わせた。四人でどうでもいい話をしながらビールを飲み、追加で頼んだ焼酎のソーダ割りと生ハムとチーズの盛り合わせなどを飲み食いしているうちに他の客も来て、店内は賑やかになった。そして四十分ほど経った頃、店の奥から星井が出て来た。カールした毛先と盛り髪はさっき見た通りだが、オフショルダーのミニ丈の白いドレスに着替え、メイクも他のキャバクラ嬢と似たようなものに変わっている。みひろは呆然としつつ、最初に面談した時の「メイクに気合いを入れたら別人のような華やかな美女になりそう」という自分の読みは間違っていなかったと確信した。
「彼女は?」
客に笑顔で挨拶をしながら少し離れた席に着く星井を指し、慎が訊ねる。振り向いて、雅は答えた。
「心愛(ここあ)ちゃん。お客さん、ああいう子がタイプ?」
「いえ。いつから働いているんですか?」
「半年ぐらい前かな。でも毎日じゃなく、週に二、三日。最近は休んでばっかりで、辞めたのかと思ってたけど……ちょっと。うちらじゃ不満なの? あり得なくない?」
大げさに顔をしかめ、雅が慎の肩を叩く。「ホントホント」とティアラが同意し、つられてみひろも頷いた。「そういうことではなく」と真顔で否定してから、慎は続けた。
「知人が夢中になっているキャバクラ嬢に、そっくりなんです。ちなみにこれが知人」
言うが早いかスマホを出して操作し、画面を雅とティアラに見せる。みひろの視界にも入り、それが黒須の顔写真だとわかった。
「やだ。クロちゃんじゃん!」
まず雅が声を上げ、ティアラも「ホントだ」と目を見開いた。すかさず、慎はさらに問うた。
「ご存じですか。ここの常連?」
「少し前はほとんど毎日来てたけど、最近は全然。そういやクロちゃんが来なくなった頃から、心愛ちゃんの休みが増えた。えっ、なんで? あの二人なんかあるの?」
好奇心で目を輝かせた雅が慎に問い返した時、「失礼します」とスーツの男がやって来て雅になにか囁いた。「ちょっとごめんなさい」と雅が席を立ち、スーツの男はティアラの耳元にもなにか言う。その隙に、みひろは慎に小声で問いかけた。
「いまいち飲み込めないんですけど、思わぬ事態になってます? でも室長は、こういう事態になるのを予想してましたよね?」
「はい」
「それなら早く言って下さいよ。私にも、心構えってものが」
「僕は、予想や憶測でものを言わない主義なんです」
すました顔で返し、慎はスマホを持ち上げて前方にかざした。心愛こと星井の姿を撮影するのだろう。呆気に取られてからうんざりし、みひろは、
「そうっすか」
と投げやりに返してテーブルの上のグラスを取り、焼酎のソーダ割りをごくりと飲んだ。