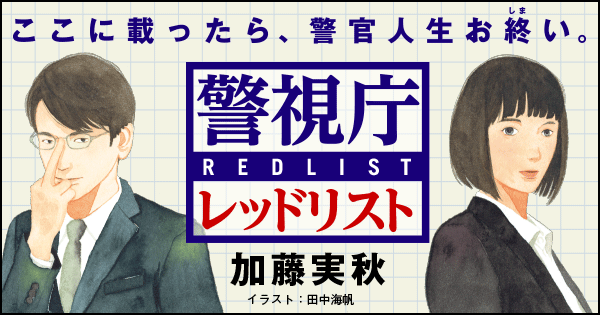〈第3回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

民間企業出身のみひろは、調査に躊躇する。
8
「非違事案報告書
発生部署:警視庁第一方面日本橋署交通課交通総務係
当事者の氏名:黒須文明 性別:男 年齢:39 階級:巡査部長
非違事案の行為区分:私生活上の行為(不適切な異性交際)
発覚の端緒:職場改善ホットラインへの内部通報。聞き取り調査の後、日本橋人形町一丁目路上にて行動調査に着手。以後、日本橋署交通課交通総務係・星井愛実巡査とのラブホテル「アネモネ」(東京都台東区浅草二丁目)に於ける複数回の接触を確認。黒須、星井への聴取の結果、事実関係を是認」
そこまで書いて手を止め、慎は報告書を見直した。完璧で、記入漏れも誤字脱字もない。報告書は表組になっていて、他に「当事者の動機」「発生から報告までの経過」「被害状況」「逮捕・告訴の必要性の有無」「非違事案が防止できなかった管理上の問題点」等々の項目が並んでいる。
再びキーボードを叩き始めようとして、ふと慎の目がノートパソコンの液晶ディスプレイの一カ所に止まった。打ち込んだ文字列の、「日本橋人形町」という住所だけが浮き上がって見える。同時に胸が騒いで強い緊張も覚え、慎は液晶ディスプレイを凝視しながら脳をフル回転させた。
見逃しがある。重要事項の何かだ。緊張はさらに強まり、慎は右手の中指でメガネのブリッジを押し上げた。記憶を探り、浮上した事柄を秒速で精査していった。
わかった。重要事項ではなく、最重要事項だ。閃き、頭の中が輝くように明るくなったのも束の間、焦燥感と後悔にかられる。
異動に伴う些末な業務が重なり、チェックに抜かりがあった。いや、言い訳より善後策だ。今からでも処置は可能か、あるいは──。
「なんだかなあ」
ため息交じりで力の抜けた、それでいて独り言というにはボリュームが大きすぎる声に慎の思考は中断された。顔を上げ、向かいの机に問いかけた。
「どうかしましたか?」
すると三雲みひろも顔を上げ、こちらを見た。
「あれ。私、声に出しちゃってました?」
「ええ。はっきり」
「すみません。なんかあれこれ考えちゃって」
眉根を寄せて会釈をしたが、さしてすまなくは思ってなさそうだ。その証拠に、みひろの机の上にもノートパソコンが載っているが、さっきからキーボードを叩く音はほとんど聞こえてこない。つまり、報告書の作成は進んでいないということだ。警視庁別館四階の職場環境改善推進室、時刻は午後二時前。今朝日本橋署で黒須、星井と話した後ここに戻り、直ちに監察係に提出する報告書の作成に取りかかった。
「黒須たちが気になりますか」
笑みを作って問いかけると、みひろは「はい」と頷いた。一緒に厚めの前髪を眉の上で切り揃えた黒い髪も揺れる。ショートボブというのか、似たようなヘアスタイルの女性を街中で見かけるが、小柄で童顔のみひろは昭和の小学生に見えなくもない。
「二人は、この後どうなるんでしょうか」
黒目がちの丸い目をこちらに向け、みひろが訊ねた。慎は即答する。
「懲戒処分は確実です。懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の四ランクがあり、星井は戒告で済む可能性が高いですが、黒須は不倫に加えてその関係を強要、すなわちセクシャルハラスメント行為も認めているので減給、または停職でしょう」
「どちらも赤文字リスト入り?」
「もちろん。加えて、罰俸転勤です」
慎が首を大きく縦に振ると、みひろは前のめりになって喋りだした。
「黒須は当然の結果だし、星井さんは気の毒だけど関係が断ち切れるのはよかったんじゃないかと思います。でも、気になることがあって。関係が始まってすぐに後悔して、星井さんは嫌々黒須と会っていたんですよね? その割に、二人が会う頻度は増えていたんです。黒須が『始めのうちは週に一度ぐらいだったけど、最近は二、三回』って言っていたでしょう。矛盾していませんか?」
「回数は問題ではありません。一度でも規則に反する行為を行えば、処分の対象になります」
「他にもあるんです。室長に不倫の強要は事実か訊かれた時の、黒須の目。怯えたり絶望したりしていた一方で、腹が決まってるっていうか、すごい覚悟みたいなものが感じられたんです。おかしくないですか?」
問いかけには答えず、慎は横を向いてメガネにかかった前髪を搔き上げた。
「異動先には部下が一人」と聞いた時、定年間近のやる気も能力も著しく低い、いわゆる「ゴンゾウ」と呼ばれる職員だと思った。ところが現実は二十代の女性巡査で、職場改善ホットラインの優秀な相談員。身上調査票によると、「死にたい」と電話をして来た職員からその原因が上司の言葉の暴力だと聞き出し、同時に自殺も思いとどまらせたことがあるという。だが組んで仕事をしてみれば感情論や主観ばかりを訴え、一年近く勤務しながら警察という組織の基本を理解していない。これならゴンゾウの方がマシだったと思わなくもないが、やるべきことをやるだけで、慎の職務への熱意と義務感は変わらない。
こちらが醸し出す空気に気づいたのか、「生意気言ってすみません」と頭を下げたみひろだったが、「でも」と言ってこう続けた。
「調査対象者にもう少し気を遣うっていうか、話ぐらい聞いてあげてもいいんじゃないですか。黒須は犯罪者じゃありませんよ」
「犯罪者ではありませんが、規則違反者です」
すかさず慎が返すと、みひろは元の勢いに戻って話しだした。
「なら、話を聞かなくてもいいんですか? 室長は規則違反者の気持ちには関心がないんですか? なぜ規則を破るに至ったのか、知りたいとは思いませんか?」
「思いません。いかなる心情を以てしても、規則の遵守を免除される理由にはならないからです」
「お疲れ~。調子はどうかな」
ノックと同時にドアが開き、豆田が部屋に入って来た。緊迫した空気と、それぞれの席に着いて深刻な顔で相対する慎たちに、たちまち豆田がうろたえる。
「えっえっ。どうしたの? この空気、なに?」
机に歩み寄り、慎とみひろの顔を交互に見た。手には差し入れのつもりか、饅頭らしき菓子折を持っている。豆田を無視し、みひろは言った。
「『なぜ』『どうして』を理解しなければ、また同じ規則違反が起こります。取り締まって赤文字リストに名前を載せて排除するだけでは、根本的な解決にはなりません。失敗に学ぶというのは人としての基本だと思うんですけど、それは元監察係員としての沽券(こけん)に関わるんでしょうか」
「元監察係員」を強調された気がして、慎はとっさに言葉を失う。すかさず、豆田が言った。
「三雲さん。あなたにそんなことを言う資格はないよ。身の程を知りなさい。ちなみに、上司の職務上の命令を厳守するのも『警察職員の職務倫理及び服務に関する規則』に定められたルールだからね」
声と表情を厳しいものに変え、みひろを見下ろす。と、勢いよくみひろが立ち上がった。ぎょっとして、豆田が後ずさる。強い目で豆田、慎の順に見てみひろは言った。
「わかりました。申し訳ありません。でも警察って規則はすごく大事にするけど、人の気持ちを無視するのは平気なんですね」
それからもう一度「すみません」と言って頭を下げ、部屋を出て行った。
その日の夕方、慎は警視庁本庁舎の十一階にいた。異動に伴う手続きのために、人事一課の庶務係を訪ねたのだ。
用事が済み、慎は庶務係を出てエレベーターホールに通じる長い廊下を進んだ。少し前までは、監察係の係長として幾度となく行き来した廊下だ。しんとして張り詰めた空気にも、傍らの窓の外に広がる霞が関のビル群にも変わりはない。と、廊下の先から四、五人の男女が歩いて来た。全員制服姿で、先頭を行くのは小柄だが眼光が鋭く、身のこなしにも隙のない五十代前半の男。監察係の首席監察官・持井亮司(りょうじ)だ。持井は斜め後方を歩く部下が差し出す書類に目を通し、深刻な顔でなにか指示している。
持井たちと接近し、慎は立ち止まって廊下の隅に避けた。背筋を伸ばして頭を下げ、持井を待つ。どやどやという足音とともに、男女が慎の前にやって来た。
「阿久津じゃないか。どうだ、職場環境改善推進室は」
足を止め、持井がこちらを振り向く気配があった。長い名前をすらすらと口にできるのは、慎を異動させるために自分で作った部署だからだろう。
「お陰様で順調です。やり甲斐のある職務を与えていただき、ありがとうございます」
頭を下げたまま、慎は返した。視界に、持井の左胸に光る警視正の階級章が映る。
「それはなによりだ。きみなら、なくてはならない部署に育ててくれるはずだ。なあ?」
問いかけて、持井は後ろを振り返った。「はい」「もちろんです」、そう賛同して頷くのは、慎のかつての同僚と部下。明るく力強い声の裏に戸惑いと気まずさ、憐憫(れんびん)の情が感じ取れた。
「ありがとうございます」と再度礼を言い、慎は話を変えた。
「その後、中森の捜索はいかがですか? 捜査一課(ソウイチ)に協力をあおいで特命追跡チームが結成されたと聞きました。加えて、総務部の情報管理課からもデータが抜き取られるまでの流れを──」
「その件なら、きみの心配には及ばない。すべてこちらで対処し、解決する」
威圧感を含んだよく通る声で、持井は告げた。慎は口をつぐみ、場の空気がぴんと緊張する。と、持井は口調を和らげてこう続けた。
「優秀な監察官であるきみに、部下の犯罪の責任を問うのは辛かった。しかしそれが我々のルールであり、きみはそれに従った。中森の件は我々に任せて、新たな道を歩んでくれ。部下もできたんだろ? 型破りの、なかなかユニークな女性らしいじゃないか。『失敗に学ぶのは、元監察係の沽券に関わるのか』と迫ったとか。実に頼もしい。きみと名コンビになること間違いなしだな」
顎を上げる気配があり、持井はいかにも楽しげに笑った。廊下にその声が響き、慎のかつての同僚と部下たちの乾いた笑いも重なる。
無言のまま慎が頭を下げ続けていると、「じゃあ」と言って持井は歩きだした。かつての同僚と部下も続く。と、最後尾の一人が立ち止まり、こちらを振り向いたのがわかった。視界の端に、ローヒールの黒いパンプスが映る。本橋公佳巡査部長だ。
躊躇するように体を動かした後、本橋は慎に向かってぺこりと頭を下げた。それから身を翻し、慌ただしく持井たちを追いかけて行った。
持井たちの気配が完全に消えるのを待ち、慎は体を起こした。中森に関するやり取りは想定内で、心は静かだった。みひろを揶揄(やゆ)した「型破りの、なかなかユニークな女性」もその通りで、これといった感想はない。「失敗に学ぶ~」云々(うんぬん)も豆田から聞いたのだろう。しかし話に出たせいで、さっきのみひろの言葉を思い出した。
「星井さんは嫌々黒須と会っていたんですよね? その割に、二人が会う頻度は増えていたんです」「矛盾していませんか?」「黒須の目」「腹が決まってるっていうか、すごい覚悟みたいなものが感じられたんです」。ふと、慎は胸に違和感を覚えた。続いて関係を強要したのかという自分の問いかけに「事実です」と答えた時の黒須の眼差しと、「すごく辛かった」と涙ぐみながらも安堵する星井の姿も脳内に再生される。違和感はさらに膨らみ、それを具現化するために勝手に頭が回り出す。
緊張と興奮を覚え、慎はエレベーターホールに向かった。早歩きだったのが小走りになり、鼓動が速まるのがわかった。