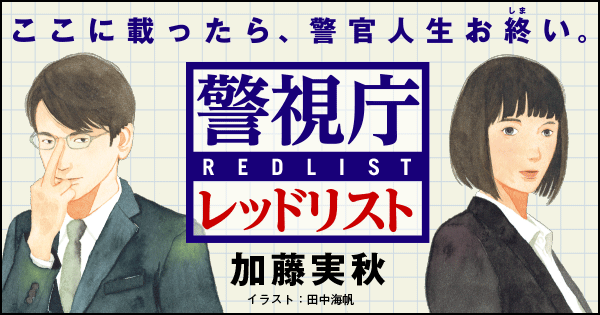〈第9回〉加藤実秋「警視庁レッドリスト」

奥多摩に向かった。
2
現場で少し休んでから、這うようにして斜面を登り脇道を戻った。車に辿り着き、中で横になっていたら間もなく吐き気は治まった。
「大丈夫ですか?」
慎が倒していた助手席を起こすと、みひろは訊ねた。運転席に座り、ファイルと書類を手にしている。
「はい。見苦しいところをお見せしました」
そう返し、慎はスーツの乱れを整え、緩めていたネクタイを締め直した。腕時計で確認した時刻は正午過ぎだ。ファイルを閉じ、みひろは首を横に振った。
「いえ。室長、ひょっとして現場で遺体を見たのは、さっきが初めて?」
「ええ」
メガネにかかった前髪を払いながら答えると、みひろは「やっぱり!」と声を上げた。
「室長が休んでいる間に、柿沼さんと話したんです。柿沼さんは室長のことを、『卒配で交番勤務を一年ぐらいやって、その後はずっと本庁の管理部門にいたはず。絵に描いたような警察官の出世コース』って言ってましたけど、本当ですか?」
一瞬躊躇したが出世コースを含めその通りなので、慎は「はい」と頷いた。
世間では警察官はみんな刑事になりたいものと考えている人も多いが、現実はそうでもない。配属先として最も人気が高いと言われているのが警務部で、これは警察の出世のシステムと大きく関わっている。
ノンキャリアの警察官が昇任するには年に一度行われる昇任試験に合格する必要があるが、地域課や刑事課など多忙を極める部署にいては試験勉強の時間は満足に確保できない。一方警務部はほぼ定時で帰宅でき、休日出勤もほとんどない。加えて警務部は「警察の頭脳であり神経」と呼ばれ、配属されれば経歴・人格ともに秀でた警察官だという証明になる。中でも秘匿性が高く重要な職務を担う人事課は、エリート中のエリート、幹部候補が集まる部署という位置づけだ。
「じゃあ、殺人とか強盗とかの事件を捜査したり、犯人に手錠をかけた経験もなし?」
みひろはさらに質問し、慎は再度頷いた。
「ふうん。世間的なイメージとはずいぶん違いますね。『おまわりさん』なのに」
最後の一フレーズは思わず本音が漏れたという感じだが、慎は気にならない。殺人や強盗の捜査経験はないが、監察官として身内の不祥事の調査を行ってきたし、むしろそれが警察組織の中枢にいることの証だと自負している。
だが、さっきの一件は醜態だ。後悔の念に駆られるのと同時に、遺体の記憶も蘇る。慎は急いで助手席の脇に置いたペットボトルを取り、ミネラルウォーターを飲んだ。少し前にみひろが「未開栓なので」と、自分用に買ったものをくれた。何らかの気配を察知したのか、みひろは言った。
「でもまあ、気にすることないですよ。遺体はなかなかの状態でしたから……そうだ。今度腐敗した遺体を見る時は、鼻じゃなく口で呼吸をすると臭いがマシになりますよ」
「三雲さんも遺体を見たんですか?」
驚いて訊くと、みひろは当然とでも言いたげに、「はい」と首を縦に振った。
「あ、『なんで平気だったんだ?』って思いました? 実は私、以前事件や事故現場も請け負う清掃会社でバイトしてたんです。社内結婚したカップルの奥さんが産休で、そのピンチヒッターで雇われました。旦那さんはすごいイケメンだけど無愛想で、他の人もキャラが濃かったなあ。御茶(おちゃ)ノ水(みず)の『クリーニングサービス宝船(たからぶね)』っていうんですけど、知ってます?」
みひろは調子よく捲(まく)し立てる。
「事故や自然死、自殺がほとんどでしたけど殺人事件の現場もあって、遺体も時々見ました。私も初めのうちは吐きまくってたし、ホント、気にすることないですよ」
慎はさっきの醜態がさらに悔やまれ、加えて十も年下の部下に二度も「気にすることないですよ」と上から目線で慰められたのがショックだった。またもや何らかの気配を察知したのか、みひろは「すみません」と言って一旦口をつぐみ、改めて慎を見た。
「着ているもので気づいたんですけど、遺体の男性は『みのりの道教団』の信者ですね」
「えっ?」
我に返って振り向いた慎の眼前に、書類が一枚突き出された。中央に大きな写真があり、広い部屋で正座をした大勢の男女が写っている。全員みぞおちのあたりで両手を重ねて俯いているので顔は見えないが、生成り色で変わったデザインの長袖シャツと長ズボンを身につけていた。
今朝、慎とみひろが職場環境改善推進室に出勤して間もなく豆田益男(まめだますお)が現れ、新たな調査事案のファイルを渡された。数日前、職場改善ホットラインに「奥多摩署の柿沼也映子は、みのりの道教団という新興宗教の信者だ」と内部通報があったという。慎はただちにみひろに出動を命じ、車で一時間半かけて奥多摩までやって来たのだ。
と、車の外で動きがあった。脇道から現場にいた警察官たちが出て来る。そのうちの二人は担架を運搬していて、上には遺体を納めた黒い袋が載せられていた。
若い警察官がワンボックスカーの荷室のドアを開け、遺体は車内に運び込まれた。肩に布製のバッグをかけた柿沼が荷室に乗り込み、それを菊池が後ろから見守る。「行きましょう」と告げて慎は車を降り、みひろは書類をファイルに戻して後に続いた。
「具合はどうですか? 無理をお願いして申し訳ありませんでした」
歩み寄って行くと、菊池が振り返って頭を下げた。慎も会釈し、返す。
「いえ。遺体は解剖に回すんですか?」
「ええ。柿沼が運びます。我々は署に戻りますが、どうします? わざわざおいでいただきましたが、今日は調査に協力できません。何しろ人手が足りないので」
再び申し訳なさそうに眉を寄せ、菊池は左右を見た。警察官たちはそれぞれパトカーやセダンに乗り込み、山道を走りだす。柿沼はワンボックスカーの荷室で、若い警察官となにか話していた。
「承知しています。明日また来ますので、調査は状況を見てお願いします」
微笑みとともに慎が告げると、菊池はほっとして「わかりました」と頷いた。それから菊池はパトカーの後部座席に乗り込み、若い警察官がワンボックスカーの荷室を降りてパトカーの運転席に乗った。パトカーが走りだし、慎はワンボックスカーに歩み寄った。みひろもついて来る。
「先ほどは大変失礼しました」
慎は荷室から降りて来た柿沼に一礼した。柿沼は荷室のドアを閉め、言った。
「意見は? まだ聞いてないけど」
一瞬面食らったが、慎は遺体の記憶を蘇らせた。
「死斑(しはん)と角膜の混濁、腐敗の進行状況から、死後推定三十六から四十時間。顔面の骨の一部が露出していますが、蛆蝕(そしょく)ではなく野生動物に食い荒らされたものと考えられます」
「警察学校の法医学の教科書通りだね」
柿沼は返し、表情を動かさずに慎を見た。とっさに言葉に詰まると柿沼は、「じゃあ」と言って歩きだした。みひろが「お疲れ様です」と会釈する中、柿沼は運転席に乗り込んでワンボックスカーを発車させた。山道を遠ざかって行く白い車体を目で追う慎に、みひろが問う。
「本庁に戻りますか?」
「いえ。柿沼の行動確認に着手します。車の行き先は三鷹(みたか)市です。多摩地区の解剖業務を担当する大学病院があります」
答えながら車に歩み寄り、運転席のドアを開けた。
「私が運転しますよ。無理しないで下さい」
慌ててみひろも車に近づいて来たが、慎は構わず運転席に乗り込んでエンジンをかけた。