連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:国谷裕子(キャスター)
今年三月、日本のジャーナリズムを代表する番組「クローズアップ現代」が二十三年間の歴史に幕をおろしました。第一回の放送から休みなくキャスターを務め、タブーなきインタビューで私たちを唸らせ続けた国谷裕子さんに、女性が活躍できる社会をつくるにはどうしたらいいのか。お話を伺いました。
第四回
女性活躍の壁は「粘土層」?
ゲスト 国谷裕子
(キャスター)
Photograph:Hisaaki Mihara

国谷裕子(左)、中島京子(右)
中島 私は「クローズアップ現代」の大ファンで、国谷さんとお話ができるのを楽しみにしていたんです。いまでも、夜七時半になるとつい習慣でNHKにチャンネルをあわせちゃう。でも、そこには、もう国谷さんはいない。ぽっかり穴があいたようです。
国谷 ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると、うれしいです。
中島 「クローズアップ現代」でのインタビューを拝見していると、国谷さんにはまったくぶれがない。聞きたいことにズバッと切り込んでいく印象があります。
国谷 とくに政治家など権力をもった方々には、なるべくストレートに聞くようにしています。メディアには権力をチェックするという役目もありますから、その点では空気を読んだり、配慮したりする必要はないと考えています。
中島 権力者との関係でいえば、いま「報道の公平中立性」が議論を呼んでいます。国谷さんは、報道のフェアネスについて、どう考えていらっしゃるのですか。
国谷 メディアの影響力は大きいので、ひとつの視点から物事を伝え続けると「みんながそう言っている」という世論ができ上がります。そうして同調圧力が強くなると誰も反対意見が言えなくなり、少数派が排除されてしまいます。だから、ある問題について考えていくときに、多数派のAと少数派のB、相反するふたつの意見があった場合、両方の意見を公平に扱うことも大切ですが、それだけが中立的な報道だとは思わないのです。視聴者には見えにくくなっているBの意見にスポットを当てる必要がある場合もある。そのときには、「今回は少数派の意見ですがBという視点からお伝えします」と宣言したうえで、番組に入っていく。それも視聴者に対するフェアネスだと考えています。
私は悪いロールモデル

国谷 NHKでは、最前線で働いている女性の姿は多いほうだと思います。しかし女性管理職はまだ八パーセントくらい。じつは、「クローズアップ現代」では番組スタート以来、番組の試写などでは私が唯一の女性だというときが多かったのです。担当者全員がより良い番組にしたいという気持ちでつくっているので、最後の最後までとことんこだわり続ける。ぎりぎりまで取材を続けるし、素材を集めようとする。追い込みに入ると、週に二、三日徹夜するのが当たり前でした。
中島 それは大変ですね。まさに体力勝負です。
国谷 私も長時間を厭わず働いていたので、後に続く女性たちにとって、ほんとうに悪いロールモデルだったと反省しています。
中島 いい番組をつくりたいという思いが強ければ強いほど、労働環境とのバランスをとるのが難しい。
国谷 そうなんです。だから小さなお子さんのいる女性たちにとっては、決して働きやすい環境だとは言えません。女性たちはあえて管理職になる道を選ばないことも多いので、女性目線の番組提案も出てきにくいのです。
中島 国谷さんご自身は、そういう女性視点で企画を提案されたことはあるのですか。
国谷 二〇一〇年にAPEC(アジア太平洋経済協力会議)で、「女性と経済」をテーマにした国際会議が開催されたときに、経済産業省の方からモデレーター(司会者)をやってほしいという依頼がありました。恥ずかしいことに、それまで「女性」と経済の関わりについて深く考えたことがなかったのです。
中島 それは意外ですね。
国谷 そこでAPECに行く前に、WLN(ウーマンリーダーズネットワーク)という世界中の女性リーダーたちが集まる会議に参加しました。
女性が経営者になれば、女性にとってより働きやすい環境が生まれる。女性が商品を企画したほうが、より競争力のある商品が誕生する。女性という埋もれた資源をもっと掘り起こして、その能力を花開かせることができれば、経済がより強くなる。もっと暮らしやすくなる。貧困もなくせるのではないか。そういうウィンウィンの処方箋が熱く語られていました。
中島 具体的にはどんな例があるんですか?
国谷 たとえばオーストラリアで炭鉱を経営している女性の話。女性が炭鉱を経営していることじたい、すでに驚きでしょう。しかも彼女がその炭鉱を経営したことによって、女性の雇用がすごく増えました。彼女はトラックの運転席のレバーの位置やシートの高さなどを女性の体形にあわせて、すこし改良したのです。
中島 たしかに石炭を掘り出すのも運ぶのも機械だから、女性でもできることはたくさんありそうですね。
国谷 それまでは、炭鉱は女性が働く場所ではないと考えられていました。でも女性が経営者になって、その地域で働きたいという女性たちの声を聞いて、どうやったら自分の会社で雇用を増やせるのだろうと考えた。そうだ、仕事を女性にあわせればいいんだ、と。
中島 まさにコロンブスの卵ですね。
国谷 「クローズアップ現代」でも、失われた十年とか十五年とか言われてきた日本経済の閉塞感を打破するために何か鍵となるものはないだろうかと考えていました。しかしなかなか突破口を見いだせないままでいたのですが、そこではじめて女性という切り口があることに気づきました。これだけニュースをやっていて、しかも女性である自分がそのことにまったく気がつかなかったことに衝撃を受けました。
中島 その経験が、その後の番組に生きてくるわけですね。
女性活躍の邪魔をする「粘土層」

中島 女性として初めてIMF(国際通貨基金)のトップに立ったラガルドさんですか。それはすごい!
国谷 海外の女性リーダーの方々は、他国の女性リーダーたちと交流を深めるのが自分たちの役割だと思っているのでしょうね。メンバーひとりひとりと積極的に意見交換されていました。
中島 女性リーダーたちと出会うことで、国谷さんの歯車が回り始めたんですね。
国谷 その席でラガルドさんが「IMFでは、女性がもっと活躍できるようになれば、日本の経済は成長するというレポートを出すことになりました。その発表をあなたの番組でしたい」と提案してくれたのです。
中島 うれしい急展開ですね。
国谷 はい。二〇一二年十月に「女性が日本を救う?」というタイトルで七十三分のスペシャル番組をつくりました。当時の経済同友会のトップ長谷川閑史さんにも参加していただいて、IMFのレポートをもとにラガルドさんに熱っぽく語ってもらいました。
中島 日本ではまだまだ女性の活用が遅れています。長谷川さんにとっては、プレッシャーだったんじゃないでしょうか。
国谷 経済同友会の中にも女性の活用について意識の高い方々がいて、すでに各加盟会社の実態調査などを行っていました。少子高齢化で、よい人材を獲得することが難しくなってきて、企業のトップの意識も変わってきているのです。女性の働きやすい会社じゃないといい人が来ない。だから女性がちゃんとキャリア形成できるような仕組みをつくろう、と。しかしトップがそう旗を振っても、なかなか浸透しないのが現実です。
中島 経済同友会としては、各企業が女性活用を推進するきっかけとしてIMFという外圧も欲しかったんですね。でも、日本企業で女性の活用が進まない原因は、どこにあるのでしょう。
国谷 ひとつには、企業の真ん中に、水を通さない「粘土層」があるからです。
中島 粘土層ですか?
国谷 育児にも参加しない、家事もやらない、長時間労働が当たり前の中間管理職の男性たちのことを、私たちは粘土層と呼んでいるのです。
中島 いいネーミングですね。私の中で大ヒットです(笑)。
国谷 今年四月に、「女性活躍推進法」が施行されて、従業員が三百一人以上の企業に対して、女性の管理職の割合など、具体的な目標を出すことを義務付けました。しかし、たしかに法律はできたのですが、自分たちの手の届く範囲だけの目標しか出してない企業もあるのが実情です。
中島 政府も女性活躍社会と声をあげはじめて、そういう社会になっていくのかなと思っていると、男性の政治家たちは同じ口で「はやく子どもを産め」など、とんでもない女性差別的な発言をします。ネットで「保育園落ちた日本死ね」が話題になったときも、安倍首相はじめ保守系男性政治家は「本当か確認しようがない」「誰が書いたんだ」など、心ない発言を繰り返しました。
国谷 日本には、本当の意味で男女平等の意識がまだ根づいていないのだと思います。日本女子大現代女性キャリア研究所所長の大沢真知子教授が行ったアンケート調査によると、二十五歳から四十九歳までの高学歴の女性たちの中で、やる気と能力の高い人ほど離職する割合が高いという結果が出ています。
中島 社会的には大きな損失ですよね。「活躍しろといっても、活躍できないじゃない」というのは、本当の心の叫びだと思うんです。
国谷 女性の働き方に関しては、かなり進んでいる企業の人事部の方のお話を伺ったことがあります。男女は平等だというスタンスでしたが、女性たちだけに向かって話すときは、「責任ある仕事を任されるようになった頃、女性はちょうど出産や育児の時期と重なります。入社した当時から男性の一・五倍働くつもりでやりなさい」と励ますそうです。
中島 うーん、それ、どうなのかなあ。真面目な女の人ほど、頑張りすぎて結局挫折しちゃうってことにならないかなあ。
国谷 女性が働きやすい企業だといわれている資生堂では、育児のため短時間勤務をしているときに管理職に登用された女性社員がいます。資生堂は女性管理職の割合も高くて、二十七パーセント。短時間勤務中の登用はまれで、彼女も会社から強いメッセージを送られたのだと感じたそうです。
中島 資生堂のような企業がどんどん増えてくると、日本もまだまだ復活の望みはありますね。
国谷 本当に。だけど彼女も最初は管理職にはなりたくないと思っていたそうです。でも管理職になってみると、企業内でも社会でも風景が違って見えたそうです。いまでは、なってよかったと、おっしゃっていました。
女性リーダーが社会にイノベーションを起こす

国谷 ロールモデルがないから、自分がその地位になったときのことを想像できないのです。でも、マネジメントの立場に立ってみると、会議の時間も自分で決められる。いままで不合理だと感じていたさまざまなことを女性目線で改善することができる。
中島 『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』というドキュメンタリー映画のエピソードでアイスランドが経済破綻状態となったとき、四つあったメジャーバンクの内三つが潰れた。それはすべて男性頭取の銀行でした。男性たちはあまりにもハイリスクハイリターンを望み過ぎて……。唯一生き残った銀行の頭取は、女性でした。
国谷 同じようにリーマン・ショックのときにも、もし経営陣に女性がいてリーマンブラザーズ&シスターズだったら、金融クライシスは起きなかったのでは、と半ば本気でいわれています。
中島 女性が経営陣に入ると男性とは違う発想が生かされる。山の頂上にたどり着く道はひとつじゃないことが示される。ダイバーシティ(多様性)が重要なのですね。
国谷 シェリル・サンドバーグさん(Facebook 社COO/最高執行責任者)ですら、「重要な事はボーイズクラブで決めてしまう」と嘆いていました。
中島 ボーイズクラブって、何ですか。
国谷 例えば仕事帰りの飲み会の席で、「次の面白い仕事を誰に任せよう」という話がいつの間にか決まっている。ビジネスのノウハウや人脈についても、この人はここと仲が良くて、こっちは仲が悪いからこうした方がいいなど、すごく大事な情報がやり取りされる。でも、女性たちは育児や家事で忙しいから、飲み会や集まりにもなかなか参加できない。
中島 なるほど、重要な情報は男性だけの課外活動、つまりボーイズクラブだけでシェアされてしまう。
国谷 ボーイズクラブだけで話していると、やはりボスの言うことを聞かなきゃいけないという雰囲気になるでしょう。まず組織の論理を優先して考える。
中島 女性たちは思ったことをぱっと言っちゃう。
国谷 ボーイズクラブの空気なんて、読んだりしない。
中島 たしかに。ボーイズクラブも粘土層なんですね。
国谷 シェリルが会議のためニューヨークの大企業を訪れたとき、その会社の男性CEO(最高経営責任者)にこのフロアの女性トイレはどこですかとたずねました。しかし、彼は知らなかったのです。CEOのオフィスのあるこのフロアには、ほとんど女性が訪れたことがないのだと思ったそうです。
中島 あ、フロア全体がボーイズクラブ的な雰囲気なんですね。居心地悪そう(笑)。

中島 最初は男ばかりだった「クローズアップ現代」に、ついに女性革命が起こったんですね。
国谷 女性活躍という掛け声で、社会からは背中を押されても、一歩踏み出せない人たちもまだまだ多いと思います。中島さんは作家になりたいという目標をずっと持っていて、それを実現されました。
中島 わたしの場合十代のときに作家を夢見てデビューが三十九歳ですから、ずいぶん寄り道回り道をしましたけれど。出版社で十年くらい編集者の仕事をやっていたので、頑張れば女性管理職の道もあったかも。でも、会社の中でキャリアを積んでいくことによろこびを感じられなくなって。やっぱり私はじぶんで書きたいんだと。
国谷 それでアメリカに行かれたのですか。
中島 占い師に手相を診てもらったら、あなたは会社を辞めるべきだといわれて……(笑)。運良く教師交換プログラムに受かったので、教育実習生としてアメリカの小学校に行きました。アメリカのよさは、「あなたは何がしたいの?」と聞いてくれるところ。「空手の先生を連れてきたい」「日本料理をつくらせたい」といってみたら、ぜんぶ「ゴーアヘッド」。どうしたら実現できるかを、ボスも一緒に考えてくれた。「やってもいいんだ」「やればできるんだ」と思ったのは大きな体験でした。日本は忖度社会なので、自分のやりたいことを「やりたい」と公言するのって、勇気がいりますよね。「責任ある地位につかせろ」と言うのも、女性にはハードルが高い。でも、そこを飛び越えていく女性が増えていくといいですね。
国谷 これからは政治の分野でも、行政の分野でも、企業の分野でも、トップに立つ女性たちが必ず増えてきます。社会的地位の高い女性たちがつながって、自ら仕事と子育てを両立できる社会をつくっていく。そういう家庭で育った次世代の子どもたちの意識は絶対に違うはず。まだまだ時間のかかるプロセスだと思いますが、そこから必ずイノベーションが起こります。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立、1996年にインターシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で第143回直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で第42回泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で第3回河合隼雄物語賞、第4回歴史時代作家クラブ作品賞、第28回柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で第10回中央公論文芸賞を受賞。
国谷裕子(くにや・ひろこ)
1957年大阪府生まれ。父親の転勤に伴い、高校時代まで米国、香港、日本で生活。1979年米国ブラウン大学卒業後、帰国。1981年、NHK「7時のニュース」英語放送アナウンサー、ライター。85年結婚し、夫の留学先の米国へ。衛星放送のNY発キャスターに。88年帰国、総合テレビ「ニューストゥデイ」、BS1「世界を読む」などを経て93年から今年3月まで、「クローズアップ現代」キャスターをつとめる。2011年日本記者クラブ賞受賞。2016年ギャラクシー賞特別賞受賞。
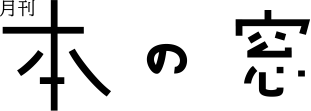
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2016/08/20)






