連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:ドリアン助川(詩人、作家、道化師)
作家であり、詩人であり、道化師、ミュージシャンであり、ラジオDJであり、俳優でもある。多彩な顔をもちながら、人間の本質をつくような「言葉」を「肉声」として表現し続けるドリアン助川氏のパワーの源に迫ります。
第十回
「怠慢のフィルター」が
やるべきことを選別してくれる
ゲスト ドリアン助川
(詩人、作家、道化師)
Photograph:Hisaaki Mihara

ドリアン助川(左)、中島京子(右)
僕にとっては、書くことイコール肉声だ
中島 初めてお会いしたのは、四年くらい前でしたね。ドリアンさんが自著の朗読会をされるというので、それを聴きに行ったんです。
ドリアン 御茶ノ水でやったときですね。お酒も飲める本屋さんでした。
中島 私もときどき、講演会などで作品の一部を読んでくださいと頼まれることがあります。照れくさいなあと思いながら読んでいたのですが、ドリアンさんの朗読を聞いたあとでは、私がやっているのはどうも朗読じゃないぞと(笑)。
ドリアン いざ読み始めると、つい観客不在になっちゃうんですよね。
中島 そうなんです。小学校の頃先生に「中島さん」と指されて「はい」と立ち上がって読んだときのような、つまらない読み方になっちゃうんです。私は作家なので、言葉は活字で読むという意識が強かったのですが、ドリアンさんの朗読では、声に出す、音になる、それが響いて立ち上がってくる。ドリアンさんの言葉によって紡ぎ出される世界が、ふわーっと広がる感じがしたんです。それ以来、朗読するときはこっそり家で練習してから出かけるようにしています(笑)。
ドリアン そう言っていただけるとうれしいですね。そもそも僕は、劇団の脚本や放送原稿、バンドの歌詞からものを書くことを始めました。ずっと声で届ける言葉を書いてきたので、常に「書くことイコール肉声」なんです。声に出して読むと、流れが悪いなぁとか、もっと簡単に表現できたのではないかなど、黙読だけではまったく気がつかない欠点が見えてきます。

ドリアン ありがとうございます。初めてフランス語の翻訳に取り組んだ作品なので、多くの人に読んでもらえたらいいなと思っています。
中島 『星の王子さま』は、子どもの頃から読まれていた大好きな作品だったんですか?
ドリアン じつは我が家は子ども用の本があまりない家だったので、最初に『星の王子さま』を読んだのもかなり大きくなってからだったと思います。
中島 えっ! そうだったんですか。でも翻訳をなさるくらいだから、フランス語には精通されていた……?
ドリアン それも、まったく(笑)。
中島 ますます、わからなくなってきた。
ドリアン 『星の王子さま』を翻訳するきっかけは、河瀨直美監督の映画『朱花の月』に俳優として出演させていただいて、二〇一一年のカンヌ映画祭に行く機会に恵まれたことです。若いときに行ったフランスにはあまりいい思い出がなかったのですが、映画祭の行われる五月は南仏が一番美しく輝く季節。魔法のような光に魅せられながら、俳優さんたちとカフェのオープンテラスでワインを飲んでいたんです。たまたま僕たちのテーブルの近くを通りかかったフランスの女性が、何か言葉を投げかけてきた。でもフランス語はまったくわからないから、英語で「いま、何と言ったんですか?」と尋ねたら、「あなた、今日こういう顔をして死んでいたわよね」と顔真似までしてくれた。
中島 うわぁ、すてき。彼女は、映画祭で『朱花の月』を観てくれたんですね。しかもカフェにいるのが、映画に出演していたドリアンさん本人だということにまで気づいてくれた。
ドリアン でも、彼女たちが去ったあと、悔しくて、悔しくて。
中島 えっ、どうして?
ドリアン もし僕がちゃんとフランス語を喋ることができたら、彼女に自分たちの映画だけではなく、他の作品の感想を聞いたりすることもできたでしょう。でも、ただの通りすがりの挨拶程度で終わってしまった。そこからフランス語をものにしてやろうという気持ちが芽生えてきたんです。帰国後すぐに、アテネ・フランセ(語学学校)の夏休みフランス語入門コースに申し込みました。でも夏休みだから、受講生の大半が女子大生。そのなかに、おじさんがひとり(笑)。
中島 それは、また、楽しそうですね。

中島 それが、サン=テグジュペリだったわけですね。
ドリアン はい。どの作品から読んでいこうかと思案したときに、『夜間飛行』も候補に上がりました。燃料切れの飛行機が台風に吸い込まれていく絶体絶命のシーン。あの無音の世界に感動した記憶があったのですが、やはりサン=テグジュペリの遺作ということで『星の王子さま』に決めました。
中島 ドリアンさんが最初に読まれた翻訳は、やはり内藤濯さんの訳ですか?
ドリアン そうです。『星の王子さま』を初めて日本に紹介してくれた方ですから。でも、原書に立ち向かって、わかったこともあります。そこにはサン=テグジュペリのエスプリがちりばめられていて、翻訳では伝わりきらない面白さを体験することができたんです。そのニュアンスを少しでも翻訳に投影できたら……。
中島 カンヌでの一瞬の出来事が、フランスの小説を翻訳するまでにつながっていく。やっぱりドリアンさんには予測不能なすごさを感じます。
ドリアン ただ『星の王子さま』の翻訳はたくさんあってもう飽和状態でしょう。他の翻訳とどうやって差別化するか悩みました。そこで思いついたのが、方言です。日本の中でも隣の地域に行っただけで言葉は変わるのに、違う星の人たちが同じ言葉をしゃべっているのはおかしいんじゃないかと思って、日本の方言をちりばめてみました。
中島 王子さまがいろんな星をめぐるところですね。とくに実業家の関西弁には笑ってしまいました。
ドリアン あのあたりは書いているときも、すごくたのしかったなぁ。三宅島から東京に帰ってくる船の上でもすらすらと筆が進みました。
トマトで三宅島を復興させる
中島 そうだ、三宅島のことも聞きたかったんです。なぜ東京から離れた島に仕事場を置こうと思ったんですか?
ドリアン 二〇〇〇年に三宅島が噴火して、全島避難になったでしょう。その様子を見てこれは何らかの形で復興させなきゃいけないと、しごく私的な使命感を持っていたんです。取材や映画『あん』の島での上映などで行き来はしましたが、本格的に三宅島にアパートを借りたのは先月(二〇一六年十一月)からです。それが、人里離れた場所で、一番近いよろず屋さんまで片道三・五キロ。カップ麺を買いに行くのも一苦労です。
中島 でも、いろんな誘惑がないから、執筆するには最高の環境ですね(笑)。それにしても、あまりに行動的なので驚きました。
ドリアン いやいや、僕はむちゃくちゃ怠慢な人間ですよ。できるなら何もしないで、酒を飲んで寝て過ごしていたい。一方で、それではいけない。仕事をしなければ、という自分もいる。でも根が怠慢だから、飲んで寝ているうちにやるべきことを忘れてしまう。そんななかでも、残っていくものがあるんです。それを僕がやるべきことを選別してくれる「怠慢のフィルター」と呼んでいます。
中島 それはある意味、理想的かもしれない。でも「怠慢のフィルター」は、ドリアンさん以外の人には、なかなか使いこなせないと思うけれど……。
ドリアン 三宅島の噴火の時期と重なっているのですが、二〇〇〇年の頭に自分がやっていることすべてに自信が持てなくなり、ラジオの仕事やバンドの活動をやめて、とにかく日本から出ようと考えました。結果的にニューヨークに約二年間滞在したのですが、そこで『メキシコ人はなぜハゲないし、死なないのか』(文春文庫)という小説を書く動機になったある本に出会ったんです。著者は、カナダの大学に自殺学の講座を持っている先生。その人の説によると、美味しいものが好きな国やおしゃべりでおせっかいな国は自殺率が低いというのです。ホントかなと一九四六年から統計をとっているWHOのデータを調べてみると、メキシコには自殺者がほとんどいなかった。自己申告なので、眉唾のところもあるのですが。

ドリアン いやいや、「怠慢のフィルター」が機能するまで時間がかかるだけで、ちゃんとつながってくるので安心してください(笑)。
中島 美食かどうかは別にして、たしかにメキシコ料理はヘルシーで美味しいですよね。
ドリアン ニューヨークでもメキシコ料理を食べあるき、メキシコにも何度も足を運んで、その中心部にあるのは、トマト、インゲン豆、トウガラシだと仮定したんです。ならば、そこに自殺が少ない秘密があるのではないかと。なかでもトマトは興味深かった。ヨーロッパにトマトを伝えたのは、大航海時代のスペイン。しかしその実が、毒性のあるマンドラゴラという植物と似ていたことから、スペインの王宮では二百年もの間、植物園から持ち出すことを禁じていたそうなんです。
中島 トマトが、最初は観賞用だったという話は聞いたことがあります。
ドリアン ヨーロッパを何度も飢饉が襲ったときに、空腹のあまりトマトを食べちゃった人がいた。でも、その人は死ななかったんですね。なんだ、食べられるんだと、あっという間にイタリアまで広がった。そして現在、調理用として使われる代表的なイタリアントマトのサンマルツァーノ種は、ヴェスヴィオ山やエトナ山など火山灰土の裾野が名産地だということがわかったんです。
中島 缶詰にもなっている、楕円形のトマトですね。
ドリアン 三宅島も火山灰でしょう。できるかも、ですよね。僕のその気持ちに火をつけたのが、「三宅島をイギリスのマン島のようなオートバイレース場にしたら復興する」という石原都知事(当時)の発言。ふざけたことを言うんじゃない。そんなこと望んでいる島の人がいるはずはないでしょう。
中島 島の人の生活など考えずに、頭から見下している暴言ですよね。
ドリアン 火山灰の島にいたるところに真っ赤なトマトが実っている。大収穫を祝って、島民が酒瓶を持って集まってくる。トマト栽培で三宅島が復興していく。その姿を見たいんだと言っても、最初は誰も相手にしてくれませんでした。縁を得て、三宅島の村長にその夢を語ったんですね。すると、トントン拍子に話が進んで、「やってみたら」ということになりました。昨年から島の若者たちに声をかけて、今、夢のチーム作りをしている最中です。
人は誰も単独では存在しない
中島 農業のプロでもないドリアンさんが、トマトを栽培するのは大変でしょう。
ドリアン 農園も参加してくれるので、そこは大丈夫なのですが、知れば知るほど三宅島はトマト栽培に向いていないことがわかってきた(笑)。
中島 あら、それはたいへんだ。
ドリアン トマトはアンデスの高地が原産でしょう。湿気と高温を嫌うんです。三宅には火山灰土が広がってはいるけれど、気候が全く向いてない。
中島 スタートから前途多難ですね。

中島 ニューヨーク、メキシコ、自殺、トマト、火山、三宅島……「怠慢のフィルター」に引っかかったことが全部意味を持ちながらつながって、ドリアンさんができているんだなぁと感じます。以前インタビューで、自分はカミキリムシの種類をものすごくたくさん知っているという話をしていたでしょう。区別できない人にとっては同じカミキリムシにしか思えなくても、ドリアンさんにとってはぜんぶ違う種類。それは個々の違いを認めているということだというような内容でした。とてもドリアンさんらしいと思って、ずっと頭に残っていたんです。ひとつの考え方や思考の方向に、みんな一緒に動いていくほうがいいんだという、同調圧力が強くなっているいま、そういう感覚がすごく必要とされていると思うんです。
ドリアン 僕は、自分という存在を単独で考えることがあまりないんです。カミキリムシと自分、鳥と自分、月と自分……常に関係性の中に自分がいる。だから与謝蕪村が六甲山で詠んだ『菜の花や月は東に日は西に』という俳句が大好きなんです。雄大な世界観ではあるけれど、太陽と月と菜の花の中に蕪村自身を描いていると思います。本誌に連載している「水辺のブッダ」もそういう感覚を大切にしながら書いています。
中島 ここまでお話を伺ってきて、気づいたことがあるんです。ドリアンさんの代表作のひとつである『あん』(ポプラ文庫)が、文庫化されたときにあとがきを書かせていただきました。私は、ハンセン病という難しいテーマを扱いながら、読後に幸福感が残るのはなぜだろうと考えていたんです。そして「この小説から得られる幸福感の源は、私たちがこの物語を読むこと、知ること、そのものが、生きる意味につながり、誰か別の人の生きる意味にもつながっているという感覚を得られることではないかと思う」と書きました。個々の違いを認めるということは、互いの存在を認めるということ。口で言うのは簡単だけど、なかなか私たちにできないことをドリアンさんは本能的にやっているんですね。
ドリアン 『あん』は、ハンセン病問題の入門書的に取り上げられることが多いのですが、まったくそうではないんです。もちろんハンセン病を背景にはしていますが、あれだけの逆境の中で生きてこられた皆さんに、僕の小さな知恵で座布団ひとつでも楽になってもらえないだろうかという義憤から書き始めた作品です。社会的に成功するとか、何かの勝ち組になるとか、そういうこととは全然違う。僕は、人間の傲慢は、「私」というものを独立させてしまったところから始まっているのではないかと思います。社会的な人間関係に限らず、トランプ大統領のようにアメリカは単独で強くなければならない、というような国家間の考え方でもそうです。自然も人も環境も、あらゆるものが関係性の中にあるとしたら、単独で強い国が登場して暴走を始めたら、間違いなく地球はひび割れてしまいます。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立、1996年にインターシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で第143回直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で第42回泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で第3回河合隼雄物語賞、第4回歴史時代作家クラブ作品賞、第28回柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で第10回中央公論文芸賞を受賞。
ドリアン助川(どりあん・すけがわ)
1962年東京生まれ。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒業。放送作家などを経て、90年に「叫ぶ詩人の会」を結成。99年のバンド解散後に渡米。2002年に帰国し以後詩や小説を多数執筆。ハンセン病の元患者と中年のどら焼き職人の交わりを描いた『あん』は樹木希林主演で映画化もされベストセラーに。現在は朗読する道化師(アルルカン)としてライブ活動も展開。本誌に小説「水辺のブッダ」連載中。
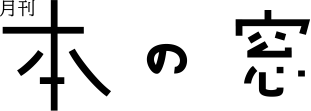
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2017/03/20)






