連載対談 中島京子の「扉をあけたら」 ゲスト:鄭義信(劇作家)
在日の人々の忘れ去られた歴史を内側から描いてきた鄭義信さん。今回初監督作品として映画『焼肉ドラゴン』を世に送り出します。在日として生まれた監督自身がそこに込めた思いをお聞きしました。
第二十三回
みんな自分の居場所を探している。
ゲスト 鄭義信
(劇作家)
Photograph:Hisaaki Mihara

鄭義信(左)、中島京子(右)
始めは特殊な家族の物語のはずだった
中島 映画『焼肉ドラゴン』は、初めてメガホンを取られた監督作品だとお聞きしてびっくりしました。鄭監督のお名前は、舞台作品や他の映画でもよくお見かけしていたので、もう何本も撮られていると錯覚していました。
鄭 舞台は脚本・演出をたくさんやっていますが、映画の監督は初めてなんです。ご覧になっていかがでしたか?
中島 この気持ちをどう表現したらいいんだろうと、観終わったあとしばらく言葉が出ませんでした。『焼肉ドラゴン』は、時代に翻弄される在日朝鮮人家族の物語です。在日として受ける差別はもちろん、戦争で片腕をなくした父や足の悪い長女、いじめによって言葉を失った息子など、社会的、肉体的、精神的なハンディキャップをかかえながらもたくましく生きていく家族の姿は、感動というありきたりの言葉では言い表すことができないものでした。映画の中の家族のはずなのに、まるで隣町の出来事のような気がして、たぶん監督ご自身やご家族が体験されてきた辛いことも織り込まれているからだと思います。「どっこい生きている」と、勇気を与えてくれる本当に素晴らしい映画でした。
鄭 ありがとうございます。
中島 『焼肉ドラゴン』は、もともとは舞台作品として制作され、読売演劇大賞や朝日舞台芸術賞なども受賞している、評価の高い作品ですね。
鄭 舞台の初演は二〇〇八年です。演劇の脚本として書いたときには、在日のなかでもすごく特殊な家族をテーマにした話だったので、受け入れられるかどうか不安でした。しかし幕を開けてみると、この家族を自分たちの本当の家族のように見てくださる人が多く、あたたかい声援をいただきました。

鄭 韓国では、在日問題は歴史の教科書にも出てきません。みんなよく知らないんですね。でも初日の幕を開けたら、日本以上にすごく大きな反響がありました。笑ったり、泣いたりする声が劇場に大きく響いて、最後はスタンディングオベーションで、拍手大喝采でしたね。
中島 今回映画にしようという話は、どういう形で持ち上がってきたんですか。
鄭 実は、何年か前にも、一度映画化の話があったんです。「在日のこういう特殊な世界を知っているのは、鄭さんだけだから、やっぱり鄭さんが監督をやるべきだ」と。それまで映画の脚本は何本か書いていましたが、やはり監督となるとすごく縁遠い世界だと思って尻込みしていたんです。
中島 舞台では脚本と演出を手がけられていても、映画はまた別なんでしょうか。
鄭 作品を作り上げるという目的は同じですが、映画は舞台制作とは桁違いのお金が動くでしょう。「うまくいかなかったらどうしよう」という、不安のほうが大きかったんです。でも、今回ふたたびお話をいただいて、いろんなひとが僕に期待してくれている。思い切ってやってみようと覚悟を決めて、メガホンを取りました。
僕の実家は、世界遺産
中島 『焼肉ドラゴン』というこの作品を、そもそもどういうきっかけで書こうと思われたのですか。
鄭 一九六二年の「原油の輸入自由化」をきっかけに、日本のエネルギーが石炭から石油に替わって、九州の炭鉱がつぎつぎに閉山していったんです。そこで働いていた朝鮮人の炭鉱労働者たちがどこに行ったのか調べてみると、伊丹空港(大阪国際空港)に隣接する中村地区(兵庫県伊丹市)に流れてきていたんですね。『焼肉ドラゴン』の舞台となった場所です。そこでは、一九七〇年の万博開催にあわせて、伊丹空港の滑走路をもう一本増やすための大工事が行われていました。元炭鉱労働者たちは、職を求めて九州から伊丹へやってきた。その話を聞いたとき、高度成長期の華やかな日本経済の裏側の歴史をそういう名もない労働者たちが支えてきたんだということを実感したんです。
中島 朝鮮戦争の特需を経て、日本経済は急成長したけれど、その陰で多くの朝鮮半島出身の人々が苦しい思いをしてきた。その事実をちゃんと受け止めないといけない。監督のご家族も同じような経験をされてきたそうですね。
鄭 僕の父は十五歳のときにひとりで日本に渡ってきた在日一世です。母方は、祖母が一世。十四歳のときに、「この人がおまえの旦那だから、日本に行きなさい」と言われて日本に渡ってきた写真花嫁です。母は次女だったのですが、父が母と結婚したときに、三女と四女そして、母方の母も引き取って一緒に暮らすようになったんです。
中島 義理の妹やお母さんまで引き取るなんて、お父さんも太っ腹ですね。
鄭 すごく不思議な家族構成でしょう。だから、おばさんたちは父のことを「兄さん」と呼んで慕い、すごく感謝していました。
中島 お話を聞いていると、鄭監督のお父さんは、『焼肉ドラゴン』のお父さんに似ている気がします。

中島 あら、まあ。どういうことですか。
鄭 僕の実家も、国有地にあったんです。姫路城の外堀の石垣の上に、戦後、土地を持たない人たちが勝手にバラックを建てて住んでいました。僕は「高級石垣朝鮮人集落」って呼んでいるんですけれど(笑)。
中島 監督は、姫路城に住んでいたんですか。
鄭 そうなんです。僕の実家があった場所は、今や世界遺産なんですよ(笑)。醬油屋をやっていた佐藤さんが「高級石垣朝鮮人集落」の一画で、お店をやっていた。それで、そこを引っ越すから、うちの父がそこを買った。国有地を勝手に売り買いしているんですね……。
中島 「醬油屋の佐藤さん」がすごく気になって、もしかしてすごく悪い人? お父さんをだましたの? なんていろいろ考えちゃった……。実在の人物だったんですね(笑)。
鄭 そうなんです。その後、立ち退きを迫られるときになって「お父さん、ここは国有地だから買えないんだよ」って諭しても「醬油屋の佐藤さんから買うた」の一点張りで(笑)。
中島 まさに、映画のお父さんそのものだ。
鄭 僕は男ばかり五人兄弟の四男なのですが、おやじが営んでいた屑鉄屋の仕事が忙しくて、実家のある石垣よりもすこし小高い丘の上にあったおばあちゃんの家で育てられたんです。おばあちゃんは姫路城の石垣の上に、畑を作っていましたから。世界遺産に勝手に野菜を植えていた(笑)。
中島 世界遺産に畑を作る。おばあちゃんも、映画になりそうですよね(笑)。でも、最後には立ち退いて、跡形もなくなるわけですよね。姫路城の石垣は世界遺産に、伊丹空港近くの中村地区は公園になってしまっている。この映画に描かれている世界は、今はどこにもない。
鄭 今でも忘れられない景色があるんです。おばあちゃんの家からは日赤病院の白い壁と火葬場の煙突と刑務所の赤いレンガの壁が見えたんです。眼下には、「生」と「死」と「罪」と「罰」ぜんぶそろっていた。僕たちが暮らした場所が、どんどんなくなっていく。当時の記憶も失われていきます。そういうものをなにかの形で残しておきたいという気持ちがありました。
日本人の根本が貧しくなっている
中島 鄭監督が脚本をお書きになった梁石日さん原作の『月はどっちに出ている』(一九九三年)や『血と骨』(二〇〇四年)が映画化された頃から、在日のヒストリーが普通に日本の観客にも受け入れられるような空気が生まれてきたと、以前にインタビューでおっしゃっていましたね。
鄭 『焼肉ドラゴン』の初演が、二〇〇八年です。韓国ドラマの『冬のソナタ』が日本で放送されたのが二〇〇〇年代の初め。ヨン様ブームが巻き起こり、その後の韓流ブームにつながっていく。その熱を受けて、初演時には、日本の観客もすごく好意的でした。しかしその後、慰安婦問題や竹島問題などが取り沙汰され、政治的な日韓関係の悪化が国民感情にも影を落とし始めます。ヘイトスピーチが出始め、韓国映画もあまり入ってこなくなった。でも僕の知る限り、日韓演劇の友好的な交流はまだ続いています。
中島 K-POPや若い子たちの韓国風メイクのブームなど、私たち普通の生活者同士の距離はそんなに後退したようには思いません。でも、ここ五年ぐらいは特にヘイトスピーチが増えてきたように感じます。
鄭 世界が右傾化していくなかで、ヘイトスピーチは日韓関係に限らず世界のどこでもありますからね。自分たちのなかに鬱積している不平や不満を、さらに弱い人たちに向けていく。ヘイトスピーチに参加している人たちを見ていると、ごく普通のサラリーマンや妊婦さんまでいたりするんです。
中島 えっ!! 妊婦さん。
鄭 そうなんです。ヘイトデモの行進の中に、妊婦さんが混じっている。
中島 胎教に悪そう!
鄭 そういうごく普通の人たちがヘイトデモに参加している姿を見ると、すごくびっくりしちゃうんですが、やはり表面的には豊かになりつつ、どこかで日本人自体の根本が貧しくなっている。

鄭 現実問題として、貧困児童や生活保護家庭が増えています。そういうニュースに触れると『焼肉ドラゴン』の人たちはお金はなくて貧しいけれど、精神的にはみんな割と豊かに、楽しそうに暮らしている……。
中島 そう。家族や仲間みんなが、助け合って幸せに暮らしている感じ。
鄭 年配の方たちは、そこに郷愁を感じてくれるんだと思います。
中島 『焼肉ドラゴン』は在日の物語なんだけど、戦後の日本はずっと貧しかった。
鄭 それも、等しく貧しかったわけです。
中島 「働いた、働いた、働いて、働いて、気づいたらもうこの歳や」と、お父さんが娘の婚約者に向かって自分の人生を語り始めるシーンがあります。日本という国で生きる人たちすべてに、そのまま自分の物語だと思う世代が存在するでしょう。
人生は悲劇と喜劇でできている
中島 舞台作品の『赤道の下のマクベス』も拝見しました。『焼肉ドラゴン』は家族のほっこりしたところもあるけど、この作品の登場人物はみんな死刑囚。チャンギ刑務所に収監されている日本兵と日本兵として戦った朝鮮人のBC級戦犯たちで、ただただ処刑されていくだけ。まったく救いのないお話なのですが、なぜか「マクベス」が演じられる。悲惨な現実なのに、そこには「笑い」があります。重いテーマに真正面から取り組むうえで、意識的に「笑い」を盛り込んでいるのでしょうか。
鄭 これらの作品に限らず、僕にとって「笑い」は生活の一部なんです。僕は関西生まれの関西育ち。吉本新喜劇を観て育っているので、笑いがくどいんですね。真面目な場面になればなるほど、どうしても笑わさずにはいられない性格なんです(笑)。それと、本人たちにとっては大真面目ですごく悲劇的だと思っていることが、引いて見ると喜劇的だったりすることもあります。
中島 そういうことは確かにありますね。
鄭 人生には、喜劇と悲劇という二本のレールが走っていて、たまに交わったりする。そんなイメージがあるんです。深刻な状況ほど、喜劇と悲劇が交差する場面でもある。だから、「笑い」を求めてしまう。
中島 死刑になる順番を待っているだけという設定です。普通なら、辛くて見ていられない。「笑い」があることで、登場人物だけではなく、演じている人たちも、観客もちょっと救われる。
鄭 『赤道の下のマクベス』をご覧になった多くのお客さんが「カーテンコールで泣ける」と言ってくれました。作品のなかでは死刑になって死んでしまった役者さんたちが全員カーテンコールで出てくるでしょう。すると、観客の間から「みんな、生きていてよかった」と拍手をくださるんです。
中島 観客は、舞台の上の死を現実のように感じたわけですね。素晴らしい。戦後七十年たって、戦争を体験し、差別を受け続けた世代が、どんどん亡くなっていく。『焼肉ドラゴン』や『赤道の下のマクベス』など一連の作品を通して、在日韓国人としてその歴史をちゃんと残しておきたいという気持ちもあったんですか?

中島 そこには、大きな歴史だけじゃなく、個人個人の小さな歴史がありますものね。小さな歴史が形あるものとして残るのはいいことですね。
鄭 韓国語がペラペラで、韓国の友達もいっぱいいる在日のスタッフを韓国に連れていくでしょう。それでもやっぱり陰では、「あの人たちは日本人だから」っていう言葉を投げつけられる。韓国に留学する在日の人たちは、みんなそういう洗礼を受けるんです。
中島 日本では「韓国人だから」と言われる。理不尽ですよね。居場所がないというか。
鄭 どこにも、居場所がない。自分はどこでどう生きればいいんだろう。在日のなかには、そういう思いを持っている人も大勢いると思います。でも、居場所がないって思うのは、きっと日本人も同じ。人それぞれ背負ってきた歴史が違うだけで、みんな誰しも、自分の居場所を探しているんです。毎年、韓国で演劇の公演を行っていて、韓国のスタッフや俳優さんたちと仕事をしています。僕は日本の教育をずっと受けてきたので、韓国の人たちとは考え方が違う。そういうときに、自分のメンタリティーの根本にあるのは日本人なんだなって思うんです。だから僕が創り出すものは、日本映画であり、日本演劇であると思っています。一方で在日という血は、やはりどうしようもないこと。いろんな局面に立たされることもあります。そのときはダブルカルチャーを味わえる、とてもラッキーな位置にいるとポジティブに考えている。だから、あんまりマイナスだとは思っていないんです。
中島 在日のカルチャーはずっと日本文化にパワーを与えてきました。そういう意味では、日本にいるすべての人が、ダブルカルチャーの恩恵を受けているんですよね。その豊かさに、私たちはみんなちゃんと気づくべきなんじゃないかなと思います。
構成・片原泰志
プロフィール
中島京子(なかじま・きょうこ)
1964年東京都生まれ。1986年東京女子大学文理学部史学科卒業後、出版社勤務を経て独立。1996年にインターンシッププログラムで渡米、翌年帰国し、フリーライターに。2003年に『FUTON』でデビュー。2010年『小さいおうち』で直木賞受賞。2014年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。2015年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。『長いお別れ』で中央公論文芸賞、2016年、日本医療小説大賞を受賞。
鄭義信(チョン・ウィシン)
1957年兵庫県生まれ。93年に「ザ・寺山」で第38回岸田國士戯曲賞を受賞。映画『月はどっちに出ている』の脚本で、毎日映画コンクール脚本賞、キネマ旬報脚本賞などを受賞。舞台「焼肉ドラゴン」では読売演劇大賞大賞、第8回朝日舞台芸術賞グランプリ、第59回芸術選奨文部科学大臣賞など国内外の演劇賞を多数受賞した。近年では「パーマ屋スミレ」「赤道の下のマクベス」と話題作を生み続けている。2014年春の紫綬褒章受章。
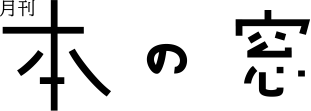
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
<『連載対談 中島京子の「扉をあけたら」』連載記事一覧はこちらから>
初出:P+D MAGAZINE(2018/06/20)






