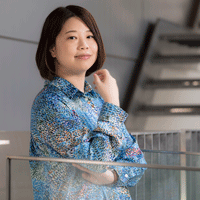映画『弟は僕のヒーロー』公開記念◈イタリア × 日本 人気作家特別対談 vol.2

公開中のイタリア映画『弟は僕のヒーロー』。同名の原作(関口英子訳)の著者ジャコモ・マッツァリオールさんと、本書の解説を担当、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』などの作家・岸田奈美さんとの夢の日伊対談が実現!
対談が進むにつれて、社会への意識や「書く」という行為そのものについての率直な言葉がどんどん飛び出して…。
個人的なこと、小さなことを書き続ける意味
――弟さんの近況は?
ジャコモ・マッツァリオール(以下、ジャコモ)
ジョーは最近、就労支援グループに参加していて、ホテルサービスを学んでいます。自分でその道にたどり着いたので、とても満足してるみたいです。ただ、多分早晩、新たな段階に直面するんじゃないかと思うんです。彼はこの先、歳を取ったらいつか、独立しなくちゃいけない。じゃあ、今やってる仕事をどういうふうに続けていくか。岸田さんはよくご存じだと思うんです。年齢的に、どうやって人間関係を構築していくか、障害を持つ人たちとも、そうじゃない人たちとも、どう関係を構築していくか、例えば、恋をするかもしれない。性の問題に直面するかもしれない。そんな自分自身の成長に対する複雑な思いをどんどん深くしていくかもしれない。何ていうか、もっと体の変化を伴う時期に突入すると思うんです。それは、この本を書いた頃のジョーとは異なる、新たな試練や変化に向き合うことになると思うんですが、今は、彼のことは兄として見守っていきたいと思ってます。
岸田奈美(以下、岸田)
私も同じ悩みに直面したことがあって。弟はグループホームでは言葉がうまく通じなくてつらそうだったんですけど、やっぱり、お姉ちゃんだから、彼の代わりに言いたいことを言ってあげようとか思ってたんです。でもいろいろやってみて1年経ってわかったのが、どんなにつらくても苦しくても、それは彼が乗り越えるべき壁なんですよね。彼が成長する機会だから、つらそうで苦しそうでショックを受けている彼を見守らないといけないっていうのは、ジャコモと一緒です。だけど、それは、お兄ちゃんとして、お姉ちゃんとして、私たちの試練でもあるなって思います。
ジャコモ
過ちも見守るっていうことですよね。今、弟さんはいくつなんですか?
岸田
28歳です。
ジャコモ
ジョーは21歳になりました。
岸田
若い! 実は弟が最初にグループホームに入ったとき、思いどおりにいかなくて、夜中に一人で荷物を持って逃げてきたことがあるんですよ。
ジャコモ
楽しいですね。映画の最初のシーンとしては最高ですよね。逃げてきて、で、まちがいなく、雨が降っていて…(笑)。

岸田
だけど、そのときに彼が一人でバスに乗れることがわかったり、あと、グループホームでけんかしていくうちにものすごく言葉をしゃべれるようになっていたり。私がいたから、家族が守っちゃってたから彼が成長できなかったことっていうのがたくさんあったんだなって気づいて、弟も私も傷ついたんだけど、傷ついた分だけ、二人とも成長できたし、彼の進化を見ることができたなって思いました。
ジャコモ
すごく面白いですね。でも、家族から離れることで自分自身が一番成長するって、だれにも起こることじゃないですか。僕自身も家から離れて、故郷から離れて初めて両親のありがたさを噛みしめた。独立して初めて、自分は何者なのかという問題と向き合うことになるというのは、だれにも起こること。ダウン症のある人だけじゃなくて、僕たちにも起こり得ると。ただ問題は、政治とか社会がリソース不足で多くを家族にゆだねちゃっていることだと思うんですよね。社会制度のなかで支えきれない部分を、家族が支えざるを得ない部分も、もちろんあると思うんです。
岸田
それはそのとおりですね。日本でも家族が障害のある人を介助するのが前提の仕組みになってて、それで、結構つらい。おじいちゃんおばあちゃんになっても子どもをずうっと介護し続けないといけないっていうような人たちも多い。その話を聞くたびに心が痛みますね、すごく。
ジャコモ
イタリアという国は、憲法でも弱者の権利が保障されていて、社会制度が整っているというか、意識が高い国だと思うんです。そういう意味で、不満を言うつもりはまったくないんですけど、実は障害を持ってる人はとても多いんですよね。イタリアは、人口6000万人のうちの300万人ぐらいが何らかの障害を抱えているといわれていて、割合としては大きいと思うんです。だから、みんなの意識を高めることがすごく大事だと。私にもあなたにもだれしも起こり得ることだと知らしめていくことが大事だと思うんです。皆で話題にしていくこと、警鐘を鳴らして、けっして他人ごとではないのだと啓蒙していくのは大事じゃないかな。
岸田
すごく大事だと思うし、素晴らしいこと、あなたにしか言えないことだと思うから、それを否定するつもりはまったくないけど、私の個人的な願いは、ジャコモさんには個人的なことをずうっと書き続けてほしい。「障害者が」とか、「ダウン症が」とか、「これで社会をよくする」というのはとても大事なんですけど、その目的で進んでいくと、いつかジャコモさんが言いたいことを言えなくなっちゃう日が来るかもしれない。私は、ジャック(ジャコモ)とジョーの物語をこれからもずっと読んでいきたいから。世の中を変えよう、変えたいっていう思いはものすごくわかるけど、書くときは、ぜひ「世の中」じゃなくて、自分のことを書いてほしいなって、今、お話を聞いていて思いました。たとえ社会が変わらなくても、イタリアも日本も障害者に対していい国じゃなかったとしても、社会が変わらなくても、ずうっとジャコモさんの家族について書いてほしいなって思いました。すみません、なんか涙が出てきた…。
ジャコモ
何で泣いちゃったの?
岸田
私はダウン症のお姉さんって見られることがすごく多くて、SNSでも、ほかの障害のある子の兄弟やお姉ちゃん・家族から、もっと私たちを代表して、社会に向けて訴えかけてほしいという声をいただくこともあって。でも、「社会はこうあるべき」とか、「日本はこうあるべき」っていう話をすると、急に言いたいこととか、私が面白がっていたことが書けなくなっちゃったときがあって、それがすごくつらかったから、もしかしたらジャコモさんも、同じところにいつか壁を感じるのかもしれないなっていうのが、何だろう、少し心配で…。一緒に戦うっていうのもおかしいのだけど、同じようなところで同じような苦しみとか悲しみとかを持ってる人が書くことで世界を変えようとしてるっていう、そういう気持ちですごくうれしくなって、感情があふれ出ました。
ジャコモ
その書けなくなっちゃったとき、どうやって乗り越えたの?

岸田
編集者さんから、作家っていうのは個人的なことを書き続ける存在だって教えてもらったんです。だから、主語を「障害者は」や、「ダウン症は」じゃなくて、常に「私は」、「私の弟は」、「私の母は」っていうふうに、主語をどんどんちっちゃくして、だれに嫌われても怒られてもいいから、思ってることを書きなさいって言われたときに、すごく持ち直しました。
ジャコモ
僕の個人的なことを話すと、InstagramやFacebookでたくさんのメッセージをもらったんですけど、中でも「あなたのこのストーリーをきっかけに私は自分のことを話すことができた」っていうメッセージがすごく多かったんですね。僕が媒介、呼び水になって、人々を語らせたっていう経験が大きかった。ただ、この本を書いたのは8年前で、この8年間にこの物語や問題意識を政治とか社会に伝えたいっていう気持ちがすごく大きくなっていって、要は、こっちを向いてみなよって、脇腹を突っつくようなことをしてみたいなと。イタリアではこの本がきっかけでムーブメントが起きて、例えば演劇になったり、写真を撮りに政治家が来たりとか。政治自体が社会を変えるために、ストーリーを必要としていたんだなと痛感したんですね。そのこともあって、主語が大きくなってしまったのかなって思いました。
あと、岸田さんと同じで、出版社の人から「とにかく細部を書け」と。細部を書くほど、ユニバーサルな、普遍的なものになるからって再三言われたんですね。でも当時は、いかんせん思春期だったので大きいことを書きがちで、理想主義者だったし、世界を変えようという思いで、引用なんかを書きがちだったんだけど、そうじゃなくておまえは自分のパーソナルな生活を書けって言われて従った経験もあって。
でもやっぱり、そのディティールがものすごく豊富に自分たちの引き出しにあるっていうのは強みだと思うんですよね。ちょっと書き始めたら、いろんな楽しいことが最後まで流れ出してくれて、エピソードも豊富にあるし、楽しんで書きました。本の中ではオルター・エゴがいて、自分が体験したことをもう一度練り直すことが出来た。それと、うそをつけばつくほど真実に近づくんだということも感じました。創造力を働かせるという意味でも自分にとってはすごくいい経験になったのかなと。実際に体験するよりも、もう一段深い思考ができた。
岸田
わかります、すごく。私もエッセイでよくフィクションを交えて書いちゃうこともあるんですけど、そのフィクションがほんとに自分が願ってたことだったのがわかったりするので、うそをつけばつくほど真実に近づくっていうのはすごくわかります。

――最後にひと言ずつ、お互いにメッセージをお願いします。
ジャコモ
岸田さんが先に始めてくれる? 多分、感動させることに関しては岸田さんのほうが上だから(笑)。
岸田
そんなことない(笑)。ジャコモさんが書いたのはすごい本です。これが、「多様性」とか、「ダウン症」とか「知的障害」とかっていう、特別な言葉で語られてしまうのは、私はすごく悔しいです。これは障害について書かれた本ではなくて、皆が家族とか友だちに対して抱く葛藤の本、成長の本で、ひとりでも多くの人に読んでもらいたいと心から思った本はほんとに久しぶりだから、この本に出合えたこととジャコモさんとお話しできたことと、すごくうれしく思います。…っていうのがきれいなところまでで(笑)。ジャコモさんは強い使命を持ってるし、社会を変えようっていう思いもすごく正直で、それに私は今、胸を打たれたというか。結構、あきらめちゃっていると思うんですよ。私が大きいことを変えようとしてもそんなに変わらないし、しんどいし疲れるから、ちっちゃなちっちゃな世界でとにかく人を笑わせ続けようってずうっと思ってたんですけど、でも、ほんとはもっと大きなことを言いたかったのかもなっていう、あきらめちゃ駄目だったのかもなって。今、お話を聞いてて、恥ずかしくも思ったし、そうかって気づかされる思いでした。
ジャコモ
ありがとう。今の岸田さんのコメントの後半への返礼からはじめるんですけど、岸田さんがやったこと自体が、もうすでに社会を変えていると思うんです。変えようと思ってやったことじゃなくても、社会は変わってると思うんです。戦ってなくても絶対変わっていると思うし、僕たちの役割っていうのは語る価値のあることを語り続けることなんじゃないかと思っていて…。グラムシっていうイタリアの哲学者で政治学者がいるんですけど、 彼が言うように、 無関心な人々は同じ罪をくり返す。やっぱり岸田さんの存在自体がとてもインパクトが強いものだと思うし、政治に訴えようとかそんなことをしなくても、届いていると思うんですよ。あと、もうひとつは、それを受け止めて行動してくれる人たちがいるっていうこと、その人たちを信じるといいんじゃないかなって思います。
岸田
ありがとうございます。
ジャコモ
あと、ジョーが、弟が僕自身に革命を起こしてくれたんですね。考え方にものすごい革命を起こしてくれたし、単純であること、純粋であること、それから、天才性とは何なのかっていう、その自分が持っていたコンセプトを大きく変えてくれたのがジョーという存在だったので、僕が弟をスーパーヒーローって呼んだのは、それはレトリックでも何でもなくて、ほんとにスーパーヒーローだと思ってるんですね、自分を変えてくれたという意味で。自分を偏見から自由にしてくれたのはほかでもない、弟だったということもあって、この本を読み、映画を観てくれた人が、それぞれ自分の心に問いかけて、自分自身の心の声を聞いてくれたらいいなって思うんです。愛ってあるだけで人を変えるじゃないですか。愛を感じたら人は変わるし、この本にも岸田さんの本にも愛があると思うんです。
岸田
実は最後に聞きたかったことがあって、今回の映画はどれぐらい気に入ってます?
ジャコモ
ど真ん中来たな。絶対ドラマについて同じ質問をするから(笑)。じゃないとフェアじゃないし。
岸田
そうか、そうか(笑)。

ジャコモ
(僕自身が)映画の製作にも(脚本家として)深くかかわっているので、ちょっと答えにくいんですけど…。本を読むとだれもが自分の想像の中で旅をするわけですけど、映画はそこが制限されるところがあって、だれもが「こうじゃなかった」って思うことがあるし、岸田さんも自ら経験したことがドラマになったので、その質問が出てくるのはよくわかるんです。実際、この本を映画化するのってすごく大変で、実際の体験には18年間のタイムスパンがあるし、多くのエピソードが描き込まれているし、何より感情を描くのは映画が不得意とするところですよね。内面を描くには映画というツールの限界があって、そこは自分もわかっているんです。ただ、脚本にもかかわることで、映画をつくってくれた人たちのエネルギーをものすごく感じたし、それがとても重要なんだって感じさせてくれて、そのこと自体が、観てくれた人にポジティブなこととして届くんじゃないかなと思ってます。
岸田
とても難しいことに挑戦している映画だと思いました。きっとこの映画もすごく褒められて、これから100年で5回ぐらい、ちょっとずつアップデートされながら何度でもこれは映像化されるだろうなって思いました。
ジャコモ
舞台を日本に移して、日本版の映画をつくるとかね。
岸田
ヒットしそうですね。
ジャコモ
オリジナルよりリメイクのほうが売れちゃったりして(笑)。
映画『弟は僕のヒーロー』
監督:ステファノ・チパーニ
出演:アレッサンドロ・ガスマン、イザベラ・ラゴネーゼ、ロッシ・デ・パルマ、フランチェスコ・ゲギ、ロレンツォ・シスト
提供:日本イタリア映画社 配給:ミモザフィルムズ
シネスイッチ銀座、新宿シネマカリテ、YEBISU GARDEN CINEMA、アップリンク吉祥寺ほか全国順次ロードショー

ジャコモ・マッツァリオール(Giacomo Mazzariol):写真左
1997年、イタリアのヴェネト州生まれ。2015年に弟ジョヴァンニと一緒に制作した動画『ザ・シンプル・インタビュー』が60万回以上視聴されて話題になり、翌年、デビュー作となる本書を発表、ベストセラーに。 Netflixのドラマシリーズ『ベイビー』の脚本、小説『サメたち(Gli squali)』(2018年)など、多彩な執筆・創作活動を続けている。
岸田奈美(きしだ・なみ):写真右
1991年生まれ、兵庫県神戸市出身。大学在学中に株式会社ミライロの創業メンバーとして加入、10年にわたり広報部長を務めたのち、作家として独立。世界経済フォーラム(ダボス会議)グローバルシェイパーズ。Forbes「30 UNDER 30 JAPAN 2020」選出。著書に『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』『傘のさし方がわからない』(以上小学館)、『もうあかんわ日記』(ライツ社)、『飽きっぽいから、愛っぽい』(講談社)など。