『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
桜目かなみの強さは、社内炎上上等、正しいことは言語化してきっちり話すというポリシーを貫いていることである。それによって自分が不利益を被ることも百も承知で、ブルドーザーのように昭和に固められたままのガッチガチの社内環境を掘り起こしまくっているのだ。彼女はそれを生きがいにしているといってもいい。
『静緒だってそうでしょ。家を買うために働く、とかって言ってたし、そういう人も少なくないけど、いざ目的がなくなってみたら目の前真っ白になったりするでしょ』
「それは、そうかも」
家を買う目的がなくなったわけではないのだが、もう買うつもりだった物件が目前で消滅して心が折れると、なかなか立ち直るのが難しい。
『ローンを組んで家を買うために、いま富久丸は辞めない。辞められない。ものすごくわかる。家を買うのを止めるとそもそも会社員である必要なくなるじゃん? 私は思うんだけど、たいていの人は家を買って、次は出世って思うわけ。数少ない六級の席目指して椅子取り合戦に夢中になる』
六級というのは肩書きとはまた別の社内等級のことで、かなりざっくりいうと役員候補である。
『それってほんとは出世したいわけじゃなくて、がんばる理由がなくなるからなんだよね。子どもも手が離れて、家のローンも完済して、気がつけば老いた体と自分だけが残る。周囲の知り合いの半分くらいは病で倒れてドロップアウトか、人生からログアウトしてる』
「ちょっと……、縁起でも無い」
とはいえ、桝家も同じようなことを言っていた。四十代になるとみな何らかの心身の故障を抱えていること、働けなくなる人間もいることに変わりは無い。
『静緒はどうしたいの?』
上の子の塗り絵を褒めながら、下の子を抱いてスクワットしながら、息を切らしながら彼女は言った。
『お母さんの病気と、家のローンのために転職も視野にいれてたわけでしょ』
「うん。ありがたいことに、母は元気でいまのところ薬の副作用もないみたい。いちばんびっくりしたのは、すごく高くなってた生命保険の毎月の支払いがなくなったこと」
夫を早くに亡くした母は、自分になにかあったときのためにと生命保険・医療特約を手厚めにかけていたようだ。それもあっていつも切り詰めた生活をしていたのだが、癌の治療費が保険からまとまって下り、なおかつ月々の支払いも免除になった。
『最近は癌は治る病気だからね。とにかくまめに検査していれば早期にみつかるし』
父の遺族年金と、早めにもらう設定をしていた基金と年金でなんとか暮らしていけるとふんでいた先、支払いがなくなった。年金生活者にとって一月二万の保険は大きい。どうせ癌になるなら住宅ローンを組んでおけばよかったといつも笑いながら電話してくる。
静緒にしてみれば、これまでは一人っ子のサガか、母の病気や介護など、いざというときはお金しか頼れないと神経が張り詰めていたのが、急にぷつっと糸が切れたような感覚なのだ。
『じゃあ、出世めざしなよ。いまなら合併で社内体制も固まってないから、チャンスだよ』
自分がわざわざ育休を早めにきりあげて戻ったのも、合併のどさくさで人事をいじられたくなかったのだ、と彼女は言った。
富久丸百貨店の大本締めはフロンティア・エンター・ホールディングスという持ち株会社で、株式会社富久丸百貨店や若者向けのファッションビルである001などを傘下に持つ。堂島や元町、東京駅などの百貨店は大きいが、所詮は地方の支店にすぎず、あくまで本丸は東京八重洲にある統括事業本部。ここの所属になれるかどうかが、今後の出世に大きく関わってくる。
静緒を引き抜いた紅蔵は、営業本部長や事業本部長を歴任し、現在はホールディングスの専務取締役である。新卒のプロパー社員である桜目かなみは菊池屋との合併を機に育休を終わらせて本部の人事に移り、だれの目から見ても出世コースを歩んでいるが、契約社員あがりの外様である静緒には、そんな花道は縁のない話だ。
……と思っていた。実際、菊池屋からやってきたスーパーキャリア室長が、静緒に本部の仕事の一端をまかせるような匂わせをするまでは。
『菊池屋さんも必死なんじゃん? このままだとウチにぜんぶ乗っ取られるから』
「合併っていってもやっぱりウチのが強いんだ」
『うちはほら、けっこう早くから不動産事業が強いじゃない? ビル経営とかがメインの柱でもあるから事業規模としては小売りのマイナスを不動産で埋めたりしてしのいでる。だけど、菊池屋さんはそこは出遅れてるから、全体的な事業規模と知名度を考えると、やっぱうちからの役員のほうが多くなるよね』
持ち株会社の役員や、メインポストのほとんどを富久丸出身者が占めることになったが、菊池屋は少数精鋭で有望株を送り込んできた。氷見塚はその筆頭株で、長年菊池屋の実質上の看板でもあった東銀座店のマネージャーを務めた辣腕であるという。
『うちが関西地盤でやってるってわかってるのに、そこのマネに送り込んでくるんだから、もう切り込み隊長だよね』
ほとんどのポストを富久丸に獲られたとはいえ、菊池屋にもプライドはある。富久丸の本家本元ともいえる堂島店の営業トップに菊池屋の元マネージャーが来るのは、向こうの自信の現れともいえる。
『氷見塚さんをはじめとして、地方店舗の店長ポストとマネージャーは菊池屋出身者が占めた。菊池屋は目先のポストにこだわらずに次世代をK(菊池屋)で固めて、次の人事で勝負にいく戦略なんじゃないかな』
彼女が言うには、菊池屋が今後伸ばして行きたいのは不動産事業方面であるが、東海地方を地場として展開してきた老舗のメンツの手前、いくら儲かるとはいえ店であることをなおざりにして、テナント業にばかり色気を出すわけにはいかなかった。
地方であればあるほど、地元の名士や中小企業との関係性も深くなる。ショッピングモールをひとつ建てるのには、地元の小売や商店街からの猛反発をどれだけ穏便にまとめるかが一番の大仕事だという。とくにやっかいなのは、地元の小売り業のまとまりである商工会や組合で、なかなか理解を得ることが難しいということだ。
『実際店長なんて、ほとんど店の中のことは見ないで、地元の集まりだ呑みだ祭りだに顔を出して仲良くやるのが仕事じゃん。まあその仲良くっていうのが一番難しいわけだけど』
百貨店の多くは、もともとは呉服店からの出発であることが多い。いわば地元の老舗中の老舗だから、これくらい大きな箱の中でいろんなものを売っても許されるという不文律がある。それに、百貨店があるからこそその周辺の商店街やストリートは集客をみこめるので、いわばもちつもたれつの関係性が何十年にわたって築かれてきたのだ。
元町店でいうと、マラソン大会があるといっては協力し、光の祭典があるといっては通り抜けを許可する、トイレ(だけ)の使用が増えることに目をつぶり、街の顔としての寛容さと懐の広さを示してきた。菊池屋の旗艦店をはじめとした東海地方の店舗も、多くはメイン駅直結の超一等地にあり、開発の歴史は常に地元との水面下での交渉、折衝の歴史であったはずだ。それをなんとかまとめあげてきたのは、それぞれの店舗の店長が、日頃から行政のイベントに協力し、地元をまとめあげてきたからである。
ECがこれだけ幅をきかせるようになった令和の時代になっても、経済指数の基準は百貨店である。景気のいい悪いは百貨店の売り上げを中心に語られるし、なにか大きなことが起これば行政の意向を受けて百貨店が真っ先に動く。経済においての行政の出先機関の一翼を担うだけの存在感が、百貨店にはあるのである。
その百貨店が、小売りの事業悪化に歯止めがかからないとはいえ、簡単に不動産業に転換できるかというとなかなか難しい。まず地元の不動産関連業界との折り合いがある。いままでいっしょにやってきた仲間だったのが、突然商売敵になるのだから。
『菊池屋的には、いままでは地方あるある、地元の力でなかなか新規転換できなかったのが、ウチとの合併を理由にどさくさに紛れて不動産経営に本腰を入れたいんだよ。まあ、あれだけの一等地を持ってるんだから事業ビルにしてしまわない手はない。だけど、地元との関係性を考えて何度も断念してきた。ウチとの合併は、全部ウチのせいにできるし、菊池屋にとってもだいぶメリットがあるんじゃないかと言われてるねー』
すでに所有資産の不動産事業展開を終えている富久丸と違って、菊池屋のほうが今後の事業の伸びが期待できる。今回の合併時は多少富久丸からの役員が多かろうが、五年後を見据えたとき、富久丸の不動産ノウハウを生かした菊池屋資産の活用事業の伸び率は倍々ゲームだろう。そのときこそ、大手をふって菊池屋出身のマネージャーや五級クラスの管理職が富久丸の役員その他を蹴落として上にあがることができる。
『つまり、一番痛い目を見るのは、ウチ出身のいま四十代から五十代の次こそは役職をと狙ってるけれど、年功序列以外のなにも手柄のないバブル世代。それから、その下』
「その下、って」
『ウチらだよ』
「なんでアラフォーまで?」
『そんなの決まってる。ぴっかぴかの業績と成績で晴れて富久丸の幹部を蹴落として上に上がった有能な菊池屋の管理職が、自分の椅子をだれに譲ると思う?』
合併には十年かかると言われているのは内部事業的な話で、本当の意味での合併には二十年かかると言われている。つまり、合併したころに生まれ合併した社名しか知らず、合併したあとの会社に就職する世代が出てきて、初めて合併は無事完了したと言えると。
それまでは、ゆっくり混ざり合いながら淘汰されていく。末端にとってはただただ降ってくる雨つぶのような合併話も人事も、実際は社内政治を動かすためのイベントに過ぎない。
「かなみは偉いなあ。産後あけすぐに、そんな修羅の国で戦っているんだねえ」
『エライでしょう。ご褒美にツマガリの焼き菓子セット送って』
電話の向こうで、『もう暑い、もう重いむり!』といううめき声がして、間髪容れずにうわーんという赤子の泣き声が響いた。どうやらやっと寝た長男君をベッドに置いたとたんに感知されたらしい。
「……かなみは最前線だけど、私は生涯一兵卒だから」
『何言ってんだか、〝御縁の会〟は去年度のグローバル賞とったじゃないの。その前はMANMA・ZONEで社長賞、今年も企画出せっていわれてるんでしょ、Kの美魔女に』
氷見塚女史のキャラの濃さは本部でも有名で、Kからの最終刺客だとかKの美魔女だとか呼ばれているらしい。ちなみに立て板に水のごとく耳の痛い正論を上司だろうが社長だろうがかまわずぶちまける芸で桜目かなみも社内では有名人であり、今まで彼女に嫌がらせをしてきた政敵を引きずり出して左遷に追い込んだ武勇伝から、〝死なばもろともマシンガン〟と呼ばれている。
静緒のようにこつこつ地味に同じ作業を繰り返す働き蟻とは違って、桜目かなみのような積極的なタイプのほうが評価される世の中になったのは喜ばしいことだ。今までは『女はうるさい』と言われるのを恐れて、本当のことを飲み込んで言えずにいた社員も多かったからである。
『Kの美魔女がわざわざ静緒を指名して直接下につけたのなんて、あからさまな社内政治じゃん。紅蔵さんの息がかかった静緒に真っ先に目をつけるなんて、上を見てないと考えつかないよ』
「そうかなあ……、たまたまだと思うけどな」
そもそも、去年は出した企画が運良く順調に滑り出したはいいが、実際に運営しているのはブライダルを一括する富久丸の子会社であり、静緒は一年中、お受験だ家出だ裁判だ、そして終活だと走り回っていただけであった、ような気がする。
それでも、清家弥栄子さんのお見送りを兼ねて葉鳥と企画したエステートセールはとても好評で、直接本部から企画としてまとめて提出しろと念押しされ、睡眠時間を削って資料を作るはめになった。
『それだよ。それそれ。静緒はさ、打ち出の小槌みたいなもんだから』
「打ち手の小槌?」
『成り行きでやってるように見えて、しっかり金脈を掘り起こしてる。嗅覚がすごい』
「いや、私が掘ろうと思って掘ったわけじゃ」
『それがいいんだよ。運っていうか、ツキっていうか、そういうのを持ってる。そう、静緒はもってんの。自分では自覚がないかもしれないけど、自然と探し当ててるの。そういうのって、すごく大事じゃん?』
ようやく乳児を帰宅した夫にバトンタッチできたのか、かなみがカメラの前に戻ってきた。もう右手には空いたビール缶を握っている。自分のメンタルと日本の経済をまわすために最初から母乳はやらないと聞いていたが本当に実践していたようだ。
『プロパーで入っても転職で入っても、まあ四級、五級まではそれなりに上がれるよね。でもそこから上がドン詰まる。現場でいくら手柄たてても本部に行けなきゃ意味が無いもん。さっきだって店長の仕事は地元との親睦って話が出たけど、四十代で抜擢された店長ならいざ知らず、定年ギリギリすべりこみなんて名誉職ポジション。六級で終わるためのあがりでしかない。役員にとどかないから定年でドン、おわり』
地方のいち支社長でしかない店長職では、ホールディングスや富久丸の経営にかかわることはできない。出世コースとは、できるだけ早いうちに本部に呼んでもらい、地方に出てポジションアップして本部に戻ってくるコースだ。もしくはずっと本部にいる総務コース、人事コース。現場あがりとなると事業本部長と営業本部長の二つの席をみんなで争うことになる。
『この歳になるとさ、実力なんてたいした意味もなくなるわけ。大きな金を動かせば動かすほど、結果が出るのはずっと先。でも株主のために目先の利益を出さないといけない。なにかニュースになるような、印象のよい、地元に貢献型やSDGsなんかの国際的な基準を意識したイベントや活動なんてどこの会社もやってる。そういうときにあっと目をひくことをやってのけられる人ってほんの一握りだよ。そういうのはもう才能っていうか生まれついてのもので、努力や社内政治だけではどうしようもないってことがわかっちゃうんだよね。二十年も社会人やってるとね』
彼女に言わせると、静緒はその、『もっている』人間だということらしい。
『周りの人間も、最初はそういう派手なことやる人間は排除しにかかるけど、そのうち社内政治に勝ちたい課長・部長クラスの人間が手駒にしようと抱き込んでくる。自分ががんばる、から、下にがんばらせる歳になる。そうなると人を見る目がある人間ほど上に上がる。静緒は今、紅蔵さんと美魔女に右腕と左腕ひっぱられかけてんのよ』
上に上がるには、人をうまく使えるかどうかだよ、と彼女は繰り返した。
『だけど、必要以上に気負っちゃだめ。いまの若い子なんてすぐフラッと転職しちゃうんだから。それもその子の人生。気にしないでいい。しがみつくだけの魅力がなかった会社が悪い』
電話を切ってから、思わず天をあおいだ。聡い彼女のことだから、静緒のいまの状況のことを、多くを語らずとも察知しているのかもしれなかった。
上は出世のために自分をうまく使おうとし、自分もまた出世したければ下をうまく扱わなければならない。それが四十代の仕事になってくる。だけど、四十代の「生きる」がすべて仕事とは限らない。
なんのために生きる? それはまあ、お金のためなのだけれど、でも……
「……どうやって、生きるんだっけ?」
まさに、彼女に聞いてもらいたかったのがその点だったのだ。
***
部下がつけば、育てなければならないと思うのは自然な感情の発露でもあり、会社的にも期待されていることでもある。自分が葉鳥にくっついてゼロから外商のノウハウを学んだように、香野や大泉を令和の女性外商として一人前に育て上げる必要があるのだろう。問題はその「一人前」というのがいったいどういう基準を満たすことなのか、静緒にはいまいちしっくりきていない
実際、売り上げというのであれば香野はもうすでに申し分ない。堪能な中国語を生かして、新規顧客は毎月のように増えている。賢い彼女は、きちんと毎月の売り上げに波がないように、顧客の来日や購入のバランスを整えており、また企画力もある。静緒が発案した「御縁の会」に中国支部を作って、国際結婚などを後押ししてはどうか、という案はおもしろいと思った。
「いまは世界的にこういう状況ですから、できれば異国籍の婚姻関係をもちたいと考えている方は多いようです。特に中国の富裕層に顕著で、留学先もアメリカやカナダは遠すぎるからと日本を選ばれる方もいまだに多いとか」
アグレッシブな香野とは全く違うタイプの大泉からは、あまり手応えのある企画や話が出てくることはない。彼女は割り当てられた仕事は堅実にこなすが、自分で自分の枠をきめてしまっているのか、どうにも積極性に欠けるきらいがある。
たとえば、先日大泉の顧客から、インスタ映えする家具に買い換えたいという依頼があった。彼女は富久丸のインテリア館をすべて回り、堂島のインテリアフロアにも案内したのだが、「どれもぱっとしない」「どんなインフルエンサーも使ってない家具がいい」と顧客の反応はあまりよくなかった。
結局、三人でランチを兼ねた報告会をした際、香野が「マッケンジーチャイルズはどうか」と案を出してくれ、そこから三人で必死に実物がおいてある輸入家具の店をあたり、日本にないものを気に入られたときのために輸入代行やBUYMAのバイヤーをあたり、運良くお客さんがそのなかのいくつかの家具を気に入って、購入してくださった。マッケンジーチャイルズのソファとオットマン、それにカウンターテーブルの三点だけでも搬入費こみで百万はかかるが、普段富久丸で取り扱っている高級家具と比べればそれほど高いものではない。
それでも、顧客の要望がインスタ映えする家具というのはいままでに無かったもので、静緒自身とても勉強になる。香野はさらにこのチャンスを企画に生かし、「インスタ映えするコーナーを、今度のオークラでの万寿会で作ってみてはどうか」といろいろ提案してきた。
香野の積極性、多角的な情報量、海外とのコネクションの強みはこれからの外商に必要なスキルだ。大泉はそのどれもに欠けている。外から見れば香野のほうが何歩も先んじているように見える。が、その香野も現代っ子らしい複雑さを抱えており、一筋縄ではいかない。彼女は一切残業をしないのだ。休日は社用スマホはオフ。逸品会などの展示会でもきっちり一時間休憩をとる。黒のパンプスは履かない。ストッキングは穿かない。一度上下黒のスーツにローファーとハイカットスニーカーのミックスのような靴を履いてきて、当然下は着圧ソックスだというのでびっくりすると、「いまどきストッキングなんて穿いてる人いるんですか?」と真顔で逆に質問された。「そんな誰も得をしない格好をするより、お客さんが買ってくれそうなものを身につけて、なにかのおりに会話のきっかけにしたほうがよっぽど合理的だと思いませんか?」
静緒自身、痛い出費だとは思いつつ普段からハイブランドの新作は身につけようと意識しているから、香野の言い分はよく理解できる。さすがは、あの桜目かなみが気に入って採用に踏み切っただけはある。
「香野さんの靴は、ロジェ ヴィヴィエの新作で、彼女はもうあれで十足は売ったんですよ。ビジューが派手で、厚底で背が高く見えて、パンプスのような窮屈さもないので、東南アジア系のお客さんにも人気です」
香野がトイレで席を外したすきに、さりげなく大泉がフォローに回った。
ロジェ ヴィヴィエはディオールやサンローランと並んで歴史あるフランスのシューズメゾン、アーティスティックな作風はシューズ界のファベルジェと呼ばれた。いまではすっかり定番となったメタル素材のバックルをつま先にデザインしたパンプスやローファーは、ロジェ ヴィヴィエの出世作である。
「最近創設者からブランドを引き継いだブルーノ・フリゾーニ氏のあとをついだゲラルド・フェローニのコレクションがすごく評判がいいみたいです。香野さんはあまりこういうことをおっしゃらなくて、自分がいいと思ったものをどんどん身につけるタイプらしいんですが、私は調べるのが好きで。ゲラルド・フェローニはプラダのスタジエールからキャリアを出発させたんですが、もともと実家がシューズの工房だったそうです。フランス流のサヴォアフェールに惚れ込んで、音楽学校に六年も通ったオペラ歌手への道から転換したと、メゾンからいただいた資料で読みました」
大泉のいいところはなんといっても豊富な知識と勉強家な生真面目さである。まるで学芸員と話しているように、すらすらとメゾンやデザイナーの歴史がでてくるのは尊敬すべき点だ。桝家とさぞかし話が合うかと思ったのだが、本人がお嬢様過ぎて、桝家のように無言の自己主張が強いタイプとはどう話していいのか気後れするということだった。
「私の場合、これが好きだから調べる!というこだわりがないんです。どのメゾンも、クチュールも、デザイナーも若手も、歴史を調べると面白くて。どれも好きだし素敵だと思うけど、自分で身につけたいとは思わないんです。今回も、香野さんがマッケンジーチャイルズを教えてくれなかったらお客さんに平凡な提案を繰り返してしまったところでした。家具の勉強をもっとしたいと思います」
香野と大泉は、うさぎとかめ、アリとキリギリスのように対照的だが、どちらが秀でているというわけではないのが現代らしい。知識を兼ね備えた堅実なバイヤーとして大泉が大成するにはいまのままでは時間がかかりすぎる。かといって、香野のように道場破りを繰り返し続けていては、いらぬところに敵を作ってしまうだろう。
実際、香野はまだ二年目のシューズ売り場にいたころ、あるアパレルブランドの催事にいた契約社員を見下すような態度をとって恨みをかったことがあったようだ。それが巡り巡って、その販売員がハイブランドの正社員として雇用され、皮肉にも二人は再会してしまった。香野は隠しているが、大泉はそのあたりの事情を知っているらしく、「私のことを恨んでいて、お客さんにバッグを売ってくれない」とぼやいているとか。
「それって本当なの? ほんとに香野と仲が良くない販売員のせいで、香野の顧客さんに影響がでているのかな」
「……どの程度やりあったのかとか、お互いにどう思っているのかはわからないです。私は先方の販売員さんを直接存じ上げないので。ただ、もともとグッチやランバンにも居た方で、交友関係も広くて楽しい方だと聞いています。芸能人の知り合いや顧客も多いとか」
短期雇用のモデルや派遣からキャリアをスタートさせたハイブランドの販売員はめずらしくない。あのクリスティアーノ・ロナウドのパートナーであるジョージナ・ロドリゲスももともとはグッチの販売員だった。ロナウド選手と出会ったのはドルガバのパーティだったらしいというから、あのクラスの販売員はすでに独自の交流ネットワークを形成している。香野がいったいなにをしたのかは知らないが、嫌な外商としてハイブランドの販売員に情報が回ってしまっている可能性もある。
香野がどのような対策をとるのかしばらく様子を見ていたが、その点に関してはとくに進展や改善はみられなかった。しかたなく静緒は、香野と話す時間をとることにした。話の内容が内容なので、会議用の事務所を三十分借りることも考えたが、のちのち社内で「香野さんがへまをして鮫島さんに会議室で指導されていた」などの噂がたつことを考慮し、半個室のあるレストランの人の少ない夕方開店直後の時間を狙って呼び出した。
(上司からの呼び出しって、呼び出すほうもこんなに緊張して気を遣うものなんだな)
すでに、呼び出す口実のバリエーションが思いつかず、〝チームで提出する催事の企画案について〟などという薄味で興味が一ミリも湧きそうもないメールを送ってしまった。
香野は上下黒のパンツスーツに桜色のエナメルがかわいらしいキトゥンヒールのパンプスを履いていた。最近の韓国の女優のように肌が真っ白で、唇の中央を嚙んだあとのように血色で塗るメイクをしている。コスメに詳しい百合子・L・マークウェバーさんに言わせると、最近は口紅ではなくティントで赤みを出すのが流行っていて、もともとは乳首を染色するためのものだったらしい。
(そういえば、私が若い頃はアイプライマーなんてなくて、みんなコンシーラーって呼んでたなあ。メイク道具もどんどん更新されていく……)
日々の時間がなさ過ぎて、メイクの勉強もメーカーの講習会や勉強会といった仕事のついでで済ませてしまう。自分の顔と向き合っていなすぎるとはわかっている。
わかってはいるが、いまさら自分の顔がどうあってほしいとか思わないのだ。恋人が欲しいわけでも婚活しているわけでもないから、最低限仕事に差し支えない程度にきれいにしていればいいと思う。たとえ何度練習しても、眉毛を太くふんわり平行に描けなくても。
「大昔、呉服店だった頃や昭和の頃は、ちゃんと店の品格を保つためにお仕着せがあったって大泉さんに聞きました。それから店員が店の品を購入するための補助費も。お給料少ないのに、仕事用のために好きでもない黒のスーツばかり買うのは気が滅入るんです」
とはいえ、やはりそこは同調圧力のようなものもあるから、スーツだけは黒を着る。しかしそれ以外は自分のポリシーを通す、というのが香野の妥協できるギリギリのラインであるらしかった。
「やっぱり黒やグレーや紺以外を着たらいけませんか?」
「特別な催事でなければいいと思う」
「よかった。やっぱりそうですよね。ガンガン富久丸を変えてる鮫島さんならそう言ってくださると思ってました!」
べつに自分ではガンガン行っているつもりも、富久丸を変えているつもりもまったくないが、若手から見るとそんなふうに感じるのかと驚きもした。
「てっきりその件の呼び出しだと思ってました。派手な靴を履くなとか」
「靴だけはおしゃれしたい気持ちはわかるし、私だって一年目から無理してルブタン履いてましたよ。それでいろいろ言われたけど、結局は周りも私に慣れたってことかな。早く周りが香野さんにも慣れてもらえたら、販売員は黒の呪縛から解き放たれるかも」
ただし、フロアの店員が黒から逃れられることは難しそうである。黒子に徹せよという意味ではなく、たんに客がだれが販売員か一目でわかるという利点において。
【12月6日発売予定!】
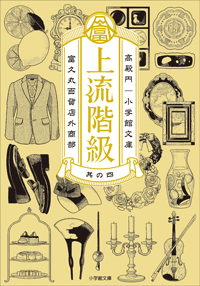
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



