『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』冒頭ためし読み!

ベストセラーシリーズ最新刊を、
ためし読み!
「自分で買いたいものがなくても、鶴さんのご招待の手前なにかお買い上げになる方も多いはず。娘さんのためにとお買いになるものを置いておいてもいいかもしれません。母娘の話題の提供にもなりますし」
そう、世の中不思議なことに、疎遠になった娘と話をしたいがためにブランドバッグをお土産に買って帰る奥様方はいらっしゃるのである。
(うちの場合でいうと、芦屋軒とか竹園の牛肉の佃煮だな……。ケタが大分違うけど)
大泉の狙い通り、ディオールのトロッターのサドルバッグ、ミニトートなどが売れ、それをきっかけに皆様に外商口座の申し込みをしていただくことになった。そもそも今日は鶴さんのご友人たちを静緒に引き合わせるための集まりでもある。
鶴さん定番のブルネロ クチネリのニット製品を中心としたウェアは、着心地だけでは無く、デザインや異素材使いもひと味違っていて、強烈にブランドロゴを主張しないものを愛用するリッチな奥様に絶大な人気がある。
落ち着いた色のウェアに、腕にはきらめくダイヤのウォッチ、というのが一種の奥様スタイル。その日さりげなくケースに並べていたクッサン・ドゥ・カルティエは、絶対売れる時計だろうと思っていたが、やっぱり売れた。つけやすいけれど、デザイン性があって定番で紹介しやすいネックレスをという鶴さんの注文には、ピアジェの POSSESSION ペンダントを用意した。ブライダルに人気のロングセラーコレクションだが、だからこそ、鶴さんのような年代の方はかぶらない可能性がある。
この歳になると、あまり若い人がいくメゾンには立ち寄りにくい、とおっしゃる方も多い。社会的な立場と年齢を考えると、他人からの視線を気にして、しなくてもよい自制をしてしまうのだという。そうなるとだんだんと地味な装いになっていくが、心の中ではもっと明るく、若く見える、若い人ももっているものも持ちたいし着たい。人からの印象と自分の希望がせめぎ合って、なにを買ったらいいかわからなくなり、結果保守的な選択をしてしまう。
だから、こういう場で少し派手で若見えするブランドをちょっと置いておくことは大事なのだ。今はシニアの方でもトレンドのバルーン袖を着てみたいと思われる方も多いはず。けれどゆるっとしたシルエットに躊躇されるのもわかる。だったらこういうクローズドサロンで少し挑戦してもらうというのはいい機会なのではないだろうか、と話し合った。
特にブルーが難しい。パステルとグレーの中間のようなブルーは清涼感もあって人気があるが、六十代の奥様にコットンシャツワンピースは勇気がいる。しかし置いてはみたい。見ていただきたい、などとせめぎ合った結果、エブールのリバーレースタックブラウスを中心に、リバーレースの商品をいくつかセットした。とにかくレースが上品で、ゆったりしていてサイズを選ばない上にいまの流行でもある。
モード色中心のワンピースやウェアとは逆に、バッグやシューズはカラフルに揃える。特に一押しはトッズのタイムレスレザーショッピングバッグで全色並べて置いてみた。荷物が増えるわりに、若い人の出勤御用達のぱかっと開くトートバッグは六十代には似合わない。肩が痛いので斜めがけのショルダーバッグもしない、手にぶら下げられて、ハンドルを腕にくぐらせることもできて、出し入れが便利で上品なかたち。トッズのこのシリーズはショルダーを取り外しでき、ペットボトルも入れられて、ちょうど形もがま口ポシェットのようなシルエットで少し和を連想させる。
「このバッグ、訪問着にも似合うと私は思うんです」
と、大泉は奥様方に切り出していた。
「鏑木清方の美人画で、こういう色ありましたよね。訪問着の奥様。浅黄色に黒の羽織の」
さらっとこういうセリフが構えなく出てくるのが大泉のいいところだ。
「そういえば、三井記念美術館でこのまえ見たわ」
「もう少し大人になったら、お着物とレザーバッグをあんなかんじで着こなすのが理想なんです。できればシューズも草履じゃなくて、もう少し履きやすいものがあれば」
「あら、着物は慣れですよ、慣れ」
「でも、いいじゃない。古いやり方ばっかり押しつけていたら呉服屋さんが潰れてしまうから。最近はブーツで着物もはやっているみたい」
「母がお茶に出かけるときなんかは、足袋のような和風の履き物でもっと厚底にしてくれれば着物と合うんじゃないかなあって思っています」
家族がごくふつうにお茶席に通うような家だと、生活スタイルも大分違う。大泉はとくにその辺りを勉強しなくても基礎知識がしみこんでいるのが強い。
(今日ついた新しいお客様は、総務とも相談して大泉に担当してもらうのがいいかも)
天気の良い日で四月だというのに全館にエアコンが入った。それでも熱い紅茶を飲むのが西洋茶器をこよなく愛する鶴さんなので、「アイスティーは出さないで」とグランドスタッフにお願いする。
「私ね、実は鮫島さんにお会いしたことがあるんですよ」
新規申し込みの書類を書き終わったお客様の一人が、静緒を見てにこにこしながらそう切り出した。
「私ですか? どちらかの特賓会でしょうか」
「あら、いいえ。あなたが富久丸の社員さんになられるもっと前。ええと、エスカレーターのところの、お店がころころ変わる場所で」
「ああ、地下の催事エリアですね」
ということは、ローベルジュの営業として店を任されていたころだ。もう二十年近く前の話になる。
「あのときのお店が、大きくなりましたねえ」
「本当に。私はもう離れてしまいましたから。オーナーシェフがしっかり経営されていますよね」
「あのときは銀行振り込みで電話注文が多かったけれど、すぐに送ってくださって。私の姉がね、子どもがちょっと手がかかる子で、なかなか買い物にもいけなくて、おやつだけが楽しみだったの。いろんな通販を頼んでいたけれど、生菓子はなかなか手に入らなくてね。ローベルジュさんのギフトボックスが楽しみだってたくさん買ってたの。私も頼まれて買いに行ったのよ。通販のたびに、手書きのメッセージを送ってくださったの、鮫島さんでしょう。姉はいまでも全部持ってるわ」
静緒は驚いて、書類から目を外してその維方さんという女性を凝視してしまった。
「地下の売り場でお客さんがいないときに、ずっとカードを書いていたのを見て姉に報告したのよ。たぶん今日売り場にいた若い女の人じゃないかなって。申し訳ないことにそのあとずっと忘れていたんだけれど、顕子さんの話を聞いてびっくりしちゃって。あ、その人私知ってるわって。姉は、長いこと身体障害者福祉家族会の県の副代表を務めていてね。今では二人の子どもも大人になって、施設で働けるようにはなったけれど、それまでが長かったから」
維方さんはそれ以上はおっしゃらなかったが、静緒には、どうにもそのお姉さまからどこかを経て、ローベルジュの存在が紅蔵か葉鳥の耳に入ったのでは無いか、と直感で思った。品のいい方々は恩着せがましいことや不確かなことを口にはしないので追求してもやんわり明言を避けられるだろう。
(でも、あのとき急に田舎の、たいして有名でもない元パン屋に、富久丸なんて一流の百貨店が催事の誘いに来るなんておかしいと君斗と話したんだった。でもとにかくチャンスだったし、紅蔵さんも葉鳥さんも信用がおける相手だったから、出店を決意した……。でもあのとき私にも君斗にも、百貨店のコネクションなんてなかった)
どれほど品質が良くても、一部に評判でも、百貨店で取り扱う商品は食品に至るまで信用がすべてだ。もちろんローベルジュの経営状況から、販売員である静緒の身元チェックまで済ませてから声がけしたには違いなかった。しかし、当時のローベルジュの規模からいうと、百貨店が声をかけるには誰かの猛烈な後押しが必要だったことぐらい、静緒にでもわかる。
(どこでだれがつながっているかわからない、御縁というのはだから怖いんだ)
その日は帰宅してすぐ、かまって欲しそうな桝家を放置して旧友である雨傘君斗に電話をかけた。
「やっぱり静緒まわりでそういうことがあったのかー」
二十年ぶりに解けた謎に、君斗もどこか感慨深げで、
「あのとき静緒が、リピーターさんにすごい長い手紙を書いてたのを覚えてるよ。文通してるみたいじゃんって言ったのを覚えてる。たしかお子さんがたくさんいて外出できないからありがたいって言ってた人、いたよね。その人じゃない?」
お金持ちであろうと、そうでなかろうと、生まれてきた子どもに育てにくい特性があったり、後天的な病気や事故で介護が必要になることもある。今でもまだ一日中見守りが必要な子どもを見たり親を介護するのは妻という風潮は強いが、二十年前はほとんど女が自主的にするのが常識だととらえられていた。実際、外商で訪問するお宅には、維方さんのお姉さまのようなお客様も少なくない。
「やっぱり、誰かが見てるってことだよなあ。よく政治家が、お礼状はぜったい直筆で書くというけれど、それだけ伝わる熱意が違うんだなと思うよ」
あのころはECなんて言葉はなかった。通販はまだ電話注文が主流の時代、費用がかさむからとクレジットカード決済にもできなくて、毎日銀行に通って振り込みを確認し、すぐに宛名を作って商品を梱包した。店に立ちながらひたすら手を動かした。実際は通販の発送作業の方が多くなり、地方発送の需要を実感し始めた。凝った商品を作るよりカタログを作って通信販売に力を入れようと君斗を説得した。
あのとき、最初の方針通りに当時の主流だった二号店、三号店を出すことこそが成功の証だという考えにこだわって店を増やしていたら、いまのローベルジュはなかった。店舗を出さないことで人件費や固定費を抑え、地方の安い土地に工場を建てて生産し、地元の人たちを雇い入れた。そのころから君斗は、夜間学校に通う生徒や母子家庭や、ハンディキャップを持つ人々の就労協力に熱心だった。
「私がどう、とかいうよりは、君斗が作業所の隣に土地を買って、作業所の人たちをまるっと雇い入れたりしたことのほうが効いたと思うな」
「いやー、もしかしたら物流かも。最近多いよ。あの頃俺らと同じで下っ端だった人が部長とか管理職になってってやつ。それに宅配の人たちはものすごい情報を持ってるから、紅蔵さんがリサーチに使っていたのかも」
良いモノは最初は密かに売れる。売れるということは動くということ。その流れを最初に把握する外部の人間は、物流に携わる宅配員である。
「結局、あのとき通販に舵を切って、店舗をもつことを諦めたから、いまこうやって独自通販サイトでも十分やっていけてる。ECの販路をもっていることは、ファイブプラットフォームに頼る必要がないってことで、そのノウハウを二十年分持っているからこそ井崎先生も声をかけてくれたわけだし」
なにが吉と転じるかはやっている時点ではわからない。諦めて切り替えることも大事だし、継続することも大事だ。その判断はいつだって人間がする。商売の起点とはだれかの判断であって、その判断をしたのは彼だからこそ、静緒はローベルジュの成功を自分のおかげだと誇ることはしない。
まだ転職する決心はつかないの? とは君斗は言わなかった。せかすようで静緒が困ることを付き合いが長い彼はわかっているのだ。その気遣いがありがたいと同時に、なかなか決心できない自分へのいらだちと焦りが募った。判断できない、決断ができなくなっている。昔はあんなに思い切りよくなにもかも決めることができたのに。
(これは、噂に聞く脳の老化? ……それとも更年期かな)
そういえば、最近明け方に尿意で目が覚めてトイレにいくことが多くなった。寝る前に一杯の水を呑んで、脱水に備えるという健康法をどこかで見て続けていたのだが、最近まで朝トイレにいきたくなって目が覚めることはなかった。これも膀胱の筋力が衰えているせいだろうか……
「あー、いやだ。決断力も筋力も落ちてる! そしてそれに対処するだけの時間も無い!」
だれも聞いていないのをいいことに、移動中の社用車のなかで叫んでしまった。最近社用車のなかにいるときが一番ほっとする。そのことを今朝部屋ですれ違った桝家に言うと、「運転に集中できて雑事を忘れているからですよ。よっぽどストレスたまってるんですね」
ストレスは言語化して調伏しないと体に毒ですよ、日記を書くのが体にいいのはそういうことですよとやさしく慰められた。なんなんだ、最近の彼はあの桝家だというのに家猫のように自由で、しかもやさしさが服を着ているようだ。
第三章 外商員、スタートアップにかかわる
京都のボンが猫化したのが桝家なら、京都のボンが素敵に歳をとった紳士こそが一樂さんだ。冬の京都は身に応えるというので、十二月あたりからずっと芦屋浜のマリーナで過ごされている。奥様はとっくの昔に成人した娘さんとお孫さんとロンドン暮らし。持病があるので日本での生活に切り替えたという京都のジェントルマンが静緒を呼び出したのは、芦屋川店の地下にある銀コーヒーだった。
「一樂さんもこちらによくいらっしゃるんですね」
「僕は駅前にくるときはずっとここ。昔からタバコがキライだから。天井が高いのもいいし」
昔ながらのチケット券をマスターがもぎっていく。しばらくして、深煎りの豆のいい匂いがカウンターを越えてきた。
いわゆるデパ地下は静緒にとっても百貨店キャリアがスタートしたところなので、独特の匂いと動線、特にエスカレーターを降りてきたお客さんの流れはすぐに目で追ってしまう。
「先日は、素敵な時計をお買い上げいただきありがとうございました。納品まで少しお待ちください。来週にはご用意できると思います」
「ああ、いいのいいの。僕は男にしては手首が細いから、昔からいっつもこうなの」
ボート遊びで日に焼けてしまって、またこれで老けてしまうわ、と頰を撫でながら一樂さんはさらっと言った。
「あのねえ、今日は鮫島さんにお願いがあってね」
「はい。お伺いします」
「こんなんお願いしたらどうなんやろおもてたんやけど……。銘月リゾートってあなたご存じ?」
突然飛び出してきた聞き慣れぬワードに戸惑いながらも、
「たしか、嵐山のほうの……」
「そうそう。あそこの二代目が僕の親友やねんけど」
銘月リゾートは、大文字焼きで有名な大文字山に隣接する京都屈指の高級レジャーリゾートである。金閣寺が近くにあって観光にも便利、鷹ケ峰と紙屋川の渓流という自然の借景だけではなく、その昔ウールの着物を発明し爆発的な人気を得て富豪となった創設者が、三万五千坪の敷地に、継承者や相続人がなくなって朽ちていくだけだった日本家屋や長屋、茶屋や武家屋敷などを移築して作り上げた、古き良き日本と京都がぎゅっと詰まった異空間でもある。もう手に入らない美しい小京都を一目見ようとする人々の間で、京都の中の京都として人気があり、最近では超高級ホテルやレストランに敷地や所有する日本家屋などを貸し出してブランド力を高めている。京都のいいところだけを集めただけあって、このリゾートにいるだけで京都を満喫できると評判が高い。
「そこのお嬢さんのことやねんけど」
「はい」
ご結婚かなにかかな、とは思ったが、そういうめでたい話にしては、こんなコーヒー店で、親戚でもない顧客の男性から話を聞かされるというのも妙なことだ。
「銘月というのは屋号で、姓は月居さんとおっしゃる」
「風流で珍しいお名前ですね」
「もともと先代さんがウールのお着物を売り出してもうけはったんやけど、そのときに三日月のデザインのものにしたんやて。明治のころに石川かどっかからいらっしゃって、もともとは加賀友禅の職人さんの家系やったらしいわ。それで着物のご縁で京都にきはって、ひいおじいさんが光悦村で働きはじめた。もともと本阿弥光悦が徳川さんから九万坪の所領をあのあたりにもらわはって、そこから芸術家とか、職人とかがぎょうさん集まるようになってたらしい」
徳川時代の初めのころ、日本の京都にそんな先鋭的な芸術村があったことは驚きで、自分の無知に恥じ入りたくなった。やはりまだまだ、人生は勉強の連続である。
「そこは、上がお嬢さんで下がぼっちゃんで。当代の社長にしてみたら、娘はいつか嫁ぐやろうから好きにしたらええと。娘さんが働きたいいうんで、まずはお土産もんまわりを任せて、それからレストラン、お惣菜、お菓子あたりをやってはったらしい。息子のほうはあととりやから、どっかに修行に出して、それが五年ほど前に当代がガンになったんであわてて呼び戻して……。まあ、ガンのほうはたいしたことなかったんやけど、大きな病気してきよわくなったんかな。息子に徐々に経営を任せるようになった。お姉ちゃんの史乃さんのほうはこつこつ任された仕事をやってた。銘月いうたら栗まんじゅうが有名やけど、タルトにしたりブッセにしたり、いろいろ商品を開発してうまいこといってたらしい」
「ああ、銘月さんとは、大昔ですけど催事でいっしょになったことがあります」
たしか、催事のたびに京都の一大ブランドと並べられるので、君斗と二人でびびりまくって、どうやったら銘月さんのお客さんに手にとってもらえるか、客をとられないか、あれこれ会議したことを覚えている。
「むこうさんも覚えてはったよ。背の高い若い女性がずっとお礼状書いてたって。計算が速くて、包むのも手早いから大学生バイトだったら次にうちにきてもらえないかと思っていたら社員で、しかも営業部長だったので驚いたと」
「営業部長といっても、社員五人でしたけれどね」
ちなみにローベルジュ時代の営業は静緒一人だった。全国の百貨店やモールに催事で呼ばれるたびに弾丸のように行って、移動日と移動日の間に宅配便などの営業所や、まだお付き合いのないデパートなどに営業に行っていた、タフで若かった頃の話である。
「もしかして、わりと背が高くて眼鏡をかけた女性ですか?」
「そうそう。声が大きくていかにも頼りがいがありそうな。リゾートホテルグループ創業家のお嬢様って感じやない。男社会の会社でいかにも実力で這い上がってきた常務、みたいなおねえさんや」
なんとなく覚えている気がする。一度や二度、互いにトイレの間店番をしたような……
「銘月さんの詰め合わせセットののし紙を書いた記憶があります……」
「せやろ。いま富久丸にいるでていうたらびっくりしてはった」
その、大富豪のお嬢様らしからぬ、すごくよく働く銘月の社長令嬢が、一樂さん経由で静緒に連絡を取りたい理由というのが、
「まあ、ケンカして家を出はったんやわ」
一樂さんは鈴でも鳴らすような手つきでコーヒーにほんの少しだけ砂糖をいれ、スプーンでかき混ぜた。
「ケンカ、ですか」
「そうそう。会社を仕切るようになった弟が、うまいこといってた食品関係にまで口を出すようになってな。まあ黒が出てるとこは赤のとことくっつけて、赤にしとくことのほうが会社にとっては税金対策になるからなあ。でも、いままで二十年かけて部門を育ててきたお姉ちゃんにとっては、そんな右から左にぽいってされても困るっちゅうはなしや」
「まあ、お気持ちはわかります」
「で、なんやかんやいろいろあったらしいけど、昔から思い切りのいいお嬢さんや。身一つで月居の家を出た。それでどうするんやいうたら、自分の会社を作るという」
「はあ」
「おもろいから、場所だけ貸してん。なにか作って売るんやったら店舗も倉庫もいるやろ。ちょうど改修しよかどうしよか迷ってた鞍馬口の長屋が一軒あいてたから、好きにつかったらええて。僕はあの姉弟のゴッドファーザーみたいなもんやからね」
子育ても仕事も終え、一人で老後を気楽にお暮らしのおじいちゃん貴族にとっては、人助けも楽しみの一つであるようだ。
「まあそれでね。なにをするにしても商売、それも小売りとなったら頼りになるのは百貨店でしょ。お嬢ちゃんも長いこと富久丸さんとはお付き合いがある。ここはちょっと僕の顔をたてて、話をきいてあげてはもらえんやろうか」
思いもかけない申し出だった。そういうのはコンサルタントとか行政書士とかの仕事なのではないだろうか。なにしろ、静緒は起業をしたことがない。ローベルジュ自体の経営は君斗が資金繰りから資材調達まですべてやっていて、静緒はそのヘルプをしていたにすぎないのだ。しかもあれらはすべて二十年以上前の話。ネットもまだ一般の隅々にまでは普及しきっていなかったころの話だ。状況が違いすぎる。
「ままま、わかりますよ。銘月のお嬢さんいうても、会社を出てしまえば無一文や。当代はぴんしゃんしてるし、生前相続なんて気の利いたことできる人やない。文字通り裸一貫の起業。それでもやるてお嬢ちゃんは言うた。それなりの事業計画も僕に提案してきた。なかなかいいセンはついてると僕は思う。だから、鮫島さんも聞いてあげて」
「私は、起業は素人、なのですが……」
「いいからいいから。お茶飲みながらとかでいいから。僕のカードでつけといて」
「はあ……」
それでも、一樂さんに「必要なものがあれば僕が買い物をするから」と笑って言われれば断ることも難しかった。このためのトップガン〝モハーヴェ・デザート〟だったのかと思うと、なにやらうまくしてやられたような。静緒と顔をつなげるために五百万の時計をぽんと買うほどのお嬢様とはどのような人だったのか、興味も湧いてきた。だてに七十年を貴族として生きていない貫禄とエスプリを感じさせながら、一樂さんは銀コーヒーでひいてもらったコーヒーを一キロ買った。
「七十過ぎたら免許を返納しなさいって家族に口やかましく言われてるんだけど、こればっかりは手放せそうにないよ」
駆体の大部分が木でできているという愛車モーガンで帰途についた。和装でモーガンを運転する芦屋のおじいちゃんの格好良さに、たまたま店の車止めで居合わせたほかの客からも注目を浴びていた。
(えらいことになってしまった……)
ちゃっかり手土産に伝票(何におつかいになるのかダイヤモンドのルースをお買い上げだった)とコーヒーを握らされ、途方にくれながら事務所に戻った。
(菊池屋からの刺客と、癖の強い部下と、新規のお客さんと、本部の仕事と会議、これ以上に、お嬢様の起業の手伝い……??)
「無理では?」
思わず本音が口からこぼれ出て、従業員用のエレベーターで居合わせた事務の子をびくっとさせてしまった。
(いやいや、どう考えてもこれ、やっかいな展開にしかならないのでは?)
やんわり断ろうと、あれこれ理由を揉んでいるうちに、一樂さんから高速でLINEが入っていた。なんとすでに紹介のためのトークルームまで設定されてある。これは逃げられない。
とにかく、一度話だけでも聞こう。それであちらさんが気が済むのであれば。そもそもお客さんからの紹介のお客さんというのはとりあえず受けるのも仕事のうちだ。大企業の創業家のお嬢様とはいえ、いまは無名の会社を立ち上げたばかり。外商口座を通してお買い物をしていただくお手伝い以外、百貨店の外商員として静緒ができることなどほとんどない。いったいなんのために、一樂さんを通して静緒とつながろうとしているのか。
その日もぎゅうぎゅうのスケジュールをなんとか刻んでこなし、家に戻るとビタミンゼリーのストックが切れていた。冷蔵庫を開けてもふよふよになった保冷剤しか入っていない有様で、なんだかその掃除もおろそかにしたままの冷蔵庫の中が、自分の中身のように思えてせつなくなった。百貨店に勤めているのに惣菜を買って帰る余裕もないとはなさけない。ほんの数年前までは、休日にお惣菜をまとめて作って冷凍したり、便利な電気調理器に感動して煮込み料理を作る気力くらいはあったのに。
せめて風呂に入って癒やされようとすると、バスソルトはおろかシャンプーまで切れている。水をいれてしゃかしゃかふってなんとか今日一回分を捻出した。半身浴の合間に部下たちへの返信を済ませ、今日お会いしたお客様、明日お会いするお客様、今週大事なイベントごとの予定があるお客様にもメールを入れる。そうこうしているうちに静緒のバスタイムは終わる。
(おかしいな、昔はここでネットドラマを英語字幕で見て、英語の勉強くらいはしていたのに)
風呂から上がるとなんと化粧水まで切れていた。さすがにストックまで切らしていることに絶望して、旅行用の小ボトルがどこかにあったなと捜しまくり、なんとかドラッグストアコスメの乳液を見つけて急いで顔に塗りたくった。思いのほかしっとりと肌になじむ。いつのまにか、自分の肌は化粧水ではものたりなくなっていたらしい。
「おや、珍しく夜九時に家にいますね」
ウォーキングから戻った桝家の顔が汗と血流でつやつやしているのが遠目でもわかる。彼氏と恋愛中だと言っていたころよりも、最近彼がまぶしいと感じる。
「そりゃやっぱりストレスがなくなったからじゃないですかね」
養子に出されたことに端を発する母親との長年の確執はすっかりなくなったらしく、最近ではよく一緒に買い物にいくという。ついでに桝家の家が持つ土地の運用やその他資産管理について、その道の先輩に指導を仰いでいるようだ。
【12月6日発売予定!】
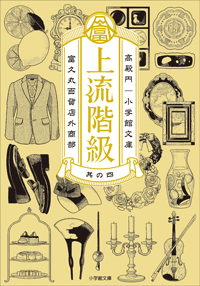
『上流階級 富久丸百貨店外商部 Ⅳ』
高殿 円



